
高齢者施設における転倒と心身への影響および転倒予防対策の現状について
高齢者の介護が必要になる1つの要因に骨折・転倒があげられております。その中で高齢者施設における転倒と心身への影響、転倒予防対策について紹介します。 高取 克彦 教授 畿央大学 健康科学部 理学療法学科 理学療法士/教員 日本理学療法士協会,日本老年医学会,日本転倒予防医学会 大阪厚生年金病院(現JCHO大阪病院),西大和リハビリテーション病院リハビリテーション科にて勤務後,平成19年より畿央大学 […]

高齢者の介護が必要になる1つの要因に骨折・転倒があげられております。その中で高齢者施設における転倒と心身への影響、転倒予防対策について紹介します。 高取 克彦 教授 畿央大学 健康科学部 理学療法学科 理学療法士/教員 日本理学療法士協会,日本老年医学会,日本転倒予防医学会 大阪厚生年金病院(現JCHO大阪病院),西大和リハビリテーション病院リハビリテーション科にて勤務後,平成19年より畿央大学 […]

認知症の方々が集まるサロンである「認知症カフェ」 私の研究室では患者の方々とそのご家族の支援活動を行っています。 今回ご紹介するメモリーブックは、当研究室で開催していました「認知症カフェ」で利用していたものです。認知症カフェとは、オランダの「アルツハイマーカフェ」から始まり世界に広がりました。認知症の方やご家族、地域住民、専門職などが交流を深めることができる場です。認知症カフェの目的は、家に閉じこ […]

「脳トレ」という言葉を聞いたことのある方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。脳トレとは脳力トレーニングの略であり、最近はゲームや雑誌などでも取り上げられています。脳トレの目的は間違い探しなど様々な問題に取り組むことで集中力や記憶力を維持したり改善させたりすることです。しかし様々な研究によってどのような脳トレを行うことが最も集中力や記憶力の維持や改善に効果があるのかは十分には定まっていない現状が […]

介護の専門職であれ,ご家族であれ,介護という営みにストレスはつきものです.介護を必要とされる方のよりよい生活・人生をサポートしていくためにも,ストレスとうまく付き合ってゆくことが重要です.以下では,その方法である「ストレスマネジメント」についてご紹介します. 北垣 智基 准教授 天理大学人文学部社会福祉学科(2024年4月から改組により名称変更) 社会福祉士/介護福祉士/教員 立命館大学大学院社会 […]

日本では年間約2万件の自殺が報告されていますが、「介護・看護疲れ」を原因・動機とした自殺も後を絶ちません。介護をきっかけとした自殺や心中という悲しい事例を減らすためにはどうすれば良いのでしょうか。本コラムでは介護者・被介護者双方に焦点を当てたコミュニケーション方法や対策について解説します。 影山 隆之 教授 大分県立看護科学大学 看護学部 精神看護学研究室 日本精神衛生学会理事長、日本自殺予防学会 […]

日本は、世界で最も高齢化が進行した超高齢社会となったが、やがて誰もが100歳程度まで生きる「人生100年」時代が到来するとも言われています。長寿は、人類の勝利であるとともに様々な課題を生み出しています。 その先頭を走っている日本において、2000年に介護保険制度を制定しました。23年におよぶ介護保険制度の存在により、公的介護保険で親や自身の介護負担が行われるという意識は定着しつつあります。制度創設 […]

皆さんは理想的な姿勢について考えたことはあるでしょうか?本コラムでは現代人に多く見られる悪い姿勢についての解説と、家でも簡単にできるストレッチを紹介します。 瀬川 大 教授 大和大学 保健医療学部 総合リハビリテーション学科 作業療法学専攻 日本作業療法士協会・日本世代間交流学会など 2008年に作業療法士免許を取得し、神戸の回復期リハビリテーション病院にて10年勤務。整形外科疾患、脳血管疾患など […]

噛む力(咀嚼力)や 飲み込む力(嚥下力)が衰えてしまった方々にとって誤嚥を防いだり、食欲を維持するための工夫を行った食事である介護食。介護食の種類や普及への取り組み、家庭での介護食の作り方について解説します。 片山直美 教授 学校法人 越原学園 名古屋女子大学 健康科学部 健康栄養学科 学士(工学)・修士(農学)・博士(医学)・管理栄養士・調理師・製菓衛生師・健康運動指導士・健康運動実践指導者・M […]

少子高齢社会の現代において、介護人材の確保の難しさは深刻です。そんな現代に介護ロボットの存在はどれほどの影響を与えるのでしょうか。 本コラムでは実際に開発された介護ロボットの例から、これからの介護ロボットの可能性について解説します。 榊 泰輔 教授 九州産業大学 理工学部 機械工学科 日本機械学会、日本ロボット学会、計測自動制御学会、日本VR学会、日本生活支援工学会、日本リハビリテーション工学協会 […]

高齢者の「社会参加」と聞くとどのような活動を思い浮かべますか?「友人と会う」「ボランティア活動に参加する」のような活動だけではなく、身体に無理のない範囲で「介護専門職の人と話す」ことも高齢者にとっては大きな意義があります。本コラムでは高齢者の活動レベルにあわせた社会参加の方法を紹介します。 太田 健一 助教 日本福祉大学 福祉経営学部 医療・福祉マネジメント学科(通信教育) 作業療法士/教員 日本 […]

国立環境研究所が2017年5月に「高齢者ごみ出し支援ガイドブック」を発行し、また環境省も2021年3月に「高齢者ごみ出し支援制度導入の手引き」をまとめました。私は、前者には協力者として、後者には検討会座長として関わりましたので、これらをベースに高齢者のごみ出し支援の動向をまとめます。 松本 亨 教授 北九州市立大学 環境技術研究所 廃棄物資源循環学会、環境科学会、日本環境共生学会など 九州大学大学 […]

ホームホスピスという仕組みをご存じでしょうか?ホームホスピスは高齢者や難病をお持ちの方など様々な方が利用できる「家」です。本コラムではホームホスピスについて解説します。 山口 健太郎 教授 近畿大学 建築学部 日本建築学会、都市住宅学会、人間・環境学会など 京都大学大学院工学研究科を卒業後、㈱メトス、国立保健医療科学院協力研究員、近畿大学理工学部講師、建築学部准教授を経て現職。専門は建築計画、高齢 […]

高齢者と幼児の関係性はそれぞれにポジティブな影響を与えると言われています。本コラムではお互いの関係性・影響に焦点を当てて,高齢者と幼児の世代間交流の大切さについて解説します。 西村 めぐみ 准教授 宝塚大学 大阪梅田キャンパス 看護学部看護学科 日本老年看護学会、日本家族看護学会、日本健康医学会 北海道旭川市出身。看護師として総合病院等に勤務後、宝塚大学所属、現在に至る。老年看護学分野の講義や実習 […]

いつまでも健康で幸せな毎日を過ごしたい、これは誰しもが望んでいることだと思います。健康寿命という言葉がありますが、健康寿命とは、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」[i]を指しています。本コラムでは、健康寿命を延ばし、最期まで自分らしく快適な毎日を送るための選択肢の一つとして、在宅療養について説明します。そして、在宅療養を支えてもらうために、在宅療養支援診療所を利用するとい […]

みなさんはおしゃべりが好きですか? 私は職業柄、認知症の方と関わる機会があります。その方々と楽しくおしゃべりをしていると、「すっきりした」、「やっぱりおしゃべりは楽しい」などの声を聴くことがあります。その中には、おしゃべりにより昔の趣味を思い出し再開された方やおしゃべりした内容を家族に伝えると「これがやりたかったのね」と家族の理解・協力を得ながら実現したこともありました。このようにおしゃべりを通し […]

理想的な介護の国はどこにあるのでしょうか?私がこれまで介護政策研究の対象にしてきた国々について、介護システムの特徴を光(長所)と影(欠点)の両面から明らかにします。以下記事の内容は、基本的に筆者がこれまでに出版してきた書籍からの引用ですが、データは最新の情報を調べ記載しています。 西下 彰俊 教授 東京経済大学 現代法学部 専門社会調査士 日本老年社会科学会、日本社会学会、日本社会福祉学会、福祉社 […]

脳卒中は後遺症を残しやすい病気であり,手・脚の麻痺は脳卒中による症状の大きな特徴です.本コラムでは家庭内で実践できる後遺症を軽くするためのリハビリ・行動を紹介します. 林 浩之 准教授 星城大学リハビリテーション学部作業療法学専攻 作業療法士,博士(リハビリテーション療法学) 日本作業療法士協会,日本義肢装具学会,日本手外科学会 名古屋大学大学院医学系研究科博士課程修了.作業療法士免許取得後,一般 […]
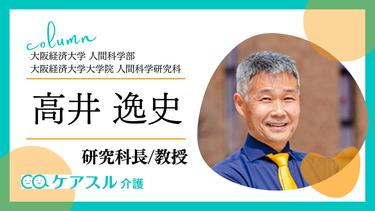
近年の日本では孤独・孤立を感じる高齢者の数が増えており、社会的孤立は生きがいの低下や孤独死といった問題を引き起こします。本コラムでは社会的孤立を深める高齢者との向き合い方を紹介します。 高井 逸史 人間科学研究科長/教授 大阪経済大学人間科学部/大阪経済大学大学院 人間科学研究科 理学療法士 日本理学療法士学会、日本老年医学会 岸和田市にある寺田万寿病院に理学療法士として16年勤務。その後は堺市に […]

近年、高齢者の認知機能向上や健康維持のために、香りが大きな注目を浴びつつあることをご存じでしょうか。「におい」や「香りのアート」を利用した高齢者ケアについて、効果や実例を紹介します。 岩﨑 陽子 准教授 嵯峨美術短期大学 美術学科 美学会、日本味と匂い学会、意匠学会 その他 一九七三年生まれ。大阪大学文学研究科博士課程修了。博士(文学)。現在、嵯峨美術短期大学准教授。専門はフランス美学・哲学。味と […]

読者の皆さんは「介護」に従事している方々に対してどのようなイメージを持っていますか?本コラムでは介護の仕事、現場のリアルに迫り、当事者の方々がどのような想いを抱えて介護に従事しているかを紐解きます。 坂井 敬子 准教授 和光大学 現代人間学部 心理教育学科 心理学専修 国家資格キャリアコンサルタント 日本キャリアデザイン学会,日本キャリア教育学会,産業・組織心理学会,など。 民間企業での人事職を経 […]

手足や首,背中,あごなどの関節の動きが悪くなり、介護の難易度を高めてしまう関節拘縮.立つ,座るといった日常生活活動も難しくてしまう拘縮は一度発生すると改善することが難しいと言われています.本コラムでは実践できる拘縮対策とそのポイントについて紹介します. 沖田 実 教授 長崎大学生命医科学域(保健学系) 理学療法士 日本基礎理学療法学会,日本結合組織学会,日本ペインリハビリテーション学会,全国介護・ […]

ここでは医療や福祉の分野で相談という方法で支援を担う、医療ソーシャルワーカー(Medical Social Worker、略称:MSW)について解説をします。 上原 正希 教授・所長 星槎道都大学 社会福祉学部・地域連携推進センター 社会福祉士・精神保健福祉士・介護支援専門員 日本福祉図書文献学会(理事)・日本ソーシャルワーカー協会(常任理事)・北海道ソーシャルワーカー協会(会長) 東北福祉大学大 […]

人生100年時代と言われる現代において、高齢期という言葉が持つ意味は変わってきている。生活を安定させ豊かな日常を過ごすためには何が必要なのだろうか。盤石な高齢期を迎えるためのポイントを解説する。 山田 知子 教授 放送大学教養学部/大学院文化科学研究科 日本社会福祉学会、社会政策学会 他 日本女子大学大学院修了後、埼玉県立大学等の社会福祉系大学において社会福祉士養成に携わる。博士(学術)。社会福祉 […]

日本では、水害や地震などの自然災害が増加しています。今年に入ってまもなくの元旦に能登半島地震が起こりました。これらの災害は、特に高齢者に多大な影響を及ぼします。災害が発生すると、医療や介護サービスの提供が困難になり、高齢者は健康問題や孤立、心理的ストレスなど、さまざまなリスクに直面します。事前の準備と正しい知識が不可欠です。ケア施設や自宅で生活する高齢者に対して、セルフケアの重要性と減災ケアの実践 […]

皆様は老後をどこで誰とどのように過ごしたいと考えていますか?本コラムでは住み慣れた自宅で住み続けるための環境の整え方について解説します。 飛永 高秀 教授 長崎純心大学 人文学部 地域包括支援学科(令和6年4月より福祉・心理学科) 社会福祉士 日本社会福祉学会・日本地域福祉学会など 東洋大学大学院社会学研究科社会福祉学専攻博士前期課程修了・博士後期課程満期退学。特別養護老人ホーム介護職員、日本福祉 […]

在宅介護者が抱える介護上の悩みは多種多様で、介護によるストレスを抱えている方も少なくありません。本コラムでは在宅介護者が抱えうる課題とその解決策について解説します。 黄 京性(ファン キョンソン) 教授 名寄市立大学 保健福祉学部 社会福祉学科 日本老年社会学会、Britich Society of Gerontology、韓国老年社会学会など 東京大学大学院医学系研究科保健学専攻で博士号を取得後 […]

宮﨑 貴朗 准教授 東京工科大学 医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 理学療法士、介護支援専門員 日本理学療法士協会、日本体力医学会、医療情報学会、情報社会学会 横浜市総合リハビリテーションセンター、東京都リハビリテーション病院を経て、介護保険施設は介護老人保健施設、介護福祉施設、通所、在宅サービスにも勤務。熊本地震後に、熊本県の母の遠距離介護、水害と地震後の復興を継続中。 1. […]

買い物は生活に必要なものを購入するだけではなく、人と出会い、自分の好みのものを探すという楽しみでもあります。高齢になり心身が弱ってくることで、買い物への不安に感じている人も多いのではないでしょうか。買い物を支援するための取り組みについて解説します。 山井 理恵 教授 明星大学 人文学部 福祉実践学科 社会福祉士 日本社会福祉学会 北星学園大学卒業後、医療ソーシャルワーカー、社会福祉協議会職員(非常 […]

高齢期の転倒は骨折を引き起こしやすく、歩行が困難になることで顕著な体力低下が生じます。転倒を予防するために日ごろからできる体力維持のための運動を紹介します。 杉浦 宏季 教授 福井工業大学 スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 博士(学術) 日本体育測定評価学会、日本教育医学会 昭和59年生まれ。福井市出身。金沢大学大学院自然科学研究科博士後期課程修了。博士(学術)。現在、福井工業大学スポーツ健 […]

日常生活や介護施設入居において「意思決定」が必要な場面は多くあります。認知症の方の意思を反映させた意思決定をするためにはどうすれば良いのでしょうか。本コラムでは意思決定に必要な支援について解説します。 金 圓景 准教授 明治学院大学 社会学部社会福祉学科 博士(社会福祉学)、社会福祉士 日本福祉大学地域ケア研究推進センター研究員、筑紫女学園大学を経て、2020年より現職。認知症のある人と家族が安心 […]