要介護認定とは、介護の度合いを客観的に判断しいくつかの段階に分けたものであり、日常生活を送るうえでどの程度の介護や支援を必要とするかを表したものになります。
介護保険サービスを利用するには、この要介護認定を受け、「要支援」や「要介護」といった認定をもらうことが必須とされています。
そのため、介護保険サービスを利用したいと思っている方は、まず要介護認定を受けなければなりません。
しかし、急に介護が必要になったという状況などでは、「どうやって申請すればいいか分からない」と思う方もいるのではないでしょうか。
本記事では、要介護認定の申請方法や申請の流れについて解説します。
疑問やお悩みの解決に役立てば幸いです。
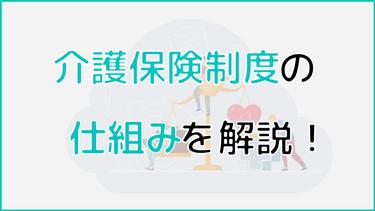
要介護認定の申請をするには
要介護認定の申請をするには、要介護認定の希望者が住んでいるエリアに該当する地域包括支援センターや役所の福祉窓口に必要書類を提出する必要があります。
要介護認定の希望者本人による提出が難しい場合には、ご家族や居宅介護支援事業所などに代行してもらうことも可能です。
要介護認定の申請についてまとめたものが以下の表になります。
| 要介護認定を申請できる人 |
|
|---|---|
| 申請先 |
|
| 申請に必要なもの |
|
| 申請の代行が可能な人 |
|
以下では、要介護認定の申請について「誰が」「どこに」「何を」という観点から、より詳細に解説していきます。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
要介護認定を申請できる人
要介護認定の対象者は、原則として介護や支援が必要と見込まれる65歳以上の高齢者と定めれらています。
ですが、例外として、国が定めた16の特定疾病であると判断された40歳~64歳の方も、要介護認定の申請をすることが可能です。
国が定めた特定疾病については、以下の通りとなります。
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
【パーキンソン病関連疾患】 - 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
出典:厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」
申請を検討している65歳未満の方は、事前に主治医に特定疾病に該当するのか診断してもらうようにしましょう。
要介護認定の申請先はどこ?
要介護認定の申請先は、要介護認定を希望する方が住んでいるエリアに該当する地域包括支援センターや役所の介護保険課になります。
以下でそれぞれの申請先について詳しく解説します。
地域包括支援センター
地域包括支援センターとは、介護・医療・保健・福祉などの面から高齢者を包括的に支える地域の総合相談窓口であり、要介護認定の申請窓口も担っています。
地域包括支援センターは、原則として1つの市区町村に1か所以上設置されており、令和4年4月末時点で全国に5,404か所存在しています。
地域包括支援センターでは、認定後の介護保険サービスの利用についても相談することができるため、認定後の手続きも円滑に済ませたいという方は地域包括支援センターでの申請が良いと言えるでしょう。
現在生活している地域に該当する地域包括支援センターについては、自治体のホームページやインターネット検索で調べることができるため、まずは該当する地域包括支援センターをチェックするといいでしょう。
出典:厚生労働省「地域包括支援センターについて」
出典:渋谷区「5720 介護保険の要介護認定申請(手続き)について教えてほしい。」
役所の介護保険課
地域包括支援センター以外にも、役所の介護保険課でも要介護認定の申請を受け付けています。
役所の介護保険課であれば、地域包括支援センターは馴染みがないという方でも申請しやすいのではないでしょうか。
申請先によって申請時の必要書類や要件が違うということはないため、申請しやすい窓口に申請するといいでしょう。
要介護認定の申請に必要なもの
要介護認定を受けるには、各自治体が定めた必要書類を提出する必要があります。
必要書類についても、各自治体によって定められているものが異なるため、事前にWebサイトや電話などによる問い合わせで確認しておきましょう。
なお、65歳以上の方と40~64歳の方では必要書類が異なるため、注意が必要です。
以下では、例として豊島区における必要書類を記載します。
65歳以上の方(第1号被保険者)
- 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証(65歳の誕生日前までに郵送されている)
- 主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号
- 個人番号(マイナンバーの確認ができるもの)
- 身元確認ができるもの(顔写真付きの身分証等)
40歳から64歳の方(第2号被保険者)
- 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
- 医療保険の被保険者証
- 主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号
- 個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの
- 身元確認ができるもの(顔写真付きの身分証明証等)
また、本人ではなく代理人(家族や居宅介護支援事業所等)が提出する場合は、以下の書類の提出が必要になります。
- 代理権の確認ができるもの(委任状等)
- 代理人の身元が確認できるもの(顔写真付きの身分証等)
出典:豊島区
この2点については、各自治体によっては提出を求めないケースもあるため、事前に申請先の自治体の窓口やWebサイトで確認するようにしましょう。
要介護認定の申請はご家族や代行での提出も可能
被保険者本人が申請することが難しい場合は、ご家族に代理で提出してもらうことが可能です。
また、遠方に住んでいるなどの理由でご家族が申請するのも困難な場合は、以下のところで代行してもらうことができます。
- 地域包括支援センター
- 居宅介護支援事業所
以下では、代行可能な施設や業者について詳しく解説します。
地域包括支援センター
本人やご家族での申請が難しい場合には、地域包括支援センターに依頼することで申請を代行してもらうことが可能です。
地域包括支援センターに依頼することで、申請書類の入手や必要事項の記入、提出などをまとめて代行してくれるため、本人やご家族での申請が難しい場合には、依頼してみるといいでしょう。
原則として、申請にかかる援助については、厚生労働省令において義務付けられているため、断られる心配もありません。
居宅介護支援事業所
地域包括支援センター以外にも、居宅介護支援事業所に依頼することで申請を代行してもらうことが可能です。
居宅介護支援事業所とは、自宅で自立した生活を送ることを目的に、ケアプランの作成やサービスの調整を行う事業所を指します。
上記の職務内容からも分かるように、要介護認定後のケアプランの作成やサービスの利用なども円滑に進めることができるため、居宅介護支援事業所が自宅の近くにある場合などは、代行での申請を依頼してみてもいいでしょう。
施設への入所を検討しているという方は、ケアスル介護がおすすめです。ケアスル介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができるためご希望に沿った施設探しが可能です。
「プロに相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
要介護認定の申請についてのよくある疑問
本章では、要介護認定の申請についてのよくある疑問を紹介します。
要介護認定の申請について分からないことがあるという方は、ぜひ参考にしてみてください。
Q. 要介護認定の申請にお金はかかるの?
A. 要介護認定の申請にはお金は一切かからないので、安心してください。
申請後の、訪問調査や主治医意見書の作成、判定等の行為にもお金はかかりません。
実際にお金が必要になるのは、介護保険サービスを利用しはじめたタイミングになります。
Q. 要介護認定の申請はいつからできるの?
A. 要介護認定の申請自体は、65歳の誕生日を迎える60日前から可能となります。
ですが、実際に要介護認定が始まるのは誕生日の前日となっており、申請可能日と要介護認定の開始日は異なるため、注意が必要です。
なお、特定疾病であると認められた40~64歳の方の場合も、40歳の誕生日を迎える60日前から申請が可能です。
Q. 入院中に要介護認定の申請をすることはできるの?
A. 入院中であっても、要介護認定の申請をすることは可能です。
ですが、原則として申請後の訪問調査は心身が安定した状態で行う必要があるため、退院の目途が立っているなど、ある程度状態が落ち着いてから申請するようにしましょう。
また、訪問調査については、「退院後自宅で行う」「入院中に病室で行う」という2通りのやり方があります。
注意点として、病室で行う場合は、本来生活を行う場所である自宅と違う環境での調査となるため、実際の要介護度と異なった認定結果となる恐れがあるため、把握しておきましょう。
Q. 要介護認定に有効期限はあるの?
A. 要介護認定は一度受けたら、そのままずっと有効というわけではありません。
新規や区分変更の場合は6か月、現在の要介護度で更新する場合は12か月という有効期限があります。
引き続き介護保険サービスの利用を希望する場合は、有効期限が終わる60日前から期限日までの間に更新申請が必要です。
しっかりと把握しておきましょう。
Q. 要介護度を変更したい場合は?
A. 被保険者の方の身体の状態や環境が変わり、要介護度の変更が必要な際には、区分変更申請をしましょう。
新規申請時と同じ窓口に、「区分変更申請書」を提出することで、区分変更申請を行うことが可能です。
新規での申請時と同様に、訪問調査や判定が行われ、正式に認定結果が通知されます。
区分変更申請を行う際は、事前にケアマネジャーやかかりつけ医に相談し、申請の必要があるか相談することをお勧めします。
要介護認定の申請の流れ
要介護認定の申請の流れは、下記の通りです。

以下では、各ステップについて詳細に説明していきます。
1. 必要書類の提出
まずは、前述の申請に必要なものを準備し提出しましょう。
お住いの地域にある自治体の担当窓口が提出場所に当たります。
なお、必要書類は各自治体によって異なる可能性があるため、事前に確認するのが望ましいと言えます。
2. 訪問調査
必要書類の提出を行い、申請が受理された場合、訪問調査が行われます。
訪問調査とは、各自治体の職員や委託されたケアマネジャーなどが申請者本人の自宅を訪問し、心身の状態や介護状況、日常生活、家族や住まいの環境等について調査するというものです。
調査項目については、以下の通りです。
- 身体機能・起居動作
- 生活機能
- 認知機能
- 精神行動障害
- 社会生活への適応
訪問調査では、普段よりも張り切ってしまう高齢者の方も多く、調査員の方に実態が伝わらないこともあります。そのようなケースを避けるためにも、必ずご家族の方も立ち会い、調査終了後に普段の様子を伝えるなどして、適切な認定を受けることができるよう注力しましょう。
3. 主治医意見書の作成
訪問調査後は、主治医意見書の作成が行われます。
訪問調査で確認した本人の心身状態について、主治医に医学的な意見を求めるために行うものです。自治体が主治医に直接作成を依頼するため、本人やご家族が主治医に依頼する必要はありません。
なお、主治医がいない場合には、自治体が決めた医師の診断を受ける必要があるため、把握しておきましょう。
4. 一次判定
主治医意見書の作成が済んだ後は、一次判定が行われます。
一次判定とは、訪問調査時の調査結果と主治医意見書を基に、必要事項をコンピューターに入力し要介護度を決めるというものです。
5. 二次判定
一次判定の後は、二次判定が行われます。
二次判定とは、一次判定の結果や訪問調査時の調査結果、主治医意見書を基に、保険・医療・福祉の専門家が介護や支援が必要か、またどの程度必要なのかを判定するものであり、要介護度を決める最終判断の場となります。
主に訪問調査の結果や主治医意見書に記載されている特記事項を判断材料とし、コンピューターで判断することができない、より複雑で専門性の高い判定がなされます。
6. 認定通知
二次判定を行った後、認定結果についての通知が行われます。
結果というのは、本人の要介護度についてであり、介護や支援が必要かどうか、またどの頻度で必要かを判断し認定したものになります。
要介護度は7段階あり、介護度の低い方から順に要支援1・要支援2・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5となっています。
また、判定の結果、非該当(自立)と認定されることもあり、その場合は介護保険のサービスを受けることはできません。ですが、介護予防事業等や高齢者保健福祉サービスであれば利用できる可能性があるため、まずは自治体の窓口に相談してみましょう。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
まとめ
要介護認定の申請は、今後介護保険サービスを利用するにあたり、重要なポイントです。
介護保険サービスの利用に必須なのはもちろんですが、万が一不適切な認定結果になってしまった場合、必要な介護サービスが利用できないというケースもあります。
そのような事態を避けるためにも、前述のような申請時の注意点やよくある疑問を把握しつつ、トラブルなく要介護認定を終えましょう。
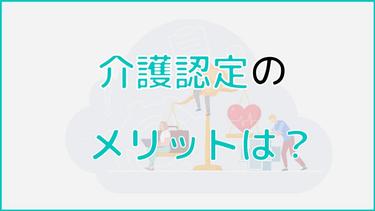
要介護認定の申請をする際は、該当するエリアの地域包括支援センター、もしくは役所の担当窓口に必要書類を提出しましょう。詳しくはこちらをご覧ください。
地域により必要なものが異なるケースもありますが、「要介護認定・要支援認定申請書」「介護保険被保険者証」等の書類が必要になります。詳しくはこちらをご覧ください。




