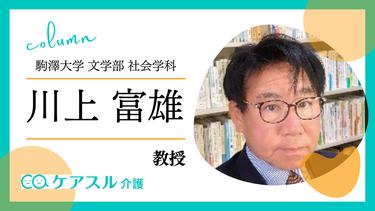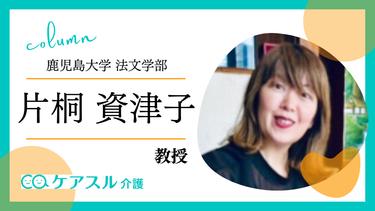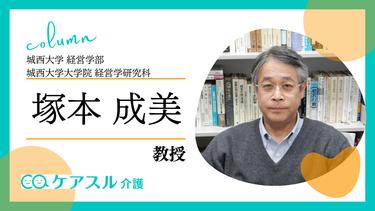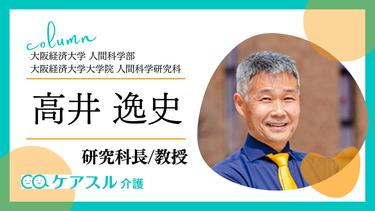人生 100年時代に対処する力
-Successful Agingを求めて-
今現在、先進国では、生まれてくる子供の50%超の確率で105歳以上生きるであろうと予測されている。我々の人生には「人生80年」ではなくして「人生100年」で設計し直す必要が喫緊の課題なのである。 今回は「人生100年時代」に対処する力という観点について解説します。 伊東 眞理子 特任教授/社会福祉学部長/同大学院研究科長 東京福祉大学 社会福祉学部 経済社会学会:常任理事、茶屋四郎次郎記念学術学会 […]