
認知症ケアを支える人材育成に向けて必要なこと
認知症の人を支える「人」の育成に向けて必要なことについて、お話させていただきます。 新井 恵子 教授 静岡福祉大学 社会福祉学部 健康福祉学科 介護福祉士/教員 日本介護福祉教育学会 日本認知症ケア学会 介護福祉士、介護支援専門員、認知症ケア専門士。介護福祉士養成施設を卒業後、介護老人保健施設の介護職(9年間)や訪問介護のサービス提供責任者を経験し、多くの認知症の人とかかわった。 現在は介護福祉士 […]

認知症の人を支える「人」の育成に向けて必要なことについて、お話させていただきます。 新井 恵子 教授 静岡福祉大学 社会福祉学部 健康福祉学科 介護福祉士/教員 日本介護福祉教育学会 日本認知症ケア学会 介護福祉士、介護支援専門員、認知症ケア専門士。介護福祉士養成施設を卒業後、介護老人保健施設の介護職(9年間)や訪問介護のサービス提供責任者を経験し、多くの認知症の人とかかわった。 現在は介護福祉士 […]

今回は、高齢者社会におけるヘルスプロモーションの現状と重要性についてお伝えいたします。 入江 由香子 准教授 大東文化大学 スポーツ・健康科学部スポーツ科学科 博士(健康福祉)、健康運動指導士、 パラスポーツ指導員上級 など 日本体育・スポーツ・健康学会、日本スポーツ産業学会、日本学校保健学会 など 福岡大学体育学部体育学科卒業。国立身体障害者リハビリテーションセンター学院リハビリテーション体育専 […]

今回は、高齢者の生涯学習とは何かをご説明しながら、主観的幸福感へのつながりについてもお話していきます。 髙橋 一公 教授/学部長 東京未来大学 モチベーション行動科学部 精神保健福祉士 臨床発達心理士 等・教員 日本心理学会 日本発達心理学会 日本老年臨床心理学会 等 明星大学大学院人文学研究科心理学専攻修士課程修了。一般企業にて適性検査の開発や安全教育活動に関する企画に従事後、立正大学非常勤講師 […]

介護を業務とする職種がはじめて成立したのは、1963年に制定された「老人福祉法」(昭和38年法律第133号)からである。その後、高齢化社会の進展により、2000年に介護保険制度が開始され、措置から契約へと移行し高齢者への介護サービスの質が一層問われることになった。介護保険制度の開始から24年が経ち、現在はサービスの質と共に介護人材の量を確保する必要に迫られている。 介護人材の確保の取り組みの一つに […]

一人暮らしをする高齢者は年々増加傾向にあります。本コラムでは一人暮らし高齢者向けのサービスやサポートについて解説します。 松﨑 吉之助 准教授 相模女子大学 人間社会学部社会マネジメント学科 社会福祉士・博士(学術) 日本社会福祉学会 日本地域福祉学会 日本認知症ケア学会等 大学卒業後に社会福祉士養成施設で学ぶ。その後、病院や地域包括支援センターで高齢者や家族等の相談業務に従事。仙台白百合女子大学 […]
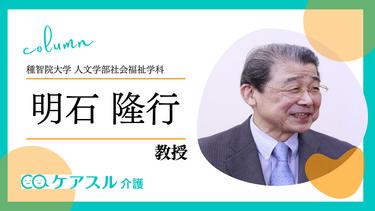
今回は、成年後見制度の仕組みなど、これだけは知っておきたいことについて事例を交えながらご説明いたします。 明石 隆行 教授 種智院大学 人文学部社会福祉学科 大学教員 日本社会福祉学会、日本地域福祉学会、種智院大学仏教社会福祉学会 1977年関西大学 社会学研究科 修士課程を修了(社会学修士)。種智院大学 仏教学部 助教授を経て2007年から人文学部教授。 大阪府市民後見人養成・活動支援事業企画委 […]

少子高齢化が進む中で、シニアの雇用を取り巻く状況は大きく変わった。2021年4月から施行されている改正高年齢者雇用安定法は、企業に対し、65歳までの雇用機会確保に加え、70歳までの就業機会確保に努めるよう求めている。 既に、60歳以降も働くことが当たり前となっており、総務省の労働力調査(2023年)によると、また、60代前半層の4人に3人、60代後半層の2人に1人が働いている。 このような中、シニ […]

私たちにとって、コミュニケーションは大変重要です。有益な情報を手に入れたり、自分の気持ちを相手に伝えたりする役割に留まらず、良い人間関係を作るためにも、コミュニケーションは基盤となるでしょう。 ここでは、我が国が直面している高齢社会で、高齢者と、ご家族、異なる世代の人、看護や介護に携わる専門職とのコミュニケーションに焦点を当て、望ましいコミュニケーションの3つのヒントをご紹介したいと思います。 長 […]

今回は、私が学んだタクティールタッチ®の方法や効果、そして手で触れることの意味についてお話しいたします。 荒木 実代 教授 神戸医療未来大学 人間社会学部 未来社会学科 教員/介護福祉士、タクティールタッチセラピスト 日本臨床教育学会、武庫川臨床教育学会、日本看護福祉学会、日本介護福祉学会 武庫川女子大学大学院 臨床教育学研究科 修士課程修了(臨床教育学修士)後、近畿医療福祉大学 社会福祉学部 生 […]

昨今、世界的に介護人材が不足してる中で、日本も選ばれる側になっています。そのような状況の中で日本を選び、介護士として働いてくれている外国人介護士について簡単にお話しいたします。 小平 達夫 准教授 富山短期大学 健康福祉学科 産業・組織心理学会、経営行動科学学会、日本レセプト学会、日本介護経営学会 立命館大学大学院人間科学研究科後期博士課程修了 博士(人間科学) 富山大学大学院人文科学研究科修士課 […]

今回は、フレイルについてご説明いたします。高齢期に自立した活力ある生活をしていくために、ぜひこの記事を読んでいただき、フレイルチェックを利用してみてください。 岸本 裕歩 准教授 九州大学 基幹教育院 大学教員 日本健康支援学会、日本運動疫学会、日本体力医学会、日本地域政策学会 2010年に九州大学大学院人間環境学府にて博士(人間環境学府)、2017年には同大学院医学研究院にて博士(医学)を取得。 […]

少子高齢化に伴い、介護施設の需要は年々増加傾向にあります。今回は、「大事に介護してくれる」老人ホームの選び方のポイントについて解説します。 大坪 勇 教授 羽衣国際大学 人間生活学部 人間生活学科 日本福祉学会 佛教大学大学院社会学研究科社会福祉学専攻博士前期課程修了後、八日市市社会福祉協議会福祉活動専門員、特定医療法人野洲病院医療ソーシャルワーカー、総合保健福祉施設ケアタウン南草津総長、大垣女子 […]

もしもの時のためにあなたが望む医療やケアについて前もって考え、家族や医療ケアチームと繰り返し話し合い共有する仕組みをアドバンス・ケア・プランニングと言います。 近年、厚生労働省が「人生会議」(ACP:アドバンス・ケア・プランニング)と名付け、普及・啓発を始めています。 国民向け普及・啓発事業 ~人生会議について考えるきっかけをつくるためにVol.1 (https://www.youtube.com […]

今回は糖尿病と上手にお付き合いするための外来看護師からのヒントについてお話しさせていただきます。 外来の看護師は、糖尿病や高血圧などの慢性疾患をお持ちの患者さんやご家族の方と長いお付き合いとなると考え、いっしょに「いい年齢」を重ねていきたいと思っています。受診と受診の間の出来事や他の医療機関でのお話しなどを聞かせてくださるとうれしいのです。 渡辺 美和 講師 日本赤十字北海道看護大学 成人看護学( […]

少子高齢化に伴い、介護にかかる費用は安いものではありません。今回は低所得高齢者の為の支援制度について紹介します。 綾部 貴子 教授 梅花女子大学 情報メディア学科 社会福祉士・介護福祉士・教員 日本ケアマネジメント学会、日本介護福祉学会、日本在宅ケア学会 施設および在宅ケアや成年後見人の実践を経験。おおさか介護サービス相談センター専門相談員。研究テーマは、ケアマネジメント(障がい者・要支援要介護高 […]

日々の口腔ケア・歯科治療は大切です。本コラムでは、認知症の方の口腔ケア・歯科治療における重要性や介護者による対応方法について解説します。 森本 佳成 教授 学校法人神奈川歯科大学 全身管理歯科学講座 高齢者歯科学分野 日本歯科麻酔学会、日本口腔外科学会、日本有病者歯科医療学会、日本障害者歯科学会など 福岡県立九州歯科大学卒業後 奈良県立医科大学口腔外科にて、口腔外科、有病者歯科、障害者歯科診療に従 […]
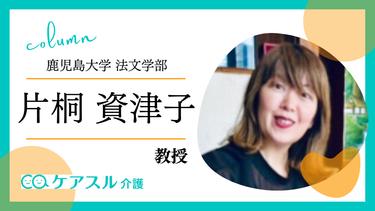
介護を必要とするような高齢期においても、自分らしさをもち、心からの幸せと満足感を維持できるでしょうか。こうした内面的な充実感を、主観的ウェルビーイングと呼びましょう。この概念は、世界保健機構(WHO)が健康の定義に用いるもので、身体的、精神的、社会的に良好な状態を意味しています。高齢者がどのようにして自己表現を通じてウェルビーイングを保っているのか、とりわけ人生の装い物語を通じて、その秘密を解き明 […]

老年期のケアにおいて重要なことは,年齢を重ね心身の変調を抱えながらでも,長寿を自分らしく人生の統合に向けていきいきと生き抜くこと,長い人生を自分なりに納得して終えることができるように支援していくことであると考えています。 本コラムでは、初期認知症の人が「人生の統合」を目指すためのケアについて解説します。 木谷 尚美 教授 富山県立大学 看護学部 看護師/保健師 日本老年看護学会,日本認知症ケア学会 […]

みなさんは、「社会福祉」という言葉を聞いて、何かイメージが浮かぶでしょうか?「社会福祉」という言葉は千差万別に捉えられ、なかなか一言で言い表すことは難しいのが本当のところだと思います。 そこでここでは、みなさんが自分なりの「社会福祉とは」というイメージを膨らますことができるように、社会福祉についてまずは“我が事”として考えてみるきっかけとなることを目標に紹介していきたいと思います。 橋本 拓 助教 […]

皆さんは、「ヘルスプロモーション」という言葉をご存じでしょうか。本コラムではヘルスプロモーションとは何か。という事から、地域で行われている事例も含めて紹介します。 丸山 裕司 教授 東海学園大学 スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 理学療法士・社会福祉士・精神保健福祉士・介護支援専門員・健康運動指導士 日本体力医学会、日本体育・スポーツ・健康学会、日本公衆衛生学会、日本健康教育学会、日本理学療 […]

少子高齢化が問題視されてる現代において、介護者の高齢化も深刻です。今回は障害者の高齢化という観点から、そのご家族の高齢化による支援の展望について解説します。 岡田 圭祐 講師 浦和大学 社会学部 総合福祉学科 修士(福祉社会学) 障害者支援施設にて3年間勤務。城西国際大学大学院人文科学研究科福祉社会専攻修士課程修了の後、介護福祉士を養成する専門学校で教務主任として4年間勤務。2008年より浦和大学 […]

介護現場が抱える課題は様々です.今回は、「人手不足の解消と質の高い介護サービスを提供するには」という観点で解説します。 大工谷 新一 学科長・教授 北陸大学 医療保健学部 理学療法学科 博士(スポーツ科学) 理学療法士,日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー/教員 1991年に京都大学医療技術短期大学部理学療法学科を卒業後,一般病院と専門学校に勤務したのち,一般病院のリハビリテーション部長お […]

少子高齢化が深刻な現代では、高齢者と若者がより良い関係を築いていくことは大切な事です。本コラムでは高齢者と若者が共生するより良い社会を目指すために実例を含めて解説します。 齋藤 征人 教授 北海道教育大学 函館校 国際地域学科 社会福祉士 日本社会福祉学会・日本地域域福祉学会・日本教育支援協働学会 など 北海道医療大学大学院看護福祉学研究科博士課程を単位取得満期退学後、高知女子大学、帯広大谷短期大 […]

デザインにおいて高齢者が住み続けられるまちをつくるためにできることといえば、バリアフリーやユニバーサルデザインがあります。皆さんはバリアフリーやユニバーサルデザインという言葉を一度は聞いたことがあると思いますが、改めて確認してみましょう。 岩瀬 大地 教授 東京造形大学 造形学部 TZU DESIS Lab.ディレクター、一般社団法人Spedagi Japan理事、タイ国立キングモンクット工科大学 […]

人手不足が深刻な福祉業界において、介護を手助けする機器の存在は不可欠です。今回は、高齢者を支援する医療福祉機器のメリットや可能性について解説します。 井上 淳 教授 東京電機大学 工学部 機械工学科 日本機械学会、日本生活支援工学会、ライフサポート学会、看護理工学会 早稲田大学先進理工学研究科にて博士号取得後、東京電機大学 未来科学部 ロボット・メカトロニクス学科助教、東京電機大学 工学部 機械工 […]

成年後見制度は、ご本人やご家族にとってもメリットが大きい制度といえます。家庭裁判所から選任された成年後見人等(主に法定後見人を指します)は、預貯金の管理や各種機関などの契約手続きなどをご本人の代わりに行い、未然に不利益になることを防ぎます。一方では、成年後見人等に費用が掛かるなどのデメリットもあるといわれています。 今回は、成年後見制度の概要と活用方法について皆さんと考えていきたいと思います。では […]

はじめに ~地域包括ケアシステムとは~ 地域包括ケアシステムとは、重度な要介護状況になった後も、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最期まで送ることができるよう、「住まい・医療・介護・予防・生活支援」の一体的な提供を目指すものです。特に、医療と介護の連携が盛り込まれた点や、要介護状態になる前の予防が重視されている点が特徴です。一般的に介護施設の利用は75歳を超えると増える傾向にあり、団塊の世代(第1 […]

「Sarcopenia(サルコペニア)」という言葉を聞いたことがありますか。これは、1989年に,Irwin Rosenbergによって提唱された造語です1)。ギリシャ語で筋肉を意味する「サルコ(sarx/sarco)」と減少・喪失を意味する「ペニア(penia)」を合わせた言葉です。高齢期にみられる筋肉の量の減少と筋肉の力の低下もしくは筋肉の機能の低下と定義されています2)。 日本におけるサルコ […]

今回は、統計学による高齢者介護の分析について簡単にご紹介させていただきます。 菅原 慎矢 准教授 東京理科大学 経営学部 ビジネスエコノミクス学科 資格:教員/学会:日本経済学会、日本統計学会、医療経済学会 東京大学大学院経済学研究科で博士号取得後、同研究科助教、東京大学大学院情報理工学系研究科特任助教を経て現職。専門はベイズ統計学、高齢者介護の経済データ分析。 最近の論文に、本校でも紹介したSu […]