親の高齢になるにつれて、いつかは訪れる「介護」の問題に頭を悩ませる方々も少なくありません。
まだ元気だと思っていた親が介護が必要になると心配の反面、どうすれば良いのか分からないという不安を抱えてしまうこともあるでしょう。
「親の介護で知っておきたいポイントにはどんなものがあるの?」
「仕事も大切だから、なるべく負担が掛かることなく親の介護を進めたい」
そんな思いをお持ちの方々のため、今回は親の介護で知っておきたいポイントをはじめ、兄弟との付き合い方、これから起こり得る注意点、利用できる介護サービスまでを徹底解説して行きます。
親の介護には義務がある!放棄はできない
子供には、親の介護について努力する義務があります。
というのも民法877条第1項では「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定められているためです。
したがって扶養義務を負っている子供や義理の息子・娘は社会的地位や収入などに応じた生活ができる範囲で、生活に困っている親を支援することには義務がある言えるでしょう。
ちなみに扶養義務があるのにも関わらず、親の介護を放棄した場合は保護責任者遺棄罪に該当し3カ月以上5年以下の懲役に科される可能性があります。
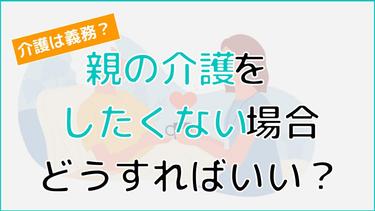
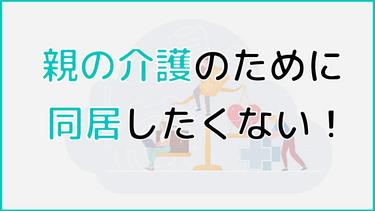
また老人ホーム・介護施設をお探しの方は、ケアスル 介護で相談してみることがおすすめです。
ケアスル 介護では全国で約5万もの施設から、入居相談員がご本人様・ご家族様のご要望にぴったりの介護施設を紹介しています。
「幅広い選択肢から納得のいく施設を探したい」という方は、まずは無料相談をご利用ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
親の介護が始まるのは平均75歳から
厚労省の調査によると、親の介護が始まるのは親の年齢が平均75歳に達したときと言われています。
もちろん介護が始まるタイミングは、親の身体状況や生活環境によって異なります。
しかし現状では80歳を過ぎたころには5人に1人が「要介護」の認定を受けているため、やはり75歳を過ぎると介護をする可能性が高くなってくると言えるでしょう。
親の介護で知っておきたいポイントは大きく分けて4つ!
今後いつか訪れるかもしれない「親の介護」について、知っておきたいポイントは以下の4つです。
- 費用面の問題
- 兄弟間のトラブル
- 在宅介護が施設介護がを巡る問題
- 自分の生活との両立に関する問題
次項からはそれぞれのポイントについて詳しく解説して行きます。
親の介護で知っておきたいポイント①費用面の問題
本章では、気になる親の介護のお金についてを解説します。
親の介護の費用はいくら?誰が払う?
生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」によると、親の介護の月々の平均費用は自宅で介護をする場合で4.8万円、施設で介護を受ける場合で12.2万円です。
ちなみに親の介護にかかる費用であれば、親の年金や貯蓄から切り崩して払っていくのが基本です。
厚生労働省の「2019年国民生活基礎調査」によると、「介護を要するもの(本人)」が負担しているという世帯が全体の87.1%です。つまり、ほとんどの世帯では本人が支払っていることがわかります。
| 介護を要するもの(あるいは配偶者)の収入 | 介護を要するもの(あるいは配偶者)の貯蓄 | 介護を要するもの(あるいは配偶者)以外の収入・貯蓄 | ||
| 総数 | 年金・恩給の収入 | そのほかの収入 | ||
| 73.60% | 72.20% | 7.10% | 13.50% | 9.10% |
しかしそもそも親の貯蓄が足りなかったり、保険や年金などからも賄えない場合は、子や親族が金銭的な援助を行うこともあります。
デリケートな部分ではありますが、親の介護が始まる前には親の金銭状況を把握しておくことは大切であると言えるでしょう。
親の介護の費用が払えない時は減免制度を活用しよう!
介護費用が払えない場合の対処法としてまず挙げられるのは、公的な減免制度を利用することです。
例えば高額介護サービス費支給制度とは、介護サービスを利用して支払った自己負担が高額になった場合、上限額を超えた分が払い戻される制度です。
収入の合計が80万円に満たない方や、老齢福祉年金を受給している方などは、自己負担額を15000円にまで抑えることができる場合もあるため、大きな支えになると言えるでしょう。
具体的な区分については以下の表のとおりです。
| 区分 | 区分 | 負担の上限額(月額) |
|---|---|---|
| 市町村民税課税世帯 | 課税所得690万円(年収約1160万円) | 140,100円(世帯) |
| 課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1160万円)未満 | 93,000円(世帯) | |
| 市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) | |
| 市町村民税非課税世帯 | 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 24,600円(世帯) |
| ・合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方・老齢福祉年金を受給している方 | 24,600円(世帯)15,000円(個人) | |
| 生活保護を受給している方 | ー | 15,000円(世帯) |
親の介護で生活保護を受けることはできる!
そのほかお金が無くて介護費用を払えば生活が維持できないという場合は、生活保護を受けることも手段のひとつです。
生活保護を受けるためには、国の定めた受給の条件である以下のようなものを満たす必要があります。
- 世帯収入が厚生労働省の定める最低生活費に満たない方
- 高齢や障害などのやむを得ない事情で、働いて収入を得ることができない方
- 生活の援助をしてくれる親族がいない方
- 資産を所有していない方
生活保護を受けると、必要な介護は介護扶助により自己負担なしで受けられるほか、細かい条件はありますが老人ホーム・介護施設にも入居することが可能です。
生活保護を受けるかでお悩みの方は、まずは地域包括支援センターや役所などの公的機関に相談し、気負わずに情報収集してみましょう。
親の介護で知っておきたいポイント②兄弟間のトラブルが起こりやすい
本章では親の介護で起こりやすい兄弟間のトラブルについて解説して行きます。
親の介護で兄弟間の不公平を感じる人は多い
長崎大学が実施したアンケート調査によると、全体の19.8%が「ほかに介護を分担してくれる家族がいない」と回答していることがわかります。(出典:長崎大学「介護状況の把握に関するアンケート調査結果 」)
親の介護において、兄弟間の不公平が生まれる理由としては以下のようなものが挙げられます。
- 親の近くに住んでいるからという押し付け
- 結婚して子供がいるからという介護の放棄
- 長男だから・長女だからという押し付け
- 役割分担がうまくいっていない
確かに兄弟には各々の生活の事情があり、介護の責任を均等に割り振ることは難しいかもしれません。
しかしだからと言って、誰か兄弟の誰かひとりに介護を押し付けて良い理由などあるはずがないのです。
物理的な距離が遠くて介護ができない人は金銭的な援助を多めにするなど、兄弟間で話し合いのうえバランスを取ることが大切だと言えるでしょう。
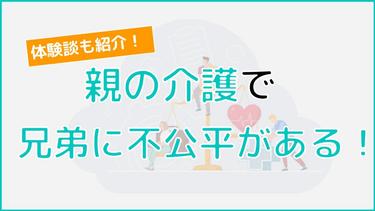
親の介護を兄弟で協力して行うには?
親の介護を兄弟でうまく分担するには、以下のポイントを抑えておくことが重要です。
- 兄弟間で親の介護についての本音を話し合う
- 親の経済状況を確認しておく
- 経済的援助・生活介助など具体的な役割分担をする
前述のとおり、親の介護で不公平が起こる原因は「経済的な余裕がない」「物理的に距離が遠い」理由がさまざまです。
したがって、それらの理由によって兄弟間の分担の方法が変わってきます。
例えば、「経済的な余裕がない」場合であればほかの兄弟が金銭面の負担を多くすることにより、身体介助面を別の兄弟が請け負ってくれるかもしれません。
兄弟間で「何ができるのか・できないのか」をしっかりと話し合いましょう。
親の介護は長男や末っ子などで責任は変わらない
親の扶養義務は子供全員にあり、法的にも責任の重さに兄弟の順番は関係ありません。
相続においても長男・長女だからと言って優遇されることはなく等分で分けられるのです。
古い考え方で「長男が介護をするのが当たり前」という主張をする方もいますが、このような押し付けを鵜呑みにする必要はありません。
兄弟の順番は関係ないことであると話合い、兄弟間で適切な役割分担をしていきましょう。
親の介護で家族や親からお金をもらうのは普通
事情があって親の介護をほとんどひとりで引き受けている場合などは、親本人もしくは他の兄弟からお金をもらうことは普通であると言えます。
そもそも介護は自分の時間が取れないなどの精神的な負担や、介助での身体的な負担、サービスの利用などで経済的な負担などのさまざまな負担が掛かるものです。
たとえ親であっても自分の時間や体力を削って捧げている介護に対して、お金をもらうことはおかしくはないのです。
しかし、親からもらったお金が原因で相続の際などにほかの兄弟とトラブルになることがあるため注意が必要です。
ひどいケースでは「認知症の親を言いくるめてお金をもらったのではないか」「勝手に貯金を使い込んだのではないか」と難癖をつけられることもあります。
親から日常生活の世話をしてくれる感謝の気持ちとしてお金をもらっている場合は、その事実を周りの兄弟にオープンにしておくことが大切と言えるでしょう。
一人っ子で親の介護をするときは頼れる相談先を作っておこう!
一人っ子で親の介護を行う場合は、叔父や叔母などの介護義務がある親族に協力を求めることもひとつの手です。
しかし、叔父や叔母の場合はすでに仕事をリタイアしていて金銭的にも体力的にも介護を行うことが難しい場合もあるため、援助を求めるにしても配慮のある対応を心がけましょう。
そのほか介護のサービス利用などで悩んだ場合は、地域包括支援センターや市役所の介護課などの公共機関に相談することが大切です。
いずれにせよ、一人で抱え込まずになるべく身の回りからの力を借りることが重要だと言えるでしょう。

親の介護で知っておきたいポイント③在宅介護が施設介護がを巡る問題
本章では、親の介護でよくある在宅介護と施設介護はどちらが良いのか?について解説して行きます。
親の介護は在宅と施設どちらが良い?
親本人や家庭の事情があるため一概には言えませんが、費用を抑えたいなら在宅介護。安心のサポートを受けたいのならば施設介護という選び方が多いと言えます。
在宅介護の平均月額費用は4.8万円に対し、施設介護は12.2万円と大きく金額が変わることは事実です。
しかしその反面で在宅サービスでは24時間の見守りを行うことはできないため、必然的に介護をする家族の負担は重くなる傾向にあります。
一方で施設介護は身体介助や安否確認をはじめ、安心の介護サービスを受けることができ、家族の負担は格段に軽くなるでしょう。
しかし、施設によって必要な費用が異なったり、なかなか希望の施設が見つからないというデメリットもあります。
親の介護をどこでするのかを考えるときは、親や家族の生活スタイルや金銭状況を加味したり、介護の専門家であるケアマネージャーに相談したりとよく考えることが大切です。

親の介護で辛いのは身体的・精神的ストレスの両方
親の介護度にもよりますが、「親の介護で辛いこと」でよく挙がるのは以下のような項目です。
- 四六時中で目が離せない
- 介護によって身体的負担がかかる
- 本人や親族から文句を言われる
- 介護費用に対する経済的ストレス
介護度が重くなると、認知症の症状が出たり排泄などで深夜に頻繁に起こされることがあったりするため、家族は休む時間も確保できないこともあります。
そのほか役割分担が上手くいっていないと親や兄弟から一方的な意見を押し付けられたり、費用が足りないことによる経済的ストレスを感じることも多いです。
介護で限界を迎えないためには、前もって兄弟で話し合いを行ったり、介護サービスの正しい活用が大切と言えるでしょう。
在宅介護を行う場合はデイサービスや訪問介護を利用する人が多い
在宅介護を行う人が利用できるサービスとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 訪問介護:介護福祉士などが自宅を訪問し、入浴や排せつ、食などの介護サービス、そのほかの日常生活を送るうえで必要となる家事などの援助を行う。
- 通所介護(デイサービス):介護施設やデイサービスセンターなどに通い、食事や入浴、排せつなどの介助、リハビリテーションやレクリエーションを行う。
- 短期入所生活介護(ショートステイ):施設に最大で30日間まで入所し、食事や入浴、排泄などの介助をはじめ、日常生活上の世話やリハビリを行う。
一般的にはデイサービスを週2回、訪問介護を3回ほど利用しながら、家族がどうしても外せない用事があるときに短期入所生活介護(ショートステイ)を利用する方が多いです。
もちろん、利用できるサービスは他にも存在します。例えば要介護認定において要介護1の認定を受けている方は、必要に応じて以下のようなサービスを利用することができます。
| サービスの種類 | サービス内容 | |
|---|---|---|
| 訪問サービス | 訪問介護 | 訪問介護員が自宅を訪問し、食事・排せつ・入浴などの介護や掃除・洗濯・買い物などの生活支援を行う |
| 訪問入浴介護 | 介護・看護職員が自宅を訪問し、持参した浴槽で入浴の介護を行う | |
| 夜間対応型訪問介護 | 24時間安心して過ごせるよう、夜間帯にも対応している訪問介護サービス。 安否確認や排せつの介助等を行う「定期巡回型」と、転倒した際や急な体調不良等の有事の際に介護をする「随時対応型」の2つに分かれている。 |
|
| 訪問看護 | 看護職員が疾患のある利用者の自宅を訪問し、主治医の指示に基づいた療養上の世話や診察の援助を行う | |
| 定期巡回・随時対応型訪問 介護看護 |
「定期巡回型」と「随時対応型」の両方に対応しており、訪問介護だけでなく訪問看護も組み込まれているサービス | |
| 訪問リハビリ | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等の専門スタッフが自宅を訪問し、心身機能の維持・回復や日常生活の自立に向けたリハビリを行う | |
| 居宅療養管理指導 | 医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士等の専門家が自宅を訪問し、療養上の管理・指導を行う | |
| 通所サービス | 通所介護(デイサービス) | 介護施設に通い、介護・生活援助・機能訓練等のサービスを受けることができる日帰りのサービス。自宅と施設までは送迎してくれる。 |
| 通所リハビリ(デイケア) | 病院・老健・診療所等に通い、専門スタッフによる機能訓練・日常生活動作等のリハビリを受けることができる。食事や入浴といった生活援助の提供もある。 | |
| 認知症対応型通所介護 | 認知症の方を対象とした通所介護サービス。 | |
| 地域密着型通所介護 | 定員18人以下の施設で、入浴や食事などの介護や機能訓練等のサービスを受けることができる。定員が少ないため、一人ひとりに寄り添った対応が可能。 | |
| 療養通所介護 | 常に看護師による観察が必要な方を対象にしたサービス。医師や訪問看護ステーションと連携して食事・入浴などの日常生活支援、機能訓練が提供される。 | |
| 短期入所サービス | 短期入所生活介護 (ショートステイ) |
介護施設に短期間入所し、介護・生活援助・機能訓練等のサービスを受けることができる。1度で最大30日までの利用が可能。 |
| 短期入所療養介護 (ショートステイ) |
老健や介護医療院といった医療体制が整っている施設に短期間入所し、介護・生活援助に加え、医療処置や看護等の医療サービスを受けることができる。1度で最大30日までの利用が可能。 | |
| 複合型サービス | 小規模多機能型居宅介護 | 施設への通いを中心として、訪問・短期入所サービスを組み合わせ、介護・生活援助・機能訓練等のサービスを受けることができる。 |
| 看護小規模多機能型 居宅介護 |
小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせたサービス。 | |
| 施設サービス | 老健(介護老人保健施設) | 利用者の在宅復帰を目的とした施設。介護・看護・生活援助・リハビリ等のサービスを受けることができるが、原則3~6か月で退所しなければならない。 |
| ケアハウス | 自立した生活が難しい高齢者の方を対象とした、少ない費用で介護・生活援助等のサービスが受けられる施設。 | |
| 介護療養型医療施設 | 比較的重度の要介護者を対象とした、充実した医療処置・リハビリ等のサービスが受けられる施設。 | |
| 介護医療院 | 介護療養型医療施設で受けられるサービスに加え、介護や生活援助にも力を入れている施設。 | |
| 有料老人ホーム | 食事・介護・生活援助・健康管理のうち1つ以上を提供している施設。24時間介護サービスを受けることができる「介護型」、生活援助を中心に受けることができる「住宅型」等の種類がある。 | |
| サ高住(サービス付き高齢者向け住宅) | 「安否確認」「生活相談」等のサービスを受けることができるバリアフリー対応の施設。 | |
| グループホーム | 認知症の方を対象とした、少人数での共同住宅の形態でサービスを受けることができる施設。 | |
| 福祉用具の 利用サービス |
福祉用具の貸与 | 車いすや介護ベッド等の福祉用具をレンタルすることができるサービス。 |
| 福祉用具の販売 | 簡易浴槽や入浴補助用具等の福祉用具を購入することができるサービス。 | |

親がデイサービスなどを嫌がるときは?
親がデイサービスを嫌がる場合もあり、その理由としては「どんな場所なのかわからない」「慣れない環境に行くのが不安」というものが多いです。
そんなときは「ここなら通いたい」と思えるデイサービスを見つけられると良いでしょう。
現在の日本は高齢化が進み、デイサービスの需要が高まっています。結果、事業所数も増え、差別化が進んでいる状況です。
参考程度に高齢者に「通いたい」と思ってもらいやすいデイサービスの特徴としては、以下のようなものが挙げられます。
- 料理や趣味に力を入れている
- 運動や機能訓練が充実している
- お料理がおいしい
- お風呂が充実している
本人の気持ちや本人の趣向に沿ったデイサービスを選択できます。通いたくなるところを見つけると、デイサービスへの意欲が高まるでしょう。
老人ホーム・介護施設の種類はさまざま
老人ホーム・介護施設は、公的機関が運営する公的施設と各種法人や株式会社が運営する民間施設の2種類があります。
公的施設の場合は比較的費用が安くなる場合もありますが、待機者が多く入居待ちとなることもあるので注意が必要です。
民間施設はプライバシーが確保された自由度の高い生活が送れますが、月額の利用料が高額になる傾向にあります。
以下の表は、高齢者施設の種類ごとの費用一覧です。
| 運営 | 名称 | 初期費用(入居一時金・敷金) | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
| 公的 | 特別養護老人ホーム(特養) | なし | 5~15万円 |
| 老人保健施設(老健) | なし | 6~17万円 | |
| 介護療養型医療施設(療養病床) ※2024年3月末に完全廃止 |
なし | 6~17万円 | |
| 介護医療院 | なし | 6~17万円 | |
| 民間 | グループホーム | 0~100万円 | 12~18万円 |
| 住宅型有料老人ホーム | 0~数千万円 | 10~35万円+介護費用 | |
| 介護付き有料老人ホーム | 0~1億円 | 10~40万円+介護費用 | |
| サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) | 0~数十万円 | 8~20万円+介護費用 | |
| ケアハウス(軽費老人ホーム) | 0~数百万円 | 8~20万円+介護費用 |
また「もうすこし施設や選ぶ手順について知りたい」という方は、以下の記事をご覧ください。
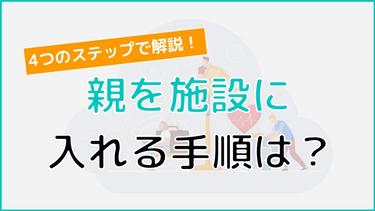
親を施設に入れるタイミングは「家族が身体的な限界を感じたとき」が多い
内閣府の世論調査によると親を施設に入れた理由としては、「家族の肉体的負担を減らすため」が全体の71.9%と最も多く、次に「家族の精神的負担を減らすため」で61.6%と介護者の負担がタイミングとして最も多いという結果になりました。
例えば、介護者である子供が腰などを痛めて介護ができなくなった場合、過度な身体的な疲れから介護者である子供が入院してしまい介護者がいなくなってしまった時などが挙げられます。
もちろん、家族が体調に不調をきたすまで在宅介護を続けることは良いことではないため、負担が肥大化しないうちに施設の利用を検討することをおすすめします。
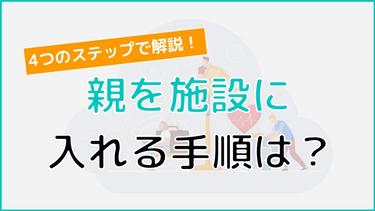
親を施設に入れるまでの手順は?
親を施設に入れるまでの手順は以下の5ステップです。
- 本人・家族で話し合う
- 施設の情報を収集する
- 条件に合った施設を選ぶ
- 施設の見学・体験入居
- 契約して入居する
実際に施設に入居するのは親本人なので、認知能力が衰えていない場合は親を含めて話し合いをしておくことが重要です。
場合によっては本人が施設への入居を拒んでしまう場合もありますが、その場合は在宅介護が難しくなってきていることや施設に対するイメージや先入観などを親の気持ちに寄り添いながら慎重に対応説得しましょう。
その後立地や費用、受けられるサポートなどの必要条件をまとめて施設を選ぶことが大切です。
入居してからなるべくギャップを感じることがないように、施設の見学や余裕があれば体験入居をしてみることをおすすめします。
契約・入居の際には、戸籍謄本や住民票に加えて健康診断書や診断情報提供書などの現在の身体の状況を把握することができる書類の提出が必要となることに注意しましょう。
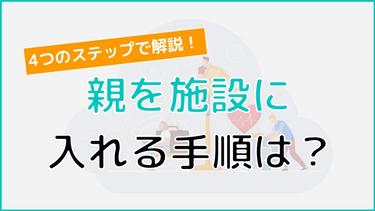
親を施設に入れて後悔した人は少ない
実際のところ、家族が親を介護施設に入れたことを後悔しているというケースは多くありません。
というのも2016年に行った調査では、家族が介護施設へ入居した人200名のうち、約9割もの人が何らかの不安を感じていましたが、そのうち約6~7割の人が入居後に解消されたと回答したのです。
したがって、親を介護施設に入れる前には不安感を抱いてる方は多いものの、最終的に自分の選択に後悔された方は少ないと言えます。
また「老人ホームに入居したいけど、施設が多すぎて何から手を付けていいか分からない」という方は、ケアスル 介護で相談してみることがおすすめです。
ケアスル 介護では、入居相談員が施設ごとに実施するサービスや立地情報などをしっかりと把握した上で、ご本人様に最適な施設をご紹介しています。
「身体状況に最適なサービスを受けながら、安心して暮らせる施設を選びたい」という方は、まずは無料相談からご利用ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
親の介護で知っておきたいポイント④自分の生活との両立に関する問題
本章では親の介護でよく問題となる、自分の生活との両立について解説して行きます。
親の介護と自分の生活を両立するには?
親の介護と自分の生活を両立するには、時間面・精神面・費用面の負担を軽減していく必要があります。
具体的な対処法の例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 時間面:介護休業制度などの公的な制度を利用する、ショートステイを利用する
- 精神面:話しやすい相手に愚痴や悩みを聞いてもらう、介護保険外のサービスを利用してリフレッシュする
- 費用面:公的な軽減制度を利用する、費用の安い老人ホームを探す
どうしても親の介護と自分の生活が難しくなったという方は地域包括支援センターやケアスル 介護の相談窓口で相談してみることも大切な手段のひとつです。
親の介護で退職することも増えている
厚生労働省の調査によると「介護・看護」を理由に退職している人の数は2017年には約9万人に増えており、2007年と比較すると数が2倍に増えていることがわかっています。
理由としては以下が挙げられます。
- 介護と仕事の両立が体力的に難しかった
- 施設への入居を拒否された
- 自分以外に介護をする人が身内にいなかった
しかし親の介護で退職することは、もちろん一定のリスクが伴います。
収入が断たれるため切り詰めた生活を強いられることになるほか、施設への入居もさらに難しくなってしまいます。
親の介護を理由に退職を検討する場合は、その前に利用できる制度や介護サービスがないか確認し後悔のない選択をすることが大切です。
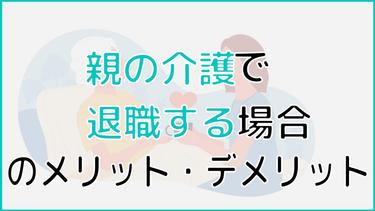
介護サービスのほか介護休業制度を使うという手段もある
親の介護と自分の仕事や私生活との両立ができない場合は、以下のようなサービス・制度を検討してみることもひとつの手段です。
- 介護休業制度:対象家族1人につき3回まで通算93日まで休業することができ、給付金として給与の67%が支給される制度。
- 短期入所生活介護(ショートステイ):施設に最大で30日間まで入所し、食事や入浴、排泄などの介助をはじめ、日常生活上の世話やリハビリを行う。
これからの日本は高齢者が増えていくため、家族が介護をサポートしなければならない状況が増えると予測されます。
あらかじめ、自分の親の介護への関わり方を意識して、介護休業制度の内容を理解しておくといいでしょう。
シングルマザーで親の介護をしなければならない時はどうすれば良い?
シングルマザーは子育てと仕事をこなさなければならないため、親の介護まで両立するとなると、心身の負担が大きくなってしまうでしょう。
そんなときは、可能な限り介護サービスを利用して負担を軽減するほかに、.介護について相談できる窓口を確認しておくことがおすすめです。
少しでも身体的・精神的な余裕を持つために活用できる窓口では、積極的に相談していくことが大切です。
| 地域包括支援センター |
|
|---|---|
| かかりつけの医療機関 |
|
| 市区町村の介護保険の担当窓口 |
|
親の介護で自分が遠方に住んでいる場合はどうすれば良い?
親の介護で自分が遠距離に住んでいる場合は、無理に親の元に帰る必要はありません。
というのも厚生労働省の「2019年国民生活基礎調査」によると、別居の家族が介護を行う割合は2016年に12.2%、2019年に13.6%と発表しています。
要介護者の単独世帯も増加しており、遠距離介護が可能であると言えるでしょう。
しかし一方で、同居介護に比べて交通費や通信費の費用がかさむなどのデメリットもあります。
親の介護が必要になり遠距離の土地から親の元に戻るかは、親や家族との話し合いや自分の気持ちを向き合ったうえで慎重に決めることをお勧めします。

親の介護で限界を感じたときは、やはり介護施設への入居
在宅介護をどれだけ頑張っても、いつかは家族の手に負えなくなる時が来ます。
限界を迎えた場合は、根本的なストレスを解消することが必要です。その手段としては、やはり介護施設に入所することでしょう。
しかし、「介護施設を利用したいけどお金がない…」「親が嫌がって話を聞いてくれない…」という悩みもあると思います。
そんな時は前述の公的な減免制度を活用したり、ケアスル 介護の窓口で費用の安い老人ホームを提案してもらうことがおすすめです。
また親が嫌がる場合は、子供から「いつまでも元気でいてほしいから施設に入ってもらいたい」といった愛情を伝えたり、本人の友人など第三者からの話をしてもらうのも手段のひとつです。
特に「子供が介護するのが当たり前」と考えている親を説得するのは難しいですが主治医などに協力してもらい、「これ以上はプロによる介護が必要である」と認識してもらうことも大切だと言えます。
親子ともに健康で生きていくためにも、自分のストレスに正直に向き合うことが大切であると言えるでしょう。
親の介護のために今から親と話し合うことは大切!
親の介護では、親自身がこの先をどう暮らしたいかという意思が何より大切になります。
というのも、介護は突然必要になることがあるためです。
いざ親の介護について子が何かしらの決断を迫られたとき、親の思いに基づいた判断ができたか否かで子どもが抱える不安の大きさはかなり異なるでしょう。
たとえば映画やテレビなどを見た後に、「人生の最期はどこで過ごしたい?」などの話をしてみると良いかもしれません。
人によっては「認知症で子供に迷惑をかけるくらいなら施設に入れて欲しい」「身体が動かなくなってまで長生きしていようとは思わない」とお思いの方もいらっしゃいます。
多少重い話にはなりますが、老後の親の人生観を聞いておくことは後々大きな価値となる可能性があると言えるでしょう。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
まとめ
子供には親の介護について努力する義務があり、自分の社会的地位や収入などに応じた生活ができる範囲で、生活に困っている親を支援することが必要となります。
親の介護の負担を抑えるために知っておきたいポイントとしては、以下の4点が挙げられます。
- 費用面の問題
- 兄弟間のトラブル
- 在宅介護が施設介護がを巡る問題
- 自分の生活との両立に関する問題
親の介護では兄弟間での介護の押し付け合いが起こることが多いですが、介護に対しての義務は全ての兄弟に平等に発生します。
誰かに大きな負担がのしかかることなく円滑に介護を行うためには、兄弟間で「何ができるのか・できないのか」をしっかりと話し合い、合理的な役割分担を行うことが大切と言えるでしょう。
また実際に介護を行うとどうしても自分の時間が取れなかったり、身体的なストレスがつきものです。
真面目な人ほど頑張ってしまいがちですが、身体が限界を迎える前にデイサービスや訪問介護などを活用したりと、なるべく自分の負担を軽減する手段を考えましょう。
親子が共に健康で生きていくためにも介護施設への入居も選択肢に入れながら、介護と自分の生活を両立していくことが大切です。
子供には、親の介護について努力する義務があると言えます。民法877条第1項では「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定められています。したがって、子が直接身体介助などを行う必要はありませんが、親が問題がなく生活ができるよう介護に対しての金銭的な援助を行う義務はあると言えます。詳しくはこちらをご覧ください。
親の介護の負担を抑えるために知っておきたいポイントとしては、以下の4点が挙げられます。①費用面の問題 ②兄弟間のトラブル ③在宅介護が施設介護がを巡る問題 ④ 自分の生活との両立に関する問題 詳しくはこちらをご覧ください。




