「先日帰省すると、一人暮らしの母の様子がおかしいと感じた」り、実家の近所に住む姉から「最近お母さんが何度も同じことを聞いてくる。何もなければよいけど、もし認知症で介護が必要になったらどうしようか」と電話がかかってくるようになった、といったご経験はないでしょうか。
認知症の患者さんをもつ家族の多くは、認知症になったあとに情報を集める方が大半ですが、実は認知症になる前にある程度対策することで、さまざまな問題を回避できます。
そこで今回は、親が認知症と分かったときのお金のトラブルと管理対策、認知症の方に使える具体的な公的制度に焦点を当てて解説します。
本記事を読んで、「親が認知症になったらどうすればよいか」を知り、資金面での不安を減らしましょう。
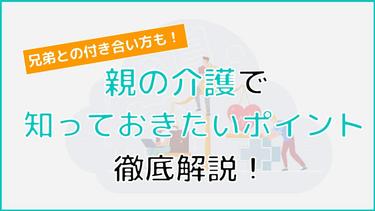
認知症とはどのような病気か?
脳の病気や障害などによって、理解力や判断力などの認知機能が低下し、日常生活にまで支障をきたしている状態を「認知症」といいます。
それでは認知症の具体的な症状とは、どのようなものなのでしょうか。
認知症は、主に加齢によるもの忘れのような状態から始まります。少しずつ「仕事や家事の段取りが悪くなる」「慣れた道で迷子になる」「自分のものを誰かに盗まれたと主張する」「金銭の管理ができなくなる」などの症状が起こります。
認知症の主な種類は以下の4つがあり、それぞれ症状が異なります。いくつかの認知症では、特殊なタンパク質が脳に滞留し、病気を引き起こすことが判明しています。
参照:『認知症の病因「タウたんぱく質」が脳から除去されるメカニズムを解明』
アルツハイマー型認知症
認知症の約60%を占める進行性の病で、脳の一部がゆっくりと萎縮していきます。主な症状は記憶障害で、早期に治療を開始すると進行スピードの抑制が期待できます。

前頭側頭型認知症
身だしなみに無頓着になったり、万引きをしたりといった、理性的な行動ができなくなる認知症です。症状がゆっくりと年単位で進行し、国の難病指定を受けている病気です。
脳血管性認知症
脳梗塞や脳出血などが原因で起こる疾患で、認知症全体の約20%が脳血管性です。脳の損傷した部位によって発症する症状が異なり、症状の出方に波がある「まだら認知」が最大の特徴といえるでしょう。
脳血管性とアルツハイマー型の混合型も多くみられます。
レビー小体型認知症
現実には見えないものが見える「幻視」や手足が震えて少しずつ動けなくなる「パーキンソン症状」といった症状が現れる認知症です。ほかの認知症と比べて進行が早く、早い方は40歳ごろに発症します。
認知症の初期のサインがみられたら、早めに病院受診を検討してください。
参照:『若年性認知症施策の展開』
参照:『レビー小体型認知症』
認知症でも入居できる施設が知りたいという方は、ケアスル介護がおすすめです。ケアスル介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができるためご希望に沿った施設探しが可能です。
「プロに相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
認知症の方にありがちなお金にまつわる4つのトラブルと対策
高齢者が認知症になると、理解力や判断力などの認知機能が低下し、さまざまな問題が生じる場合があります。ここでは、認知症の方にありがちな「お金」にまつわるトラブルを4つご紹介します。
1.銀行口座が凍結され、お金が引き出せなくなる
2.詐欺に引っかかりやすくなる
3.お金の管理が上手にできなくなる
4.お金を盗まれたと被害妄想が現れる
「親が認知症になったら、このようなトラブルがあるかもしれない」と心構えをしておくと、よいかもしれません。
ひとつずつ解説していきます。
1.銀行口座が凍結され、お金が引き出せなくなる
口座名義人が認知症であることを銀行が把握した場合、詐欺などを防ぐために銀行は口座を凍結します。アカウントが凍結されると、治療費などの本人の身の回りのものを支払えなくなり、介護者が立て替えるケースが多々みられます。
のちに紹介する「成年後見制度」を利用することで、名義人の預金が使えるようになります。
家族信託・後見・遺言・相続などについてお悩みの方はご相談されてみてはいかがでしょうか?スマート家族信託
2.詐欺に引っかかりやすくなる
認知症により判断力や理解力が衰えると、相手が話した内容が真実かどうか分からなくなります。特に認知症の方は、振り込め詐欺にだまされやすい傾向があります。
実際にあった例は、下記の通りです。
- 高齢者の自宅を訪問し、家の売却に同意させる
- 知らない業者から電話がきて、いつの間にか電気回線の切り替え申込がされていた
詐欺被害にあわないように、留意しましょう。
3.お金の管理が上手にできなくなる
認知症患者の中には、お金に対する金銭感覚が分からなくなる方もいます。食品やトイレットペーパーなどの日用品を買った記憶を失い、何度も同じものを買ってしまう、高額な買い物をしてしまうといった事例があります。
また、ハイリスクで損失額が大きくなりやすい金融商品に手を出すケースもあるため、用心してください。
4.お金を盗まれたと被害妄想が現れる
認知症になると、財布が手元にないことに不安を感じたり、同居している家族にお金を盗まれたと疑念を抱いたりといった、被害妄想が現れる場合もあるでしょう。
物取られ妄想は、財産の減少や健康状態の悪化などの不安な感情が根底にあります。もし「財布が盗まれた」と疑われたら、落ち着いて話を聞き、いったん別の話題に切り替えるか、同居家族に間に入ってもらい助けてもらいましょう。
参照:『高齢者の消費者被害』
【認知症の際に活用しよう】公的なお金の管理対策2つ
認知症にまつわるお金のトラブルを回避するために知っておきたい公的制度をご紹介します。
1.成年後見制度を検討する
2.日常生活自立支援事業を利用する
認知症になると、判断能力が鈍るケースが少なからず見られます。金銭トラブルを回避するために、公的な制度を上手く活用していきましょう。
1.成年後見制度を検討する
成年後見制度は、加齢や認知症などさまざまな事情で判断能力が低下した方の財産を守るための制度です。意思決定能力に不安を感じている保護者に代わって、裁判所が定めた後見人が金銭管理をサポートすることもできます。大きく分け、下記の2つの制度が存在します。
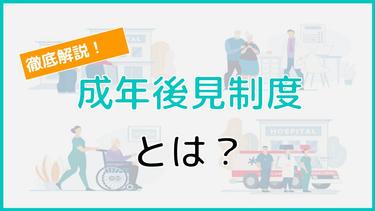
法定後見制度とは?
法定後見制度は、裁判所が本人の判断能力に応じて、後見、保佐、補助の3つの支援方法を設けています。
本人の判断能力が低下した段階で、家庭裁判所に後見、補佐、補助いずれかの開始を申し立てます。家庭裁判所は要件を満たしていると判断した場合に審判を行い、成年後見人(あるいは保佐人、補助人)を選任します。
申立人は家庭裁判所に対して、成年後見人(あるいは保佐人、補助人)を推薦できます。ただし、裁判所はあくまでも本人の財産や権利を保護する上で適任かどうかを個別に判断するため、必ずしも推薦者が選ばれるとは限りません。つまり、親族が推薦通りに後見人になれることもあれば、なれないこともあるのです。
法定後見制度の3つの具体的な違いは、下記の通りです。
| 後見 | 保佐 | 補助 | |
|---|---|---|---|
| 対象者 | 常に判断能力が欠けている方。
日用品(食料品や衣料品等)の買い物などの日常生活が困難な状態。重度の認知症・重度の知的障害者・脳死判定を受けた方など。 |
判断能力が著しく不十分な方。
日用品の買い物はできるが、不動産の契約締結などの大きな買い物の判断が困難な状態。 中度の認知症の方や中度の知的障害者の方など。 |
判断能力が不十分な方。
日常的な買い物や不動産の契約締結など購入も一人で可能だが、サポートが必要と判断された状態。軽度の認知症の方や、軽度の知的障害者の方など。 |
| 申立てができる方 | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など | ||
| 申し立てをする場所 | 本人の所在地を管轄する裁判所 | ||
| 法定代理人の名称 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
| 本人の同意の有無 | 不要 | 必要 | 必要 |
| 取り消しが可能な行為 | 日用品の購入など日常生活に関する行為以外全て | 民法13条1項で定められたすべての行為(借金・訴訟・相続の承認や放棄・新築・改築、契約等の法律に関することなど) | 民法13条1項の中で家庭裁判所から与えられた一部の行為(借金・訴訟・相続の承認や放棄・新築・改築など) |
詳しくは、最寄りの地域包括支援センターや、家庭裁判所、社会福祉協議会などに相談してください。
任意後見制度とは?
法定後見制度と同じく、判断能力が低下した人の財産や権利を保護するための制度で、家庭裁判所への申し立て及び審判によって開始されます。ただし、任意後見の場合は、本人の判断力があるうちに、任意後見人との間で契約を結んでおく必要があります。
法定後見の場合、サポートの範囲は裁判所が決定しますが、任意後見では任意後見の権限は本人と任意後見人との間の契約であらかじめ決めておくことになります。誰に後見人を頼み、どこまでの範囲をお願いしたいのか、本人の意思決定が反映しやすいのが特徴です。
2.日常生活自立支援事業を利用する
日常生活自立支援事業は、判断力が不十分な方の福祉サービスの利用援助などをサポートする事業です。
認知症の高齢者や知的障害のある方が、自立した生活を送れるよう支援することを目的としています。実際の福祉サービスのサポート範囲は、どのくらいあるのでしょうか。
日常生活自立支援事業の具体的な内容は、以下の通りです。
- 必要な福祉サービスの金銭的援助
- 苦情解決制度の利用アシスト
- 住宅の改造
- 居住家屋の貸し借り
- 日常生活上の消費契約に関すること
- 住民票の届出などの行政手続の援助
実施主体は、各都道府県または市町村の福祉協議会です。日常生活自立支援事業を利用したい方は、最寄りの福祉協議会へ相談に行ってください。
参照:『日常生活自立支援事業』
参照:『任意後見制度について』
参照:『Q3~Q15 「法定後見制度について」』
【認知症の際に活用しよう】自分でできるお金の管理対策2つ
親が認知症と判明する前に、準備しておくとよいことはあるのでしょうか。ここでは、公的なもの以外でお金の管理方法のコツを3つご紹介します。
- 1.「家族信託」を活用する
- 2.「エンディングノート」を作る
ひとつずつ解説していきます。
1.「家族信託」を活用する
家族信託(かぞくしんたく)とは契約に基づき、家族に財産の管理や処分を任せる仕組みです。
家族信託で行う財産管理の内容は依頼する側とされる側との契約で取り決められます。
例えば、高齢者本人が持っている不動産に関して本人の意向に沿った形で、信頼のおける家族が管理を行い、家賃収入は高齢者に支払われるようにできます。いずれ、必要が生じたら家族の責任と判断で不動産の売却を行うこともできます。
また、通常の遺言と異なり、自分が死んだあとの財産管理者を指定できます。
2.「エンディングノート」を作る
エンディングノートとは、言葉だけでは伝えられない細かい自分の思いをノートに記すことです。
例えばお金に関して言及すると、以下のような項目を記載しておくとよいでしょう。
- 財産の一覧管理
- 財産分与はどうするのか
- 預貯金や有価証券の受け渡し
- 生命保険の加入の有無と、受取人は誰か
- 銀行引き落としの情報
- クレジットカードの契約
意外に忘れがちなのは、親が仕事や社会でどのような方たちと関わり合い、どのような思いで過ごしていたかを知ることです。いざ葬儀の準備の段階で「葬儀屋さんに親が誰と仲が良かったか聞かれて、答えられなかった」といった方も多くいるようです。
葬儀を知らせる方・そうでない方、葬儀の方向性、喪主が誰にしてもらいたいかなどできる限り細かくエンディングノートに記してください。
最後に、信頼できる方にエンディングノートの保存場所を伝えておきましょう。エンディングノートの執筆には、時間がかかります。短い時間で完成を目指さず、ゆっくりと考えながら作成してください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
【認知症になったら使える制度】公的な経済サポート2つ
認知症になると、認知症本人だけではなく家族も金銭的負担が増す可能性もあります。公的支援を利用すると、ある程度負担を軽減できるケースは多いでしょう。
ここでは、認知症の方や家族が使える公的な経済サポート制度を3つ紹介します。
- 障害者手帳の申請
- 生活保護の相談
公的な支援サービスは、申請して支援が適用されるまでに時間がかかります。可能な限り早急に申請しましょう。
障害者手帳の申請
障害者手帳の申請は、認知症の初診から6カ月以上経ってから、市区町村の障害・福祉に関する窓口で相談できます。
認知症で身体に障害がない場合は「精神障害者保健福祉手帳」、脳血管性認知症などで身体に障害がある場合は「身体障害者手帳」をそれぞれ申請できるでしょう。
障害者手帳があると受けられるサービスは、以下の通りです。
- 所得税・住民税などの各種税金の控除や減免
- 公営住宅への優先入居
- 公共施設の割引
- 障害者法定雇用率適用のサービスなど
ただし、地域によって受けられるサービスの対象や内容が異なります。詳しくは、お住まいの市町村の福祉に関する窓口に問い合わせてください。
生活保護の相談
認知症などで働けない方に最低限の生活を保障する制度です。申請条件は、申請者本人と家族全員の収入と資産の合計が、政府が定める公的扶助の基準を下回っていることです。
親族からの援助が期待できる場合は、そちらが優先されるでしょう。自治体の福祉に関する窓口に相談してください。

参照:『高次脳機能障害支援に関する制度』
参照:『生活保護制度とはどのような制度ですか。』
参照:『特別障害者手当のしおり』
公的な対策を優先して進めていこう
親が認知症と分かったときのお金のトラブルと管理対策、認知症の方に使える具体的な公的制度に焦点を当てて解説してきました。認知症の症状がいろいろあるように、本人や家族が使える公的支援やサービスも異なります。
認知症に限らず、高齢になるとこれまで当たり前のようにできていた金銭管理が難しくなることも珍しくありません。親が元気なうちから家族で話し、本人でなければできない手続きを一緒に進めていくことが大切です。
「私の親は問題ない、大丈夫」と思わずに、「親が認知症になったら…」と考えて、高齢の両親と今後のことを話し合う機会を持つよう、心掛けてみましょう。
Q1.介護者から見てどのような症状が現れたら、病院を受診するとよいですか?
以下の行動がみられたら、病院の受診を検討し始めるとよいでしょう。ただし、本人が嫌がっているのにやみくもに受診を強制するのは逆効果になることも。本人の意志を尊重しながら受診につなげましょう。
- 繰り返し同じことを聞く
- 以前より室内の整理整頓ができなくなっている
- 財布の中身が硬貨ばかりになっている
- 探し物をいつもしている
- 性格が怒りっぽくなる
Q2.認知症に関する相談はどこにしたらよいですか?
全市町村に設置されている地域包括支援センターのほか、以下の窓口でも電話相談を受け付けています。
- 公益社団法人 認知症の人と家族の会
電話番号:0120-294-456(フリーダイヤル)
※携帯電話・PHSの場合(有料):075-811-8418
受付時間:午前10時~午後3時(月~金 ※祝日除く)
このほか、全国47か所の支部でも電話相談ができます。
- 認知症介護研究・研修大府センター65歳未満の若年性認知症の方や家族専用の相談コールセンターです。
電話番号:0800-100-2707(フリーダイヤル)
受付時間:午前10時~午後3時(月~土 ※年末年始、祝日除く)





