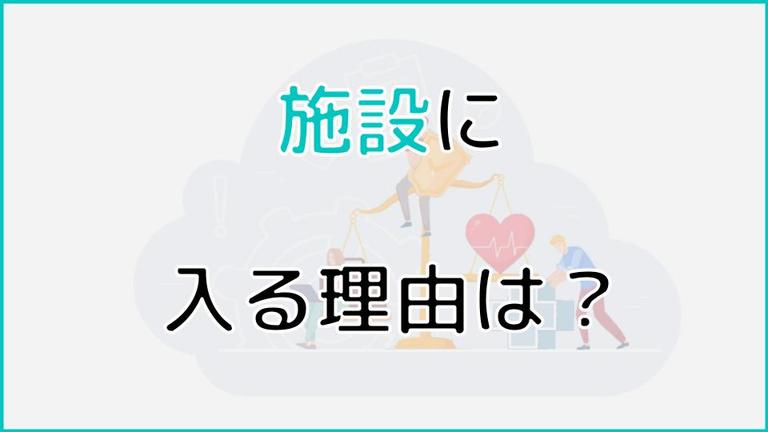「できるなら最期まで自宅で過ごしたい」「家族に支えられながら生活したい」など、自宅での介護を希望する方が多く、施設への入所は悩ましい問題の一つです。
しかし、自宅での介護は家族への負担が大きく、収入減少により生活が立ち行かなくなる可能性があります。
さらには、施設に入所する適切な時期を逃すと希望に沿った施設に入れないかもしれません。
どのタイミングで施設に入るのかは、人生において大きな決断です。そこで今回は施設に入る理由や入らないリスクについて詳しく解説します。
施設を選ぶ際のポイントや入居拒否への対応方法も紹介するので、施設入居を検討中の方はぜひ最後までご覧ください。
施設に入ることを希望する理由|上位3位
内閣府の世論調査によると、施設に入ることを希望する上位3位は以下の通りです。
- 第1位:家族に迷惑をかけたくないから
- 第2位:専門的な介護が受けられるから
- 第3位:介護の時間を確保できないから
上記について、順に詳しく解説していきます。
第1位:家族に迷惑をかけたくないから
最も多い理由には「家族に迷惑をかけたくない」が77.1%と圧倒的に多い結果でした。
また、同じ世論調査で「どこで介護を受けたいか?」との質問に対しての解答は以下の通りです。
- 可能な限り自宅で介護を受けたいと考えている方:44.7%
- 介護保険施設(特別養護老人ホームや老人保健施設など)で介護を受けたい方:33.3%
- 住み替えて(介護付き有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など)介護を受けたい方:9.0%
自宅での介護を選択した際に、介護の主な役割を担うのは家族です。
介護は、心身ともに負担がかかります。そのため多くの方は自宅で介護を受けたいと考える一方で、家族に迷惑をかけたくないと考えて入居を決めるようです。
第2位:専門的な介護が受けられるから
専門的なスタッフによる介護を受けられるため、施設に入所したいと考える方もいます。
自宅は住み慣れた環境での生活ができ安心できるといったメリットはありますが、施設への入居や外部の介護サービスを利用しなければ専門的な介護を受けられません。
施設には、看護師や介護福祉士、理学療法士などが在籍しています。
資格を持っていなくても施設内の研修や自己学習などで介護を学び、業界で働き続けている方ばかりです。
多くの施設では24時間365日体制でスタッフが常駐しているため、昼夜問わず安心した生活を送れます。
急な病気やケガの際にスムーズな対応が受けられるサポート体制がある点も、施設へ入りたいと思う理由の一つとなっているようです。
第3位:介護の時間を確保できないから
家族が介護の時間を確保できないために、施設へ入ることを考える方もいます。
その割合は25.9%です。介護の役割を担っている家族は、働きながら介護をしている方が多く見受けられます。
しかし仕事をしながらでは仕事と介護の時間、両方を十分に確保するのは難しいです。
また、厚生労働省によると仕事をしている方(雇用者)で、介護をしている者は2,399,000人。
そのうち女性1,372,000人、男性1,027,000人となっています。
家族の介護が原因で仕事を辞めなければならない「介護離職」をする人数は年間約10万人。
このことから、仕事を継続しながらの介護がいかに難しいのかわかるでしょう。
参照元:『厚生労働省 第3節 仕事と介護の両立について P1』
初めての施設探しをしているという方はケアスル介護で施設探しをするのがおすすめです。
入居相談員にその場で条件に合った施設を提案してもらえるので、初めての施設探しでもスムーズに探すことが出来ます。
始めればよいかわからないという方はぜひ利用してみてください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

実際に施設に入ることを決めた理由とは?
実際施設入所を決めた理由に多いのは、以下の通りです。
- 家族の負担が増えたから
- 退院後に在宅介護が困難となったから
- 独居での生活が困難となったから
- 認知症が進行したから
上記の項目について、詳しく解説していきます。
家族の負担が増えたから
「最期まで自宅で生活したい」など、自宅での介護を希望する方は多いです。
特に介護が始まった当初は、本人の希望を重視して自宅での介護を続けてしまいがちですが、介護を担う家族の負担は大きいです。
夜間のトイレ介助や徘徊など、本人の状況によっては昼夜問わず介護しなければならない場合もあるでしょう。
介護度が上がるとさらに負担は大きくなり、自宅での介護の継続が困難になってしまいます。
介護をしている家族が限界を感じたり、何らかの理由により「これ以上自宅での介護は難しい」と感じたりするケースもあります。
これにより、家族だけの介護では対処できないと感じる点が理由の一つです。
退院後に在宅介護が困難となったから
歳を重ねていくと病気やケガなど、何らかの治療を要する状態となる機会が増えます。
そのため、治療や手術のために入院する場合もあるでしょう。
入院すると療養のために行動が制限されたり体力が低下したりなどの理由から、入院前と比較して日常生活動作のレベルが下がる方が多く見受けられます。
そのため入院前から自宅で介護を受けていた方や退院後から介護が必要となった方、いずれの状況でも入院前より介護度は上がることが予想されます。
介護度が重度になってしまうと、自宅での介護を継続するのは困難になる可能性が高いです。
このようにときに、介護施設などへの入所を決める方も多いとされています。
独居での生活が困難となったから
総務省の調査によると高齢者(65歳以上)で一人暮らしをしている方は男女ともに増加傾向で、2015年には男性192万人、女性400万人となっています。
つまり、65歳以上の高齢者で一人暮らしをしている方は600万人程度いることになります。
65歳以上の人口のうち男性は13.3%、女性は21.1%が該当しており、高齢者の5人に1人は一人暮らしであるとわかるでしょう。
介護を要する場合ではなくても、高齢となると一人で暮らすことはもちろん、特に夜間一人で生活しなければならない場合は強い不安を覚えます。
「急に体調が悪くなったらどうしよう」「ケガをして動けなくなっても誰も助けてくれない」などと感じる方も多いかもしれません。
しかし施設には24時間スタッフが常駐しているところもあり、これが施設入所を選択する要因の一つとされています。
参照元:『家族と世帯|令和元年版高齢社会白書(全体版)』-内閣府
認知症が進行したから
認知症は現在の医学では完治できず、症状を遅らせる治療しか受けられません。
認知症になるとこれまでできていた日常生活動作ができず、コミュニケーションも取れなくなります。
認知症を発症したばかりの頃は日中も一人で生活できるため、家族は仕事に行けるなどほとんど制限なく行動可能です。
しかし認知症の症状は徐々に進行し、重度になると介護が必要になります。
症状によっては徘徊や被害妄想などがみられ、昼夜問わず介護しなければならないケースもあるでしょう。
家族だけでの介護が難しくなったときに、施設への入所を決めるケースも多いようです。
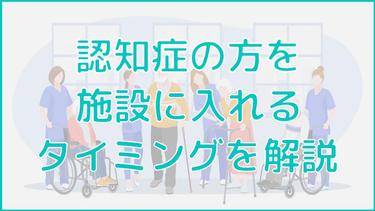
介護施設に入るための必要な条件
介護施設は誰でも入れるわけではなく、以下のように一定の条件が定められています。
- 一般的には60~65歳以上
- 要支援・要介護度による区分
- 必要な医療ケア・処置
- 身元引受人と保証人
本人の状況だけではなく、身元引受人や保証人の存在も条件の一つです。
以下で詳しくみていきましょう。
一般的には60~65歳以上
施設へ入れる年齢は、一般的に60〜65歳以上の方です。
老人ホームの中には、若年者を対象とする施設もあります。そのため、40代・50代でも既往症や心身の状況によっては施設へ入れる方もいるかもしれません。
要支援・要介護度による区分
受けている要介護認定の区分によっても、入れる施設は異なります。
特別養護老人ホームなどの公的施設や民間施設による入居条件の区分の違いは、以下の通りです。
| 施設 | 入所の条件 |
| 介護老人保健施設・介護療養型医療施設
・介護医療院 |
要介護度1以上 |
| 特別養護老人ホーム | 要介護度3以上(要介護1、要介護2の方は特別な事情がある場合のみ入所可能) |
| 介護付き有料老人ホーム | 要介護認定関係なく入居可能 |
| 住宅型有料老人ホーム | 要介護認定関係なく入居可能 |
参照:『厚生労働省 特別養護老人ホームの「特例入所」に係る国の指針について』
公的施設は、要介護1以上など要介護度の区分により入居条件が定められています。
介護付き有料老人ホームや住宅型有料老人ホームなどの民間施設では、施設によって要介護度の条件が定められているので入居を希望する方は直接施設へ確認してみましょう。
必要な医療ケア・処置
身体の状況や既往症によっては、医療ケアを必要とする方もいます。
介護施設でよく行われる医療ケアや処置は、以下の通りです。
- 痰の吸引
- 胃ろう・経管栄養
- 膀胱留置カテーテルの管理
- 在宅酸素療法の管理
- 褥瘡の管理
介護施設は医療機関ではないため、日常生活への支援は行われていても一部の施設では医療的ケアに対応していないケースもあります。
また、医師や看護師などの医療スタッフの配置がない施設もあります。
医療的なケアが必要な方をどの程度受け入れできるかどうかは、医療スタッフの配置によって異なるので施設へ確認してみるとよいでしょう。
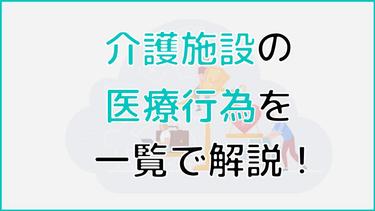
身元引受人と保証人
施設に入る際、身元引受人と保証人の選定を求める施設が多くなっています。
身元引受人や保証人は施設入所の際に必要な書類へサインするだけではなく、入居中に発生する問題に責任を持って対処しなければなりません。
つまり、施設側の危機回避のために必要とされます。身元引受人や保証人が求められる主な例は、以下の通りです。
- 死亡後の手続きや遺品の整理
- 入居者同士でのトラブル時の対応
- 入所に関わる費用が払えない場合の対応
- 施設内の設備を破損した際の保障
身元引受人や保証人は、トラブル対応や代理での保障など対応すべき事柄が多々あります。
実際、施設側から上記のような対応を求められる場合もあります。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
施設に入る適切なタイミングを逃すことで起こりうる3つの問題
本人に施設入所を拒否され、施設に入らせることをやめ自宅での介護を継続するケースもあるでしょう。
しかし、施設入所の適切なタイミングを逃すと次の問題が生じる可能性があります。
- 家族の介護負担の増加
- 収入が激減する可能性
- 希望する施設に入れない
上記3つの問題点について、詳しく解説します。
家族の介護負担の増加
そもそも自宅での介護は、家族にとって身体的、精神的な負担をともなう場合が多いです。
タイミングを逃すと、次の理由から以前よりもさらに負担が増加する可能性があります。
- 介護を受けている方の要介護度が上がった
- 認知症の症状が増悪した
- 病気やケガなどにより家族自身の心身の状況が悪化した
「住み慣れた自宅で最期まで生活したい」といった本人の思いを尊重できるのはよい点ですが、一方で家族の介護負担は増加する可能性があります。
家族の介護負担の増加は施設に入る大きな理由でもあるので、家族が疲弊し生活に支障をきたす前に施設への入所を検討するとよいかもしれません。
収入が激減する可能性
介護を担っている家族の多くは、仕事を継続しながら介護をしています。
介護の負担が大きくなると仕事を続けられなくなり、離職せざるを得ない状況となる場合があります。
総務省の調査によると、介護をしている方は約628万人。
そのうち約6割の346万人が仕事を継続している状況です。
しかし、高齢化の進展に伴い介護離職の人数は増加傾向で過去1年間に9.9万人が離職に至っています。
離職すると収入が激減してしまうために、家族の生活費に加え介護費用がかさむと生活が立ち行かなくなる可能性もあります。
希望する施設に入れない
高齢化社会に伴い、施設への入所を希望する方は増加傾向です。
交通の便がよかったり周辺に商業施設などが多く利便性が高かったりする施設は人気となっています。
ほかにも費用が抑えられる施設などは、入居待ちの場合が多いです。
特に特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの公的な施設は、民間施設と比較し費用が安価で人気が高いとされています。
しかし介護度が上がったり認知症が重度になってしまったりして施設への適切な入居タイミングを逃すと、本人や家族の希望通りの施設に入居できなくなってしまう可能性もあります。
施設に入るのを本人に拒否された場合の対処法
家族の介護負担の増加により、施設への入所を検討する場合もあります。
施設に入る理由は人それぞれです。
しかし家族が希望していても、施設に入るのを本人が拒否する事例も少なくありません。ここでは、施設への入所を拒否した本人への対処方法を解説します。
本人の想いを傾聴する
まずは、本人が「なぜ施設への入所を拒否しているのか」について、想いを傾聴することが大切です。
無理に施設へ連れていくと「入所するなんて聞いていない」「無理やり連れてこられただけだ」「今すぐ家に帰る」などと話しトラブルになりかねません。
施設に入ると生活環境が大きく変わり、人によっては大きなストレスとなるでしょう。
アドバイスなどはせず、まずは本人の想いをじっくり聞くのが大切です。
「あなたを第一に考えている」と伝える
家族が「あなたを第一に考えている」との想いを伝えるのも大切です。
施設への入所を「家族に捨てられた」「家族が私を面倒がっている」「もう家族は会いに来てくれないのではないか」と感じる方も少なくはありません。
決してそのような想いはなく「あなた」を大切に想っていて、安全・安心に暮らして欲しいからこそ施設への入所を勧めていると伝えましょう。
施設に入るメリットを説明する
また、施設に入るメリットの説明も大切です。
施設に入るメリットには、以下のようなものがあります。
- 24時間スタッフが常駐しているため安心
- 医療機関と連携している施設では急な体調不良やケガにスムーズに対応してもらえる
- 専門的な介護を受けられる
- 家族の負担が減る
家族からだけではなく、施設スタッフから直接説明してもらえるとより効果を得られる可能性もあるので本人の性格に合った方法で説明を行ってみましょう。
施設を選ぶ4つのポイント
厚生労働省の調査によると、2019年時点で介護老人福祉施設は8,234施設、介護老人保険施設は4,337施設、介護医療院は245施設、介護療養型医療施設は833施設あるとされています。
また、民間の施設で最も多いのは有料老人ホームで、その数は14,118施設です。数多くある施設は、以下4つのポイントで選ぶとよいとされています。
- 公的施設または民間施設であるか
- 入居の条件は本人の状態に合っているか
- 家族が支援を続けやすい立地であるか
- スタッフや入居者の雰囲気はどうか
上記について、それぞれ詳しく解説します。
参照元:『厚生労働省 結果の概要』
参照元:『厚生労働省 高齢者向け住まいの今後の方向性と 紹介事業者の役割』
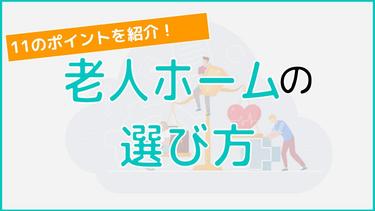
公的施設または民間施設であるか
高齢者を対象とした施設は数多くあります。施設は公的施設と民間施設の大きく分けて以下2つに分類できます。
| 分類 | 施設 |
| 公的施設 |
|
| 民間施設 |
|
特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの公的施設、もしくは介護付き有料老人ホームや在宅型有料老人ホームなどの民間施設に分類できます。
施設の種類によって受けられるサービスや費用が異なるため、公的施設か民間施設かは選ぶうえで重要なポイントです。
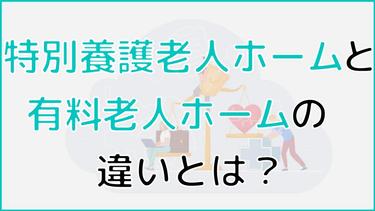

入居の条件は本人の状態に合っているか
施設の入居条件と本人の状態が合っているのかは、施設を選ぶうえで大切なポイントです。
主な施設の入居条件は、以下の通りです。
- 要介護度
- 年齢
- 既往症や認知症の有無
- 必要な医療ケア・処置の有無
- 身元引受人・保証人の有無
- 支払い能力(資産や収入)
- 居住している地域
入居条件は、それぞれの施設によって異なります。
一般的には公的施設の方が民間施設よりも介護度が重い方を対象としており、介護保険制度により安価で利用可能です。
施設の利用が安価で済むのが施設に入る理由の一つとなる場合もあります。
また、上記で紹介した以外の条件を定めている施設もあります。
本人の状態や希望、家族の意向などと合っているのかを事前に確認しておきましょう。
家族が支援を続けやすい立地であるか
家族が支援を続けやすい立地であるかどうかは、施設を選ぶうえで重要です。
施設に入所したあとも家族の支援は必要です。
必要な書類へのサインや必要な物品を届けたり、病院の受診に付き添ったりなど支援しなければなりません。
定期的に様子を見に行ったり、話し相手になったりするために通う場合もあるでしょう。
そのため、自宅から近いところや交通の便がいいところを選んだ方が通いやすく支援を継続しやすいといえます。
また、周辺にコンビニやスーパーがあるのか、公園など自然を感じるところはあるのかなどといった居住環境も施設で生活していくために大切なポイントです。
スタッフや入居者の雰囲気はどうか
施設内の雰囲気も大切なポイントです。
一度施設に入ると、ほとんどの方は長期間の入居になります。看取りのサービスを提供している施設であれば、入所してから最期のときまで過ごすことになるでしょう。
施設によって雰囲気は大きく異なるので、どのような雰囲気・生活環境の中で暮らしているのかを確認しておきましょう。
施設では、見学や体験宿泊を受け入れているところが多いです。
チェックしたいポイントを事前に把握して見学へ行くと、より効果的に情報収集できます。
ホームページだけでは分からない情報を得られるため、気になる施設があれば一度見学をしてみましょう。
施設に入る理由を知り、適切なタイミングで利用して負担を軽減しよう
施設に入る理由や実際に入所した理由を理解すると、適切な入所のタイミングを知れるでしょう。
多くの方は自宅での介護を希望していますが、本人や家族の想いばかりを尊重してしまうと適切なタイミングを逃す可能性があります。
適切なタイミングで入所しなければ、家族への負担が大きくなったり生活が立ち行かなくなったりする可能性が高いです。
今回紹介した施設を選ぶ4つのポイントを参考にして、本人や家族の希望、意向に合った施設を選びましょう。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
施設に入る理由に関するよくある質問
Q. 認知症の家族を施設に入れるタイミングはいつですか?
A. 一人でトイレに行けなくなったときが、施設への入所を検討する一つのタイミングです。一人でトイレに行けないと、夜間2~3回起きて介助をしなければなりません。その状況が毎日続くと体力的・精神的に介護の継続が難しくなるために施設入所を決意するきっかけになるようです。
Q. 施設に入る理由には、どのようなものがありますか?
A. 家族の負担が増えたり、認知症が進行したりした点が施設に入る理由として挙げられています。また、独居での生活が困難になったときも施設に入ることを決める理由となるようです。