急に遠距離介護が必要になってしまい、困っている方は多いのではないでしょうか。「仕事をしながら介護できるのかな?」と不安になる方もいるのではないでしょうか。
この記事では、遠距離介護においてのメリット・デメリット、便利なサービスや制度などについてくわしくご紹介します。
遠距離介護における3つの問題点
遠距離介護とは、遠い場所に住む家族が行う介護をいいます。いざという時に、すぐに行ける距離ではないからこその問題点があるでしょう。
遠距離介護では、以下の3つの問題点が考えられます。
- 健康状態やリスク管理などの把握が難しくなる
- 移動に多くの時間と費用がかかる
- 詐欺犯罪に巻き込まれる危険がある
それぞれの問題点について詳しく解説します。
健康状態やリスク管理などの把握が難しくなる
一緒に生活していないと直接顔を見られないので、様子を確認するのは難しいといえます。そのため、健康面や生活面などでの微妙な変化に気付くのは困難であるといえるでしょう。
重大な病気や認知症などは、いち早く気付いて早期に対処する必要があります。しかし、様子が見えない状況では、早期発見するのは簡単ではありません。
万が一、認知症を発症すれば家族の心配事は増えるでしょう。物忘れがあれば、火の消し忘れによる火災の危険性が高まります。
また、徘徊するようになれば交通事故や行方不明になるなどの危険も考えられるでしょう。認知症の度合いによっては、高齢者のみの生活だと命に係る事態にも直結します。
移動に多くの時間と費用がかかる
遠くに住む家族の距離が離れれば離れるほど、移動にかかる時間・交通費の負担は大きくなります。介護のために何度も通えば、その分交通費の負担は増すでしょう。
移動に数時間かかるような距離であれば、一度に数万円単位での出費が考えられます。また、場合によっては仕事を休む必要があり、収入に影響が出てしまう方もいるでしょう。
金銭的な余裕がなくなれば、介護者自身の生活や老後に対する不安が大きくなり、精神的なストレスにもつながります。
詐欺犯罪に巻き込まれる危険がある
近年、警察が「刑法に違反する犯罪」と認知した犯罪件数は減少傾向にあるものの、高齢者の被害件数の割合は年々増加しています。警察庁のデータでは、令和元年における主な罪種別の被害割合は、詐欺などの知能犯が37.6%と最も多いです。
ニュースでもよく見聞きする「オレオレ詐欺」「架空請求詐欺」「還付金詐欺」は、特殊詐欺といわれ高齢者の被害が目立ちます。令和元年の被害割合でみると、特殊詐欺被害の高齢者の割合は83.7%と非常に高く、大勢の方が被害にあっているのが現状です。
家族が離れているからこそ、日ごろから密にコミュニケーションを取れる状態を作っておくのが、犯罪防止のために重要だといえます。
遠距離介護が難しく施設を検討している方はケアスル介護がおすすめです。
入居相談員にその場で条件に合った施設を提案してもらえるので、初めてでも安心して相談することが出来ます。
初めての老人ホーム探しで何から始めればよいかわからないという方はぜひ利用してみてください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
遠距離介護のメリット
遠距離介護は、介護に加え家事・仕事の両立、移動時間の多さから大変なイメージがあるのではないでしょうか。
ただ、遠距離介護には以下の3つのメリットが挙げられます。
- 引っ越しの必要がなく生活が守られる
- 介護者のストレスが大幅に軽減される
- 介護保険サービスが受けやすくなる
それぞれについて解説していきます。
引っ越しの必要がなく生活が守られる
遠距離介護において、引っ越しの必要がないのはメリットといえるでしょう。親は住み慣れた地域で生活を続けられるので、精神的なストレスがかかりません。
介護者も、介護のために退職や離職せずに済むので、収入面や環境変化に対する不安はないでしょう。親の介護をする世代は、一度離職してしまうと新しい仕事を探すのが困難な年代でもあるため、不安が大きくなります。
介護をしつつ、仕事を続けられれば将来に対する不安は生まれません。そのため、お互いの生活を守りながら無理なく介護を続けることが可能です。
介護者のストレスが大幅に軽減される
いくら自分の親の介護といえど、介護者にとっては身体的にも精神的にも負担が大きいため疲弊してしまいます。例えば在宅での介護は、常に介護中心で生活しなければならなくなり、自分の時間を確保することは難しくなるでしょう。
そのため精神的に追いつめられ、介護うつになってしまう方も少なくありません。しかし、遠距離介護であれば、自宅に帰り自分の生活に戻ることで気持ちの切り替えが可能です。
自分の時間が確保されるので、精神的に追い詰められる心配もなく、介護者自身の健康維持にもつながるでしょう。
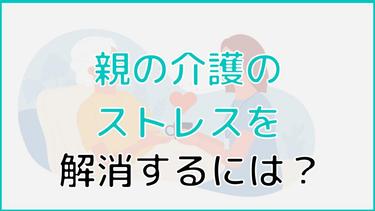
介護保険サービスが受けやすくなる
遠距離介護をしていると、介護保険サービスを利用しやすくなる利点があります。同居して介護している場合には難しい「生活援助」の利用が可能です。
生活援助は、以下のような内容となります。
- 掃除
- 洗濯
- 買い物
- 調理
体力の落ちている高齢者にとって、日々の家事は重労働です。家事を援助してもらえるので、家事労働の負担を減らせるでしょう。
事業所によっては、通院のための乗車・移送・降車の介助サービスを受けられます。また万が一、親が認知症で要介護状態になったときに、特別養護老人ホーム入所の優先順位が高くなる傾向があるのも安心材料の一つです。
遠距離介護のデメリット
遠距離介護には、離れて暮らしているからこそのデメリットがあります。デメリットとして、下記の2つが考えられるでしょう。
- 緊急時の対応が遅くなる
- 移動費以外の費用負担が大きくなる
デメリットを理解しておけば、前もって対策することが可能です。一つずつ解説していきます。
緊急時の対応が遅くなる
親が急に倒れたりケガをしたりしても、遠距離介護ではすぐに対応するのは難しいでしょう。親が一人暮らしで連絡がなければ、気付くまでに時間がかかりさらに多くの時間を要します。
自分の生活が忙しいと、こまめな連絡が取れない場合もあるでしょう。普段から連絡を取れない状況が続けば、親の異変に気付くのも当然遅くなり、対応が遅れてしまう可能性もあるのです。
だからこそ、遠距離介護は周囲の協力が不可欠といえます。
移動費以外の費用負担が大きくなる
遠距離介護では、移動費の負担が大きなネックとなるのは前述のとおりです。しかし、移動費以外にも発生する費用があります。
移動費以外の費用としては、以下のものが挙げられるでしょう。
- 通信費
- 住宅改修費
- 介護サービス費
親やケアマネジャーとこまめに連絡を取れば、その分の通信費がかかります。また、親の身体の状態によっては、家をバリアフリーに改修する必要が出てくるでしょう。
そのほか、ホームヘルパーなどの介護サービス、福祉用具のレンタルなどが必要になれば、その分も出費が増えていきます。介護の出費を少しでも抑えるために、早い段階でケアマネジャーに相談しておきましょう。
遠距離介護を成功させるためのポイント
遠距離介護を、家族だけでやっていくには限界があります。家族の負担が大きくなり、生活に支障が出てしまう前の対策が必要です。
遠距離介護を成功させるために、以下のポイントを取り入れましょう。
- 親とこまめに連絡を取っておく
- 職場に事前報告をしておく
- 手助けしてくれる協力者を見つけておく
- 利用できる施設や精度を調べておく
それぞれ解説していきます。
親とこまめに連絡を取っておく
日頃から親とこまめに連絡を取るようにしましょう。普段から話しやすい関係を築いておくのが大切です。
そのうえで、親が元気なうちに介護について話し合っておきましょう。話し合いの中では以下の内容をヒアリングしておくようにします。
- 親の生活リズムについて
- 親の経済状況について
- 親の交友関係について
- 親の老後の希望について
前もって親の希望をしっかり聞いておけば、いざ介護が始まったときに迷わず準備ができます。また、現在はスマートフォンなどで簡単にテレビ電話が利用できるので、日頃から様子を確認し微妙な変化にも気付けるようにしておきましょう。
職場に事前報告をしておく
遠距離介護が必要になれば、仕事を休まなければならない可能性があります。職場で協力してもらうためにも、前もって上司に報告し相談をしておきましょう。
また、介護による離職を防ぐために「介護休暇」や「介護休業」の制度があります。介護休暇と介護休業の違いは以下のとおりです。
- 介護休暇:年に5日間の取得が可能。対象家族が2人以上で10日間。
- 介護休業:要介護者1名につき通算93日を限度とし、3回まで分割して取得することが可能。
会社によっては、独自の制度を用意している場合もあります。自分の勤務先にどのような介護制度があるのかを確認しておきましょう。
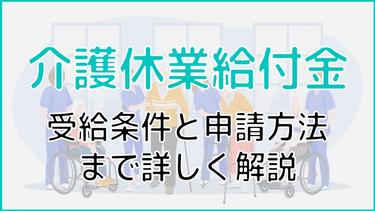
手助けしてくれる協力者を見つけておく
遠距離介護は、周囲の協力があってこそ成功します。現在は一人っ子世帯が増えており、1人で介護するには負担が大きいでしょう。
無理をして介護者が倒れてしまっては、元も子もありません。親の近くに住む親せきや友人、近所の方などに協力依頼をしておくことが重要です。
年に数回、手土産を持参しお礼を伝え交流しておくなど、協力の継続をお願いできる環境を作っておきましょう。電話に出ないなど、心配なときに代わりに確認してもらえれば、介護者自身も安心です。
自分がすぐに行けない距離だからこそ、周囲の方に協力してもらえば、何かあったときの早期発見にもつながります。
利用できる施設や制度を調べておく
遠くに住む親の介護が必要になったら、周囲の施設や制度を上手に活用しましょう。最近では、遠距離介護を助けてくれる高齢者向けのサービスが増えています。
困ったら、まずは高齢者の暮らしをサポートしてくれる「地域包括支援センター」で相談してみましょう。全国に5000ヵ所以上あり、親の居住地近くの地域包括支援センターで相談ができます。
またケアマネジャーや、親の主治医などと話す機会を設けてもらい信頼関係を築いておくのも大切です。困ったときに、電話で相談にのってもらうなどのサポートが期待できます。
相談できる人がいないというときはケアスル介護がおすすめです。
入居相談員が見学予約から日程調整まで全て無料で代行しているので、スムーズに施設探しをすることが出来ます。
急いで施設をさがしているという方はぜひ利用してみてください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

遠距離介護で押さえておきたいサービスや制度
介護が必要になったとしても、離れたところに住んでいるとすぐに駆け付けるのが難しいため、心配はつきものです。だからこそ高齢者向けのサービスや制度を活用して、家族が安心して暮らせる環境にしておくのが重要となります。
介護者の負担を減らし安心して介護するために、便利なサービスの利用を検討してみましょう。
- 見守りサービス
- 介護保険サービス
- 各交通機関の割引制度
それぞれの特徴について詳しく解説します。
見守りサービス
今や見守りサービスは多種多様となっています。遠距離介護に便利な見守りサービスには、以下のようなものがあります。
- センサー型・カメラ型の見守り
- スマートフォンアプリによる見守り
- 見守り家電などIoT機器を活用した見守り
- 食事宅配型の見守り
- デイサービス・訪問介護などの見守り
見守り機器は価格も手ごろで取り入れやすく、リモコンに入れる電池や使用頻度の高いポットなど、高齢者でも使いやすいものが増えています。スマートフォンも、高齢者でも簡単に操作できるものが豊富に発売されていますので検討してもよいでしょう。
宅配型やデイサービス・訪問介護は、人と話ができるので社会との関わりが持て、高齢者の安心やストレス発散にも繋がります。自分の家族にあったサービスを探して取り入れてみてはいかがでしょうか。
どんなものを取り入れるか迷ったときには、ケアマネジャーに相談するのもよいですね。
介護保険サービス
介護保険サービスの中に「居宅介護サービス」があります。要介護・要支援の状態の方が、自宅にいながら受けられるサービスです。
居宅介護サービスの種類には、以下のようなものがあります。
- 自宅に訪問してもらうサービス
- 施設に通って受けられるサービス
- 一時的に施設に入所できるサービス
- 有料老人ホームなどに移り住んで利用するサービス

有料老人ホームでは、部屋が自宅とみなされるため居宅介護サービスに含まれます。通常であれば、限度額の範囲内でサービスを受け、料金の1割(所得により2~3割)の自己負担が必要です。

介護保険サービスは、要介護・要支援度によって利用料の限度額が設定されます。自分の親に必要なのはどのサービスなのか、ケアマネジャーに相談しながら決めるとよいでしょう。
各交通機関の割引制度
結論から申し上げますと、介護を目的に割引できる制度は実質ありません。しかし、各交通機関が色々な割引制度を展開しています。
遠距離介護をしているとネックになるのが、移動にかかる費用です。交通費を少しでも抑えるために、各交通機関で設けている割引制度を活用しましょう。
航空会社では「介護割引」を設定している会社もありますが、それぞれ利用期間や利用条件があり確認が必要です。また格安航空会社は、介護割引こそないものの費用を抑えられます。
新幹線やJR・バスには介護者に対する割引は用意されていません。ただし介助を必要とする方が利用する場合、「障害者手帳」や「療養手帳」を提示すれば付添人も一緒に割引になります。
種類が豊富にあるので、自分に合った割引サービスを活用することで、出費を少なくできます。
遠距離介護の負担を軽減するには周囲の助けが大切
遠距離介護を無理なく成功させるためには、自分一人で抱え込まず周囲に協力してもらうのが大切です。遠距離介護をするうえで必要なポイントやサービス・制度を活用し、家族の生活を守ることができます。
家族の関係を密にし、周囲の助けを借りて上手に負担を減らしながら、家族みんなが笑顔で過ごせるようにしましょう。
Q1.遠距離介護の悩みはどうやって解決すればいいですか?
A1.まずはケアマネジャーに相談してみましょう。ご家族の現在の状態からケアプランを作成し、サポートしてくれます。
ケアマネジャーをこれから探すというときは、市区町村の介護保険課や地域包括支援センターで相談してみましょう。
Q2.遠距離介護の帰省頻度はどれくらいにすべきですか?
A2.帰省の頻度は、ご自分の負担にならない程度でいいと思われます。
もし、ご家族の様子が気になるというのであれば、テレビ電話などを活用して連絡の回数を増やすなどの工夫をしてみましょう。
また地域の介護サービスなどを利用することで、ご家族が快適に生活できるでしょう。




