「処方された薬がちゃんと飲めていなかった」「火を消し忘れて鍋が丸焦げになっていた」
親の老いに伴って、親だけでの生活が心配だといった声はよく聞かれます。
このような親の生活の実態を目の当たりにすると、子どもである自分が親と同居して介護をするべきなんじゃないかと考える方も少なくないでしょう。
しかし同居となれば自分の生活に変化や生活が制限ができてしまうため、気が進まないのが正直な所です。親の介護のために同居したくないと思っている方に向けて、この記事では同居をしなくても親も子どもも安心して生活を送れる方法を提案します。
この記事を読んで、親も子もお互いを尊重した生活への第一歩となれば幸いです。
親の介護のために同居しなくてもよい
親の介護について考えると、誰でも次のような考えが頭をよぎるものです。
- 親の介護のために同居した方がよいのではないか
- 同居したら、今の生活や仕事は続けられないのではないか
いくら親のためといっても、自分の生活環境を大きく変えることは難しいと感じていている人は多いです。しかし親の介護はある日突然やってくるため、慌てて同居を決めたり仕事を辞めたりした方もいるでしょう。確かに子どもには、親の面倒をみなければならないといった義務はあります。
しかしそれは、同居をして24時間介護をしなければならないものではありません。介護保険制度や地域のボランティア・近隣住民など、フォーマル・インフォーマルそれぞれの社会資源を駆使すれば、同居をしなくても親の介護が実現します。
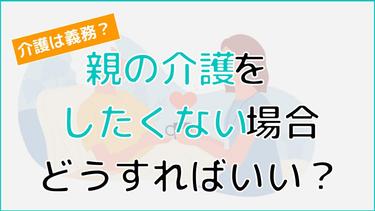
同居せずに親の介護をなんとかしたいと考える方にはケアスル 介護がおすすめです。同居ではなく施設を検討中の場合、全国で約5万件の情報を掲載しているケアスル 介護が条件に合った施設探しまで無料で行います。
悩んでいる方は、まずプロに相談してみませんか。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
親の介護で同居せずにお互いが安心して生活を送る方法
「同居して介護をする義務はない」「同居して介護をしなくても大丈夫」
そうは言われても実際に親の介護が必要になったら、親だけで生活できるイメージが湧かない方も多いのではないでしょうか。
ここでは、親に介護が必要になった場合でも、親と同居せずに親の介護を行う方法をお伝えしていきます。
在宅系の介護保険サービスを駆使する
住み慣れた地域で生活を継続できる地域包括ケアシステムの観点から、介護保険制度は益々充実してきました。特に定期巡回随時対応型訪問介護看護や小規模多機能型居宅介護支援事業所のサービスは、柔軟な対応が可能なため独居の高齢者には特に適したサービスです。
そのほか、福祉用具を借りたり自宅を改修できたりするサービスもあり、それらを利用し環境を整えれば同居をしない生活も叶います。しかし介護保険制度は複雑で、サービスの内容や違いも分かりづらいのが正直な所です。
介護保険のプロであるケアマネジャーに相談すれば、一人ひとりにあったサービスを提案してくれるため安心です。認定の段階によって利用できるサービスは異なるため、まずは介護保険の申請から行いましょう。
介護保険以外のサービスを利用する
フォーマルサービスは介護保険だけではありません。介護保険外の民間サービスもたくさんあります。介護保険では賄えないペットの世話や正月の大掃除・旅行に同行してくれるサービスもあるため、生活の質の向上も期待できます。
地域のボランティア・近所の方・新聞や郵便配達の方などインフォーマルな社会資源の活用も可能です。また現代では、アレクサなどの見守りカメラ・靴に付けられるGPSなど、離れていても見守れるアイテムがたくさんあります。
ケアマネジャーは介護保険以外の社会資源にも詳しい場合が多く、インフォーマルな資源もケアプランに盛り込めるため相談するのもよいでしょう。地域の介護相談を引き受ける地域包括支援センターでも相談を受け付けています。
施設に入所する
自宅での生活が難しくなったら、施設入所の選択肢があります。施設の種類は多岐に渡り、同じ種類の施設でも力を入れている支援はさまざまです。親や家族のニーズにあった施設を選ぶとよいでしょう。
施設には大きく分けて2種類あります。施設ではなく「住宅」と位置づけているものもありますが、ここでは分かりやすく施設として説明します。
1つ目はケアマネジャーの配置が義務付けられ、施設内で介護が完結する介護保険サービスの施設です。例えば以下の施設があります。
- 特別養護老人ホーム
- 介護老人保健施設
- 認知症対応型共同生活介護
- 介護付き有料老人ホーム
2つ目は在宅として位置づけられ、自分にあった在宅系の介護保険サービスを使いながら生活を送る施設です。
- 住宅型有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- ケアハウス
施設によってサービス内容はさまざまです。「どの施設がどんなサービスをするのかさっぱりわからない…」とお悩みの方は、ケアスル 介護がおすすめです。
ケアスル 介護では、入居相談員が施設ごとに実施するサービスや立地情報などをしっかりと把握した上で、ご本人様に最適な施設をご紹介しています。
「幅広い選択肢から納得のいく施設を探したい」という方は、まずは無料相談をご利用ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
介護が必要な親と同居しようと考えるのはどんなとき
家を出て独立した子どもは、親の介護のためでも同居はしたくないと考える方が多い傾向にあります。親を心配して焦って同居を決める前に、親の今の状況を客観視して同居後の生活を冷静に考えてみましょう。
ここでは親がどのような状態のときに、子どもが焦って同居を考えてしまうのかご紹介します。
他人に迷惑をかけたとき
介護が必要になれば、ヘルパーさんにお風呂に入れてもらったり排泄の世話になったりする場合が多くあります。これらは他人の世話にはなってはいますが、迷惑をかけているわけではありません。
ここでいう他人への迷惑とは、認知症に由来する以下のような行為です。
- お金を盗ったなど被害妄想に陥り、近所の方に言いがかりをつける
- 家に帰れなくなってしまい警察に保護される
- 家の管理ができなくなり、ゴミ屋敷化し悪臭を放つ
このような状態になったとき、トラブルになってしまうといった焦りから同居を考える子どもが多い傾向にあります。
ひどい物忘れが現れたとき
高齢になれば誰にでも物忘れは現れますが、ここでいう「ひどい」とはどの程度の物忘れをさすのでしょうか。ひどい物忘れとは以下のようなケースです。
- コンロやストーブの火を消し忘れてボヤ騒ぎを起こす
- まだ冷蔵庫に入っているのに同じ食材を何度も買ってくる
- 薬の飲み忘れが大量にあったり、飲んだのを忘れて1日に何回も飲んだりしてしまう
このような場合、火事などの物忘れによって引き起こされる二次被害が懸念されます。足を複雑骨折して床に足を付けてはいけないのに、折れているのを忘れて歩いてしまうといった実例もあります。誰かが見ていないと何をするか分からず家族としては心配です。
親だけでは生理的欲求を満たせなくなったとき
マズローの欲求5段階説をご存じでしょうか。人間の欲求をピラミッドに見立てて5段階に分けたものです。下層の欲求が満たされなければ、その上層の欲求は生まれないとしています。
生理的欲求は睡眠欲・食欲・排泄欲など身体の動きに関する最下層の欲求です。高齢者が満たされていないケースとして次の例があげられます。
- 生活が昼夜逆転してしまい、眠たくて食事を食べられないなど昼間の活動に支障をきたしている
- お腹がすいているのに自分で食事を用意できない
- 排泄が上手にできなくて常に尿や便を漏らしている状態になっている
親がこのような状態の場合、同居して介護をしなければと感じてしまう方も多いでしょう。
親に介護が必要になったらなぜ同居といった考えに至るのか
誰しも高齢になれば、身体が弱り介護を必要とするのは当然です。しかし親の介護のために、子どもが同居をして面倒をみなければと誰もが考えるのはなぜでしょう。この考え自体が、子どもを縛り付けて悩ませる原因となっているのではないでしょうか。
介護と同居を結びつける理由を紐解いていきます。
家族以外の力を借りるのは恥などの昔ながらの根強い考え方
一昔前の日本には、子どもが家を継いで家長となりその家を守っていくといった、いわゆる家制度がありました。制度自体は半世紀以上前に廃止されていますが、今でもその風習から家族の面倒は家族が見るのを美徳とした考えが残っています。
小さいうちから子どもを保育園に預けるのは「かわいそう」といった考えや、子どもやお嫁さんが親の介護をしていれば「えらいわね」と言われるのもその名残です。
昔は拡大家族で男は仕事・女は家庭といった家がほとんどであったため、同居しながら親の介護ができたのでしょう。しかし現代は、核家族や単身者が増えるなど昔とは真逆の社会となり、時代に合わせて介護の方法も変えていく必要があります。
今まで苦労をかけてきたから今度は自分が世話する番といった責任感
子どもの頃は、誰でも多かれ少なかれ親に苦労をかけて成長してきました。なかには思春期にやんちゃをしたり、金銭面で多額の援助をしてもらったりした方もいるでしょう。今まで迷惑をかけた分の恩返しとして、同居をして介護をしてあげようと考えるためです。
しかし、子どもとの同居を必ずしも親が喜ぶとは限りません。身内に弱った姿を見せたくないと思う方もいるでしょう。このような状況での介護は、介護者主体となってしまう場合が多くみられます。本人主体とならなければ、ただの自己満足になる可能性があるため注意が必要です。
同居は当然といった考え方をまわりが押し付けてくる
親の介護のために同居したくないと思っていても、まわりがその考えを押し付けてくるケースがあります。親や自分の兄弟姉妹が「子どもが同居して介護をするのは当たり前」「長男が同居して面倒みるのが当然」といって同居させようとしてくる場合です。
心配だけど自分が同居をして介護をしてやれないから、別の身内に同居して介護をさせようといった考えのためでしょう。まわりから言われると、自分がやらないといけないと思い込み、したくもない同居をしてしまう方もいるかもしれません。
介護サービスなどの利用で、同居しなくても介護が可能であると理解してもらう必要があるでしょう。

介護が必要な親と同居するメリット
親の介護のために同居したくないと考える方は、無理に同居する必要はありません。しかし同居にはメリットもあります。メリットを知れば同居してもよいと思える方もいるかもしれません。
メリットの詳細をご紹介します。
急変時にすぐに対応できる
毎日一緒に生活をしていると、親の少しの体調の変化にも気が付くことができます。いつもより食べる量が少ない・顔が浮腫んでいる・トイレに行っていないようだなど、普段の様子を知っている家族が見た「何となくいつもと違う」が、急変のサインである場合も多いのです。
早期発見がしやすく、病院に連れて行くなどの迅速な対応ができるため、万が一のときも大事に至るのを防げる可能性があり安心です。
生活費や介護に対する費用が抑えられる
同居によって生活に必要なお金を節約できるのは、大きなメリットの1つです。親は年金暮らしといっても大切な収入源であり、家賃も折半でよいため貯蓄にまわせます。
また親の介護に必要なお金が節約できるのも魅力です。介護保険を使えばサービスは受けられますが、1割から3割の負担はかかります。できる範囲で同居する家族が介護を担えば、介護費用の節約にもつながります。
家族間交流が増える
自分の子どもと親、つまり孫と祖父母の交流ができ、子どもにも親にも生活のなかでよい影響がたくさんあるでしょう。子どもは祖父母に、お小遣いをもらったり伝承遊びを教えてもらったりでき、親にとっては孫の成長が生きる意欲にもつながります。
また疎遠になっていた身内が集まる場所になるなど、家族で過ごす時間が増えます。離れていた時間を埋めるように、思い出話に花を咲かせ楽しい時間を過ごせるでしょう。
介護が必要な親と同居するデメリット
親の介護のために同居をしたくない方のほとんどは、同居をして生じる生活の変化をデメリットとして考えてる場合が多くあります。同居によるどのような生活の変化が、デメリットと感じるのでしょうか。
デメリットの詳細についてご紹介します。
生活スタイルの違いによりストレスがかかる
幼い頃は一緒に暮らしていたとしても、大人になってからはそれぞれの生活を送ってきた親と子どもです。別々に暮らしていたのに突然一緒に暮らすとなれば、生活スタイルの違いにストレスを感じる場合も多いでしょう。
洗濯のタイミング・掃除の仕方・トイレの使い方・観るテレビ番組など、小さい違いが積み重なって大きな不満につながる場合もあります。もめそうなものは、最初に決まりをつくっておくのがトラブル回避のコツです。
介護者に休む暇がなくなる
親の介護の程度にもよりますが、介護は24時間休みがありません。介護が必要な親を持つ子どもは働き盛りの世代がほとんどのため、昼は仕事をして家に帰ったら親の介護が待っています。
夜中にトイレやオムツ交換といった親の排泄介助をしたり、夜中に家から出て行って戻って来ず探すなどの対応をしなくては行けなかったりと休む暇がないのです。介護者である子どもが休めるようにレスパイトケアも充分考えなくては共倒れになってしまいます。
もし介護と仕事の両立が難しく、介護施設を検討しているならばケアスル 介護がおすすめです。
ケアスル 介護では、家族のレスパイトケアの観点からも施設探しを行います。プロの入居相談員が条件に合った施設を探し、見学予約から日程調整まで無料で代行します。
「後悔しない施設選び」がしたいという方は、まずは無料相談をご利用ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
同居すると利用できないサービスがある
同居をすると利用できない介護サービスもあります。例えば訪問介護の生活援助です。同居家族がいる場合、家族ができる可能性があれば掃除や調理・洗濯といったサービスをケアプランに組み込めません。同居家族が働きに出ていて調理が難しい、老々介護で同居人も掃除を行えない状況といった場合は利用可能ですが、それでも同居人の分のサービス提供はありません。
またいずれも状況によりますが、特別養護老人ホームの入居の順番が下がったり介護保険サービス以外にも生活保護を受給しにくかったりします。
親に介護が必要になってもお互いに尊重した生活を送ろう
親の介護が必要になり弱った姿を見ると、ほとんどの子どもが親との同居を考えるでしょう。しかし本当は同居したくないと思っているのに、義務感や焦りから親と同居をしても、お互いにストレスがたまってしまいます。
お互いの生活を尊重し合い、お互いが安心して生活を送れる方法をみつけるのが1番大切です。同居をするしないにかかわらず、親が元気な頃から老後どのように暮らしていきたいか家族で話し合っておけば、いざ介護が必要になったときも安心です。
いいえ。同居をするしないで言うならばどちらでもよいのです。子どもにとって大切なのは、親の面倒を見る義務を果たしているかどうかです。詳しくはこちらをご覧ください。
親が元気なうちに、介護が必要になったら親自身はどうしたいのか身内も含めて話し合っておくのが大切です。同居には、メリット・デメリットがそれぞれあります。いざといったときにすぐに動けるよう、定期的に話し合いの機会を設けましょう。詳しくはこちらをご覧ください。





