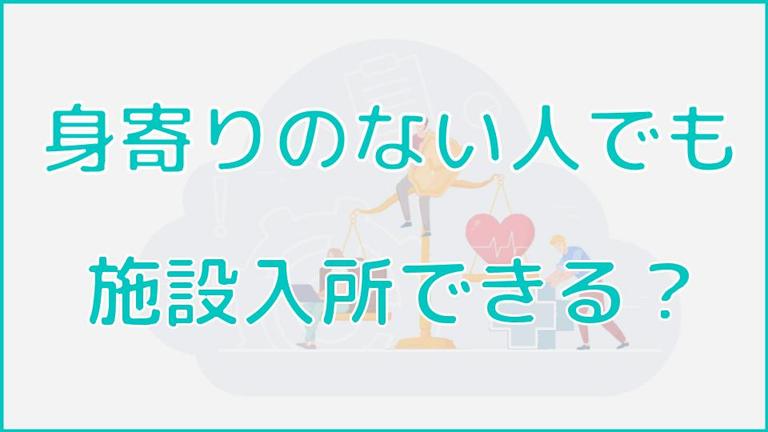「身寄りのない人が施設入所は出来る?」「何かあった場合、身寄りのない人はどうすればよい?」「子どもが居ないから老後が心配」こんな悩みを抱えている方は、少なくないでしょう。
身寄りのない人が抱える問題について、悩みや不安が解決できるよう、この記事では以下の内容を詳しく解説いたします。
- 身寄りのない方が受けられる支援
- 入所手続き・サポートの方法
- 将来の自分自身に関する役立つ知識
また、施設法人の定めや日々の法改正により、受けられる支援は異なります。この内容に関して、実例を基に解説していきます。
ぜひ、未来のため・ご家族のためにぜひチェックしてみてください。
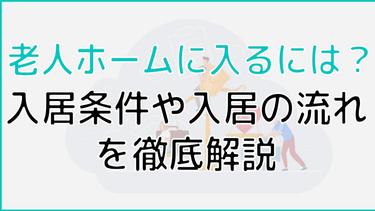
身寄りのない人が施設入所するためになにが必要?
身寄りのない人が施設入所するとき、ほとんどの場合が身元保証人を必要とする傾向にあります。
その理由は、主に以下の内容です。
- 緊急時の対応・判断
- 金銭面に関する保証
- 各種手続き
- 死去後の引き受け
一方で、施設によっては保証人なしで入れる場合があるのも事実。そのため、結果的に施設により違いがあるといえるでしょう。
今回は、施設入所に関して保証人が必要な場合について、詳しく解説していきます。
身寄りのない人が施設入所するために必要な3つの「人」とは?
身寄りのない人が施設入所するために必要な3つの「人」とは次のように分類されます。
- 身元保証人
- 連帯保証人
- 身元引受人
また、施設によって「身元保証人」「身元引受人」は用語が異なる場合があります。よく似ている用語になるので、施設入所を検討する際には、施設の方に用語の確認をしておくと安心です。
3つの「人」には少しずつ違いがあるので、次で詳しく解説していきます。
身元保証人・連帯保証人・身元引受人│それぞれの役割
身元保証人・連帯保証人・身元引受人という言葉が難しく、さらに法的に定められた内容も加わるため、責任を重く感じてしまう方も少なくありません。
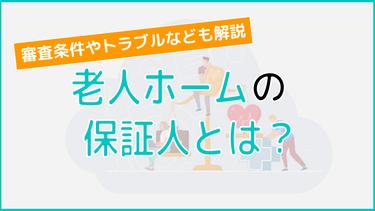
それぞれの役割は以下のようになります。
| 身元保証人 | 連帯保証人 | 身元引受人 | |
| 役割 | 本人が認知症や身体に何か起こった場合、身元保証人となった方が代理となる。
主になって手続きや対処、損害に関する対応を行なう。 |
本人が認知症や身体に支障をきたした場合、その責任を負う立場となる。
主に金銭面での責任を持つ場合が多い。 |
法的な用語として「身元引受人」はない。施設によって捉え方は多様。
入居者が退所または死去した場合に立会いを求められる場合や、保証人のような関わり方をする場合もある。 |
施設側が契約する際、不安を軽減するために「保証人」を立てておきたい意図があるというのもポイントです。不安を解決するための、役割があるともいえるでしょう。
身元保証人・連帯保証人・身元引受人│それぞれの違い
身元保証人・連帯保証人・身元引受人の3つの違いについて解説していきます。
| 身元保証人 | 連帯保証人 | 身元引受人 | |
| 違い | 本人が原因で施設側に損害が生じた場合に、その損害の代わりを担う役割。
総合的な役割でもある。 (一例として)
|
施設側から滞納などで請求などを求められた場合や、何か主張があった場合に施設側へ意見ができない立場。
身元保証人に比べ、不利な立場ともいえる。 |
3つの中では最も身軽な立場。
緊急時の連絡先や、入退院の手続き、退所時に身柄を引き取るなど。 施設によっては左記にある「保証人」と捉えられる場合もある。 |
また2020年4月1日からは新たに「根保証契約(ねほしょうけいやく)」が加わりました。
「根保証契約」とは、契約した時点で保証人が支払う金額の最低ライン(極度額)を決めて契約するもの。「〇〇円」と明確な金額を定めておく必要があります。
根保証契約は保証人にとって、より細かな契約ができるので保証額の想定がしやすいです。反対に、施設側は支払いの請求が無効または、契約無効にされるリスクがあるといえるでしょう。
保証人の必要なく入所することが出来る施設を探しているという方はケアスル 介護で探すのがおすすめです。
入居相談員にピッタリの施設を提案してもらえるので、初めての施設探しでもスムーズに探すことが出来ます。後悔しない老人ホーム探しがしたいという方はぜひ利用してみてください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
身寄りのない人の施設入所│なぜ保証人が必要?
身寄りのない人の施設入所には金銭面、生活面、保険外でのやり取りなど、本人だけでは解決できない課題がいくつかあります。
保証人が必要な理由は主に3つです。
- 契約・各種手続きの代行
- 緊急時の判断
- 入所費用・金銭の管理
これらの手続きや内容を、ご家族や、身寄りのない状態で1人で抱え込むのは大変でしょう。
施設側も入所者に関するリスクマネジメント(危機管理)として、身元保証人なしでの生活を安易に受け入れることは少ないです。施設が入所者に対して「責任は負えない」主張ともいえます。
保証人が必要な理由を明確にしておくと、いざ自身が同じ状況に立った場合の参考になるでしょう。上記に挙げた3つの内容を詳しく解説していきます。
契約・手続きの代行
契約や各種手続きは施設入所にとって、欠かせない手順の1つです。同時に入所から退所まで、一連の流れを把握・担う役割でもあります。
入所時に必要な書類は施設によりますが、おおむね次の通りです。
- 健康診断書
- 入居契約書
- 各コピー(健康保険証・介護保険証など)
- 戸籍関係の書類
入居時に必要な荷物の用意もしなければなりません。一例を紹介します。
- 衣類(肌着・上下の衣服・パジャマ)
- タオル・バスタオル・歯ブラシ・コップ
- 服用中の薬
また、退去時の手続きや荷物の撤去・死亡後も保証人が対応する役割があります。
死亡後の流れは、以下のようになります。
- 死亡診断書の受け取り
- 葬儀会社へ連絡
- 遺体の搬送に立ち合い
- 葬儀の打ち合わせ・葬儀
- 入所施設の遺品の引き取り
実際に契約となった場合、施設側が丁寧に説明をしてくれますのでご安心ください。
緊急時の判断
入所者に何かあった場合、すぐ連絡を取れる親族の存在は必要不可欠。「緊急連絡先」の把握は、施設側にとって重要なポイントです。
次の場合、保証人に連絡が入ったり判断を求められたりします。
| 連絡が入る内容 | 判断を求められる内容 |
|
|
入所中の緊急時の対応はさまざま。時間帯に関しても急を要する内容については、いつ連絡が入るかわかりません。
特段、急ぎでない場合は、施設側も保証人の要望により配慮してくれるでしょう。
入所費用・金銭の管理
入所費用や金銭問題は、大きなトラブルになりやすい問題の1つです。
自立度の高い方が入所する、有料老人ホームやサ高住(サービス付き高齢者住宅)の場合、金銭管理の方法は異なります。
- 施設側は本人の所持金について一切管理しない
- 管理が難しい場合、決められた金額内で施設側が管理
- 本人から買い物の依頼があれば一旦、施設が立て替える
上記のような決まりを設けている施設は少なくありません。
トラブル回避のため、細かな決まりがあるので事前の確認が必要です。
ほかには、入所者本人に判断能力がある場合は、問題ないですが、認知症や病状の悪化で支払い能力が低下した場合、代わりに支払う必要があります。
身寄りのない人の施設入所│保証人がいない場合は?3つの入所手段を解説
身寄りのない人が施設入所する際に「家族や身内がいない」「いても頼れる人が居ない」など、保証人になってくれる方がいない場合はどうすればよいでしょうか。
保証人がいない場合でも、施設入所できる方法はあります。それが以下の3つの方法です。
- 保証人不要の施設を検討する
- 成年後見制度を利用する
- 保証会社と契約する
3つの中でも「保証人不要の施設」は、ある程度の条件が付いてる可能性が高く、施設側も入居者側も安心できる契約内容になっています。
この内容をよく理解して、お互いが納得した状況で施設入所をするのが適切です。
保証人がいなくても入所できる方法3つを、詳しく解説していきます。
入所手段①身元保証人不要の施設を検討する
1つ目は、身元保証人不要の施設を検討する方法です。
保証人が不要の条件を出しているのは、ほとんどの場合が有料老人ホームやサ高住(サービス付き高齢者住宅)になります。
しかし、すんなり入れるとは限らないのが現状です。条件は曖昧で「保証人要相談」とする場合があります。結果的に、何らかの形で保証人が必要となる可能性も考えられるでしょう。
中には施設法人自体が、保証人としてサポートをしてくれる場合があります。施設により設定料金や内容は異なりますが、ある施設では基本的な保証プランで84万円から契約が可能です。
ご家族が支援する部分を、介護に関わる事業所が代行してくれるのは情報共有の統一や安心感もあるでしょう。
検討する施設が、どのような契約内容かを事前に確認しておきましょう。
入所手段②成年後見制度を利用する
2つ目は、成年後見制度を利用する方法です。
成年後見制度とは、さまざまな契約や手続きを一緒にサポートしてくれる制度です。
認知症の方、身体的・精神的障害のある方は、1人で判断や決断するのは不安が大きかったり難しかったりします。このような場合に正しく契約・手続きができるよう支援してくれます。
また、判断能力が低下している方などに対する詐欺被害も多発傾向です。被害を軽減するためにも、成年後見制度には、状況に応じた2つの制度に分類されます。
- 法定後見制度
- 任意後見制度
分類される2つの制度には、どのような違いがあるでしょうか。2つの違いについて、詳しく解説していきます。
成年後見制度│法定後見制度について
法定後見制度とは、認知症や障害によって自分で決めるのが不安だったり困難と感じたりする場合に、家庭裁判所によって選ばれた方(法定後見人)が支援してくれる制度です。
法定後見制度は、本人の不安・悩みの程度により3つの型に分類されます。
| 対象になる方・支援内容 | |
| 補助類型 |
|
| 保佐類型 |
|
| 後見類型 |
|
本人の判断能力、生活状況のレベルに合わせて法的に支援してくれる制度となるのです。
成年後見制度│任意後見制度について
任意後見制度とは「決められない」「判断できない」となる前に、事前に選んでおいた方(任意後見人)に代わりにしてもらう内容を契約できる制度です。
任意後見制度は、事前に内容を細かく決めておくのがポイントです。
- 誰を任意後見人にするか(法的に問題なければ親族・友人でも可能)
- 金銭管理全般(財産・年金・公共料金など)
- 介護認定の申請手続き・介護サービスの契約
- 入退院の手続き
- 入所施設の契約
前提として、これらの細かな内容を任意後見人が同意・契約する必要があります。そのためにも本人の要望がどんな内容なのかを、明確にする必要があります。
任意後見制度は、元気な間に契約しておく制度です。そのため「いつから支援してくれるの?」と疑問に思うかもしれません。
任意後見人になった方が家庭裁判所に開始する旨の申し立てを行い、家庭裁判所が必要だと判断して初めて任意後見人としての支援を開始できます。
成年後見制度を利用する際の注意点
成年後見制度は、身寄りのない方にとって安心できる制度です。
しかし、利用する際に注意しておく点があります。
- 検討する時期が遅いと自ら希望した人を選任できない場合がある
(判断能力の低下が、著しくみられるなど) - 本人が選んだ方が後見人として選任されない場合がある
(相応しくないと家庭裁判所が判断するなど) - 親族や友人ではなく専門家に依頼した場合は費用がかかる
- 資産運用、生前贈与ができなくなる等、本人のためにならないと判断された場合は認められない可能性がある
- そもそもの手続きに時間がかかる
成年後見制度を利用する際は、事前準備とともに注意点を理解したうえで利用を検討するとスムーズに対処できます。
入所手段③身元保証会社を利用する
3つ目は身元保証会社を利用する方法です。
身元保証会社とは、保証人が必要な方に対して、契約や手続き・金銭面などのサポートをしてくれる会社です。
保証会社を使用する方法も1つ目で紹介した「身元保証人不要の施設を選ぶ」のように、内容やプランによって利用料金はさまざまあります。
一例として、ある保証会社のプラン・料金設定をご紹介します。
| プラン | 料金 | サービス内容 |
| ランクA | 入会金1万円
+ 38.5万円 |
健康相談・生前遺品整理の見積・日常生活サービス 入院時サポート・介護時サポート・緊急時対応など |
| ランクB | 入会金1万円
+ 148.5万円 |
健康相談・生前遺品整理の見積・連絡代行・葬儀や納骨・行政手続き・遺品整理・相続サービスなど |
| ランクC | 入会金1万円
+ 187万円 |
すべてのサービスが利用可能 |
検討する際は、サービス内容が相応しいか、金銭的に問題はないか確認が重要です。また、いろいろな会社の資料と比較すると判断材料が見えてきます。
身元保証会社を利用する際の注意点
保証会社の内容を踏まえて、身元保証会社を利用する際の注意点をご紹介します。
| 内容 | 注意点 |
| 要望内容の整理 |
|
| 支払い能力の有無 |
|
| 契約内容の確認 |
|
| 考えられる今後の対応 |
|
身寄りのない人が施設入所する際は安心できるサポート体制かどうかが重要
身寄りのない人が施設入所する際は、一般的には身元引受人や保証人を必要とする場合がほとんどです。親族がいても、頼れる関係性でなく疎遠な場合も考えられます。
身寄りのない人でも施設入所を検討する際は、どのような施設があるか、または保証人制度や保証会社を検討すれば選択肢は広がります。
現状に不安が無くても、高齢になった未来の自分を見据えておくのは大切です。事前に対策を練り、物事を判断できている間になるべく解決して、安心できる老後を送りましょう。
お住まいの地域にある「地域包括支援センター」や「消費生活センター」でご相談が可能です。支援者(担当ケアマネジャーなど)がいらっしゃる場合は、その方にご相談もできます。詳しくはこちらをご覧ください。
保証人だった方が死去された場合や、何らかの理由により変更する事は義務となっています。変更時の注意点として、契約内容に相違がないか確認しておくとよいでしょう。トラブル回避のためにも重要です。詳しくはこちらをご覧ください。