「老人ホームの面会って、どれくらいの頻度で行くものなのだろうか。毎週行かなければならないのだろうか」
老人ホームへ入居している家族に会う面会は、本人に安心感を与えるうえで大切なことですが、どれくらいの頻度で行くべきなのかお悩みの方も多いと思われます。
本記事では、老人ホームの面会頻度と、面会時のマナーについて解説します。これからはじめて面会に行くという方も、ぜひ参考にしてください。
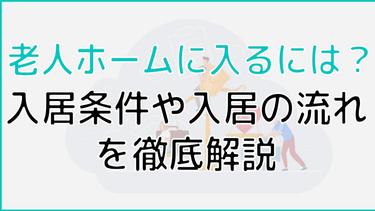
老人ホームの面会頻度はどれくらい?
老人ホームの面会頻度は、少なくとも1か月に1回は会いに行く人が多い傾向があります。
ほぼ毎日顔を見せに行く人もいれば、毎週1度は洗濯ものや消耗品を届けるために訪れる人もいます。
定期的に面会に行くことにより、本人の顔色や表情の変化に気づくことができます。場合によっては、症状の進行を遅らせることにつながる可能性もあります。
とはいえ、仕事や老人ホームの物理的な距離から、月に1度または2~3か月に1度は面会に訪れる人もいます。面会に訪れる家族にも事情があるため、周りの面会頻度に合わせて面会の回数を決める必要はありません。
面会は頻度が多ければ多いほど良いとは一概には言えません。ただ、何よりも入居している本人のことをどれだけ気にかけているかが大切です。
本人にとっても、家族にとっても無理のない頻度で面会に行きましょう。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
老人ホームの面会のマナー
老人ホームへ面会に訪れるにあたって、いくつかマナーがあります。この章では、老人ホームにおける面会のマナーについて説明します。
面会時は事前連絡をする
老人ホームに面会に行く前に、必ず施設に連絡を入れましょう。
老人ホームでは入居者が安全な生活ができるように、セキュリティを強化しています。そのため、入居者の家族やその親族から連絡がある人以外の面会はお断りすることが多いです。
無用なトラブルを避けるためにも、身内であっても事前に老人ホームに面会の旨を連絡しておくと良いでしょう。
面会しやすい時間
老人ホームの面会しやすい時間は、15~18時がおすすめと言われています。
基本的には、どの老人ホームであっても受付窓口が対応している時間ならいつでも面会に行くことができます。とはいえ、朝早い時間だと健康チェックや朝食があり、お昼は入浴や昼食でスケジュールが埋まっていることが多いです。
15時のおやつタイムを過ぎた辺りから、レクリエーションや自由時間を設けている施設が多いため、ゆっくりと面会したい方は15~18時辺りに訪れることをおすすめします。
面会の滞在時間
面会の滞在時間は、入居している本人の様子や顔を見て判断すると良いでしょう。
なかなか会う機会が少ないから、なるべく長い時間一緒にいたいとお考えの家族も多いです。しかし、長時間の滞在は入居している本人にとっても疲れを感じてしまいます。
入居している本人が「眠そう」「言葉数が少なくなった」と感じたら、面会終了の合図としましょう。
面会頻度同様、面会時間は長ければ長いほど良いとは一概に言えません。入居している本人にとっても、家族にとっても負担に感じない時間で楽しく過ごしましょう。
職員へのお土産は不要
老人ホームに面会するにあたり、施設職員へのお土産は不要です。
施設職員へのお土産などは、持参した本人に意図はなくとも、社会通念上賄賂になってしまう可能性があります。施設側も現金や菓子折りなどは受け取らないという規則を設けているところが多いです。
施設のスタッフに感謝の気持ちを伝えたいならば、「ありがとう」と言葉で伝えてもらえると幸いです。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
老人ホームの面会前に確認すること
老人ホームへ面会に訪れるにあたって、事前にいくつか確認しておくことがいくつかあります。順に解説します。
面会可能か確認する
老人ホームに面会に行くにあたり、対面での面会が可能か予め確認しておきましょう。
近年は流行り病の影響もあり、多くの老人ホームで面会に制限を設けています。徐々に面会制限が緩和されてはいるものの、免疫力の低下している高齢者は感染のリスクが高く、対面での面会をお断りしているケースも多いです。
なお、直接対面での面会ができなくとも、ガラス越しでの面会やzoomなどを用いたオンライン面会を行っているところもあります。施設職員がサポートしてもらえるため、感染のリスクを減らして、安心して面会を受けることができます。
また、面会の際には老人ホームのルールに従い、検温やアルコール消毒、マスクの着用などを徹底しましょう。
参照:厚生労働省 [高齢者施設における面会の実施に関する取組について]
同伴者について確認する
老人ホームへ面会に行く際に、子どもやペットを連れていく場合は、予め施設に確認しましょう。
施設によっては他の入居者への配慮で、お子さまの来館をお断りしているところもあります。
また、ペット可の老人ホームであっても、お部屋以外の同伴はお断りしているケースもあります。
老人ホームの規模やルールにより異なりますので、予め子どもやペットの同伴について確認しておきましょう。
食べ物や手土産について確認する
食べ物や手土産などを持参する際には、持ち込みの可否について確認しておきましょう。
老人ホームに訪れた際に、手土産として入居している本人が好きな食べ物やお菓子を持っていきたいと思う方は多いです。
老人ホームでは入居者の栄養管理やカロリー計算を行っているため、手土産の食べ物を食べてしまうと、カロリーなどを調整する必要性が生じます。入居している本人が施設で食事制限をしていないか、施設職員に聞いておきましょう。
また、食べ物を部屋に残す、本人に直接預けることは、体調悪化や嚥下の原因になりかねないため、禁止されていることが多いです。食べ物を持ち込む際には、必ず施設職員に連絡しましょう。
食べ物以外の手土産としては、衣服やタオルやブレンケットなどの日用品を持参する人が多いです。もしレクリエーションや趣味で必要とあれば、それらで使用する道具や材料などを持ってくるのも良いでしょう。
なお、流行り病の影響もあり手土産自体をお断りしている可能性もあります。面会に行く際には、事前に施設職員から手土産について確認しておくと良いでしょう。
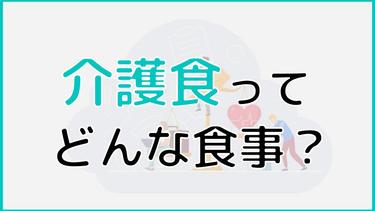
担当スタッフがいるか確認する
面会の日に、入居している本人を担当している介護スタッフが出勤しているか聞いておきましょう。
入居者の中には、介護スタッフの前と家族の前での態度や振る舞いが違う人もいます。担当の介護スタッフがいれば、心配事の相談や日々の生活に関して情報を共有することができます。
担当スタッフは面会時にずっと付き添ってもらうことはできませんが、何か不都合があった時にフォローしてもらいやすいです。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
老人ホームの面会時には何を話せばいいの?
はじめて老人ホームの面会に行くにあたり、どんな話をすればいいか、話題にお困りの方もいるのではないでしょうか。
入居している本人にとっては、顔を見ることが何より嬉しいため、ざっくばらんに日々の近況を話すだけでも嬉しいものです。
本章では、老人ホームで面会するときに、どんな話をすればいいのか一例を提示します。
老人ホームでの生活のこと
老人ホームでの食事やレクリエーションでの過ごし方など、入居している本人の生活について聞いてみましょう。
入居している本人にとっても、気にかけてくれていることが何より嬉しいものです。スタッフから生活の様子について説明を受けているとしても、日々の生活について聞いてみると良いでしょう。
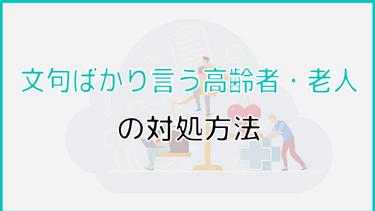
家族のことや思い出話
家族や身内で起きたこと、例えば身近なお孫さんの成長や家族の生活ぶりを知ることにより、生活にハリが出てきます。家族の写真や動画があれば、一緒に見るのも良いでしょう。
注意すべき点として、名前や思い出を忘れてしまったからと言って、無理に訂正しようとしないことです。
認知症によって物覚えが悪くなると、頻度に関わらず身内の名前や思い出を忘れてしまうケースもあります。そこへ高圧的な態度を取ってしまうと、面会に行くことがネガティブなことになりかねません。
入居している本人のペースに合わせて、ゆっくり話をすると良いでしょう。
大切に思っている気持ち
何より大切なことは、離れて暮らしていても大切に思っているという気持ちです。
入居している本人にとっても、家族と離れて老人ホームで生活することに寂しさを感じているものです。
面会の頻度が多い方が、入居している本人にとっても嬉しいことではありますが、離れていても気にかけているよと言葉で伝えることが、お互いにとっても大切なことと思われます。
老人ホームの面会頻度は無理のない範囲で
本記事では、老人ホームの面会頻度と、面会時のマナーや注意点について紹介しました。
一般的には月に1回以上面会に訪れる人が多いですが、仕事や事情もあるため、無理のない範囲で面会に行くことが大切です。
なお、面会の際には事前の連絡や確認しておく点がいくつかあります。老人ホームが定めたルールなども確認しつつ、お互いに有意義な時間になるような面会をしましょう。
老人ホームの面会頻度は、少なくとも1か月に1回は会いに行く人が多い傾向があります。とはいえ、ほぼ毎日顔を見せ行ける人もいれば、遠方で2~3か月に一度面会に訪れる人もいます。無理のない頻度で面会に行くことが大切です。詳しくはこちらをご覧ください。
面会に行く前に、必ず施設に連絡しましょう。入居者の安全を守るため、セキュリティを厳しくしている施設が多いです。身内であっても無用なトラブルを避けるために、必ず事前に施設へ連絡を入れましょう。詳しくはこちらをご覧ください。




