老健とは、長期入院からの在宅復帰などを目的として、専門的なリハビリテーションや医療ケアを受けることができる施設のことです。
公的な介護施設のため、比較的低価格な料金ながら、手厚い医療・介護サービスを利用できることが魅力となっています。
そんな老健ですが、入所を検討するにあたって「条件的に自分(親)は入所できるのかな?」と気になる方も多くいらっしゃいます。
- 親は要介護1なんだけど、入所できるのかな…
- 年齢と要介護度の条件は満たしているんだけど、他に条件はあるのかな…
- 老健に入所するときにはどんな手続きになるんだろう…
そんな疑問をお持ちの方々のため、今回は老健の入所条件から入所の手続き方法、老健についてのよくある質問まで詳しく解説していきます。

老健(介護老人保健施設)の入所条件
老健の入所条件は、以下の5つとなっています。
- 65歳以上であること
- 要介護1以上の認定を受けていること
- リハビリや医療ケアが必要なこと
- 支払い能力に問題がないこと
- 保証人がいること
それぞれについて順番に解説して行きます。
老健(介護老人保健施設)の入所条件①65歳以上であること
老健の入所条件として1つ目は、入居者本人が65歳以上であることです。
というのも、老健は介護保険が適用される公的施設のため、要介護認定の申請を行い認定を受けた方しか利用することが出来ないからです。
また、例外的に40歳~64歳の方でも以下の特定疾病が認められている方は入所することが出来ます。
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ※
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(出典;厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」)
以上より、老健は65歳以上の高齢者または40歳以上で16の特定疾病が認められていることが入所条件となります。
老健(介護老人保健施設)の入所条件②要介護1以上の認定を受けていること
老健の入所条件として2つ目は、要介護認定にて要介護1以上の認定を受けていることです。
要介護認定を受けるには、市区町村の窓口にて要介護認定の申請をしたのち、認定員による訪問調査や主治医による意見書の提出を行います。
そして、一次判定・二次判定により要介護度を判定することになります。要介護認定の結果たとえ65歳以上であったとしても要介護1以上の判定がなされなかった場合は老健には入所できません。
したがって、老健の入所条件として、要介護1以上の認定を受けていることが挙げられます。
老健(介護老人保健施設)の入所条件③リハビリや医療ケアが必要なこと
老健の入所条件として3つ目は、リハビリや医療ケアが必要なことです。
というのも、老健は上述したように在宅復帰を目的としている方のための施設なので、リハビリや医療ケアが必要でなく生活介助のみで十分という方は、入所できないことがあるのです。
老健は同じ公的施設の特別養護老人ホームと違って、作業療法士・理学療法士・言語聴覚士を入所者100人に対して1人以上配置することが義務付けられており、看護師の割合も多くなっているのが特徴です。
したがって、医療ケアを必要としておらず食事や入浴、排せつなどの生活介助のみを必要としている方は入所の条件に合わない可能性があるため、注意しましょう。
以上より老健は入所条件として、比較的病状が安定していて、リハビリや医療ケアが必要なことが挙げられます。
老健(介護老人保健施設)の入所条件④支払い能力に問題がないこと
老健の入所条件として4つ目は、支払い能力に問題がないことです。
というのも、上述したように老健などの老人ホームは費用が払えなくなっても簡単に退去させることはできないので、事前に支払い能力を確認されます。具体的には通帳の提示などが求められる場合があります。
とはいえ、老健などの公的施設は生活保護を受給していても入所することができ、生活保護を受給していると介護保険料や施設の家賃・食費・介護サービスの自己負担額もすべて介護扶助や生活扶助で賄われるので自己負担0で利用することが出来ます。(実際には日用品他で1~2万の自己負担は発生しています。)
そのため、支払い能力が無いという場合は子供から援助してもらったり、生活保護の受給を検討しましょう。
以上より老健の入所条件として、支払い能力に問題がないことが挙げられます。
老健(介護老人保健施設)の入所条件⑤保証人がいること
老健の入所条件として5つ目は、入所時に保証人がいることです。
ただし、入所時に保証人が必要かどうかは、施設によって異なります。
現に東京都の老健では、201施設のうち185施設が「保証人なし」で入所できることとなっているため、必ずしも保証人は必要ではないことを理解しておきましょう。
保証人が求められるケースがある理由としては、利用料の支払い、緊急時の連絡先、施設サービス計画書(ケアプラン)や治療方針の承諾、入院や死亡時の対応などが考えられます。
老健は、費用を払えなくなっても賃貸住宅などとは違ってすぐに退去させるということが難しくなります。このため、保証人が必要である施設もあることは気に留めておいてください。
したがって、民間の介護付き有料老人ホームなどの場合は保証人がいない場合は保証会社を利用するケースなどもまれにありますが、公的施設である老健では一部の施設を除いて保証人は必要なく入所することができる状況にあります。
以上より、老健の入所条件として、入居時に保証人がいることが挙げられます。
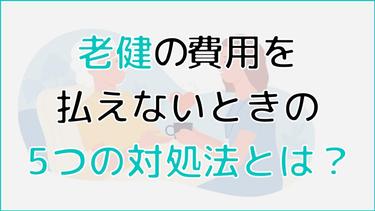
「老健に入居したいけど、どこまで医療行為やリハビリが必要になるか分からない」という方は、ケアスル介護で相談してみることがおすすめです。
ケアスル介護では、入居相談員が施設ごとに実施するサービスやアクセス情報などをしっかりと把握した上で、ご本人様に最適な施設をご紹介しています。
「身体状況に最適なサービスを受けながら、安心して暮らせる施設を選びたい」という方は、まずは無料相談からご利用ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
老健(介護老人保健施設)の入所に関するよくある質問
本章では老健の入所に関するよくある質問をまとめて解説して行きます。
「一般的な入所条件だけでは、本当に自分や親が入居できるのか分からない」という方も、ぜひ参考にしてみてください。
疾患を持っているけど入所できる?
治療中でなければ、基本的に疾患を持っていても老健への入所は可能です。
老健は糖尿病や心疾患、パーキンソン病のほか、認知症の方の入所にも対応しています。
インスリン注射や経管栄養、たん吸引などの医療行為も行えるため、疾患をお持ちの方も安心の環境だと言えるでしょう。
しかし入所者に医療行為を必要とする方が多い時期などは、看護師の管理上の都合から入所を制限されることがあります。
また、末期がんなどの重度の医療行為が必要な場合や、重度の認知症で入所者に危害を加える恐れがあると入所を断られる場合があるため注意しましょう。
寝たきりや末期がんなどの重度の状態である場合は、同じ公的施設の「介護医療院」への入所を検討することをおすすめします。
ずっと入所することはできる?
基本的に老健にずっと入所することはできません。
というのも老健は、入所者の在宅復帰と目的としてリハビリや医療行為を行う施設のためです。
したがって施設から「もう入所者の身体状況に問題がない」と判断されると、原則として3~6ヵ月で退所を促されます。
一方で6ヵ月が経っても「身体状況的にまだ在宅復帰が難しい」と判断された場合、以降も老健に入所していることは可能です。
原則として3~6ヵ月での退所が必要ですが、身体状況によってそれ以上の期間を老健で過ごせることもあることを理解しておきましょう。
家族は遠方に住んでいるけど入所できる?
家族が遠方に住んでいても老健への入所は可能です。
しかし介護の都合上、外部の病院への付き添いなどに家族の協力が求められることがあります。
したがって入所自体は可能ですが、家族はできる限りの協力体制を整える必要があるため、理解しておきましょう。
身内が全くいないけど入所できる?
身内が全くいなくても老健への入所は可能です。
ただし、この場合は契約・手続きなどを行うことができる保証人が必要となります。
具体的には後見人や福祉事務所のワーカーなどにお願いする必要があるため、理解しておきましょう。
また老健への入居をご検討の方は、ケアスル介護で相談してみることがおすすめです。
ケアスル介護では、ご本人様の希望に沿った施設をご紹介するだけではなく、施設の見学予約や日程調整の代行も行っています。
複数の施設と比較して、納得のいく施設選びをしたいという方は、まずは無料相談からご利用ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
老健(介護老人保健施設)に入所する際の注意点
老健は公的な介護施設であり、利用する方も多い施設ですが、実際に入所する際にはいくつかの注意点があります。
老健に入所する際の注意点については、以下の通りです。
- ずっと入所していることはできない
- 多床室が中心であるため、プライバシーの確保が困難
- かかりつけ医の診療が受けられなくなる
- 希望している薬が処方されない場合がある
それでは、1つずつ見ていきましょう。
ずっと入所していることはできない
老健は介護施設ではありますが、ずっと入所していることはできません。
と言うのも、老健は「要介護高齢者の自立支援を促し、在宅復帰を目指す」ことを目的とした施設であるためです。
在宅復帰を目的とした施設であるため、医療行為やリハビリなどのサービスを受け、在宅復帰が可能であると判断された場合には、老健を退所する必要があります。老健に入所していられる期間については、3~6か月が一般的ですが、依然として在宅復帰が困難であると判断された場合には、6か月を超えて入所していることができます。
とは言え、在宅復帰が可能と診断されたタイミングで退所を促されるため、ずっと入所していることはできません。
老健への入所を検討している方は把握しておきましょう。
多床室が中心であるため、プライバシーの確保が困難
老健は安い費用で利用できる施設ですが、その一方で居室タイプについては多床室が主であるため、プライバシーの確保が困難となっています。
多床室とは、2~4人で利用する居室であり、大きな部屋をパーテーション・カーテンなどで簡易的に仕切った部屋となります。病院の病室を意識してもらうと分かりやすいかと思います。
パーテーションやカーテンで仕切られているため、最低限のプライバシーは守られていますが、それでも同じ部屋の入所者の方の生活音が気になる、また生活音が聞かれてしまうなどの事態は避けられません。
個室タイプの居室もありますが、そもそも個室タイプの居室が少ないことに加え、多床室と比べると費用が高くなる傾向にあります。
老健への入所を検討している方は、把握しておくといいでしょう。
かかりつけ医の診療が受けられなくなる
老健に入所すると、これまでお世話になっていたかかりつけ医の診療が受けられなくなります。老健入所中は衣料保険サービスが利用できないため、入所者の診療は施設に常駐している医師が行わなければいけないと決められています。
そのため、長い間お世話になっていたかかりつけ医がいたとしても、入所後には老健に常駐している医師からの診療しか受けられないことを知っておきましょう。担当医師が変わることに不安を感じる方も多いと思いますが、医師同士でこれまでの診察状況や症状の情報を共有しているので問題はありません。
それでも気になる点があれば、入所相談の際に施設側にお問い合わせください。
希望している薬が処方されない場合がある
老健へ入所後は老健が薬の処方を行いますが、その医療費については施設側が負担するため、入所前に高い薬を服用していた場合などは、入所後は安価なジュネリック医薬品への変更や薬の処方を制限されるケースがあります。認知症の方に処方されるアリセプトなどは高価で、処方を条件とすると場合によっては入所拒否の理由となることがあります。
今まで服用していた薬は継続して処方してもらえるのか、処方してもらえない場合はどんな代替方法があるのかなど、入所の際にきちんと確認することが大切です。
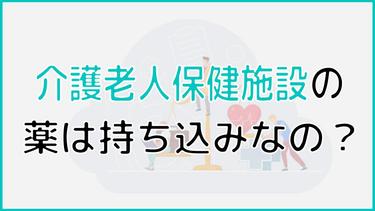
老健(介護老人保健施設)の入所条件のまとめ
老健の入所条件としては以下の5つの要件を満たしておく必要があります。
- 65歳以上であること
- 要介護1以上の認定を受けていること
- リハビリや医療ケアが必要なこと
- 支払い能力に問題がないこと
- 保証人がいること
老健の入所条件は基本的にはどの施設においても同一ですが、施設によっては保証人の有無などが変わる可能性があるので入所前は施設側に再度入所条件の確認をしておきましょう。
老健の入所条件は以下の5点です。①入居者が65歳以上であること ②要介護1以上の認定を受けていること ③リハビリや医療ケアが必要なこと ④支払い能力に問題がないこと ⑤保証人がいること詳しくはこちらをご覧ください。
老健は入所一時金などの初期費用は掛からず、月額費用は8~14万円と比較的安価な金額で利用することができます。要介護度・居室タイプごとに料金が異なるほか、年金収入やその他の合計所得金額などの年収によって負担割合と自己負担限度額が決められることになります。詳しくはこちらをご覧ください。





