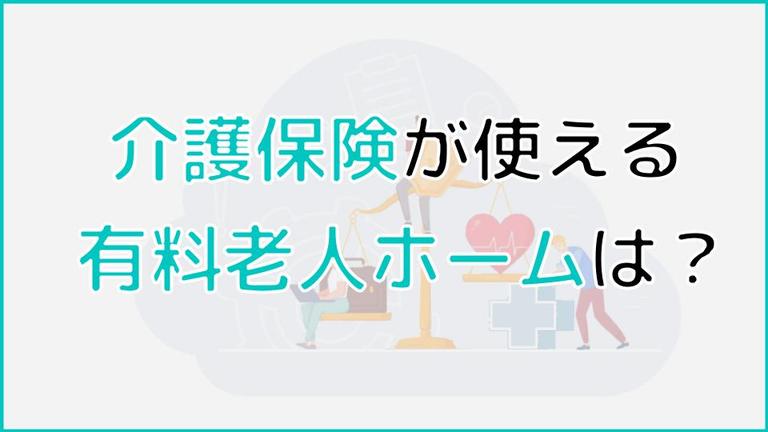有料老人ホームの入居を検討する時に「介護を必要とする」方も少なくないと思います。その中で「介護保険は使えるの??」と疑問に思っている方は必見です。
ここで学べるポイントはこれらのものがあります。
- 介護保険が使える有料老人ホームがわかる
- 介護保険が適用されるサービスがわかる
- 利用する費用を抑える方法がわかる
気になる方は、ぜひ最後までご覧ください。

介護保険が適用される有料老人ホームは2種類ある
介護保険を利用した介護サービスが受けられる有料老人ホームを探す場合、介護付き有料老人ホームと住宅型有料老人ホームから選ぶことになります。
しかし上記の通り、住宅型有料老人ホームは介護付き有料老人ホームと違い、施設のスタッフが介護サービスを提供することはありません。外部の介護サービス事業所と契約し、介護保険サービスを受けます。
介護付き有料老人ホーム
介護付き有料老人ホームとは、生活支援サービス介護サービスが一体となっている施設で、介護が必要になった場合は施設のスタッフから介護サービスを受けることができます。介護付き有料老人ホームのメリットは下記の通りです。
| 対象 | 60歳以上で自立・要支援・要介護の方 |
| メリット |
|
介護付き有料老人ホームの介護サービス費は、介護度別に定額料金が設定されており、介護度が変わらない限り毎月の介護サービス費は固定され追加費用はありません。
介護スタッフは24時間常駐で夜間や緊急時も安心です。施設によっては看護師も24時間常駐し、看取り体制が整っているところもあります。それぞれの施設でさまざまな特徴がありますので、入居予定者に必要な条件が揃っているところを探しましょう。

住宅型有料老人ホーム
住宅型有料老人ホームとは、高齢者の生活をサポートするサービスを提供する施設です。下記のようなメリットがあります。
| 対象 | 60歳以上の自立・要支援・要介護の人 |
| メリット |
|
住宅型有料老人ホームのサービスには、介護サービスはないので、介護が必要な場合は外部の介護サービス事業所との契約が必要になります。
比較的お元気な人は、利用するサービスも少なく済むので、介護付き有料老人ホームより介護サービス費が安くなる傾向にあります。
自立や要支援の人は、住宅型有料老人ホームが費用的にお得です。
介護サービスが提供される有料老人ホームを探しているという方は、ケアスル介護がおすすめです。ケアスル介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができるためご希望に沿った施設探しが可能です。
「プロに相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
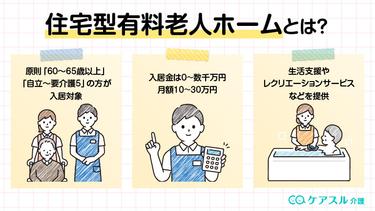
有料老人ホームにおける介護保険の適用範囲
介護保険が適用されるのは介護サービスのみ
有料老人ホームの施設サービスにおいて、介護保険が適用されるのは介護サービスのみです。
住宅型有料老人ホームでは、介護が必要になった場合は、外部の事業所との契約で介護保険サービスを受けることになります。
具体的には以下のような介護保険サービスが利用できます。ます。
- 訪問介護サービスのヘルパーから受ける食事・入浴・排せつの介助掃除、洗濯などの生活支援
- 施設から通うデイサービスやデイケア
- 理学療法士などのリハビリ専門家に施設に来てもらう訪問リハビリ
- 車いすやベッドの福祉用具レンタル
- ポータブルトイレやシャワーチェアなどの福祉用具購入
住宅型有料老人ホームで利用する介護サービスは在宅サービスと同じもので、自己負担額1〜3割(介護度による)で使える支給限度額が決まっています。それを超えるサービスを利用した場合は超えた分は全額自己負担となります。
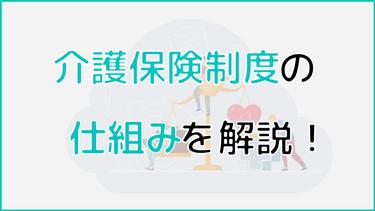
介護保険が適用されないサービス
介護サービス費以外の食費、生活費、居住費などは介護保険の対象外です。
また、草むしりや旅行の付き添いなど、生活するうえで必ずしも必要ではないサービスも介護保険は適用されません。以下が、介護保険を使用できない具体的なサービスになります。
- 利用者様の家族絵へ食事提供
- 入院や外泊時の空室の清掃
- 草むしり
- ペットの世話
- 旅行やプライベートの外出への付き添い
- 理美容
- お買い物の代行
介護付き有料老人ホームは、介護サービス費は介護度別に定額となり、自己負担額は収入により1〜3割と決まっています。しかし、上記のようなサービスは介護保険適用外で別途費用がかかるオプションサービスになることを覚えておきましょう。

また、介護保険は要介護認定を受けた人が介護サービスを利用した際にその費用の1部を国や自治体が負担するという制度で、介護度別に支給限度額(介護サービス費)が設定されており、利用者の自己負担額は収入によって1〜3割と定められています。
住宅型有料老人ホームでは、契約した外部のの事業所に利用した分の介護サービス費の1〜3割(収入による)を支払います。
認定された介護度により自己負担1〜3割で利用できる1ヶ月の限度額(支給限度額)が決まっており、限度額を超えた費用に関しては全額自己負担となります。
介護付き有料老人ホームは、介護度別に介護サービス費が決まっています。自己負担額は収入によって1〜3割で、それ以上の追加費用はありません。
●介護付き有料老人ホームの介護度別介護サービス費・自己負担額(1割負担)
| 要介護度 | 介護サービス費 | 自己負担額/月(1割) |
| 要支援1 | 54,600円 | 5,460円 |
| 要支援2 | 93,300円 | 9,330円 |
| 要介護1 | 161,400円 | 16,140円 |
| 要介護2 | 181,200円 | 18,120円 |
| 要介護3 | 202,200円 | 20,220円 |
| 要介護4 | 221,400円 | 22,140円 |
| 要介護5 | 242,100円 | 24,210円 |
●住宅型有料老人ホームにおける介護サービス費の介護度別支給限度額・自己負担額(1割負担)
| 要介護度 | 支給限度額 | 自己負担額/月(1割) |
| 要支援1 | 50,320円 | 5,032円 |
| 要支援2 | 105,310円 | 10,531円 |
| 要介護1 | 167,850円 | 16,765円 |
| 要介護2 | 197,050円 | 19,705円 |
| 要介護3 | 270,480円 | 27,048円 |
| 要介護4 | 309,380円 | 30,938円 |
| 要介護5 | 362,170円 | 36,217円 |
有料老人ホームの費用
初期費用はいくら必要?
初期費用として必要になるのが、入居一時金です。これは施設で定めた想定入居期間分の家賃として計算されています。
入居一時金は0円から数億円と開きがあり、それぞれの立地条件や設備、サービス内容や人員体制によって変わります。
また、施設によっては入居一時金を設定していない(0円)ところもあります。
同じ施設でも入居一時金と月額費用の支払い方法が選べる複数のプランを用意しているところもありますので、しっかり確認しましょう。
- 介護付き有料老人ホームの初期費用 0~数億円
- 住宅型有料老人ホームの初期費用 0~数億円
月額費用はどれくらいかかるの?
住宅型有料老人ホームの月額平均費用は12~30万円、介護付き有料老人ホームは月額平均費用15~35万円です。これは、介護サービス費や生活費、食費、家賃、光熱費などが加算された費用です。
この金額はお部屋の広さや設備、施設のサービスや食事の内容などで変わってきます。
また、入居一時金を多く払うことで月々の家賃相当分を安くすることもできます。
有料老人ホームの平均費用っていくら?
月額利用料としてはおおよそ19.4万円で、内訳としては以下のようなものになります。
- 家賃:5万~30万円程度。土地の値段や立地条件、建物の新旧、設備の充実度などで変わり、都市部ほど高額になる傾向にある
- 管理費:3万~20万円程度。部屋の広さ、入居者数などで変わる。光熱費が別途請求される場合もある
- 食費:4万~10万円程度。3食の食事分の材料費、調理スタッフの人件費も含む
- 上乗せ介護費:介護付き有料老人ホームの場合、要介護者2.5人に対して1人以上(2.5:1)の介護スタッフを配した場合、上乗せ介護費として月額費用で徴収することがあり、これは基本体制(3:1)に対して手厚い人員体制を敷いた人件費にあたる。その他別途費用:介護サービス費自己負担額、レクリエーション参加費、嗜好品・娯楽費、生活用品費、医療費など、入居者個人によって変わる費用費用は、人員体制やサービス内容などのソフト部分以外に、土地や建物・設備などのハード部分(不動産敵要素)でも大きく変わります。費用を抑えたい場合は、施設の立地条件等もも注意しましょう。
予算内に収まる有料老人ホームが知りたいという方は、ケアスル介護がおすすめです。ケアスル介護は、約5万件の施設情報を掲載しているため幅広い選択肢から検討することが可能です。
「納得いく施設を探したい」という方は、ご気軽に活用ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
有料老人ホームの費用を抑える方法
有料老人ホームの費用を抑えたい場合、入居する前にまずは扶養控除の申請を検討しましょう。老人扶養親族として扶養控除が適用されれば48万円の控除が受けられます。ただし入居者本人の所得が遺族年金等の非課税所得以外が48万円以下の場合に限られます。
また、介護費軽減制度として高額介護サービス費制度と高額介護合算療養費制度が挙げられます。
高額介護サービス費制度とは
毎月の支払いで、介護サービス費の自己負担合計額が、所得ごとに分けられた上限額を超えた時、超えた分が介護保険から払い戻される制度です。これには居住費や食費、福祉用具購入費は対象となりませんので注意しましょう。
| 区分 | 月の負担上限額 | |
| 現役並みの所得相当の方がいる世帯の場合 | 年収約1,160万円以上
(課税所得690万円) |
140,100円
(世帯上限) |
| 年収770万円~1,160万円未満
(課税所得380万円~690万円未満) |
93,000円
(世帯上限) |
|
| 市町村民税課税~年収770万円未満
(課税所得380万円未満) |
44,400円
(世帯上限) |
|
| 世帯全員が市町村民税非課税の場合 | 24,600円
(世帯上限) |
|
| 世帯全員が市町村民税非課税の場合 | 前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下 | 24,600円
(世帯上限) 15,000円 (該当者の負担上限) |
| 生活保護を受給している場合 | 15,000円
(該当者の負担上限) |
|
生活保護や前年度の年間収入が80万円以下の場合のみ、個人の負担上限とされていますが基本は世帯当たりの負担上限となります。
高額介護合算療養費制度とは
高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険の自己負担額合計が限度額を超えると超過分が払い戻される制度です。
これは所得によって負担の上限額が異なり、医療保険と介護保険の両方に利用者負担がある世帯が対象となります。期間は毎年8月から翌年の7月の1年間です。
| 区分 | 負担の上限額 | |
| 70歳未満 | 70歳以上 | |
| 年収1,160万円以上 | 212万円 | 212万円 |
| 年収770〜1,160万円未満 | 141万円 | 141万円 |
| 年収370〜770万円未満 | 67万円 | 67万円 |
| 年収165〜370万円未満 | 60万円 | 56万円 |
| 住民税非課税世帯 | 34万円 | 31万円 |
| 住民税非課税世帯(一定額以下) | 19万円 | |
例を示すと、全世帯者が市町村民税非課税であり、69歳の妻が医療保険で20万円、介護保険で20万円の年間負担合計40万円だった場合、申請をすると上限額34万円を超えた6万円が返還されます。
まとめ:有料老人ホームで介護保険サービスが使えるのは
ここまでの内容を簡潔にまとめると、以下のようになります。
- 有料老人ホームで介護保険サービスが使えるのは、住宅型有料老人ホームと介護付き有料老人ホーム
- 住宅型は介護が低い人がお得、介護付きは介護度が高くなっても安心
- 介護保険が適用されるのは介護サービス費のみ
- 支払い方法は3通り、無理のない支払い方法を選びましょう
- 控除や制度を活用して費用を賢くお得に
費用は、前述したように、立地条件や人員体制、サービス内容等で変わるので、実際に費用の内訳やサービス内容等を確認し、本当に必要かどうかをしっかり検討しましょう。
入居一時金を抑えたい場合は、入居一時金0円など初期費用が少ない施設を探してみると良いでしょう。
ただしその場合、月額費用が高くなるケースがあります。費用を検討する場合は、入居一時金と月額費用を総合的に見て、だいたいどのくらいの期間入居することになるかを想定して、総額費用を出してみることが大切です。
なります。ただし、どの有料老人ホームでも適応になるわけではありません。具体的には住宅型有料老人ホームと介護付き老人ホームの2つになります。詳しくはこちらをご覧ください。
あります。費用を抑える方法として控除を適応する方法と、介護負担費を軽減する制度を利用する等があげられます。控除は老人扶養控除、制度では高額介護サービス費制度と高額介護合算療養費制度になります。詳しくはこちらをご覧ください。