これから家族を在宅で介護する際、最も気になるのが「介護に必要なもの」ではないでしょうか。
特に初めて介護をする場合は、具体的に何を準備すればよいのかわかりません。スムーズに介護を進めるだけでなく、介護される側と介護する側の両方が抱える負担を減らすためにも、事前に自宅介護で必要なものを理解・準備しておくのが大切です。
今回は介護に必要なものを大きく5つのカテゴリーに分けて、それぞれの詳細を解説します。また、介護者の負担を軽減させるためのポイントも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
介護に必要なものは全部で5つある
自宅で介護するメリットの一つが、介護されるご本人が住み慣れた地域や家で暮らし続けられる点です。しかし、終わりが見えないため、介護する側にとっては大きな負担となるケースも少なくありません。
負担を少しでも減らし、スムーズな介護を始めるために事前準備を念入りにしましょう。介護に必要なものは主に「介護用品や便利グッズ」「介護保険サービスの申請」「協力体制の確認」「住環境の整備」「おおまかな費用の確認」の5つです。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
介護に必要なもの①:介護用品や便利グッズをそろえる
介護に特化した用品や便利グッズを上手に取り入れると、在宅介護にかかる負担を減らせます。主なものは次の通りです。
- 電動ベッド
- 車いす
- 歩行器
- 杖
- ポータブルトイレ
- シャワーチェア
- クッション
- 介護用の食器
- 介護食品
電動ベッドや車いすといったサイズが大きなものは、あらかじめ寸法を測っておきましょう。自宅に設置できるサイズかどうか、窮屈さを感じないかどうかの確認が大切です。
介護用品の中には介護保険サービスでレンタル、または購入できるものがあります。必要なものがあれば担当のケアマネジャーなどに相談し、ケアプランを作ってもらいましょう。
そのあとで福祉用具の業者を選び、事業所の福祉用具専門相談員がレンタルや購入のアドバイスをしてくれます。
介護用品のレンタル料金については、下記の記事をご覧ください。

介護に必要なもの②:介護保険サービスを申請する
自宅で介護をする際は、介護保険サービスの利用を検討しましょう。対象者は65歳以上で要介護・要支援状態にある方、または40~64歳で特定疾病の診断を受け、要介護・要支援状態にある方の2種類があり、条件に該当すればさまざまなサービスを受けられます。
介護保険サービスには大きく3種類がある
介護保険サービスは大きく、次の3種類に分けられます。
- 居宅サービス
- 施設サービス
- 地域密着型サービス
居宅サービスは自宅に住みながら受けられるものを指し、訪問介護や訪問看護、訪問入浴介護、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)などが該当します。介護スタッフが自宅へ訪問して食事や排泄などの介助をしたり、デイサービスへ日中通ってレクリエーションやリハビリをしたりと、在宅介護を支えてくれる重要なサービスです。
施設サービスとは、特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護療養型医療施設といった介護保険施設へ入所し、必要な介護サービスなどを受けるものを指します。
地域密着型サービスは、事業所がある市区町村に住んでいる方向けのサービスです。介護を必要とする状態になっても慣れ親しんだ地域で暮らせるように、訪問・通所型サービスや認知症対応型サービスなどがおこなわれます。
施設への入居を検討しているという方は、ケアスル介護がおすすめです。ケアスル介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができるためご希望に沿った施設探しが可能です。
「プロに相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
介護保険サービスの申請手順
介護保険サービスは何もしなくても、自動的に受けられるものではありません。利用するためには所定の手続きを踏み、申請する必要があります。
一般的な申請手順や必要となるものを、以下で見ていきましょう。
①役所や地域包括支援センターに連絡する
まずは現在住んでいる市区町村の役所、または地域包括支援センターに連絡を入れましょう。
役所の担当窓口の名称は「福祉課」や「介護保険課」「高齢者支援課」など、自治体によって異なります。わからない場合は総合窓口などで「介護保険サービスの申請をしたい」と伝えれば、担当の部署を案内してもらえるでしょう。
地域包括支援センターとは主に自治体が設置している、高齢者に関わる総合相談窓口です。社会福祉士や保健師、主任ケアマネジャーといった専門職が配置され、介護保険サービスを含むさまざまな相談・支援を担当しています。
②要介護認定を申請する
介護保険サービスを利用するためには、要介護認定を受けなければいけません。要支援1・2と要介護1~5、そして非該当に分かれており、要支援と要介護では利用できるサービスに違いがあります。
申請に必要な書類は次の通りです。
- 要介護認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 医療保険証(40~64歳までの場合)
- マイナンバーカード、または個人番号と身分証明書
詳細は役所の担当窓口や地域包括支援センターで案内してもらえるので、事前に連絡をして準備しておくとよいでしょう。必要な書類を担当職員へ提出します。
③認定調査を受ける
申請が受理されると、市区町村の担当職員などが自宅を訪問して、認定調査をおこないます。現在住んでいる自宅の環境や家族の状況、身体機能、生活機能、認知機能、特別な医療などについてチェックされます。
状況を正しく伝えるためにも、家族が必ず同席しましょう。ただし、本人の前で「一人ではできない」「トイレの失敗がある」などと伝えると、自尊心を傷つける恐れがあります。あらかじめメモにまとめて担当職員へそっと手渡したり、本人がいないところで帰り際に伝えたりするとよいでしょう。
④一次判定と二次判定により要介護度が決定する
認定調査による結果を基に、コンピューターが要介護度の一次判定をします。さらに、医師が記載する主治医意見書が一次判定の結果に加わって二次判定がおこなわれ、最終的な要介護度が決定されます。
主治医意見書は市区町村が直接医師へ依頼し、申請者の費用負担はありません。主治医が記載するのが通常ですが、中には「主治医がいない」「要介護に至った原因と担当診療科が異なるため、作成を断られてしまった」といったケースがあるかもしれません。
市区町村が指定する医師に依頼できるため、あらかじめ役所の担当窓口や地域包括支援センターへ相談してみましょう。
⑤それぞれに合ったケアプランを作成してもらう
要介護認定がおこなわれたら、介護保険サービスを利用するための介護(介護予防)サービス計画書(通称ケアプラン)を作成してもらいます。要支援1・2の方は地域包括支援センターが、要介護1以上の方は居宅介護支援事業所が担当です。
居宅介護支援事業所はたくさんあるため、役所の担当窓口や地域包括支援センターなどに紹介してもらうとよいでしょう。自宅から近いところや通院先に併設しているところなど、それぞれの事情に合わせて選んでください。
一人ひとりの心身状況や希望、家族のニーズなどを聞き取ったうえで、利用する具体的なサービスを決めていきます。
申請からサービス利用までの必要な期間は、1カ月ほどとなります。有効期間は新規と変更申請が6カ月、更新申請が12カ月です。
介護保険については、下記の記事をご覧ください。
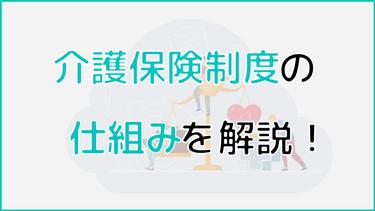
介護に必要なもの③:協力体制を確認する
自分一人だけで家族の介護を続けるのは、体力的にも精神的にも大きな負担となるものです。終わりが見えないものだからこそ、まわりの協力を得る必要があります。
専門家と家族、それぞれの協力体制を確認しましょう。
専門家による協力体制
在宅介護を支えてくれる専門家は前述した地域包括支援センターや居宅介護支援事業所のケアマネジャーを始め、通院先の主治医、訪問看護師、訪問介護事業所・デイサービスセンターのスタッフなど、たくさんいます。
状況に合わせて連絡を取り合い、必要なアドバイスやサポートしてくれるため、相談先や協力体制を確認しておくとよいでしょう。「いつでも相談できる相手がいる」と理解するだけで、介護にかかる負担が小さくなります。
家族間における協力体制
兄弟姉妹を含む家族がほかにいる場合、家族間における協力体制を作る必要もあります。特に以下で紹介する「介護の方針を明確にする」「役割分担をする」の2点に重点を置いて、よく話し合っておきましょう。
介護の方針を明確にする
自宅で家族の介護をする際は介護の手や時間、お金に限りがあります。そのため、介護を受ける本人やその家族が、どのような生活や介護を希望しているのか、具体的に実現できそうなものなど、おおまかな方針を家族間で明確にしておきましょう。
例えば「姉は毎週末に訪問して介護を手伝ってくれるため、平日を中心に訪問介護や訪問看護などのサービスを受けたい」といった方針が立つと、ケアプランをスムーズに作成できます。
役割分担をする
介護にかかる負担を一人に集中させず、また、家族間における関係性の悪化を防ぐためにも、役割分担をしておきましょう。介護する側とされる側の状況が急に変化したときも、対応しやすくなるメリットもあります。
まずは協力を仰げそうな家族一人ひとりの状況を整理して、「どのくらい介護に携わってもらえるか」「費用の負担をお願いできるか」などを明確にしてください。なかなか口に出しにくい内容かもしれませんが、思い立ったときに話題を切り出すと、話がスムーズに進みやすいでしょう。
介護に必要なもの④:住環境を整備する
自宅で介護をスタートさせる場合、住環境の整備を考えましょう。これまでは不自由なく暮らせていた環境でも、介護を必要とする状態になると不便さを感じる場面が出てくるものです。
「メインとなる生活スペースを決める」「スムーズに移動できるように導線を調整する」「必要に応じてスロープや手すりなどを設置する」の3点に絞って、環境を整えていきます。
メインとなる生活スペースを決める
まずはメインとなる生活スペースを決めましょう。
トイレや浴室が近いと身体が不自由な方も、必要なときにスムーズに移動できます。日当たりがよく、風がよく通る場所は明るい気持ちで快適に過ごせるでしょう。
また、家族と顔を合わせやすい場所かどうかも大切です。家族の顔を見てコミュニケーションを取ると、認知症やうつ病の予防につながります。
介護を受ける方にとって快適に過ごせる観点から、具体的な生活スペースを考えてください。
スムーズに移動できるように導線を調整する
安全に、かつスムーズに移動できるように日常生活上の導線をチェックしましょう。居室やトイレ、浴室、リビング、玄関といった生活の場で実際にどのように動いているかをよく観察し、スムーズな移動を妨げるものをあらかじめ排除・調整しておきます。
特に注意したいのが転倒です。高齢になると思っている以上に足が上がらず、つまずきやすくなります。そのため、すべり止めがないマットやゴザ、軽くてフワフワした敷物などは使用しない方がよいでしょう。
必要に応じてスロープや手すりなどを設置する
生活に不便さを感じるところがあった場合、必要に応じて住宅を改修しましょう。以下のような改修工事は、介護保険サービスが適用されます。
- 手すりの設置
- 段差の解消
- すべり防止や移動の円滑化のための床材変更
- 引き戸への交換
- 洋式便器への交換
ただし、改修費用の上限は20万円のため、1割負担の場合は18万円までが支給されます。改修を希望する場合は、ケアプランを担当しているケアマネジャーなどへ事前に相談しましょう。
必要書類を市区町村へ提出し、工事終了後に費用発生がわかるものを再度提出。償還払いのため、業者へ費用を支払ったあとで改修費が支給されます。
自己負担があるものの、改修によって介護する側・される側の負担が少なくなるでしょう。
介護に必要なもの⑤:おおまかな費用を確認する
介護では介護保険サービス料を始めとする、さまざまな費用が毎月必要です。公益財団法人生命保険文化センターの「生命保険に関する全国実態調査 令和3年」によると、在宅介護の一時費用は平均74万円、月額費用は平均8.3万円となっています。
費用があまりにも高額になると、経済的な負担が大きくなってしまうでしょう。そのため、事前におおまかな費用を確認しておいてください。
また、以下で紹介するような費用を抑えるためのポイントがあります。
参照:「生命保険に関する全国実態調査 令和3年」
費用をセーブするためのポイント①:状況に合ったケアプランを作成してもらう
介護保険サービスを利用する場合は、担当のケアマネジャーなどへあらかじめ家庭の金銭的な状況や希望を伝えておきましょう。何も伝えずにいると、費用を考慮しないお任せのケアプランが提示されるかもしれません。
例えば、毎月支払える上限額を伝えておくと「まずは費用がリーズナブルな、半日のデイサービスから始めてみましょう」など、状況に合わせたケアプランを作成してもらえる可能性が高まります。
費用をセーブするためのポイント②:加算や自費が少ないサービスを選ぶ
加算や自費が少ないサービスを選ぶと、費用のセーブにつながるでしょう。
例えば、同じデイサービスをおこなっている事業所でも職員配置や条件などによって、事業所ごとに取得している加算が異なります。加算が多くなればなるほど、加算がない事業所と比べて支払う費用が大きくなるのは当然です。
また、デイサービスセンターといった通所系の事業所では、食事代は基本的に自己負担です。具体的な食事代は事業所によって異なるため、費用を節約したい方は自費の部分にも着目するとよいでしょう。
介護の負担を軽減するためのポイント
無理がないように介護を続けていくためには、できるだけ負担を減らす必要があります。負担を軽減するためのポイントは次の3つです。
- 介護保険外サービスを利用する
- 介護のスキルを高める
- 同じ悩みを持つ方たちと交流する
介護保険外サービスは原則全額が自己負担ですが、金銭的な余裕がある場合は利用を検討してみるとよいでしょう。家族の衣類の洗濯や客間の掃除、食事の宅配など、さまざまなサービスがそろっています。
介護のスキルアップも大切です。スキルを持ち合わせていない状態で排泄介助や移動介助などをすると、身体的な負担が大きくなります。自治体によっては介護教室などを開催しているので、参加してみるとよいでしょう。
また、自分と同じ悩みを持つ方たちと交流する方法もあります。同じような体験や悩みを共感し合い、精神的な負担の軽減が期待できます。
市区町村や担当のケアマネジャーなどへ交流する場がないかどうかを尋ねてみましょう。
介護に必要なものを把握して準備を進めていきましょう
自宅でスムーズな介護を始めるためには、事前に準備しておきたいものがいくつかあります。まずは介護保険サービスの申請を検討しましょう。要支援や要介護に認定されると、認定に応じたさまざまなサービスを利用できます。
さらに協力体制の確認や住環境の整備、介護用品のレンタル・購入、費用の確認などを通して、少しずつ準備を進めていくのが大切です。
市区町村の担当窓口や地域包括支援センターなどは、無料で相談できます。わからない点や不安な点などがあれば、気軽に利用してはいかがでしょうか。
介護に必要なものに関するよくある質問
Q.介護の制度やサービスについての知識が全くありません。どこに相談すればよいのでしょうか?
A.現在住んでいる市区町村の役場、または地域包括支援センターへ相談してみましょう。介護保険を始めとする、さまざまなサービスについての情報を得られます。また、介護保険サービスを申請する場合は、手続きの方法についても教えてもらえます。
Q.65歳未満でも、介護保険サービスを利用できますか?
A.40歳以上65歳未満の方で介護保険サービスを利用する場合、以下で挙げる16の特定疾病のいずれかに罹患している必要があります。
・末期ガン
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・骨折をともなう骨粗しょう症
・後縦靭帯骨化症
・パーキンソン病関連疾患
・初老期の認知症
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・多系統萎縮症
・早老症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・糖尿病神経障害、糖尿病腎症、糖尿病性網膜症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節または股関節に著しい変形をともなう変形性関節症
ただし、同じ疾患名でも発症原因や症状によっては、特定疾病として認められないケースがあります。該当するかどうかは医師が判断するため、主治医に相談してみましょう。




