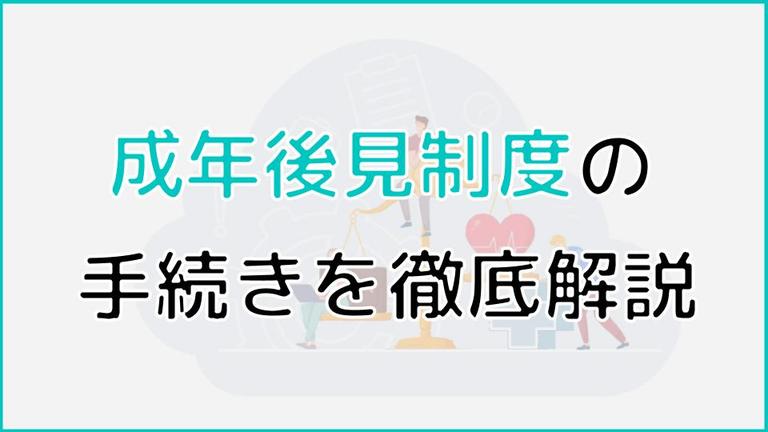認知症による判断能力の低下などによって財産の管理や処分などが出来なくなった、もしくは今後その心配がある場合に活用したい制度として成年後見制度があります。
既に判断能力が不十分な方が利用する法定後見制度、被後見人が元気なうちに事前に契約を結んでおく任意後見制度の2種類を使い分けることが大切です。
そこで今回は、成年後見制度の中でも法定後見制度、任意後見制度それぞれの認定手続きについて解説していきます。制度を利用する際の流れを理解して賢く活用しましょう。
法定後見制度の手続きと流れ
法定後見制度を利用して成年後見人になるには家庭裁判所への申し立ての準備から、成年後見人として行動できるようになるまで平均して3~6か月間の期間かかります。
法廷後見人が認定されるまでの流れは以下の5つのステップで進みます。
【法廷後見制度の手続きと流れ】
- 後見(補佐・補助)開始の申し立て
- 申立人、申し立て先の裁判所の確認
- 医師の診断書を取得する
- 必要書類を作成する
- 審理
- 申立人・後見人候補者との面接
- 裁判官の本人面接(必要な場合のみ)
- 親族への意向照会(必要な場合のみ)
- 医師による鑑定(必要な場合のみ)
- 審判(申し立てから1~2カ月程度)
- 審判確定(審判から2週間後)
- 後見登記
それぞれのステップについて解説していきます。
STEP1:後見(補佐・補助)開始の申し立て
法定後見人の申し立てを行う場合、まずは家庭裁判所に必要書類を提出しなくてはなりません。細かい手続きについて解説していきます。
STEP1-1 申立人、申し立て先の裁判所の確認
まず初めに法定後見人の申し立てができる人、申し立てを行える家庭裁判所の場所について確認しておきましょう。
- 申し立てを行える家庭裁判所:本人の住所地を管轄している家庭裁判所
- 申し立てができる人:本人・配偶者・4親等内の親族・市区町村長
- 4親等内の親族とは:親・祖父母・子・孫・ひ孫・兄弟姉妹・甥・姪・叔父・叔母・いとこ
特に申し立てを行うことが出来る裁判所は本人の住所地を管轄する裁判所であることに注意しましょう。そのため、遠方に被後見人が住んでいる場合はその住所地にある裁判所から申し立て書類を郵送してもらうこともできます。
STEP1-2 医師の診断書を取得する
法廷後見人の申し立てを行うには、被後見人の判断能力が低下していることを証明するための医師の診断書が必要となります。
法定後見制度は判断能力によって、判断能力が全くないと認定された場合の「後見」、多少の判断能力はあるものの著しく低下していると判断された場合の「補佐」、判断能力が不十分と判断された場合の「補助」の3段階に分かれています。
法定後見制度のどの類型で認定するかの判断材料として、主治医の診断書を取得しましょう。診断書は精神科医などに依頼する必要はありません。
STEP1-3 必要書類を作成する
医師の診断書を取得したら家庭裁判所に提出する書類の作成を行います。書類の提出までの流れは以下の通りです。
- 各裁判所のHPなどから申し立て書類をダウンロードする
- 本人に関する資料を用意する
- 申し立て書類に必要事項を記入する
- 収入印紙や郵便切手を用意して家庭裁判所に郵送する
STEP1-3-1 各裁判所のHPなどから申し立て書類をダウンロードする
申し立てに必要な書類は家庭裁判所ごとに様式が異なるので、被後見人の住所地を管轄している家庭裁判所のHPなどから書類一式をダウンロードしましょう。HP以外からも、
- 家庭裁判所の窓口で書類を受け取る
- 家庭裁判所から郵送してもらう
などから取得できます。以下は代表的な都市の家庭裁判所のHPとなります。
STEP1-3-2 本人に関する資料を用意する
申し立て書類の用意が完了したら、本人に関する資料を準備しましょう。具体的には、本人の健康状態、財産、収支を証明するために記入済みの申し立て書類と併せて提出する書類となります。
具体的には、以下のような書類が考えられます。
- 健康状態がわかる資料:身体障碍者手帳、精神障碍者手帳、療養手帳、介護保険認定書など
- 収入についての資料:年金額決定通知書、確定申告書、給与明細など収入がわかるもの
- 支出についての資料:各種税金の納税通知書、国民健康保険料や介護保険料の決定通知書等
これら以外にも不動産などの資産を所有している場合は、それらを証明する資料を準備しましょう。

STEP1-3-3 申し立て書類に必要事項を記入する
本人に関する資料を準備したら、申立書に必要事項を記入しましょう。ホームページからダウンロードした場合はパソコンで入力することも可能です。
また、家庭裁判所から郵送または紙で申し立て書類を取得した場合は手書きで記入しても問題ありません。
STEP1-3-4 収入印紙や郵便切手を用意して家庭裁判所に郵送する
最後に、本人に関する資料を準備して申し立て書類の記入が完了したら、収入印紙を準備して郵送しましょう。
収入印紙や郵便切手は最寄りの郵便局や家庭裁判所内で購入することが出来ます。金額は、
- 申し立て費用(貼用収入印紙) 800円
- 登録手数料(貼用収入印紙)2600円
- 郵便切手(予納郵便切手) 3200~3500円程度
が一般的です。
収入印紙は申し立て書に張り付け、裁判所からの返信用の郵便切手は封筒などに入れて郵送しましょう。
STEP2:審理
家庭裁判所への申し立てが出来たら審理が始まります。
審理とは、裁判官による申し立て書類の審査の他本人の状況やその周囲の状況を総合的に考慮する過程です。審査が完了したら家庭裁判所から法定後見人が選任されます。
審査から審判までの期間はおよそ1~2カ月で完了します。
STEP2-1 申立人・後見人候補者との面接
審査の最初のステップは申立人・後見人候補者との面接です。事前に予約した面接日時に家庭裁判所にて行われます。
面接相手は裁判所が指定した参与員(非常勤の裁判所職員)によって、申立人・後見人候補者から申し立てに至った背景や本人の判断能力、生活状況、財産状況等が確認されます。
面接の所要時間はおよそ1~2時間で完了します。
STEP2-2 裁判官の本人面接(必要な場合のみ)
裁判官が必要と判断した場合のみ裁判官と本人の面接が行われます。同じように家庭裁判所で行われるのが原則ですが、本人が入院中であったり体調不良で外出困難な場合は、家庭裁判所の担当者が自宅や入院先に訪問します。
裁判官の本人面接は、医師の診断書などから本人の判断能力が全くないと容易に判断できる場合は省かされることがあります。
STEP2-3 親族への意向照会(必要な場合のみ)
裁判官の判断で本人の親族に対して、後見申し立てや後見候補者についての親族の意向を確認することを親族への意向照会と言います。
申し立ての際に親族全員から同意書が提出されている場合はこの手続きが省略されることもあります。また、申立人や後見人候補者から親族への意向照会を品期で欲しいという要望があっても裁判官が必要と判断したら意向照会が実施されることもあります。
親族への意向照会で親族からの反発があった場合は、申し立ての際に指定している後見人候補者が選ばれない可能性も高くなります。
STEP2-4 医師による鑑定(必要な場合のみ)
申し立て書類や親族からの意向照会だけでは本人の判断能力を判定できない場合は、より詳細に医学的に判定してもらうことを鑑定と言います。
通常は本人の症状を把握している主治医による鑑定が行われますが、主治医による鑑定を行うことが出来ない場合はその他の医師による鑑定が行われることもあります。
こちらに関しても、医師の診断書などで明確に本人の判断能力がわかる場合は省略されることがあります。
STEP3:審判
審理が完了したら家庭裁判所の裁判官が調査結果や申し立て書類に基づいて法定後見人を選任することを審判と言います。
法定後見人の申し立てにおいては、「後見(補佐・補助)開始の審判」を行うと同時に最も適任とされている人を「法定後見人に選任」します。
また、場合によっては成年後見人を監督・指導する成年後見監督人が選任されることもあります。
STEP4:審判確定
審判の内容を記した審判所が選任された成年後見人に送付されて、2週間以内に不服の申し立てが無ければ後見開始の審判の効力が確定となります。
申立人や親族などの利害関係人は審判の内容に不服がある場合、2週間以内に限って即時抗告という不服申し立てを行うことが出来ます。
しかし、誰を成年後見人等に選任するかという点に関して不服申し立てを行うことはできませんので注意しましょう。
また、親族が後見人になりたいと思っていても、被後見人の財産額によっては、親族が後見人になれないケースも多くなっています。第三者が後見人に選任された場合は、被後見人が亡くなるまで、費用がかかる点を理解しておく必要があります。
STEP5:後見登記
審判が確定したら裁判所から法務局へ後見登記の依頼が行われます。
後見登記とは、後見人の氏名や後見人の権限などが記載されたもので、裁判所が依頼してから約2週間で完了後後見人へ登録番号が通知されます。
通知された登記番号をもとに法務局で登記の申請を行いましょう。
登記を行わないと本人の財産調査、預金口座の解約などの後見人としての権限を証明することが出来なくなるので、必ず行うようにしましょう。
後見登記が終了した後は、職務説明や初回報告などがおこなわれます。その後は定期的な報告業務が繰り返されていきます。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
任意後見制度の手続きと流れ
任意後見人制度は、将来的な認知症や障害などによる判断能力の低下にあらかじめ備えて、本人が選んだ人(任意後見人)に代わりに行ってほしいことを、あらかじめ契約で決めておく制度です。
家庭裁判所は任意後見契約が登記されている場合において精神上の障害などによって本人の判断能力の低下が見込まれた時に任意後見監督人を選任できます。
任意後見監督人の選任によってはじめて任意後見契約の効力が生じ、契約で定められた任意後見人が任意後見監督人の監督のもと契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行います。
任意後見制度の手続きと流れは、主に以下の5つのステップです。

- 任意後見契約の締結
- 自分を支援してくれる人を決める
- 任意後見契約内容を決める
- 任意後見契約の締結及び公正証書の作成
- 公証人から法務局へ後見登記の依頼
- 判断能力の低下が発生
- 任意後見監督人専任の申し立て
- 任意後見監督人の選任
- 任意後見契約の効力が発生
それぞれの流れについて詳しく解説していきます。
STEP1 任意後見契約の締結
任意後見制度の手続きの最初のステップは将来的に自分を支援してくれる人を決定し、契約内容を決めることから始まります。詳しく解説していきます。
STEP1-1 自分を支援してくれる人を決める
まずは任意後見人として選任する将来的に自分を支援してくれる人を決めましょう。将来任意後見人となってくれる人のことを「任意後見受任者」と呼びますが、家族や知人以外にも弁護士などの専門職、またNPO法人や社会福祉協議会などの法人を選ぶこともできます。また法定後見制度と異なり、後見人は利用する側の希望が通りやすくなります。
自分が将来、判断能力が低下したときに任意後見人として財産管理や老人ホームへの入居手続きなどを代わりに行う人になるので、信頼できる人を選びましょう。
STEP1-2 任意後見契約内容を決める
任意後見受任者が決まれば、任意後見契約内容を決めます。契約内容としては、
- 認知症と診断された場合、介護を受けるための手続きを代行して欲しい
- 在宅介護が難しくなったら○○の施設に入所したい
- 体調が悪化したら入院先は△△病院がいい
- 墓参りは年に○○回行きたい
など将来の生活に関する具体的な希望や金額を記載したライフプランから具体的に決めていきましょう。したがって、契約内容として決めておくこととしては、
- 介護や医療の受け方の希望について
- お金の使い方や不動産などの財産の活用・処分など
- 任意後見人の報酬や経費について
- 任意後見人に依頼する業務の範囲について
などが代表的なものです。
STEP1-3 任意後見契約の締結及び公正証書の作成
任意後見契約は法律によって公正証書で作成することが義務付けられているので、契約内容をまとめた原案を公証役場に持ち込んで公正証書を作成してもらいましょう。
公正証書とは、公証役場という法務省管轄の役所で作られる高い証明力を持つ文書となります。公正証書作成の流れは以下の通りです。
- 構成役場に契約内容をまとめた原案と必要な資料を提出
- 公証人が作成した任意後見契約の草案を事前に確認
- 公正証書の作成日時の予約を実施
- 本人と任意後見受任者が公証人の前で契約内容を確認し、署名押印する
公正証書を作成する際の必要書類と費用の目安は以下の通りです。
| 項目 | 内訳 |
|---|---|
| 公正証書作成の基本手数料 | 11000円 |
| 登記嘱託手数料 | 1400円 |
| 登記所に納付する印紙代 | 2600円 |
| 必要書類 | ①任意後見契約と代理権の範囲の原案 ②本人の戸籍謄本、住民票、実印、印鑑証明書 ③任意後見受任者の実印、印鑑証明書 |
STEP1-4 公証人から法務局へ後見登記の依頼
任意後見契約の締結が完了したら、公証人は法務局へ後見登記の依頼をします。公証人が依頼してから2~3週間で登記は完了し、登記内容を書面化したものを「登記事項証明書」と言います。
登記事項証明書によって任意後見人の氏名や代理権の範囲が明確になるので、任意後見人が銀行などでの手続きを行う際の証明書となります。
STEP2 判断能力の低下が発生
任意後見契約を結んだ後は、認知症を発症したり、精神障害などによる判断能力の低下が発生するまで、手続きは一旦ストップします。
判断能力の低下が発生するまでの期間は、社会福祉協議会やNPOなどの法人を任意後見人に選任している場合は、数週間に一度程度、家庭訪問などを通じて本人の判断能力が衰えていないかの確認が行われます。
仮に個人を任意後見人に選任している場合も、本人では判断能力の低下に気が付くことが出来ない場合もあるので様子を確認し連絡を継続的に取っておくことが重要です。
STEP3 任意後見監督人選任の申し立て
本人の判断能力の低下がみられる場合は、家庭裁判所に申し立てて任意後見監督人を選任してもらいます。
任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したと同時に効力を発揮することとなります。
任意後見監督人は、判断能力が低下している本人に代わって任意後見人が契約通りに適切に財産管理を行っているかどうかを監督する人です。任意後見人による横領などの発生を防止するために選任します。
任意後見人選任申し立ての流れとしては以下の通りです。
- 各裁判所のHPなどから申し立て書類をダウンロードする
- 本人に関する資料を用意する
- 申し立て書類に必要事項を記入する
- 収入印紙や郵便切手を用意して家庭裁判所に郵送する
法廷後見制度の場合と同じように各家庭裁判所によって申し立ての書類の書式が違っている場合があることに注意しましょう。
書類の内容は異なりますが、手続きの流れはおおむね法定後見制度の手続きと同じ流れで進んでいきます。詳しく知りたい方は1章の「公証人から法務局へ後見登記の依頼」をご覧ください。
STEP4 任意後見監督人の選任
申し立てがあった後は家庭裁判所が本人の状況や任意後見人受任者の事情などを踏まえて審理し、任意後見監督人を選任します。
選任の結果は書面で家庭裁判所から任意後見人に郵送され、任意後見監督人の情報と任意後見が開始されたことは家庭裁判所の依頼によって法務局が登記します。
STEP5 任意後見契約の効力が発生
上述したように任意後見監督人の選任をもって任意後見契約の効力が生じます。
任意後見契約の効力が発生したら契約内容の範囲内で任意後見受任者は代理として銀行や役場などで手続きを行っていきます。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
成年後見制度の手続きでかかる費用
成年後見制度には法定後見制度、任意後見制度の2種類ありますが、それぞれでかかる費用について振り返ります。
法定後見制度でかかる費用
法定後見制度でかかる費用は12,000~20,000円程度です。申立手数料および後見登記手数料として3,400分の収入印紙代がかかる他、連絡用の郵便切手として3200~3500円程度、その他医師の診断書の作成費用が数千円かかります。
また、審査の過程で本人の判断能力を審査するために鑑定が行われ場合、通常かかる費用に上乗せで、10万円程度の費用が必要となります。ただし、上述したように鑑定は裁判所が必要とした場合のみかかる費用となります。
法定後見人に専門職が選任された場合は高検事務を行った場合の報酬として通常月額2~5万円程度の報酬を支払わなくてはならないことに注意しましょう。
任意後見制度でかかる費用
任意後見制度でかかる費用は15,000~20,000円程度です。構成役場の手数料として1契約につき11,000円かかる他、法務局に納める印紙代2,600円、法務局への登記嘱託料1,400円や書留郵便料、謄本の作成手数料が数百円かかります。
また、法定後見人と同じように専門職に依頼した場合は月2~5万円程度の報酬の支払いが発生することに注意しましょう。
成年後見制度の手続きは代行できる?
成年後見人制度の手続きは代行することもできます。法定後見制度の場合、成年後見人の選任手続きの代行を頼む場合は10~30万円、任意後見契約を締結する際の公正証書の作成を依頼すると10万円前後、任意後見監督人の選任手続きの代行を依頼すると20万円前後の費用が必要となります。
具体的な金額は司法書士や弁護士によって異なりますが、成年後見制度の手続きを代行する場合は10~30万円の費用を支払うことで代行も可能です。
成年後見制度の手続きのまとめ
認知症などで判断能力が低下した人の財産や権利を守ることが、成年後見制度の重要な役割です。本人に代わってさまざまな法律行為を行う後見人は、対象となる人の要件があったり、行える行為が限定的に定められていたりします。
法律上の決まりが多いため、制度についてはできるだけ詳細に理解することが大切です。また法定後見制度については、制度の利用がスタートすると、被後見人が亡くなるまで、利用を終了することができません。その間、費用がかかり続けますので、費用の見積もりも重要なポイントになります。制度をきちんと理解したうえで、成年後見制度を上手に活用して、高齢者の財産や権利を賢く守りましょう。