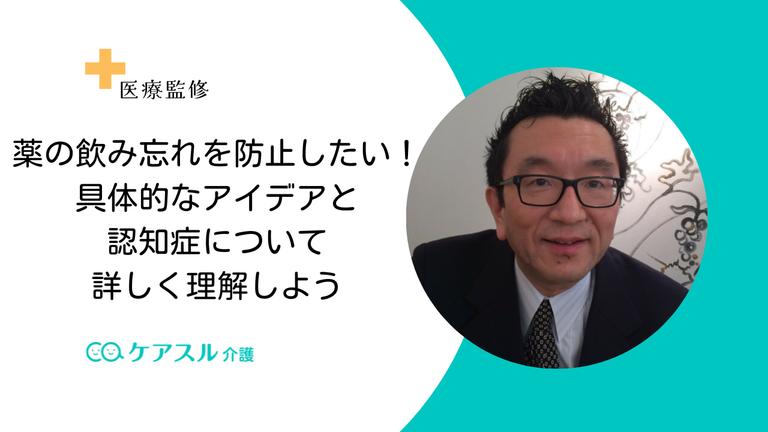多くの方が病院から処方された薬を飲み忘れた経験があるはずです。実際、全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社の調査によると50%以上の方が薬の飲み忘れた経験があるとのことでした。
そこで今回は、認知症の方でも薬を飲み忘れ防止するためのアイデアを解説します。また併せて、認知症について生じる原因・今後の傾向まで解説しますので、本記事をぜひ参考にしてください。
認知症でも薬の飲み忘れ防止するためのアイデア
認知症の方でなくても薬の飲み忘れは多くみられるため、認知症の方になると、その可能性はより高くなります。
ここでは、認知症の方でも少しでも薬の飲み忘れを防止するためのアイデアについて紹介します。
生活リズムを合わせる
服薬を忘れると、健康に悪影響なこともあるため、何としてでも薬を飲ませようとする場合がありますが、無理に飲まそうとすると、服薬に対してマイナスな記憶が残り逆効果です。
そのため、無理に飲ませようとせずに、生活リズムを合わせることも重要です。ただ、服薬の時間がズレてしまう可能性もあるので、医師に対して状況を説明し、許可を得ておく必要があります。
薬を一包化する
薬の飲む種類が増えると、薬の間違え・飲み忘れなどが生じる可能性は高くなってしまいます。
しかし、全ての薬をまとめて一包化すれば、薬の間違え・飲み忘れが生じる危険性は下がります。そのため、医師に相談して、可能なのであれば調剤薬局などで服用時間を刻印し、一包化してもらいます。
ピルケースを活用する
ピルケースに薬を朝・昼・夜の3つに分けて、時間になったら取り出して飲むことで、1人で薬を飲めるが適切な服用量がわからない場合でも、飲み間違いを減らすことができます。
また、同居人が服薬管理する場合でも、薬がピルケースに分けられていることで、ある程度、服薬の有無を把握できます。
服薬管理を支えるグッズを使用する
近年では服薬管理するのに、下記のようなさまざまなグッズが出ています。
- お薬カレンダー
- 服薬時計
- 用法別配薬袋
それぞれのグッズについて紹介します。
お薬カレンダー
お薬カレンダーは、収納グッズで、壁掛けタイプ・シートタイプなどの種類があります。お薬カレンダーの特徴として、時間・曜日などが記載されているため、いつどの薬を飲む必要があるのか一目で分かります。
ただ、服薬の量が多いと、1つのポケットに入りきらない、入れ間違いなどが生じる可能性があるため注意が必要です。
服薬時計
置時計タイプで、セットしている服薬時間になると音声で教えてくれます。そのため、本人だけでなく、家族も薬の飲み忘れを防ぐことができます。
ただ、自宅での問題なく使用できるものの、音声アラームが鳴るため、多くの人がいる場所などでは使用しにくいデメリットがあります。
訪問薬剤師を利用する
訪問薬剤師とは、在宅で介護を行っている利用者の自宅へ訪問して、薬剤の提供・管理だけでなく、健康に関する相談に応じる場合もあります。
一般的な調剤薬局・病院の場合であれば、処方箋を持って来局し、その場で処方・服用指導を行いますが、認知症などが原因で通院することが難しい場合は、訪問薬剤師を利用できます。
訪問薬剤師を希望する場合は、まずはかかりつけ医に相談をして薬剤師による在宅訪問の許可をもらいます。その後、医師が薬剤師に指示をし、認知症の方や家族と訪問日時を話し合うことで利用できます。
ただ、何回も使用できるわけでなく、病院などの薬剤師であれば月に2回、薬局の薬剤師であれば月に4回までという利用制限があるため注意が必要です。
認知症について詳しく理解しよう
「認知症」は、特定の病名ではなく、何らかの病気や障害などによって脳の働きが悪くなり、記憶、判断力などの認知機能が低下して、もの忘れや日常生活や仕事に支障をきたすようになった状態のことをいいます。
なお、「加齢によるもの忘れ」と「認知症によるもの忘れ」は下記のような違いがあります。
| 加齢によるもの忘れ | 認知症によるもの忘れ | |
| 自分が経験したこと | 朝ごはんの内容など一部忘れる | 朝ごはんを食べたこと自体忘れる |
| もの忘れしている自覚 | ある | ない |
| 日常生活への支障 | ない | ある |
| 症状の進行 | 極めて徐々にしか進行しない | 進行する |
年齢を重ねると多くの場合、物覚えが悪くなる・人の名前を忘れるなど脳の老化が出現します。しかし、上記から分かるように認知症の場合、進行してしまうと、体験したこと自体を忘れてしまい、何かヒントを与えても思い出すことは困難です。
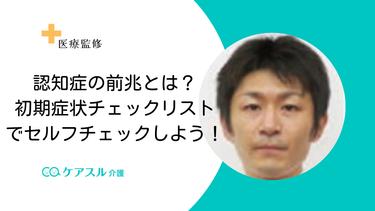
認知症は今後さらに増加する
令和4年版高齢社会白書によると、国内の高齢者人数は年々増加しており、2021年10月時点では、総人口1億2550万人のうち65歳以上人口は28.9%の3,621万人となっています。高齢者の中でも65〜74歳が14.0%の1,754万人、75歳以上は14.9%の1,867万人となっており、75歳以上の方が多い割合となっています。
高齢者の割合が多くなる程、認知症の人数も増え、「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」によると、2025年に約650~700万人、2040 年に約800~950 万人、 2060年に約850~1150 万人と時代が進むにつれて人数が増加すると予測しています。
認知症の初期症状
認知症を生じた原因によって、初期症状は異なるものの多くの場合「もの忘れ」が原因で認知症に気付くことが多くあります。その他にも、物事に対する「理解・判断速度の低下」「集中力・作業能力の低下」などの症状もみられます。
具体的な状況は下記のような場面です。
| 症状 | 場面 |
| もの忘れ | ・同じ話を繰り返し行う
・約束したことを忘れる ・以前買ったものを不必要に何度も買う ・鍵や財布をよく無くす |
| 理解力・判断速度の低下 | ・買い物の支払計算が難しくなる
・普段の会話速度についていけない ・信号が赤になりそうでも渡る |
| 集中力・作業能力の低下 | ・読書好きなのに本を読まなくなる
・テレビドラマなどが追えない ・趣味の料理などの家事を途中でやめる |
症状の自覚はなくても、今まで問題なくできていたことができなくなったなどから、漠然とした強い不安や混乱、怒りを感じることも多くあります。
認知症の中核症状とは
認知症の症状は大きく2種類に分かれ、その1つが「中核症状」となり、下記のような症状があります。
| 症状 | 出来事 |
| 記憶障害 | ・数分〜数日のことに対する短期記憶が失われやすく、数か月〜数十年前にわたる長期記憶は保たれやすい傾向です。
・体験した記憶を一部ではなく、丸ごと失ってしまう特徴があります。 |
| 見当識障害 | ・いまが何時か、何月何日かがわからなくなる
・今どこにいるのか分からなくなる ・始めは普段会わない方、徐々に家族など近い方も分からなくなります。 |
| 実行機能障害 | 物事の計画を立てた後に工程を順序通りに行う能力が低下します。 |
| 理解・判断力の障害 | 物事の状況を正確に理解して、判断することが難しくなります。 |
| 失行、失認、失語など | 道具の使い方が分からなくなる「失行」、目から得た情報を適切に認識できなくなる「失認」、言語の理解や発話が難しくなる「失語」などが生じます。 |
中核症状は、程度の差はあるものの、認知症となれば必ず生じる症状で、進行するとともに徐々に重くなります。また、症状の進行も薬を使用すれば遅らせることはできるものの、完全に進行を止めることはできない特徴があります。
認知症の周辺症状とは
認知症の2つ目の症状は「周辺症状」です。先程解説した中核症状が続くと、本人に強い不安・混乱などが生じてしまった結果、二次的に引き起こされる症状で下記のような特徴があります。
| 症状 | 出来事 |
| 興奮、暴力・暴言 | 不安・混乱・感情のコントロールができないなどの理由により、興奮する、暴力・暴言などがあります。 |
| 介護への拒否 | 「手を煩わせて申し訳ない」というストレスと、迷惑をかけているという悲しみなど、多くの感情が重なって生じてしまいます。 |
| 抑うつ、不安、無気力 | できないことが少しずつ増え、日常生活に影響が出だすと、食欲不振・意欲の低下・不眠など気分が落ち込んだ結果、抑うつ状態になってしまいます。 |
| 徘徊 | 外出時に道に迷うだけではなく、自宅などよく知っている景色も初めての場所と感じてしまい、「家に帰らないと」などと思い徘徊するようになります。 |
| 妄想 | 記憶障害が進むと、財布やお金が周囲の人に盗られたなどと言う「もの盗られ妄想」など、普段では生じえない考えを思い込んでしまいます。 |
| 幻覚 | 衣服などを人と見間違えるような、普段では間違えないものを見間違うことが多々あります。 |
周辺症状は必ずしも引き起こるわけではありませんが、置かれている環境や周囲の対応によって発症する可能性があります。ただ、中核症状とは異なり環境などが落ち着けば症状が軽減する場合もあります。
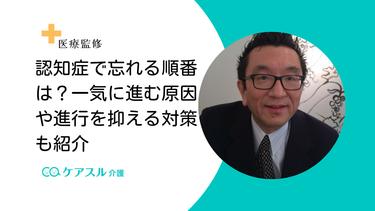
認知症が生じる原因
実際に認知症が生じる原因は1つではなく、さまざまな原因があり、その種類は100種類以上といわれています。
ここでは、その中でも原因疾患の90%を占める4つの原因について解説します。
アルツハイマー型認知症
認知症の原因となる約50%がアルツハイマー型認知症です。
アルツハイマー型認知症は、脳にタンパク質の種類であるアミロイドβ・タウタンパクが異常に溜まった結果、脳細胞が損傷・神経伝達物質が減少して、脳全体が萎縮して引き起こされると考えられています。
アルツハイマー型認知症は、脳の変性・萎縮がゆっくりと進行する特徴があり、現在ではまだ効果的な予防や根本的治療がありません。
また、60歳以上で年齢が高くなるにつれて多くみられますが、40〜50歳代など比較的若い世代でも発症する場合もあります。
レビー小体型認知症
認知症の約20%がレビー小体型認知症となっており、女性よりも男性に発症が多い傾向です。
原因としては、「レビー小体」と呼ばれる変性したたんぱく質が、脳の大脳皮質に溜まることで発症しますが、なぜレビー小体が生じるのかは不明です。
また、他の認知症と比較すると進行が速いことが特徴です。
発症する多くは高齢者の方ですが、場合によっては、若い頃にパーキンソン症候群を発症して、その後、レビー小体型認知症へ移行する場合もあります。
前頭側頭型認知症
前頭側頭型認知症は、前頭葉・側頭葉の神経細胞にタンパク質が変化した塊がみられ、脳の前頭葉・側頭葉が萎縮します。そのため、物忘れ・幻覚・妄想などのような認知症に多い症状が中心ではなく、人格の変化・自発性の低下・行動障害などの症状が現れる病気です。
また、前頭側頭型認知症の方は国内において約12,000人いると予測されており、その多くは40〜60歳代となっており、認知症の原因でも比較的若い年齢で発症する傾向です。
脳血管性認知症
脳血管性認知症は認知症全体の約20%となっており、アルツハイマー型認知症と比較しても女性より男性の方が高い割合で、その割合は女性の2倍近くと報告されています。
脳梗塞・脳出血・くも膜下出血などの脳血管障害によって引き起こされ、記憶の面に関して症状が、はっきり理解している事柄と理解していない事柄が混在するなどまだらに出るので、まだら認知症とも呼ばれています。
特徴としては、新たに血管の詰まりや血管障害が発生するなどの原因がなければ、アルツハイマー型認知症などとは異なり、症状が進行することはありません。
関連記事
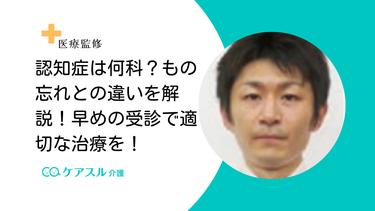 認知症は何科?もの忘れとの違いを解説!早めの受診で適切な治療を!カテゴリ:認知症更新日:2025-02-25
認知症は何科?もの忘れとの違いを解説!早めの受診で適切な治療を!カテゴリ:認知症更新日:2025-02-25関連記事
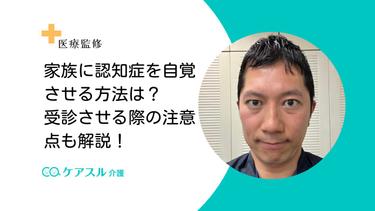 家族に認知症を自覚させる方法は?受診させる際の注意点も解説!カテゴリ:認知症更新日:2025-02-25
家族に認知症を自覚させる方法は?受診させる際の注意点も解説!カテゴリ:認知症更新日:2025-02-25
認知症の防止方法
多くの認知症は進行を止めることはできませんが、進行を遅らせることは可能です。そのため、今回紹介する認知症の防止方法を取り入れておくと、認知症になってしまっても、症状の進行がゆるやかになる効果があります。
生活習慣病を予防する
アルツハイマー型認知症・脳血管性認知症は、糖尿病・脳卒中などの脳血管障害は、生活習慣から引き起こされる病気との関連が強くあり、実際に体格指数(BMI)と腹囲周囲径、糖尿病、高血圧、高コレステロールなどをしっかりとコントロールしていないと、アルツハイマー型認知症などのリスクが高まることが明らかになっています。
そのため、すでに生活習慣病になっている場合は適切な治療を受け、そうでない場合は定期健診を受けるなど、生活習慣病の予防を積極的に行うことが重要です。
食生活を見直す
認知症の予防には、常に脳を健康な状態にしておくことが重要で、その中でも食事内容は非常に重要です。
実際、糖尿病になるとアルツハイマー型認知症・脳血管性認知症ともに発症する可能性が高くなります。また塩分の取り過ぎた結果、高血圧による動脈硬化を発症すると、脳血管性認知症の危険性が高くなります。そのため、普段から糖質・塩分を控えめにすることを意識すると、間接的に認知症を予防できます。
注意することは、緑茶・ココナッツオイルなど、特定の食物が認知症の予防に効果的といわれる場合がありますが、そのような情報を意識しすぎて、逆に過剰に摂り続けないことです。例えば、緑茶も摂り過ぎればカフェインによる睡眠の質の低下に繋がるなどデメリットもあります。
そのため、たんぱく質・脂質・炭水化物・ビタミン・ミネラルをバランス良く摂ることが最も重要です。
他人とのコミュニケーションをしっかりととる
認知症になると、どうしても他人とコミュニケーションをとらずに、塞ぎ込む傾向が高くなります。しかし、他人との交流が最も脳を刺激するため、予防効果が非常に高いです。
そのため、ご家族などさまざまの方と会話する、同じ取り組みをする仲間と交流する、共同作業を行うなどの機会を多く持つことが重要です。
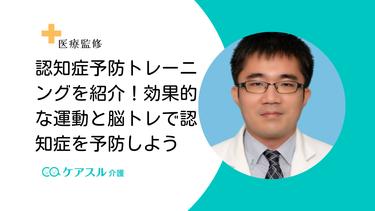
薬の飲み忘れは多くの方が経験している
薬の飲み忘れは、認知症の有無関係なく多くの方が一度は経験しています。実際、全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社の調査によると50%以上の方が薬の飲み忘れた経験があるという結果からその多さが分かるはずです。
認知症になると上記で解説したように、記憶面の低下が強くなるため、薬の飲み忘れする頻度は多くなってしまいます。
認知症の方によくみられる服薬トラブル
日常生活において、認知症の方は服薬トラブルがよくみられます。ここでは、その中でも主要なトラブルについて紹介します。
医師の指示通り薬を飲めない
一般的に病院というのは、風邪をひいたなどの体調不良があるため、病院へ行き、医師から薬を処方してもらいます。そして、体調不良を改善・完治するために薬を飲むと理解しているからこそ飲むことができます。
しかし、認知症の方は「自分の身体はどこも悪くない」と思っている。また薬の必要性自体を理解していないなどの理由で医師の指示通り薬を飲むことが困難な場合があります。
服薬を拒否する
認知症の方は不安を感じやすい傾向のため、薬に対して不安な思いを強く持っている場合も多くあります。そんな気持ちの中、無理に薬を飲むようにすると嫌な記憶が残ってしまった結果、服薬に対する不安感・家族に対する不信感などが強くなり、服薬拒否に繋がってしまいます。
認知症の方は最近のことを忘れやすいのですが、感情が結びつく記憶は残りやすいといわれているため注意が必要です。
服薬したことを忘れる
薬を飲んでいなくても「飲んだ」と訴えたり、逆に薬を飲んだにも関わらず「飲んでない」などと訴える場合があります。
認知症の方は、実際に薬を飲んだ・飲んでいないが重要ではなく、本人が思ったことが事実になるため理解してもらうのは非常に困難です。
薬の飲み忘れは少しのアイデアで大きく減らせる
今回解説したように、認知症の症状事態を改善させることは、現時点では困難です。しかし、認知機能が低下しているからといって、薬の飲み忘れを防止できないわけではなく、今回紹介したような工夫・アイデアを積極的に取り入れることで薬の飲み忘れ頻度を大きく減らすことができます。
錠剤・カプセル・粉薬が飲みにくい場合は、ゼリー状のオブラートを使うと飲みやすくなります。また、服薬介助をする場合は、上体を約30度に起こしてから薬を飲ませ、服用後はしばらくそのままの姿勢を保つことがポイントです。詳しくはこちらをご覧ください。
相手がもし間違ったことを言ったとしても、否定することなく一旦受け入れることが大切です。服薬を忘れたことについて指導しているつもりでも、言い方によっては「責められている」「否定された」と感じる場合もあるので注意が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。