介護保険は介護が必要になった場合、介護サービスの料金を1~3割の負担で利用できる安心の制度です。
すべての人に40歳からの加入が義務付けられており、以降は生涯にわたって介護保険料を支払うことになります。
しかし65歳になった時には介護保険料の支払い方法が変わったりと、制度上で大きな変更点が存在します。
「65歳になったら、介護保険で何が変わるの?」
「安心の老後を過ごすために、介護保険の仕組みについて知っておきたい」
そんな思いを抱えている方々のため、今回は65歳以上になると介護保険はどう変わるのか、介護保険料の支払い方法、その他よくある質問などについて、詳しく解説して行きます。
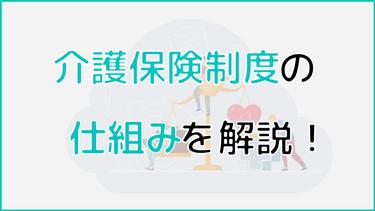
65歳以上になると介護保険はどう変わる?
65歳になったとき、介護保険で大きく変わるのは以下の2点です。
- 介護保険料が年金から天引きとなる
- 介護保険サービスの利用が可能となる
それぞれについて詳しく解説して行きます。
介護保険全体の仕組みについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
関連記事
 介護保険料はどのようにして決まるのか?仕組みや計算方法も解説カテゴリ:介護保険料更新日:2023-03-23
介護保険料はどのようにして決まるのか?仕組みや計算方法も解説カテゴリ:介護保険料更新日:2023-03-23
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
65歳以上になると介護保険料が年金から天引きとなる
65歳以上になると、介護保険料が年金から天引きされることになります。
40歳から64歳までは加入している健康保険料と合わせて給与からの天引きとなっていましたが、この支払い方法が変更されるのです。
65歳以降も働いている場合は健康保険料は勤務先の健康保険組合や協会けんぽへ支払いますが、介護保険料はお住まいの自治体へと別々に納めることになるので理解しておきましょう。
ただし、65歳以降ですでに退職していて、国民健康保険に加入している場合は、健康保険料も自治体へと収めます。
なお年金からの自動天引きを行うには、半年から1年程度の準備期間が必要です。
したがって65歳になった当初は、市区役所・町村役場から送られてくる納付書や口座振替での介護保険料納付となります。
介護保険料の年金からの天引きが始まるタイミングは、65歳なった翌年の4月・6月・8月・10月(誕生月により異なる)からとなります。
65歳以上で介護保険料はいくら払う?
65歳以上の人が支払う介護保険料は、本人の所得や世帯(毎年4月1日現在)の課税状況に応じて決まることになっており、自治体によって算出される金額が異なります。
年間の介護保険料は毎年6月から新しい金額に改定されます。、前月くらいには自治体から介護保険料額決定通知書が届くため、よく確認してみましょう。
例えば世田谷区の例で見ると、介護保険料は次のようになっています。
|
保険料段階 |
対象となる方 |
年間保険料額 |
|---|---|---|
|
第1段階 (基準額×0.3) |
・生活保護または中国残留邦人等生活支援給付を受けている方
・老齢福祉年金を受けている方で本人および世帯全員が住民税非課税の方 |
22,248円 |
|
第2段階 (基準額×0.3) |
本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入額と合計所得金額(年金に係る雑所得金額を除く)の合計が80万円以下の方 | 22,248円 |
|
第3段階 (基準額×0.5) |
本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入額と合計所得金額(年金に係る雑所得金額を除く)の合計が80万円を超え120万円以下の方 | 37,080円 |
|
第4段階 (基準額×0.65) |
本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入額と合計所得金額(年金に係る雑所得金額を除く)の合計が120万円を超える方 | 48,204円 |
|
第5段階 (基準額×0.85) |
本人が住民税非課税で、本人の年金収入額と合計所得金額(年金に係る雑所得金額を除く)の合計が80万円以下で同一世帯に住民税課税者がいる方 | 63,036円 |
|
第6段階 (基準額) |
本人が住民税非課税で、本人の年金収入額と合計所得金額(年金に係る雑所得金額を除く)の合計が80万円を超え同一世帯に住民税課税者がいる方 | 74,160円 |
|
第7段階 (基準額×1.15) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 | 85,284円 |
|
第8段階 (基準額×1.25) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 92,700円 |
|
第9段階 (基準額×1.4) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 103,824円 |
|
第10段階 (基準額×1.6) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上400万円未満の方 | 118,656円 |
|
第11段階 (基準額×1.7) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 | 126,072円 |
|
第12段階 (基準額×1.9) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が500万円以上700万円未満の方 | 140,904円 |
|
第13段階 (基準額×2.3) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が700万円以上1,000万円未満の方 | 170,568円 |
|
第14段階 (基準額×2.7) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方 | 200,232円 |
|
第15段階 (基準額×3.2) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が1,500万円以上2,500万円未満の方 | 237,312円 |
|
第16段階 (基準額×3.7) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が2,500万円以上3,500万円未満の方 | 274,392円 |
|
第17段階 (基準額×4.2) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が3,500万円以上の方 | 311,472円 |
(出典:世田谷区の介護保険料額)
どの自治体でも基準額が決められていて、高所得の人ほど段階は上がり、年間で支払う保険料の総額は高くなる仕組みになっていることが分かります。
逆に所得が少ない人の介護保険料は、減免される仕組みになっています。
保険料の詳細は自治体によって違うため、お住まいの地域ではどれくらいの金額がかかるかをチェックしておきましょう。
65歳以上で介護保険料を支払う場合の注意点
65歳以上の介護保険料は、基本的に年金からの天引きとなります。
しかし本人が1年に受給している年金年額が18万円以下である場合、支払方法が変わるため注意が必要です。
一般的な納付方法である特別徴収と、年金年額が18万円以下の場合に行われる普通徴収についてそれぞれ解説します。
特別徴収の場合
年間で受給している年金額が18万円以上の場合は、特別徴収という方法で支払います。
これは一般的な納付方法であり、年金から天引きされる方法を指しています。
また前述のとおり、年金からの自動天引きを行うには1年程度の準備期間が必要となります。
したがって65歳になった当初は、市区役所・町村役場から送られてくる納付書や口座振替での介護保険料納付となるため、理解しておきましょう。
普通徴収の場合
年間の年金受給額が18万円未満の場合は、普通徴収という方法で介護保険料を納付します。
これは納付書や口座振替などによって支払います。普通徴収の場合は自身で支払いの手続きをしなければならないため、納付忘れに注意しましょう。
また、年金の年間受給額が18万円未満の人だけではなく、年金の受給繰り下げを行った場合も普通徴収となります。

条件に当てはまれば減額・減免してくれる自治体も
介護保険料は40歳以上から生涯支払わなければならず、経済的な状態によっては、保険料の負担が苦しくなることもあります。
自治体によっては介護保険料の減額や減免に対応していることもあるため、地域ごとの情報をチェックしておきましょう。
失業や被災によって著しい収入減があった場合や、そもそももらえる年金が少ないなどの場合も減額や減免の対象となることがあります。
保険料の支払いが難しい場合は、滞納しないうちに減額や減免の制度を利用して、滞りなく納付できるようにしておきましょう。
介護保険料の減免制度について知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
関連記事
 介護保険料は免除してもらえる?カテゴリ:介護保険料更新日:2024-05-31
介護保険料は免除してもらえる?カテゴリ:介護保険料更新日:2024-05-31
65歳以上の介護保険料についてよくある質問
介護保険料の仕組みは複雑で、よく理解できないまま疑問や不安が残ってしまう方も多いです。
そこで本章では、65歳以上の介護保険料に関してよくある質問をまとめて答えていきますので、ぜひ参考にしてみてください。
介護保険料は何歳まで払うの?
介護保険料は生涯にわたって払うことになります。
40歳から健康保険料と合わせてて納めることになり、65歳以上でも年金からの天引きという形で納めることが必要です。
介護保険料の支払いは国民の義務となっているため、脱退することはできません。
しかし生活保護を受けていたり、もともとの所得が少なく生計の維持が困難な場合は減免措置が取られるため、自治体に確認してみましょう。
65歳からの介護保険料が高いのはなぜ?
65歳以上になると、介護保険料の計算方法が変わるためです。
65歳以上(介護保険第1号被保険者)は、お住まいの市区町村で必要となる介護費用を65歳以上の人数で割り、保険料の基準額を決めます。
40歳~64歳(介護保険第2号被保険者)では、介護保険料=標準報酬月額×介護保険料率で保険料を決めます。
高齢者が多い市区町村では介護費用が掛かるので、介護保険料は高額になりがちです。
ちなみに40歳から64歳までの第2号被保険者は、全国一律で給与(標準報酬月額)の1.82%になっています(協会けんぽの場合)。
これに対して65歳以上の人が主に加入する国民健康保険では、均等割という加入者全員が支払う金額に、所得に応じた料率で計算された介護保険料を支払います。
現役時代に比べて、所得が少なくなっている中では、介護保険料の負担が重く感じられるのが一般的です。
介護保険料の負担の仕組みがわからない場合は、お住まいの市区町村の窓口で計算方法について尋ねてみましょう。
妻(被扶養者)が65歳になったら介護保険料はどうなる?
専業主婦など健康保険の被扶養者になっている人も、65歳になると介護保険料の支払いが必要となります。
これまでは扶養者である夫などが2人分の保険料を払っていましたが、妻が65歳以上になった場合は妻の年金から介護保険料が天引きされることになります。
なお、国民兼保険には被扶養者の考え方はありませんので、国民健康保険に夫婦で加入する場合は、それぞれが均等割を支払います。
勤労収入のない妻であっても、年金収入などがあって、公的年金控除などを差し引いても所得認定される金額があれば、所得割を支払うことになり、それによって介護保険料の負担にも影響が出ます。
65歳以上でも働いている場合は介護保険料はどうなる?
65歳以上で働き続けている場合も、65歳になったタイミングで介護保険料の支払い方法が変更となります。
したがって65歳以上で働き続けている場合も、介護保険料は健康保険料と合わせて納めるのではなく、年金からの天引きとなることを覚えておきましょう。
65歳になったのに健康保険から介護保険料が引かれているのはなぜ?
二重の支払いとなっている可能性があるため、ご加入の健康保険組合や協会けんぽに尋ねてみることがおすすめです。
前述のとおり、65歳以上の方はお住まいの市区町村に個別に納めていただくことになります。
したがって、ご加入の健康保険組合等へのお支払いは原則不要となるのです。
ただし、健康保険組合によって納付期間・扶養家族の介護保険料の取り扱いが異なる場合があるため、ご不安な場合は確認してみましょう。

65歳以上になると介護保険サービスの利用が可能となる
前項までは65歳以上の介護保険料について解説してきました。
ここからは65歳以上になった場合のもう1つの大きな違いである、介護保険サービスの利用が可能になることについて解説して行きます。
利用できる主なサービス内容
介護保険を適用して利用できるサービスは豊富であり、将来的にさまざまな優遇が受けられます。
どのようなサービスが受けられるのかを知り、介護保険料を払う意味を理解しておきましょう。
施設サービス
施設サービスとは、老人ホームや施設で介護を受けながら暮らせるサービスのことです。
有料老人ホームや介護保険福祉施設などがこれに該当し、介護保険によって施設でかかる費用を1~3割の自己負担で利用することができます。
施設への入居は介護職員や医療関係者による専門のサービスを受けることができ、24時間体制の見守りを実施している施設も多いです。
また、日常的な生活動作の介護はもちろん、その人の状態に合わせた食事の提供や、心身ともの健康を目指すレクリエーションなどもあり、サービスの内容はさまざまです。
リハビリなどのトレーニングを実施しているサービスもあるため、利用者が心身ともの健康を目指しやすいでしょう。
また介護を受ける人はもちろん、利用者の家族の負担が軽減できることも、施設を利用するメリットです。
プロによる介護を受けることが、利用者とその家族療法の負担軽減につながるため、施設サービスを利用する魅力は大きいと言えるでしょう。
居宅サービス
居宅サービスとは訪問介護や訪問入浴、デイサービスなどをはじめとする、在宅で生活しながら介護が受けられるサービスのことです。
居宅サービスは自宅で介護をする人におすすめであり、介護の一部をヘルパーなどの外部さーじす提供者に委託することで、家族の負担は減らせる点が魅力です。
居宅サービスを利用することで、利用者の身体的な負担を軽減することはもちろん、デイサービスの利用などは日々の楽しみになることも多くあります。
家族と暮らしながらプロによる介護を受けられるため、利用者・家族の双方にとってメリットは大きいと言えるでしょう。
地域密着型サービス
地域密着型サービスとは、利用者が住み慣れた場所でいつまでも過ごせるよう地域に根付いた事業者が提供する介護サービスのことです。
なじみの地域で生活環境を大きく変えずに済むことから、利用者への精神的な負担が少ない点がメリットと言えます。
地域密着型のサービスとしては、地域密着型通所介護や夜間対応型訪問介護、小規模多機能がた居宅介護などがあります。
地域の事業者を見つけるには、地域包括支援センターなどを利用して、ケアマネージャーに相談することがおすすめです。
ケアマネージャーに相談することで、利用者に合ったケアプランの作成をしてもらえます。また、ケアプランの管理もしてもらえるため、まずは専門家に相談することが大切です。
介護保険サービスの利用には要介護認定が必要
保険を適用した介護サービスは65歳以上から受けられますが、本人が要介護認定を受けることが必要となります。
要介護認定とは、本人の身体状況に応じてどの程度の介護が必要なのかを示す認定のことです。
介護保険はこの要介護度に応じて適用されることになり、介護サービスを利用した際の料金の7割から9割を介護保険制度が負担してくれる仕組みになっています。
申請には市区町村の役場で介護認定を受けたい旨を伝えることが必要です。
市区町村の職員やケアマネージャーなどによる自宅訪問を経て、要支援1~要介護5までの7区分の認定を受けることになります。なお、申請をしても「非該当」に区分されるケースもあります。
要介護認定について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
関連記事
 要介護認定の申請について解説!申請先や必要なものなど徹底解説!カテゴリ:要介護認定更新日:2025-05-07
要介護認定の申請について解説!申請先や必要なものなど徹底解説!カテゴリ:要介護認定更新日:2025-05-07関連記事
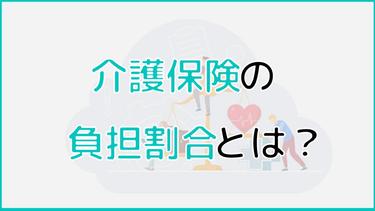 介護保険負担割合とは?介護保険の仕組みやお得な制度を解説カテゴリ:介護保険更新日:2025-02-25
介護保険負担割合とは?介護保険の仕組みやお得な制度を解説カテゴリ:介護保険更新日:2025-02-25
また老人ホーム・介護施設をお探しの際には、ケアスル介護で相談してみることがおすすめです。
ケアスル介護では全国約5万もの施設から、入居相談員がご本人様のニーズに合った施設をご紹介しています。
「納得のいく施設選びをしたい」という方は、まずはぜひ無料相談をご利用ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
関連記事
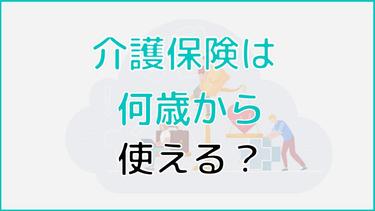 介護保険は何歳から使える?サービスの利用方法や支払う時期も徹底解説カテゴリ:介護保険更新日:2025-02-25
介護保険は何歳から使える?サービスの利用方法や支払う時期も徹底解説カテゴリ:介護保険更新日:2025-02-25
65歳以上で介護保険料を滞納してしまったら?
介護保険料は滞納した場合、ペナルティが課されるため注意しなければなりません。
老後の生活を安心して過ごせるように、知識として知っておくことが大切です。
介護保険料を滞納した場合の延滞金・督促料
まず、介護保険料を納付期限までに支払わずに20日を経過すると市区町村から支払い督促状が届きます。
そして督促状の納付期限に遅れると督促手数料と延滞金が加算されることになるため、注意しましょう。
延滞金と督促量の計算は市区町村によって異なりますが、一般的には以下の割合・金額で加算されています。
| ペナルティ内容 | 金額 |
|---|---|
| 督促料(1回あたり) | 100円 |
| 延滞金(翌日~1ヶ月未満) | 年4.3%~14.6%増加 |
| 延滞金(1ヶ月以上) | 年14.6%増加が一般的 |
また介護保険料を1年以上滞納すると、督促料・延滞金以外にも追加でペナルティが延滞期間別に課されます。それぞれ期間別の追加のペナルティについて解説していきます。
1年以上滞納してしまったら
介護保険料の支払いを1年以上滞納すると、介護保険適用のサービスを利用する場合でも、いったん全額を自己負担しなければなりません。
保険料を払っていた時は1割負担で1,000円の負担で介護サービスを受けられていたものが、サービス利用時に1万円を支払い、後から給付を受けることになります。
最終的には支払った介護サービス費の9割分(1割負担の場合)は戻ってくるものの、一時的に自己負担となるため、介護サービスを利用するために自己資金を用意しておかなければならないことは覚えておきましょう。
1年6ヶ月以上滞納してしまったら
滞納期間が1年6ヶ月以上になると、介護保険を利用した場合のサービス費用を全額自己負担することに加え、給付される金額の一部または全部が差し止めとなります。
1年以上滞納してしまうと、保険料を支払っていれば1割負担で1,000円の負担で済むところ、一時的な負担金額は1万円となり、後で9,000円の費用が戻ってきます。
しかし、1年6ヶ月以上の滞納を続けていると、9,000円全額が返金されず、後からもらえる給付額が一時的に差し止めとなるため注意しなければなりません。
また、さらに長期間滞納を続けると、差し止め分から介護保険料の滞納分を差し引くことになります。
滞納分をすべて支払うことで差し止め分は手元に戻ってきますが、滞納期間が長くなることで、本来戻ってくるはずの分が、滞納分の支払いに充てられるため注意しましょう。
有効期限の2年以上滞納してしまったら
2年以上の滞納をすると、一定の期間、自己負担割合を引き上げられます。
そのため、本来なら安く済むはずの介護サービスの費用が、高額になってしまうため注意しなければなりません。
また保険料をきちんと支払っている場合は、介護サービスの負担が多くなると、高額介護サービス費という制度によって利用限度額を超過した分の払い戻しが受けられます。
しかし長期間介護保険料を滞納していると、この制度の利用も停止となってしまい結果的に自己負担する介護費用は高額となるのです。
以上のように滞納期間が長くなることで自己負担の割合が増えるだけではなく、利用する介護サービスや制度の幅が狭くなってしまいます。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
まとめ
65歳になったとき、介護保険で大きく変わるのは以下の2点です。
- 介護保険料が年金から天引きとなる
- 介護保険サービスの利用が介護の理由に関わらず可能となる
介護保険料が年金からの自動天引きとなるまでには、半年から1年程度の準備期間が必要です。
したがって65歳になった当初は、市区役所・町村役場から送られてくる納付書や口座振替を使っての介護保険料納付となるので理解しておきましょう。
また65歳以上になると、介護保険サービスの利用も可能となります。
介護サービスで必要となる料金が保険適用により、1~3割の自己負担に抑えられることは大きなメリットです。
安心の老後生活のため、介護保険について正しい知識を身に着けた上で、今後の計画を立てていきましょう。
65歳になったとき、介護保険で大きく変わるのは以下の2点です。介護保険料の支払い方法が変わり、年金からの天引きとなる。40歳から64歳までは、16種類の特定疾病が原因の場合にしか使えなかった介護保険サービスが、65歳以降では介護になった理由に関わらず利用可能になる。詳しくはこちらをご覧ください。
介護保険料は生涯にわたって払うことになります。40歳から健康保険料の一部として納めることになり、65歳以上でも年金からの天引きという形で納めることが必要です。介護保険料の支払いは国民の義務となっているため、脱退することはできません。詳しくはこちらをご覧ください。





