「親がオムツ替えが必要になってしまった」「親のオムツ替えはどうやってすればいいのだろう?」と悩み、ショックを受ける方も多いでしょう。オムツ替えをする際に介護を受ける方、介護をする方がいずれも負担を感じない手順と必要な物品を紹介します。
丁寧かつ迅速なオムツ替えで本人の羞恥心も、介護者の衛生的な問題も解決しましょう。
介護する自分が心身の負担を感じた時に、参考になる具体的なオムツ替えの方法だけでなく、相談できる窓口なども紹介します。ぜひ最後までご覧ください。
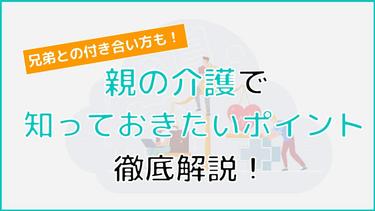
親の介護におけるオムツ替えとの向き合い方
現在は高齢化社会であり、親の介護を担う方は多いでしょう。介護を行うなかで欠かせない役割の一つがオムツ替えです。
オムツ替えは受ける親自身と、行う家族に負担が大きいです。受ける親は羞恥心を感じ、自尊心を損なう可能性があります。
家族は、親がオムツ替えが必要という現実にショックを受けるかもしれません。また身体的にも大変な作業なので、負担は大きいです。
しかし、オムツ替えを否定的に思いすぎず、適切に行うと問題は解決できます。状況によっては、介護保険サービスを受けたり、施設を利用したりして負担を軽減する対応も必要です。
親の介護に困った方はケアスル 介護で検索してはいかがでしょうか。全国約5万件の施設情報や介護情報を掲載しており、条件に合ったサービスが受けられるでしょう。手早く情報を入手したい方は、まずは検索してください。
親の介護でオムツ替えに必要な道具類と事前準備
親の介護でオムツ替えを行う際に必要な道具類などを紹介します。以下の2つです。
- オムツ替えに必要な道具類
- オムツ替えの事前準備
オムツ替えには必要な道具を準備するだけではなく、事前の準備が重要です。適切に準備できなければスムーズにオムツ替えできず、親や家族両者に負担がかかるでしょう。それぞれ具体的に紹介します。
オムツ替えに必要な道具類
オムツ替えに必要な道具類は、以下のようなものが挙げられます。
- オムツ
- 尿取りパッド
- 使い捨てエプロン
- 吸水シーツ
- 使い捨てのウェス(人肌に温めたものと乾いたもの)
- 使い捨ての手袋
- トイレットペーパー
- 新聞紙
- ゴミ袋
- 手洗い用石鹸
- 手指消毒剤
- ペーパータオル
- 陰部洗浄ボトル(ペットボトルでも代用可能)
オムツ替えの方法やその方の身体機能によって必要な道具は変わります。適宜対応しましょう。
オムツ替えの事前準備
オムツ替えに際して必要な事前準備について解説します。以下の2つの準備を行います。
- 体形と用途に合ったオムツの選択
- ニオイ対策
オムツは、体形と用途に合ったものを選択しましょう。また、オムツ替えではニオイの対策が重要です。オムツ替えの事前準備が適切であり、ニオイ対策ができれば、不快感を軽減できるだけではなく、介護の心身の負担を軽減できるでしょう。
体形と用途に合ったオムツの選択
オムツには大きく分けて3つあります。
- パンツタイプ
- テープタイプ
- パッドタイプ
パンツタイプかテープタイプは、親の生活様式によって選ぶのが適切です。
パンツタイプは、自立して歩行ができたり、座位保持ができたりする方で尿失禁がある場合に適しています。テープタイプは、前にテープがついていて、寝ている体勢が多い方でもスムーズに替えられて便利です。パッドタイプは尿取りパッドとも言われ、前者2つのオムツと併用して使います。
S〜Lサイズがあるので、本人の体型や生活様式によって適切に選びましょう。
ニオイ対策
オムツ替えで大切なのが、ニオイ対策です。以下の要点を抑えると不快感を軽減できます。
- オムツ専用のビニール袋で捨てる
- 空気清浄機を使用する
- オムツ交換する際に清拭や洗浄を行う
- オムツ交換後に換気する
オムツ専用のビニール袋は、Amazonや楽天市場でも購入できますし、市区町村によっては無料で配布している地域もあります。お住まいの地域に問い合わせてみましょう。
とはいえ、こうした衛生用品もある程度のコストがかかるものです。購入が経済的に負担になる場合は、紙オムツやパッドを新聞紙で包み、普通のビニール袋でも良いのでしっかりと縛っておくだけでもニオイの対策になります。
また使用後の紙オムツは外のゴミ箱へ捨てる、トイレにゴミ箱を置くなど、生活スペースでニオイがすることのないよう心がけましょう。
親の介護でオムツ替えするときの実際の手順
実際にオムツ替えをするときの手順を説明します。
- オムツと尿取りパッドを用意する
- 替えた後の汚物など捨てる入れ物を用意する
- 介護者の負担にならないよう、ベッドの高さ等を調整する
- 使い捨ての手袋をつける
- 使用済みのオムツを外す
- 陰部の洗浄・清拭を行う
- 新しいオムツをつける
- 更衣介助を行う
- 使用済みのオムツ等の捨てるものを処理する
適切に正しくオムツを交換できれば、ズレたり漏れたりする心配がいりません。交換の頻度も減り、清潔な状態を保てて衛生的です。
またオムツ替えの手順は本人の身体の動く範囲などによって、本人ができる動作や適切な交換方法は異なります。個人に合わせて柔軟に対応しましょう。
オムツと尿取りパッドを用意する
まずオムツと尿取りパッドの準備をしましょう。
どちらもそれぞれ、縦半分に折りましょう。さらに縦長の上下を持ち、引っ張るとギャザーが簡単に立ち、ギャザーをしっかり立てると肌にフィットして、漏れを回避できます。
オムツと尿取りパッドが用意できたら、オムツ替えを受ける本人のお尻の横におきましょう。清潔な場所に置いておき、尿取りパッドはオムツの中にセットしておきましょう。
替えたあとの汚物など捨てる入れ物を用意する
床に汚物などを置かないようにしましょう。新聞紙などを敷いた上にゴミ袋を用意します。
ゴミ袋は、一般のゴミ袋ではなく、ニオイを抑えられるオムツ専用ゴミ袋を使用するといいでしょう。夏場でもニオイが漏れず安心です。
介護者の負担にならないよう、ベッドの高さ等を調整する
オムツ替えに必要な物品を準備できたら、本人に声をかけて、ゆっくりベッドの高さを調整、またベッドを平らにしましょう。
その時には「オムツ替えるので、ベッドをあげます」などと声をかけると、オムツの言葉に羞恥心を感じる方もいます。そのため「ここ交換しますね」「ここ綺麗にしますね」といった声かけにするといいでしょう。
そして、身体の向きを変える際にも必ず「右をむきますよ」などと声掛けをしないと、びっくりさせてしまったり体を痛めてしまうこともあるので気をつけましょう。
おむつ交換の際は「肩・腰・下肢」の3点を一つの線としてとらえ、まっすぐに一緒に動かすようにしましょう。片手で行うと「肩・腰・下肢」の3点が同時に動かず、高齢者の身体をひねってしまったり骨折や筋肉痛を起こすケースもありますので注意して下さい。
ベッドの高さは、オムツ替えを行う家族の負担にならない高さにしましょう。その際に介護者側のサイドレールを外すと、作業がしやすいです。
また、オムツ交換後はベッドの高さを戻すことを忘れないようにしましょう。介護者がベッドの高さを戻すことを忘れてしまい、要介護者の足が床に届かない高さのまま目を離すと、トイレに行こうとした要介護者が転倒するケースもあります。
使い捨ての手袋をつける
利用者と介護者、互いの感染予防のために、使い捨ての手袋をつけましょう。
テラックス手袋かプラスチック手袋があります。これらの素材は、洗剤や漂白剤などに強く、破れにくいので清潔を保持しやすく適しています。
使用済みのオムツを外す
使用済のオムツを外しましょう。排泄物を扱うため、親の自尊心を尊重しながら家族の衛生面や身体の負担を考慮しなければなりません。
替え始めるタイミングで、仰向けの状態で腕を組んでもらっておくと体位を変えるときスムーズです。
また、可能であれば手すりを持ってもらいましょう。膝を曲げたり腰をあげることができるなら、残存機能を使って協力動作をしてもらうことも大切です。麻痺がある方の介助には、麻痺側に注意しないと骨折することがあるため注意が必要です。
外すときは、替えられる本人の身体を仰向けにした状態で、テープパンツはテープを外します。オムツの前面と側面が開けられるので、身体の下に敷かれた形です。
リハビリパンツなら横を切ることができるので、オムツと同じように開くことができます。
汚れたオムツは外してしまいますが、少しの汚れであれば洗浄を行うまでお尻にしいたままにします。洗浄の受けとして利用し終えたら、新しいオムツに交換します。
陰部の洗浄・清拭を行う
陰部の洗浄・清拭を行いましょう。排便のときは毎回、最低でも1日1回が目安です。
順番は、①排便を先に取り除く②次にお尻の洗浄③最後に尿の(陰部)洗浄を行います。
陰部を洗浄する方法は、女性と男性で異なります。
まず女性の場合を解説します。排泄物を優しく拭き取り、陰部の上からお湯を流しましょう。上から流すのは、尿路感染や膣炎を予防するためです。陰唇を開き、しっかり洗いましょう。
そして、上から下に陰部を優しく拭き上げ、最後に軽く押さえ拭きをして水分を取ります。
次に男性の場合を解説します。排泄物を取り除いた後、亀頭、陰茎、陰嚢の順で拭きます。お湯が尿道口に入らないように気をつけましょう。尿道口から陰茎にかけての皮膚をのばしながら、汚れを取ります。最後に乾いたウェスで軽く押さえ拭きをします。
新しいオムツをつける
陰部の洗浄・清拭を行い、清潔になったら新しいオムツをつけていきましょう。親の姿勢を側臥位に変更します。
新しいオムツを挿入していきます。このときに、背骨に当ててオムツの中心を合わせましょう。その中心に片手を当ててずらさないようにしながら、左右のウエストを伸ばすのがポイントです。このときパッドを使用する場合は、位置を調整しておきましょう。
そして、体位を仰向けに戻しオムツの位置を調整します。オムツを半分に折った状態で足の間から引き出し、鼠径部に合わせて、一度左右に開きます。
メーカーにより中心に印があるので、身体の中心に印を合わせましょう。そして、オムツの前側を腰の下に差し込み最後にテープを貼ります。
更衣介助を行う
オムツ替えが終わったら、脱いでいた服を更衣介助しましょう。
更衣介助は、親の身体の動く範囲に合わせて普段と同様に行いましょう。おむつ替え前と同じ服を着る際は、替える前に汚れていないかを確認するのが大切です。
またベッド上で行う時は、防水シーツ、衣類のしわをしっかり伸ばします。少しのしわでも褥瘡につながりますので気をつけましょう。
使用済みのオムツ等の捨てるものを処理する
最後に使用済のオムツやウエスを捨てましょう。オムツ専用の袋にまとめて入れると、ニオイもせず不快感を軽減できます。
手洗いも忘れないようにしましょう。
親の介護でオムツ替えをする際に注意すべき3つのポイント
介護においてオムツ替えは、羞恥心を伴い、介護者に心身の負担がかかります。羞恥心と心身の負担を軽減できるかがポイントです。以下の3つに注意しましょう。
- 羞恥心に配慮した環境づくりをする
- 交換時に皮膚の状態を観察する
- オムツを替える際に必要な声かけをする
オムツ替えでは、身体の観察を通して普段気づかない皮膚トラブルや体調の変化などにも気づけます。正しいオムツ替えで本人の自尊心を保ち、不快感を軽減するための注意点を解説します。
羞恥心に配慮した環境づくりをする
オムツ替えは、羞恥心を強く感じます。
そのため、カーテンを締め切るなどの配慮を行い、外の空間とシャットダウンする必要があります。
また、替えてる最中に何度も道具類を取りに行くと、中途半端な状態で置かれてしまうため羞恥心を感じやすいです。必要なものは事前に確認し、用意しましょう。
オムツ替えにともなうニオイは、オムツ専袋を使用したり、終了後に換気したり、空気清浄機を利用したりして対応しましょう。
交換時に皮膚の状態を観察する
オムツ替えでは、普段目に見えない範囲の皮膚の状態を確認できます。
尿路感染症やムレによるかぶれ、寝た状態が長い場合は褥瘡が起きている可能性があります。そのため、オムツ替えをしながら、注意深く観察しましょう。
また、必要な時は医療につなげましょう。
オムツを替える際に必要な声かけをする
介護を受ける方のなかには、オムツ自体の言葉や交換中の声掛けの内容にも羞恥心を感じる場合があります。オムツ替えの際は、些細な言葉遣いにも気をつけましょう。
オムツ替えをしている最中であっても、突然身体を触られると驚いてしまうので、適宜声かけが必要です。
また、親であるからとはいえ、冗談混じりであったとしても「クサイ」「汚い」などの言葉で本人の自尊心を損なってしまうため、注意しなければなりません。

親の介護でオムツ替えに限界を感じたときに利用できるサービス
オムツ替えには、多くの手順や注意点があります。介護の必要度が上がり、オムツ替えの頻度や難易度が上がっていくと、家族の負担が増していくでしょう。
しかし「家族なのだから」と一人で抱え込む必要はありません。オムツ替えに限界を感じたときに利用できるサービスは以下の3つです。
- 地域の行政窓口を利用しよう
- 介護保険サービスを利用しよう
- 紙おむつ助成制度を利用しよう
それぞれのサービスを具体的に紹介します。
地域の行政窓口を利用しよう
介護上の問題を相談するのに適した窓口は、以下の3つがあります。
- 自治体・社会福祉協議会での相談
- 医療機関での相談
- 地域包括支援センターでの相談
それぞれに相談窓口を対応する部署があり、相談料は無料です。在席しているのは、保健師や社会福祉士、ケアマネジャーなど介護のプロです。
居住している地域の相談窓口で相談すると、適切なサポートや支援制度を教えてくれるため、オムツ替えだけではなく、介護の負担を軽減できるでしょう。
事前に調べて、予約まですると相談までがスムーズです。
介護保険サービスを利用しよう
要介護者の心身の状態に合ったケアプランが作成され、デイサービスや訪問介護、訪問看護などの介護保険サービスを受けられます。自宅での生活を続けながら受けられるのが特徴です。
オムツ替えだけではなく、入浴介助や食事介助などのサービスも受けられるため、家族の介護負担を軽減できるでしょう。また、介護度が上がれば、家族の負担は大きくなるため、特養(特別養護老人ホーム)や老健(介護老人保健施設)、有料老人ホームなどの施設への入居サービスの利用も検討できます。
ケアスル 介護では約5万件の施設情報を掲載しています。親の介護で負担を強く感じている方は、まずはプロに相談してみませんか。
紙おむつ助成制度を利用しよう
オムツや尿取りパッドは毎日使うものであり、少額でも毎日使えば金銭的負担も増えます。
そこで利用を勧めたいのが紙おむつ助成制度です。
居住している自治体によっては、介護用のオムツや排泄用品の現物支給、助成金制度があります。東京都荒川区でのおむつ購入費の助成対象者は、65歳以上の方または介護保険の第2号被保険者で次のいずれかに該当している方です。
- 要介護4・5
- 要介護1~3でかつ認知症のある方
- 身体障碍者手帳1・2級の方
- 愛の手帳1・2度の方
上記の条件に該当しない場合にも医師の診断によっても受けられる場合があります。
その他、60歳以上で失禁があり紙オムツが必要な方に支給している市区町村もあります。
給付を希望する場合は、居住している市区町村の保健福祉課や地域包括支援センター、健康サポートセンターなどに申請し給付を受けましょう。
適切なオムツ替えの手順を把握し、双方が快適になろう!
オムツ替えの具体的な方法等と利用できるサービスの紹介を紹介しました。
親の介護を担うなかでオムツ替えは、身体的・精神的な負担がかかり、羞恥心をともなうものです。本記事では、オムツ替えの必要物品や手順を具体的に紹介しているので、参考にしてスムーズにできるように取り組みましょう。
また、心身に限界を感じれば行政のサービスを利用するのも大切です。それぞれの家庭の状況や心身の状態に応じて柔軟に対応し、介護を受ける親も介護を担う家族も、双方が快適に生活できるようにしましょう。
個人差もあるので一概には言えません。水分補給の量や排泄の回数にもよりますが、 吸水性の高い尿取りパッドやオムツを使用すると回数は減らせます。詳しくはこちらをご覧ください。
親が相手であるからこそのショックや抵抗はあってしょうがないです。一人で抱えず、相談できる専門職や窓口は活用しましょう。詳しくはこちらをご覧ください。







