遠く離れて暮らす親の介護が必要になったとき、遠距離介護を検討する方もいるのではないでしょうか。
本記事では親の介護を遠距離で行うメリット・デメリット、事前の準備などについて詳しくご紹介していきます。
この記事を最後まで読み終えてもらえれば、遠距離で暮らしながらスムーズに親の介護を始めるのに役立ちます。
遠方に暮らす親の介護で悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
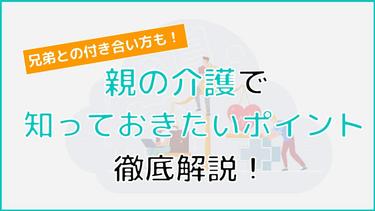
親の介護を遠距離で行う方が増えている
近年、親の介護を遠距離で行う方は増えつつあります。
厚生労働省の「2019年国民生活基礎調査」によると、別居の家族が介護を行う割合は2016年に12.2%、2019年に13.6%と発表しています。
要介護者の単独世帯も増加しており、遠距離介護が増加傾向にあるといえるでしょう。
親の介護が始まるとき、子は40代~50代と働き盛りの年代であり、管理職や責任あるポジションに就いているケースも少なくありません。
また、毎月自分の子どもの学費や教育費もかさみ、家計を圧迫している家庭は多いです。そのため、安易に仕事を辞めて親元へ引っ越すのは現実的ではないでしょう。
親の介護が難しいという方は、ケアスル介護がおすすめ。土日を含む毎日10:00-19:00まで入居相談員が対応しているので、親に合った施設選びの相談から紹介までその場で受け付けています。
親の介護を遠距離で行うメリット
遠方に暮らす親の介護を考える際、仕事や家庭の事情から遠距離介護を検討する方は少なくありません。ここでは親の介護を遠距離で行う場合のメリットを紹介します。
親の遠距離介護を検討している方は、どんなメリットがあるかチェックしてみましょう。
メリット1:親も子も転居しなくてよい
親の介護を遠距離で行うと、親も子も住み慣れた土地から離れる必要がありません。特に親は長年同じ土地に住んでいる場合が多いので、ご近所に顔なじみの方が多くいます。
転居しないとご近所の方たちとの交流が途絶えず、引き続き安心感のある生活を送れるでしょう。
また、子は転居しないことで仕事を続けられます。親の介護を遠距離で行うと、親も子も環境を変えずに今まで通りの生活を送ることが可能です。
メリット2:介護保険サービスが利用しやすい
高齢者の一人暮らしの世帯や高齢者だけの世帯は、家族が同居している場合よりも訪問介護の生活援助を受けやすくなります。
また、今後要介護度が上がり遠距離介護が難しくなった場合、家族が同居している場合と比べて特別養護老人ホームの入所の優先順位が高くなりやすいです。
特別養護老人ホームは費用の安さから入居希望者数が多く、入居待ち年数が長期化しやすい傾向にあります。
待機者数が多いため、入所の優先順位が高くなるのはメリットといえるでしょう。
メリット3:身体的・精神的な負担が少ない
同居介護は介護中心の生活になりやすく、自分のペースで休めない、生活リズムが違うなど、介護を担う方は身体的・精神的に大きな負担がかかってしまいがちです。
一方、親の介護を遠距離で行うと子は直接介護を行う機会が少ないため、身体的・精神的な負担が少なくなります。
また、親と遠距離で暮らしていると、物理的・精神的に一定の距離を置くことができます。
親の介護にかかりきりになることもなく、親の状況に対して客観的な目線で見ることができるため、子の身体的・精神的な負担が少ないでしょう。
親の介護を遠距離で行うデメリット
親の介護を遠距離で行う場合、メリットだけでなくデメリットもあります。そこで、遠距離介護を行うデメリットについてご紹介していきます。
メリット・デメリットを比較したうえで、遠距離介護を選ぶのか慎重に検討しましょう。
デメリット1:費用がかさむ
親の介護を遠距離で行うと、同居介護に比べて交通費や通信費の費用がかかります。
遠距離介護は帰省するために新幹線や飛行機を利用するので、回数が増えるほど経済的な負担が大きくなるでしょう。
また、親と頻繁に会えないため体調確認の電話や、ケアマネジャーとのやりとりがあり通信費もかさみやすくなります。
そのほかにも、お世話になっているご近所の方への手土産も必要になるため、同居介護に比べて遠距離の介護は費用がかさみやすいのです。
関連記事
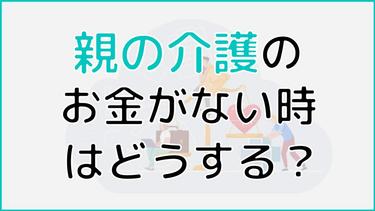 親の介護のお金がない場合はどうする?カテゴリ:親の介護更新日:2025-10-03
親の介護のお金がない場合はどうする?カテゴリ:親の介護更新日:2025-10-03関連記事
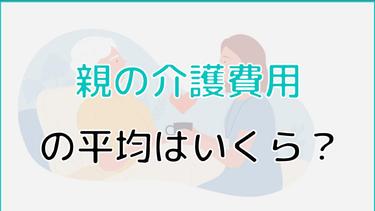 親の介護費用の平均はいくら?費用負担を減らす7つの方法を徹底解説カテゴリ:親の介護更新日:2022-12-28
親の介護費用の平均はいくら?費用負担を減らす7つの方法を徹底解説カテゴリ:親の介護更新日:2022-12-28
デメリット2:容体が急変したときの対応が困難な場合も
遠距離のため親の容体が急変したとき、すぐに駆け付けることが困難な場合があります。
深夜に連絡が来た場合、新幹線や飛行機が動いていないため、すぐに親元へ向かえません。新幹線や飛行機が動く時間まで待つ必要があります。
車で向かうとしても、時間がかかってしまうでしょう。遠距離介護は、家族だけでは充分にフォローやサポートができない場面が出てくるものです。
もしもの場合に備えて、ご近所の方やケアマネジャーとのコミュニケーションを密にとり、緊急時に備えましょう。
デメリット3:仕事を休む機会が増える
親の介護を遠距離で行う場合、定期的に帰省しなければならないので仕事を休む機会が増えてしまいます。
病院からの呼び出し、同行、入退院の手続きで帰省しなければならない場合や、親が体が思うように動かなくなってきたら、身の回りの世話をすることも必要です。
同居介護や近距離介護の場合は仕事を遅刻や早退をすれば済むことも、遠距離介護では移動を含めると一日仕事になってしまうでしょう
介護への理解が充分に得られない職場の場合、職場での居心地の悪さや、休みにくさを感じる場面も増えます。
親の介護を遠距離で行う際の準備
事前の準備をせずに親の遠距離介護を始めてしまうと、思いがけないトラブルに発展するケースがあります。そのため、親の介護を遠距離でスムーズに行うには事前の準備が大切です。ここでは遠距離介護を行う際の準備について解説していきます。
1.親の希望を聞く
介護が始まる前に、親本人の介護に関する希望をしっかりと聞いておきましょう。
- 万が一の介護が必要となった場合の対応
- 今後どんなふうに暮らしていきたいか
親の希望や要望を確認しておかないと、いざ介護が始まった際に親子で意見が対立して関係が悪くなってしまうかもしれません。
最期まで住み慣れた家で暮らしたいだろうと思い込んでいたら、「子どもに介護の世話になりたくないから老人ホームに入所する」と割り切って考えていることもあります。
親としっかり話し合っておくと、いざというときに親の気持ちを尊重した介護が進められます。そのため、親子で認識をすり合わせておくことが大切です。
2.親の経済状況を理解する
基本的に介護の費用は親のお金を充てるので、親の年金額や貯蓄額を知っておきましょう。そのほかにも、相続の対象となる、借金やローンといった負の財産の有無も確認する必要があります。
また、認知症を発症した際に詐欺や悪徳業者に引っかかる可能性もあるため、印鑑や権利証の貴重品類の保管場所も確認できると安心です。
親の経済状況は聞きにくい話題ではあるものの、将来の金銭トラブル防止のためにも少しずつ確認するようにしましょう。
3.親の生活リズムを理解する
親が日々どんな生活リズムで過ごしているのか、把握しておきましょう。食事の時間や外出の生活パターンといった親の生活リズムを知っておけば、親が日々の生活で何を楽しみにしているか分かります。
また、生活リズムを知る中で日々の生活で親が不安に感じるようになったことや今後支援が必要になるであろうことを確認することも大切です。
親の生活リズムや好きなことや不安に感じていることを知ることで今後の支援や、介護保険サービスを利用する際の参考にもなります。
4.親の人間関係を理解する
親のご近所づきあい、所属している集まりやサークルの親の人間関係を理解しておくことで、相談できる体制が作りやすくなります。
離れて暮らしていると頻繁に様子を見に行くことが難しいため、ご近所の方や近くに住む友人に様子を見に行ってもらうようにお願いしておくとよいでしょう。
気心知れた方が気にかけてくれることによって、親も安心して暮らしやすくなります。
5.親が住む地域の相談窓口へ相談する
親の介護が必要になる前に、親が住む地域の相談窓口へ遠距離介護について相談しておくとよいでしょう。相談窓口は以下のものがあります。
- 地域包括支援センター
- 社会福祉協議会
- 民生委員
まず相談するのは地域包括支援センターが良いでしょう。介護保険サービスだけでなく市区町村が行う独自のサービスや、見守りを行う配食サービスやボランティアなどの紹介もしてくれます。
また民生委員は、地域の生活や福祉全般に関する相談や援助活動を行っているため、親にとっても頼れる身近な存在となるでしょう。
また、事前に相談窓口へ相談しておくと、地域の介護サービスの情報を収集することができ、いざ遠距離介護が始まっても焦ることなく準備ができます。
6.インターネット環境を整える
インターネット環境を整えると、スマートスピーカーなどのIT機器の導入ができます。スマートスピーカーは音声通話機能があり、面倒な操作なしで気軽に通話が可能です。
また、音声操作ができるので、万が一親が転倒して動けない場合もスマートスピーカーの通話機能で離れた家族に助けを求めることもできます。
インターネット環境を整えると、スマートスピーカー以外にも見守りカメラやスマートセンサーの導入が可能です。
親を遠距離で介護する際は、親の家のインターネット環境を整えるとよいでしょう。
親の介護を遠距離で行う際に利用可能なサービス
サービスを積極的に活用することで、親子ともに安心・快適な遠距離介護が目指せます。そこで、親の介護を遠距離で行う際に利用したい便利なサービスを紹介します。
親の遠距離介護でさまざまなサービスの活用を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
1.介護保険制度における住宅改修
介護保険制度では、自宅改修の助成金を出しており、親が要介護認定を受けている場合は、介護保険から一人あたり20万円の助成金を受けることが可能です。
介護が必要になったら早めに住宅改修を検討してみましょう。
介護が必要となった親が安全に住み続けるためにも、以下のように住環境を整えることが大切です。
- 住宅の老朽化している部分の修繕(助成金対象外)
- バリアフリー化
- 廊下や階段に手すりを設置する
こうしたバリアフリーリフォームは、屋内での転倒のリスク予防にもつながります。早めに住宅改修を行い、怪我のリスクを減らしましょう。
2.交通費の割引サービス
飛行機を使って帰省する場合は航空会社の介護割引のサービスを利用できます。介護割引を行っている航空会社は以下の通りです。
- JAL
- ANA
- スターフライヤー
- ソラシドエアー
介護割引を利用する場合は必要書類をそろえて事前に申し込む必要があります。利用を希望する場合は早めに準備を行いましょう。
なお、新幹線は介護割引のサービスを取り扱っていません。しかし、会員登録することで割引を受けられるサービスがあるので、うまく活用することで交通費の節約が可能です。
3.高齢者向けのサービス
高齢者向けの見守り・安否確認のサービスとして以下のものがあるのでチェックしてみましょう。
- 自治体による安否見守りサービス
- 民間会社の宅食サービス
- 民間警備会社の見守りサービス
特に、民間会社の宅食サービスはお弁当の配達時に安否確認や見守りを兼ねている場合が多いです。また、民間警備会社の見守りサービスでは自治体と提携している場合もあります。
自宅に緊急通報システムを設置して、緊急事態時はボタン1つで警備員が自宅まで駆けつけるサービスを受けることが可能です。
4.職場の介護休暇・介護休業の制度
親の遠距離介護が本格化する前に職場の介護休暇・介護休業制度の確認をしておきましょう。
介護休暇・介護休業制度は「育児・介護休業法」で労働者の権利として認められています。制度を利用した場合の賃金については法的な定めがないので職場に確認が必要です。
また、職場の制度の確認と同時に上司や人事に親の介護を遠距離で行う可能性がある旨を相談しておくとよいでしょう。早めに相談することで介護離職を防ぐことにもつながります。
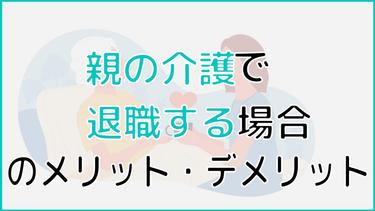
親の介護を遠距離でもうまく行うポイント
親の介護を遠距離で行っていると距離が離れているので楽な部分がある反面、なかなかうまくいかず悩んでしまう場合もあります。
ここでは親の介護を遠距離で行う際に特におさえておくべきポイントを紹介します。快適な遠距離介護を行うためにぜひ参考にしてみてください。
1.親とまめにコミュニケーションをとる
親の介護を遠距離で行うと親の表情や態度を直接見て感じる機会が少なく、親の些細な変化に気が付きにくいです。
また、親は子に負担をかけないために自分の体調不良や困りごとを言わない場合もあります。
親の状況を把握するためにも、子の方から親に連絡をまめにとって相談しやすい環境を作ることが大切です。
また、まめに連絡をとって親の状況を把握すると、病気の前兆やケガのリスクを予想できるだけでなく、高齢者に多い詐欺被害などのトラブルを未然に防ぐことにも繋がります。
2.親の住む地域に気軽に相談できる方を作る
親の住む地域に気軽に相談できる方を作ると、万が一の場合にすぐに駆けつけてもらいやすい体制作りができます。
ご近所の方、ケアマネジャー、地域包括支援センター、民生委員の協力を仰ぐことが大切です。
また、子に相談しづらい話しも、ほかの人には話せる場合もあるでしょう。
子は親の住む地域に気軽に相談できるネットワークを広げることで、親の些細な変化を教えてもらえる体制作りもできます。
3.限界を迎える前に施設入居を検討する
親の介護を遠距離で行う場合、直接的な負担は同居介護に比べて少ないかもしれません。
しかし、遠距離介護には遠距離介護の大変さがあるため、限界を迎えるまで1人で抱え込まず、困難を感じたら施設入居を検討しましょう
要介護度が軽く特養に申し込めない場合でも有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、シニアマンションに入居ができます。
施設によっては生活の自由度が高く、見守りがある中で今まで通りの生活を送ることが可能です。
自立の方が入れる老人ホームを探しているならケアスル介護がおすすめ。全国で約5万件の老人ホーム情報を掲載しているので自立の方が入れる老人ホームの情報も豊富に掲載されています。
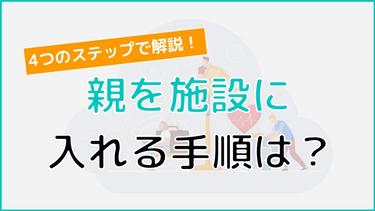
まとめ:親の介護を遠距離で行うには事前の準備が大事
遠距離介護では、親も子も転居せず、住み慣れた地域での生活を続けることができ、身体的・精神的な負担が少なく済みます。
しかし、費用がかさんだり、容体が急変した際に迅速な対応が困難だったりといった弊害が生じる可能性があるので、注意してください。
スムーズに親の遠距離介護を始めるには、あらかじめ親の希望や経済状況などを確認しておきましょう。
また、遠距離介護に役立つサービスの内容についても把握しておけば、いざという時に備えやすくなります。
親の介護を遠距離で行うにはさまざまな人の手をかり、親も子も1つのチームとして準備を行いましょう。
親の今後は子にも関係することを伝えましょう。お互いの今後のために前向きな話し合いであることを伝え、急がずゆっくりと話し合っていきましょう。詳しくはこちらをご覧ください。
まずは親の住む地域を管轄する地域包括支援センターに相談しましょう。今後のことや、今受けることができるサービスの相談に乗ってくれます。詳しくはこちらをご覧ください。







