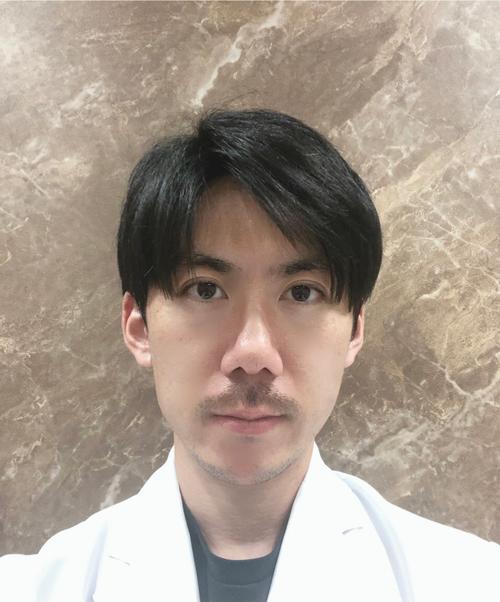「なぜ認知症の方は夜行動するの?」「正しい対処法がわからない」「改善策があったら知りたい」と感じながら介護に励んでいる方は多いのではないでしょうか。
この記事では、認知症患者が昼夜逆転する原因を紐解き、正しい対処法や改善策を紹介します。さらに、避けるべき対応方法についても詳しく解説していきます。
認知症患者に対する理解を深めたい方、介護で日々負担を感じている方はぜひ参考にしてください。
認知症における昼夜逆転とは?
認知症は環境の変化に対応しにくくなり、睡眠障害につながりやすいとされています。すぐに寝付けない、何度も目が覚めてしまうなど睡眠が妨げられてしまい、最終的には昼夜逆転へと発展します。
認知症患者に昼夜逆転認が起きた場合、本人の身体的・精神的影響はもちろんのこと、まわりで支える介護者の生活にも影響を及ぼすでしょう。
では認知症における昼夜逆転を詳しくみていきます。
認知症は活動の低下や神経系の変性で睡眠障害が起きる
認知症は睡眠障害が起きやすい病気です。なぜなら、「記憶障害」「理解力・判断力の低下」によって、日中の活動が減少してしまい睡眠のリズムを作る光の暴露量が減ってしまうからです。合わせて、体内時計を調整している神経系にも悪影響を与えてしまう病気であり、睡眠障害が起きやすいとされています。
また高齢者の場合、自然と睡眠時間が短くなる傾向があり、認知症と合併するとより睡眠リズムが崩れてしまうでしょう。
アルツハイマー型認知症に昼夜逆転が起きやすい
| アルツハイマー型認知症 | レビー小体型認知症 | |
|---|---|---|
| 特徴 | 睡眠リズム障害 | レム睡眠障害 |
| 症状 | 朝まで寝れない、昼に眠くなる | 睡眠中に体が動く・怒鳴る |
認知症には「アルツハイマー型認知症」と「レビー小体型認知症」があり、睡眠に関わる症状が違います。日中の眠気が強くなる、不眠になるなど昼夜逆転が起きやすいのは、”アルツハイマー型認知症”です。
アルツハイマー型認知症に多いとされる理由は、眠気を誘うホルモンの一つメラトニンの減少、覚醒と睡眠の交換作用が低下といった症状がでやすいとされています。
認知症の方でも入所可能な施設が知りたいという方はケアスル介護がおすすめです。ケアスル介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができるためご希望に沿った施設探しが可能です。
「プロに相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
認知症による昼夜逆転が起きてしまう6つの原因
認知症による昼夜逆転は6つの原因が予想されます。
- 不規則な睡眠と覚醒で体内時計が変化
- 不安・恐怖・怒りの感情による不眠
- 日中活動量の低下による不眠
- せん妄の影響
- 日没症候群による能力の低下
- 投与している薬の副作用
昼夜逆転が起きてしまった認知症患者に対して正しい対処を進めるには、原因を追求して相手の状態に合わせた対応が必須です。認知症患者の生活リズムや普段の行動をよく観察し、昼夜逆転につながっている根本的な問題を把握しましょう。
専門家に相談する場合も、「感情のコントロールができず夜眠れない様子がある」といった具体的な内容で相談できるようになるため、より適切な回答を得られやすいです。
不規則な睡眠と覚醒で体内時計が変化
認知症患者は、生物時計システム(体内時計)の器質障害が発生しやすく「不規則型睡眠・覚醒パターン」になるケースがあります。
不規則型睡眠は浅い眠りが続き、夜間睡眠が分断されてしまいます。短時間睡眠による質の低い睡眠をとり続けてしまうと、覚醒状態が頻繁に起きてしまい、体内時計に異常が発生するでしょう。また体内時計がずれてしまえば、昼間の時間に眠気が襲い無駄に昼寝時間を長くとってしまう場合もあります。正しい生活リズムが崩れた結果、睡眠障害が発生して昼夜逆転につながっているといえるでしょう。
不安・恐怖・怒りの感情による不眠
認知症は不安や恐怖を感じやすく、過去に体験したマイナスの感情を「今」に置き換えてしまうなど不安定な精神状態に陥ってしまうケースが多いです。また些細な出来事に怒りを覚える様子も多いでしょう。本来であれば不安や怒りの感情をコントロールして解消するはずが、認知症患者は知能の低下によって上手にコントロールができません。
よって負の感情が蓄積してしまい、寝る直前まで不安や怒りを解消できず不眠になってしまうケースが多いです。日頃から感情を発散する手段がない方ほど不眠に陥りやすいでしょう。
日中活動量の低下による不眠
認知症の症状が悪化していくと、日中の活動時間が少なくなり、夜眠れず昼夜逆転になるケースがあります。日中の活動量が減る理由は、体の不調や自発的に体を動かす意識の低下が発生するからです。日中だらだらと過ごす、居眠りをしすぎてしまうと体に疲労感がなく自律神経に刺激もないため、夜の不眠へとつながるでしょう。
日中の活動量が低下すれば、基礎体温や体内時計の調整ができなくなるのも1つの要因です。
せん妄の影響
せん妄とは、精神障害の一つで、注意力および思考力の低下、見当識障害、覚醒(意識)レベルの変動を起こす状態です。頻繁に夜間の覚醒がおきる認知症は、せん妄の発生が多くなってしまい、意識障害を引き起こします。また覚醒状態にも入るため不眠へとつながるケースも多いでしょう。
せん妄は、急激な環境変化・社会からの隔離による外部刺激からの遮断などの増悪要因が加わることにより顕在化、重症化しやすいとされています。せん妄が悪化すればより睡眠への影響が増加します。せん妄が原因と予想された場合は、詳しい専門家への相談がよいでしょう。
日没症候群による能力の低下
日没症候群は、夕方から夜間にかけて認知能力が著しく低下し、徘徊・興奮・覚醒を起こす病気です。認知症は日没症候群を引き起こしやすいとされています。本来寝るべき時間に覚醒状態となり睡眠を妨げ不眠状態につながるでしょう。
日没症候群は日中よりも夜間にかけて症状を増す傾向があるため、日没症候群を発病してしまうと昼夜逆転を治すのは簡単ではありません。せん妄同様、日没症候群が原因と予想された場合は、早めの相談が必要です。
投与している薬の副作用
病院や専門家から診断の元、症状に見合った薬物療法を行った結果、薬の副作用で睡眠を妨げ睡眠障害につながっているケースがあります。認知症患者は薬による副作用の出現頻度が高いとされ、痛みや苦痛で不眠につながっている場合が多いです。
認知症に対する薬物療法の効果は一過性が多く、効果がでなくなったからと睡眠薬や鎮痛剤を増やせば、より副作用が悪化して睡眠を妨害している可能性があるでしょう。また、薬によっては副作用で眠気を誘うものもあります。昼間に薬を服用したことで、日中眠ってしまい夜寝付けないケースもあるので注意が必要です。
認知症以外の原因が昼夜逆転を引き起こしている場合がある
認知症の症状が直接的な原因ではなく、別の要因も合わさって昼夜逆転を引き起こしている可能性もあります。昼夜逆転になってしまった原因を適切に追求するには、多角的な方面から解決策を探していくのが大切です。
- 睡眠無呼吸症候群
- レストレスレッグス症候群
高齢者がかかりやすい睡眠障害の代表例を2つ紹介していきますので、知識を深めておきましょう。
睡眠時無呼吸症候群
睡眠無呼吸症候群は、睡眠中に10秒から1分程度にわたって無呼吸になる時間が頻繁に発生します。男性に多い傾向で、気道周りに脂肪がついている方がなりやすいです。頻回に無呼吸状態が続くため、血液中の酸素濃度が低下してしまい酸素を取り入れようと脳が何度も目覚めてしまいます。よって、「寝る」「起きる」を繰り返すと夜間睡眠が分断され、睡眠の質が低下し、日中の眠気を増加させる要因となります。
睡眠時無呼吸症候群を発病している方の特徴は、朝まで続くいびきや昼間に強い眠気を感じている様子が表れます。また無呼吸になる症状自体は、寝ている最中でしか確認ができないので、睡眠中の状態も定期的に確認するようにしましょう。
レストレスレッグス症候群
むずむず症候群とも呼ばれ、入眠時に足の不快感を感じてしまいなかなか入眠できない状態が発生します。不快感を感じる症状とは痛み、かゆみ、突っ張る、不快感、虫が這う感じなど人によってさまざまです。下肢を動かすことで不快感が軽減しますが、入眠に入る前に再度不快感が発生して睡眠を妨害するケースが多いでしょう。
動かない時に症状が強まる傾向があり、夜間に症状がでやすいです。ただレストレスレッグス症候群の進行が進むと昼間に症状が現れるようにもなります。日中の活動中に足に違和感を感じているようでしたら、レストレスレッグス症候群を疑ってみましょう。
認知症の場合、足の不快を自分の口で訴えられない可能性があり、ストレスを溜め込んで睡眠障害につながる危険性もあります。
認知症で昼夜逆転する患者の対策・対処法
認知症で昼夜逆転する患者の対処法を詳しくみていきましょう。
昼夜逆転が起きてしまった原因を追求して、認知症患者の状態に合わせた対処を実践していくのが大切です。一気に対処法を実践してしまうと認知症患者・介護者ともに負担が大きいので、順番に試していく形がよいでしょう。
日光を浴びてメラトニンを抑制する
日光は眠気を誘うホルモンの一種であるメラトニンの分泌を抑える作用があり、昼間にたくさん眠ってしまう状態を防ぎます。本来、人は日光を浴びて覚醒状態に入り、日が沈んで太陽光がなくなるとメラトニンの分泌が始まって眠気が誘発されます。日光を浴びなければリズムが崩れ睡眠に影響を及ぼしてしまうので、できる限り生活ルーティンに日光を浴びる習慣を作ってあげましょう。
- 朝起きたらカーテンを開ける
- 毎朝決まった時間に散歩をする
- 起きたら花に水をあげる
- 朝一で新聞をポストまで取りにいく
上記のように、無理なく実施できる行動パターンはおすすめです。
眠りやすい環境づくりをする
認知症患者が眠りやすいように、寝室環境の整備も効果的です。寝室環境が認知症患者に適していないとリラックスできず、寝付けないケースも多く注意が必要でしょう。認知症患者は不安や恐怖を感じやすいため、寝室環境に目を向けていなかった場合はぜひ改善してください。
寝室の環境づくりにおいて検討すべき点は4つです。
- 寝室の明るさ
- 室内・室外の音
- 室温
- 寝具の種類
また、眠りやすい環境づくりのポイントも紹介します。
- 好きな香りがするものを置く
- 本人が傍にあると安心できるものを置く
- マッサージ器などリラックスできる道具の設置
- 適正な湿度管理をする
- 癒しのBGMを用意する
生活リズムを整え規則正しく過ごす
規則正しい生活リズムを送っていれば、自然と夜に眠気がおとずれるようになって昼夜逆転の解消に期待できます。生活リズムがバラバラで不規則な生活をしている状態が続けば、睡眠のリズムが崩れてしまい、不眠に陥る可能性は高いです。規則正しい生活を続けるには、習慣化が必須になるため、生活の流れをルール化してルーティンに落とし込んでいきましょう。
規則正しい生活リズムを作るおすすめの方法は2つです。
- 1日の生活リズムを時間毎に設定してタイムスケジュール化する
- 睡眠日記を作成して生活のリズム・睡眠時の状況を記録してヒントを得る
注意すべきは、認知症患者の意思を強制的に抑えつけるような行為はNGです。本人の意思を無視した行動は症状を悪化させる可能性があります。最終的に不安や恐怖を抱えてしまい、不眠につながってしまう可能性もあるでしょう。
痛みや不安を取り除く
認知症は身体面・精神面で不調を抱えやすいため、認知症患者が抱えている痛みや不安を取り除くケアが大切です。不調を抱えやすいのは、以下のようなケースが頻回に発生してしまうからでしょう。
- 注意力の低下によって転倒・転落のリスクが増加して怪我をする
- 認知症の進行によるかゆみ・だるさなどの不快感増加
- 記憶力低下によってイライラや気分が滅入る
- 不意に恐怖や不安感を感じてしまう
また認知症によって引き起こされる症状は日中よりも夜に増加するケースが多く、睡眠に影響を与える痛みや不安を取り除くことが最優先です。認知症患者の状態を観察して、介護者は相手に合わせたケアを日々実施してあげましょう。
- 就寝前に痛みがある箇所のマッサージ
- 痛み改善を目的とした病院の受診
- 積極的なコミュニケーション
認知症患者によっては体の痛みや心の不安を訴えられない方も多く、精神的負担を抱えているケースもあります。身体や行動をよく観察して不調を介護者が見つけてあげることも重要です。そのためにも相手の声に耳を傾ける・話相手になるなど、できる限り寄り添う気持ちが痛みや不安を取り除くには大切でしょう。
無理をせず専門家へ相談する
認知症で引き起こされる昼夜逆転で苦しんでいる場合、自分達でなんとかしようとせず専門家や医師に相談するのも大切です。本人・介護者だけの力で改善できない事例も多く、無理に対策を進めることで認知症患者が悪化してしまう可能性もあるでしょう。
また現在服用している薬が睡眠を妨害する要素を含んでいる可能性もあります。薬の服用が昼夜逆転につながる原因のケースもあるので、無理に服用を進めず一度医師へ相談してください。医師に相談すれば、薬の調整をしてもらうこともできます。
介護は想像している以上に負担が多く、介護者の心や体が乱れてしまい、結果的に認知症患者に悪影響を及ぼすケースもあります。誰かに頼るのは悪いことではないと自覚して一人で抱えないようにしましょう。専門家へ相談する行為が認知症患者にとってプラスに働くこともあります。
認知症による昼夜逆転の治し方として薬物療法はどう?
現在、認知症患者の睡眠障害(注射逆転)の対応として効果の高いエビデンスは存在していない状態です。よって、薬物療法においては必ずしも正解とは言い切れないでしょう。
医師の判断の元、認知症患者に合わせて薬物を投与するケースもあります。しかし認知症患者は薬による副作用の出現頻度が高いとされているため、結果的に解決につながるかは未だ不明です。薬物療法は筋脱力や日中の覚醒低下に影響する可能性もあるため、投与する場合は「少量、短期」で進めていくのが大切でしょう。場合によっては、短期的な睡眠薬の利用が認知症患者と介護者の負担軽減となりメリットになることも考えられます。
認知症による昼夜逆転の治し方として薬物療法を取り入れる場合、常にリスクと照らし合わせて検討するようにしてください。
認知症による昼夜逆転を早急に解決する意識は悪化させる
認知症患者・介護者の負担を早期に減らすのが正解と考え、やみくもに解決策を実施する意識は危険です。特に早い段階での睡眠薬の投与や半ば強制的な行動制限・サポートはかえって症状を悪化させてしまい逆効果をもたらす可能性があります。
認知症による昼夜逆転の状態になった原因は1つとは限らず、さまざまな要素から発生している可能性があるでしょう。まずは認知症患者の行動や言動をみて原因の追究を行い、少しずつ行動していくのが大切です。
効果を確かめていくためにも1つずつ対処法を試していく方法がおすすめです。実施していく中で観察日記を導入して、認知症患者の状態を日々記録に取っていくと相手に合った最適な答えを導き出せる可能性があるでしょう。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
まとめ
認知症は睡眠障害を引き起こす要素が多く、昼夜逆転してしまうケースが多くあります。考えられる原因は複数存在し人によって差があるため、個人の症状や状態をよく観察したうえで根本的な原因を追究する必要があるでしょう。
認知症による昼夜逆転の対処法は以下にまとめておきます。
- 日光を浴びてメラトニンを抑制する
- 眠りやすい環境づくりをする
- 生活リズムを整え規則正しい生活をする
- 痛みや不安を取り除く
- 無理をせず専門家や医師へ相談をする
介護は負担が大きく早急に昼夜逆転している状況を解決したいと考える方も多いですが、無理に対処を進めると悪化する可能性が高いとされています。今回の記事を参考にして原因の追求を行い、相手に合わせたペースで対処を進めるようにしてください。
まずは昼夜逆転になってしまった原因を探しましょう。原因は1つではなく、さまざまな要素が複合している可能性もあります。日中の活動や本人の行動をよく観察することが大切です。また、認知症とは直接関係のない要素が原因になっている場合もあります。原因がみえてきた段階で適切な対処をするようにしてください。詳しくはこちらをご覧ください。
現在、認知症の睡眠障害に対する効果の高いエビデンスはありません。薬物療法もありますが、確実な効果があるとは言い切れず、副作用の心配があります。また、早急に解決しようと認知症患者の意向を無視した対応は症状の悪化をもたらす可能性もあります。介護は負担が大きく、周囲の方が疲弊しやすくさまざまな問題を早急に解決したい気持ちが出てしまうのも当然でしょう。しかし、相手に寄り添って解決方法を探るのが最も近道となります。困ったときは無理をせず専門家に相談する姿勢も大切です。詳しくは、こちらをご覧ください。