
レスパイト入院とショートステイの違い|デメリットや保険適用についても解説
レスパイト入院とショートステイの違いは、医療ケアが必要な方の受け入れ可否にあります。 レスパイト入院では医療ケアが必要な方を受け入れてますが、ショートステイでは、施設によっては受け入れが難しい場合があります。 レスパイト入院とショートステイの違い レスパイト入院とは、自宅療養中の患者の方に一時的に入院をしてもらうことにより、その方を自宅で介護している家族が休息を取れるよう支援する入院のことです。 […]

レスパイト入院とショートステイの違いは、医療ケアが必要な方の受け入れ可否にあります。 レスパイト入院では医療ケアが必要な方を受け入れてますが、ショートステイでは、施設によっては受け入れが難しい場合があります。 レスパイト入院とショートステイの違い レスパイト入院とは、自宅療養中の患者の方に一時的に入院をしてもらうことにより、その方を自宅で介護している家族が休息を取れるよう支援する入院のことです。 […]

訪問看護でできることとしては、健康管理や医師の指示に基づく治療といった医療ケア、利用者やその家族の心理的ケア、そのほか生活支援などが挙げられます。 一方、訪問看護でできないことは、病院や専門施設で行われるような高度な医療行為やリハビリ、日常的な家事など医療行為の範囲を超えた生活支援が挙げられます。 訪問看護でできること 訪問看護でできることとして、以下のようなことが挙げられます。 健康管理や医師の […]
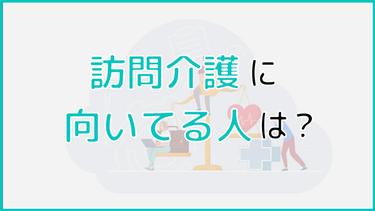
訪問介護に向いてる人は、以下のような能力を持っている人だと言えるでしょう。 相手の心情に寄り添い、信頼関係を築いていく力 利用者の在宅環境を観察し、適切に判断する力 地域医療や家族と連携する力 訪問介護に向いてる人は? 訪問介護職に向いてるかテストしてみよう 以下の質問に対し、「はい」か「いいえ」のどちらが近しそうか考えてみてください。 【第1問】 環境が急変しても、その状況下でどのように対応でき […]

高齢者に合う食事とはどんなものでしょうか。今回は、高齢者の食事の献立を作るコツについてご紹介します。 石井 香代子 教授 福山大学 生命工学部 健康栄養科学科 管理栄養士、教員 日本給食経営管理学会、日本調理科学会、日本栄養改善学会ほか 岡山県立大学大学院 保健福祉学部研究科 栄養学専攻 修士課程修了 瀬戸内短期大学 食物栄養学科准教授(2002₋2008年3月) 福山大学 生命工学部 健康(生命 […]

今回はいつまでも元気に健康でいられるよう、高齢者の口腔機能低下を防ぐためのケアについて紹介いたします。 田村 暢章 教授(医学博士) 明海大学 歯学部 病態診断治療学講座 高齢者歯科学分野 歯科医師/教授 日本口腔外科学会専門医・指導医、日本口腔インプラント学会専門医・指導医(代議員)、日本顎顔面インプラント学会専門医・指導医、日本口腔科学会認定医、日本口腔ケア学会評議員、日本老年歯科医学会代議員 […]

今回は、認知症による高齢者の意思能力と、不動産取引に関しての事例や制度を紹介いたします。 安藤 清美 教授 青森大学 社会学部 日本私法学会、日本家族〈社会と法〉学会、等 帝京大学大学院博士課程において、川井健教授(故人)の指導を受ける。 専門は民法(特に親族相続法)。 主な著書・論文は、『入門民法総則』法学書院、『民法総則・親族相続法』文教出版会、「判例評論第694号60」判例時報社、等がある。 […]