生活保護受給者でも介護保険に加入することは可能です。40歳から65歳までの生活保護受給者は介護保険料の支払いは無く、65歳以上の場合も介護保険料は生活保護費としてすべて賄われるので介護保険料を負担することもありません。
また、年齢関係なく介護保険サービスを利用した場合も「介護扶助」が支給されるので、実質自己負担なしで介護保険を利用することができます。
介護保険には40歳から65歳までの第二号保険者と65歳以上の第一号保険者があるので、保険料の支払いや徴収方法にも違いがあるので注意が必要です。
本記事では、生活保護で介護保険サービスを利用するうえでの保険料の支払い方、要支援・要介護認定された場合の措置、どのような扶助や加算が出るのかなどについて詳しく解説していきます。
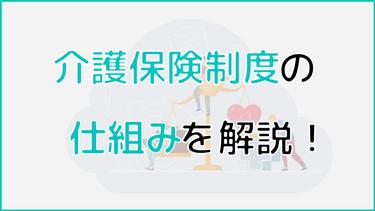
生活保護を受給していても介護保険サービスは受けられる
そもそも介護保険とは、満40歳から加入が義務付けられており、保険料の支払うことで要介護状態となった時に介護保険適用内のサービスを自己負担額1~3割で受けることができる保険です。介護保険サービスは基本的には65歳以上で要介護認定を受けると利用することができます。
介護保険料は通常医療保険に上乗せして納付しますが、生活保護受給者は医療保険から脱退するため無保険の状態となります。したがって、通常の支払いとは違った方法で納付します。
まず40~64歳の生活保護受給者は医療保険料を支払わないので介護保険費用も支払いもありません。また、65歳以上の場合は介護保険の第一号被保険者となるので保険料を支払いますが、65歳以上の介護保険受給者の保険料は生活保護費の「生活扶助」に保険料が足されたうえで年金から天引きされます。(実費の支払いは無し)
また、40~64歳の生活保護受給者で介護保険費用を支払っていない人でも特定の疾病の場合は例外的に要介護認定を受けられ、介護保険サービスを利用できます。介護度の限度内であれば自己負担はなく、生活保護費の介護扶助から支払われます。
したがって生活保護を受給していても限度額を超えない限り、保険料の支払いや介護サービス、老人ホームの利用料の自己負担はなく利用することができるのです。
介護保険について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
老人ホームへの入居を検討しているという方は、ケアスル介護がおすすめです。ケアスル介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができるためご希望に沿った施設探しが可能です。
「プロに相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
年齢によって生活保護受給者の介護保険サービスは異なる
介護保険制度には2つの区分があり65歳以上の人は第一号被保険者、40歳から64歳までの人は第二号被保険者に分類されます。それぞれ費用の支払い方などに違いがあります。
介護保険制度の2つの年齢区分
介護保険制度には2つの区分があり、65歳以上の人は第一号被保険者、40歳から64歳までの人は第二号被保険者に分類されます。第一号被保険者になり、かつ要介護の認定を受けると、介護保険のサービスが利用可能です。
通常40歳になると、国民健康保険料や社会保険料に上乗せされる形で介護保険料が徴収され、強制的に加入することとなります。
要介護認定とは、現在の介護の度合いを客観的に判断し自立、要支援(1~2の2段階)・要介護(1~5の5段階)に数値化したものです。要介護・要支援状態となった時に介護保険の利用が可能になり、それぞれの段階別に限度額が設定されているのです。
生活保護受給者と通常の場合の違い
65歳以上の人は第一号被保険者、40歳から64歳までの第二号被保険者それぞれで通常の場合と比較して保険料や介護保険サービス費用の負担について一覧表でまとめたのが以下の表となります。
| 年齢 | 生活保護受給の有り無し | 保険料 | 介護保険サービス費用 |
| 40~64歳(第二号被保険者) | 生活保護受給の場合 | 納付額は無し | 本人の出費はなく、生活保護費の介護扶助によって支払う |
| 通常の場合 | 国民健康保険、社会保険に介護保険料が上乗せされる | 所得によって1~3割の自己負担 | |
| 65歳以上(第一号被保険者) | 生活保護受給の場合 | 生活保護費の「生活扶助」に保険料が足されたうえで天引き(実質自己負担なし) | 1割の自己負担が発生するが、生活保護の介護扶助で支払い(実質自己負担なし) |
| 通常の場合 | 年金から天引きされる | 所得によって1~3割の自己負担 |
生活保護における「生活扶助」とは、被保険者の日常生活で必須になる需要を満たすための扶助です。地域や年齢によって異なる「基準生活費」に加えて妊産婦加算や母子加算などの「加算」があります。その一つとして「介護保険料加算」があるので、65歳以上の生活補助受給者は「介護保険料加算」によって実質自己負担なしで介護保険に加入できます。
40~65歳の生活保護受給者が介護保険を利用する場合
介護保険は満40歳から加入し、40歳から65歳までの間は第2号被保険者と分類されます。第2号被保険者の場合は、保険料の支払いのみを行い、基本的には介護保険サービスは利用できません。
生活保護受給者も同様に基本的には介護保険サービスは利用できませんが、一部要件を満たすことでサービスが利用できることはあります。また、生活保護受給者だと、分類が少し異なるため、この点も理解しておきましょう。
介護保険料の支払いは無い
生活保護を受給すると国民医療保険から脱退することになります。つまり、公的医療保険から外れるので無保険の状態となります。
通常であれば、介護保険料は国民健康保険料や社会保険料に上乗せされる形で介護保険料が徴収されますが、公的医療保険から脱退するので生活保護を受給している40~65歳までの生活保護受給者は介護保険の納付ができません。
したがって、40~65歳までの生活保護受給者は介護保険料の支払いは必要ないのです。なお、国民健康保険から脱退しても医療費や入院費は生活保護費から出してもらうことができるので、自己負担額無しで医療サービスを受けることができます。
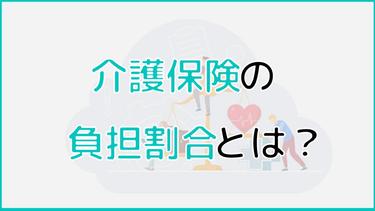
介護保険サービスを受けたい場合
第1号被保険者以外でも、一定の要件を満たすことで介護保険サービスは利用可能です。40歳から65歳までの人でも、特定の疾病によって要介護の認定を受けている場合は、介護保険サービスは利用できます。特定の疾病とは、次の通りです。
- がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
疾病の種類については、生活保護を受給しているかどうかに関係なく共通しています。
生活保護で施設に入りたい方はこちらの記事もご覧ください。
- 生活保護を受けていても老人ホームに入れます!|気になる費用や入る流れまで解説
- 生活保護でも施設に入居できる?条件や手続きの流れについて解説
- 生活保護を受けても介護保険料は自費? 介護サービスは利用できるのか、介護保険の仕組みまで詳しく解説
関連記事
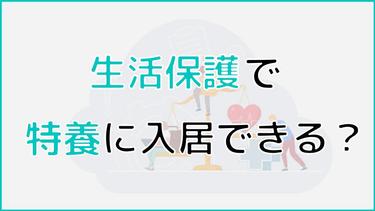 生活保護受給者は特養(特別養護老人ホーム)に入居できる?費用と条件を解説カテゴリ:特養(特別養護老人ホーム)の費用更新日:2024-05-24
生活保護受給者は特養(特別養護老人ホーム)に入居できる?費用と条件を解説カテゴリ:特養(特別養護老人ホーム)の費用更新日:2024-05-24
第2号被保険者ではなく「みなし2号」と分類される
本来なら40歳以上で65歳までの人は第2号被保険者に分類されますが、生活保護受給者の場合はこの分類にはなりません。これは医療保険料を支払っていないことが理由であり、介護保険料も納付できないからです。
しかし、上の特定の疾病をり患しているなどの場合は介護保険サービスが必要となるため、介護保険上は「みなし2号」という分類になります。
「みなし2号」は第2号被保険者と同じと判断されるものです。また、生活保護の介護扶助によって、費用の全額が支給されるため、自己負担はありません。
65歳以上の生活保護受給者の介護保険料
年齢が65歳以上の場合は、介護保険制度では第1号被保険者に該当します。生活保護を受けていても介護保険料の支払いは必要であり、これは医療の保険料を支払っていない場合も同じです。
年齢が65歳以上になると、自動的に第1号被保険者と分類されるため、年齢による被保険者分類の切り替わりがあることは覚えておきましょう。
介護保険料の支払い義務が発生する
通常65歳以上の場合は第一号非保険者となるため、年金からの天引きで介護保険路湯を支払います。
生活保護受給者の場合も65歳以上となった場合も第一号被保険者となるため、生活保護費に上乗せされた「生活扶助分」から天引きされることとなります。上乗せされた生活扶助分から天引きされるので、実質的な自己負担額は0円ということとなります。
生活扶助の加算は生活保護から外れるか、介護保険料が年金からの特別徴収になるまでつつきます。なお、特別徴収された介護保険料も介護保険料控除という控除で賄うことができるので実質自己負担額は0円のままです。
- 当該年の4月1日現在において、65歳以上(国民健康保険は、かつ75歳未満)であること。
- 当該年の4月1日現在において、特別徴収の対象年の年金支払額が、年額18万円以上であること。
- 年金の支払いに対して担保設定がされていないこと。
介護保険料の納付方法
第1号被保険者の場合は、代理納付という方法で介護保険料が徴収されます。これは、生活保護費から天引きして保険料を支払う方法です。
福祉事務所が生活保護費を天引きし、それを市区町村に納付するため、代理納付と呼ばれています。仕組みとしては生活保護費からの天引きとなるため、自身で納付の手続きをする必要はありません。
かつては現金での納付が一般的でしたが、介護保険料分を加算しているのにもかからわずに滞納するという事例田多発するため、「代理給付」が一般的な方法となりました。
場合によっては現金納付もあることに注意
生活保護受給後に一時的に介護保険料の上乗せ分を現金で支給している場合は天引きにはならないため、現金での納付となります。
また、老人ホームに入居している場合は通常であれば福祉事務所が代理納付します。しかし、住宅地特例制度※を使って老人ホームに入居しており、住民票と施設の住所が違っている場合は現金での納付が必要になることに注意しましょう。
- ※1住所地特例対象施設(※2)に入所又は入居し、その施設の所在地に住所を移した者については、例外として施設入所(居)前の住所地の区市町村(保険者)が実施する介護保険の被保険者になる制度。
- ※2介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)、特定施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム、上記(1)(2)に該当するサービス付き高齢者向け住宅)、養護老人ホーム
出典:東京都福祉保健局「住所地特例(サービス付き高齢者向け住宅)について」
老人ホームへの入居を検討しているという方は、ケアスル介護がおすすめです。ケアスル介護は、約5万件の施設情報を掲載しているため幅広い選択肢から検討することが可能です。
「施設選びで失敗したくない」という方は、ご気軽に活用ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
介護保険サービスの自己負担額は介護扶助が出る
「介護扶助」とは介護サービスの費用を生活保護で賄うための制度で、具体的なお金の流れは以下の通りです。まず、介護サービスの必要性が確認されたら生活保護の指定を受けた介護機関から介護サービスを現物給付で提供されます。
次に、指定介護機関は生活保護受給者に対して福祉保健センターへの介護券の交付を申請します。介護券が届いたら介護券に記載されている情報をもとに、国民健康保険団体連合会に介護扶助費の請求をするのです。
そのため、生活保護を受けている人は介護券の申請を適切に行うことで自己負担なしで介護サービスを利用できます。
生活保護受給者ではないが支払いが難しい場合
生活保護受給者ではなくても、介護保険料の支払いが苦しくなることもあります。65歳以上の高齢者で生活保護を受けている人は約45%と増えており、自治体での負担が大きいことから認定が難しくなっています。
そのため、生活保護を受けたくても受けられないという人はおり、介護保険料が支払えないということもあるでしょう。介護保険料は滞納するとさまざまなペナルティがあるため、注意しなければなりません。
滞納することでどのようなペナルティが発生するのか、また支払いが難しくなった場合にはいかに対処するのかなどは知っておきましょう。
介護保険料を滞納してしまった場合
介護保険料の納付期限は2年と決まっており、滞納期間に応じたペナルティがあります。ペナルティは期限の2年滞納した時点から起きるわけではなく、1年以上滞納した時点で生じることは理解しておきましょう。
支払いを1年以上滞納すると、本来1~2割負担で受けられる介護保険サービスの支払いを、一度全額自己負担しなければなりません。
例えば、1割負担で1万円で済むサービスの場合でも、最初に10万円実費で支払い、後から申請して9割分が給付されます。一時的な自己負担が大きくなるため、この点には注意しましょう。
1年6ヶ月以上滞納すると、介護サービスの料金を一度全額自己負担することはもちろん、その後申請によって戻ってくるお金の一部、または全額が差し止められます。さらに滞納期間が長くなると、差し止め分から保険料の滞納分を差し引くことになり、手元に残るお金が減ってしまうため注意しなければなりません。
有効期限の2年以上滞納すると、自己負担が1~2割から3割に引き上げられてしまいます。介護保険サービスが高額になった場合の、高額介護サービス費制度なども利用できなくなるため、この点も覚えておきましょう。
滞納期間が長くなるほど、ペナルティは大きくなってしまうため、滞納せずにスムーズに納付することが大切です。
境界層措置という方法もある
生活保護は受けられないものの、経済的に苦しい場合は、境界層措置を利用することも選択肢の1つです。境界層とは、生活保護を受けるほどではないものの、経済的な困窮が認められる人を指します。
自治体に申請して「境界層該当措置証明書」を発行してもらうと、介護保険料を滞納してもペナルティがありません。また、保険料の減額や介護施設の居住費や食費を減額してもらえるなどのメリットもあるため、介護保険料の支払いが苦しい場合は境界層措置の利用を検討しましょう。
他にも被災者や低所得者を対象に、介護保険料の減額や減免を行っている自治体もあります。自治体独自の支援策によって介護保険料の負担は減らせるため、ケアマネージャーなど知識が豊富な人に相談しながら、利用できる制度がないか調べておくことがおすすめです。
介護保険は社会全体で介護を支えることが目的
介護保険は社会全体で高齢者を支えることを目的とした制度です。制度を活用することで、介護サービスを利用した際の費用を抑えられ、介護コストの削減ができます。生活保護受給者でも、介護保険サービスの利用は可能です。
生活保護受給者の場合は、保険料の支払い方法が通常とは異なるため、この点はチェックしておくことが大切です。介護保険料を滞納なく支払い、適切なサービスを受けるためにも、制度についての理解は詳細まで深めておきましょう。
そのほか介護保険料について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
関連記事
 介護保険料は免除してもらえる?カテゴリ:介護保険料更新日:2024-05-31
介護保険料は免除してもらえる?カテゴリ:介護保険料更新日:2024-05-31
生活保護を受給している方でも、介護保険サービスを利用することは可能です。また、生活保護を受給している方は、限度額を超過しない場合には自己負担なく利用することができます。詳しくはこちらをご覧ください。
生活保護は受けられないものの、経済的に苦しい場合は、境界層措置を利用することも選択肢の1つです。境界層とは、生活保護を受けるほどではないものの、経済的な困窮が認められる人を指します。詳しくはこちらをご覧ください。




