「要介護認定ってどんな制度なの?」「親がそろそろ介護サービスを使った方がよさそうけど、認定されないと利用できないの?」と疑問に感じている方もいるでしょう。
要介護認定とは、要支援と要介護の2つに分けられます。介護保険を利用して受けられる介護給付や予防給付のサービスを利用するためには、要介護(要支援)認定を受けることが必須条件です。
そこで今回は要介護の区分の違いや申請方法、実際に介護保険サービスを利用する方法について詳しく解説します。認定結果に不服があるときの対処方法まで解説しているので、スムーズに要介護認定の申請ができるでしょう。ぜひ参考にしてください。
要介護認定とは
要介護認定とは、日常生活においてどの程度介護が必要であるのかを客観的に評価して数値化したもので、「要介護状態にある65歳以上の方」もしくは「40歳以上65歳未満で特定疾病により要介護状態にある方」が対象です。
国が定めた一定の基準と方法に則り、各市町村がチェックして「要支援」と「要介護」、もしくは「自立」の3つに分けられます。要介護認定を受けると、自己負担額1〜3割で介護保険サービスを利用できるようになります。
以下の2点は要介護認定を知るうえで大切なため、詳細を解説していきます。
- 要支援と要介護の違い
- 支給限度基準額の違い
要支援と要介護の違い
要支援と要介護では心身の状態が異なります。要支援は、基本的に日常生活において他者の介助を必要としません。一方の要介護では、一人では日常生活を送ることができないため、他者の介助を要します。
また、要支援と要介護では受けられるサービス内容が大きく異なります。
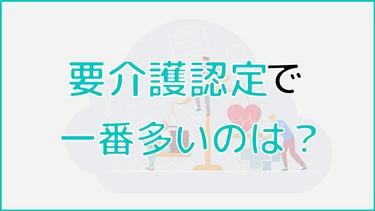
支給限度基準額の違い
要支援と要介護では1ヶ月に利用できるサービスの量(支給限度額)が大きく異なります。それぞれの区分ごとの支給限度基準額は以下の通りです。
| 区分 | 区分支給限度基準額(単位) | 支給限度額(円) |
|---|---|---|
| 自立 | 0 | 0 |
| 要支援1 | 5,032 | 50,320 |
| 要支援2 | 10,531 | 105,310 |
| 要介護1 | 16,765 | 167,650 |
| 要介護2 | 19,705 | 197,050 |
| 要介護3 | 27,048 | 270,480 |
| 要介護4 | 30,938 | 309,380 |
| 要介護5 | 36,217 | 362,170 |
出典:厚生労働省
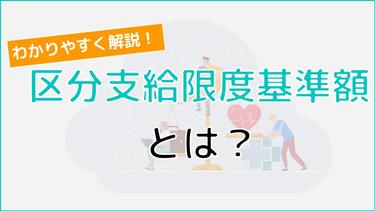
また、要介護認定で自立と判定された方でも入所できる施設を探すならケアスル介護がおすすめです。全国で約5万件以上の施設情報を掲載しているので、幅広い選択肢からピッタリの施設を探すことが出来ます。
何から始めればよいかわからないという方はぜひ利用してみてください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
要介護認定の区分
要介護認定は、要支援の2区分、要介護の5区分と、該当なしの自立の8つに分けられます。それぞれの区分は以下の通りです。
- 【2区分】基本的には1人で生活できる:要支援1~2
- 【5区分】1人では日常生活を送れない:要介護1~5
- 【該当なし】自立
介護を必要とする度合いは自立が最も軽く、要介護5が最も重い区分です。この判定によって介護保険料の支給限度額や利用できる介護保険サービスが決定します。ここからは、それぞれの区分について具体的に解説します。
要支援1~2:基本的には1人で生活できる
要支援は、要支援1と要支援2の2つの区分に分けられます。要支援1や要支援2の方は、食事や排泄、着替えなどの日常生活の動作を自分で行うことが可能ですが、将来支障があると見込まれる状態であり、要介護状態になることを予防する必要があると判定されます。
判定する基準の指標として、要介護認定等基準時間が用いられます。この指標は要介護者を介助するのにどのくらいの時間を要するのかを表しています。ただし、要介護度は要介護認定等基準時間だけで判断されるわけではありません。そのほかの要素も考慮されます。
要支援1や要支援2の要介護認定等基準時間は以下の通りです。
| 区分 | 要介護認定等基準時間 |
|---|---|
| 要支援1 | 25分以上、32分未満 |
| 要支援2 | 32分以上、50分未満のうち要支援状態にある者 |
(引用:厚生労働省「要介護認定にかかる法令」)
要支援1と比較して、要支援2の方がより支援を必要とする状態です。受けられるサービスの違いはほとんどありませんが、認知証対応型共同生活介護(グループホーム)が利用できるのは要支援2からとなります。
要介護1~5:1人では日常生活を送れない
要介護は、要介護1から5までの5つの区分に分けられます。基本的には1人で日常生活を送れないために、何らかの支援・サービスの提供が必要な方を対象としています。
それぞれの要介護認定等基準時間は、以下の通りです。
| 区分 | 要介護認定等基準時間 |
|---|---|
| 要介護1 | 32分以上、50分未満のうち、要介護状態にある者 |
| 要介護2 | 50分以上、70分未満 |
| 要介護3 | 70分以上、90分未満 |
| 要介護4 | 90分以上、110分未満 |
| 要介護5 | 110分以上 |
(引用:厚生労働省「要介護認定に係る法令」)
自立
要介護認定の申請を行っても、日常生活を一人で送ることができ普段の生活を営む際に介助は必要ないと判断されると、非該当により自立と判定されます。
「自立」と判定されると、要介護認定が利用基準となっている、介護保険を利用したデイサービスやホームヘルパー、通所リハビリなどを利用できず、福祉用具のレンタルもできません。
また、特別養護老人ホーム(特養)や介護老人保健施設(老健)など公的な施設や、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などの民間の施設でも、要介護の認定を前提条件としている施設が多いため、入居できない可能性があります。
自立と判定された方は、市町村が提供する介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)をうまく利用することで、生活の不安を減らすことができます。お住まいの市区町村又は地域包括支援センターに相談しましょう。
要介護認定を受ける方法
介護保険サービスを利用するためには、要介護認定を受けることが条件です。日常生活に手助けが必要な方は、まずは適切に要介護認定の申請をしなければなりません。
ここからは要介護認定を受けるために必要な申請書の準備や申請場所について、以下の順番で具体的に解説します。
- 申請に必要な書類などを準備
- どこに申請する?
- 本人が申請できないときの対処法
申請に必要な書類などを準備
要介護認定を受けるために、必要な書類を準備しなければなりません。必要書類として主に挙げられているものは以下の通りです。
| 申請時に必要なもの | 注意点など |
|---|---|
| 申請書 | 市区町村のホームページからダウンロードまたは窓口 |
| 介護保険被保険者証 | 65歳以上の方が対象 |
| 健康保険被保険者証 | 64歳以下の方が対象 |
| マイナンバーカード | カードがなければ通知書でも可 |
| 身分証明書 | 免許証などの顔つきの写真 |
| かかりつけ医の診察券など | 主治医の情報が確認できるもの |
市区町村により必要となるものが異なる場合もあるため、詳しい情報はホームページや、直接電話で問い合わせて確認するとスムーズです。
介護保険申請ができる人は?具体例からできない人、申請の流れまで解説
どこに申請する?
要介護認定の申請は、対象者本人が居住している市区町村の窓口で行います。介護保険課、介護福祉課、高齢介護課など受付窓口の名称は市区町村によって異なるため、ホームページなどで確認しましょう。
要介護認定を受けるための制度はかなり複雑です。確認したい内容がある場合は、申請時窓口で直接聞いてみると、理解を深められるでしょう。

本人が申請できないときの対処法
要介護認定は基本的に介護サービスを受ける本人や家族が申請します。しかし、何らかの事情で市区町村の申請窓口に行けない場合もあります。そのときは親族や事業所の代行による申請が可能です。該当する事業所は以下の通りです。
- 居宅介護支援事業所
- 地域包括支援センター
- 特別養護老人ホーム(特養)
- 介護老人保健施設(老健)
- 介護医療院
- 介護療養型医療施設
なお、既に施設に入居している場合は、入居施設ののスタッフに代行してもらえます。
要介護認定の申請から判定までの流れとは
申請してから要介護認定を受けるまでの流れは、どのようになっているのでしょうか。実際の流れは以下の通りです。
- 市区町村での申請
- 認定調査員による訪問調査
- 主治医の意見書
- コンピューターによる一次判定
- 介護認定審査会による二次判定
介護認定を受けるには、この5つのステップを踏み、要介護認定と判定された後、ケアプラン作成を経て介護保険サービスが利用可能となります。
認定結果は、基本的に申請してから30日以内に申請者へ通知がきます。ただし、地域によっては申請から判定まで1ヶ月以上かかる場合もあります。通知が遅れる場合は、申請者に遅れる理由や結果を通知するまでの見込みの期間が通知されます。
市区町村での申請
居住している市区町村の窓口で申請します。介護保険課、介護福祉課、高齢介護課など受付窓口の名称は市区町村によって異なるため、詳細はホームページなどで確認しましょう。ほかにも、申請は地域包括支援センターでも受け付けています。
申請書は市町村の窓口でもらえるほか、ホームページからダウンロード可能です。本人や家族以外の代理人が申請する場合は、委任状などの代理権が確認できるものや代理人の身元が確認できるものなどが必要となるため、事前に準備しておきましょう。
認定調査員による訪問調査
所定の書類を揃えて申請したあと、認定調査員による訪問調査があります。これは「生活していく中で申請者がどれくらい介護が必要なのか」を確認するためです。
実際には、市区町村の職員や事業受託会社の職員が申請者の自宅を訪問します。申請者が入院している場合や、施設などに入所している場合は、病院や施設に訪問する場合もあります。具体的な訪問調査の内容は以下の通りです。
| 調査 | 内容 |
|---|---|
| 概況調査 |
|
| 基本調査 | 身体や生活機能などの74項目
|
| 特記事項 | 上記以外で特別に配慮すべき点 |
参照:厚生労働省「認定調査員テキスト2009改訂版 P13-14」
このように、申請者の身体や生活機能、置かれている環境などを約1時間程度かけて聞き取り調査します。
なお、聞き取りの対象は、申請者本人だけではなく、介護を担っている方へも行います。本人が返答できない場合は代弁しなければならないため、介護を主に担う方もスケジュールを調整して、同席するようにしましょう。
関連記事
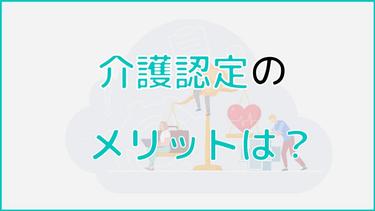 介護認定の5つのメリットを解説!受ける流れから注意点まで紹介カテゴリ:要介護認定更新日:2025-02-25
介護認定の5つのメリットを解説!受ける流れから注意点まで紹介カテゴリ:要介護認定更新日:2025-02-25関連記事
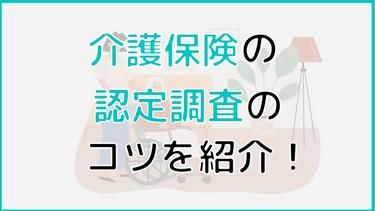 介護保険の認定調査のコツ6選!納得できない時の対処法も解説カテゴリ:介護保険更新日:2025-09-11
介護保険の認定調査のコツ6選!納得できない時の対処法も解説カテゴリ:介護保険更新日:2025-09-11
主治医の意見書
認定調査員が行った訪問調査と同様に、認定の結果に影響を及ぼすのが主治医の意見書です。主治医は医学的な観点から、介護の必要性について記載します。
また、主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
意見書に記載される項目は以下の通りです。
- 傷病に関する意見(診断名や症状の安定性、生活機能低下の直接の原因となっている傷病、治療内容など)
- 特別な医療(過去14日間以内に受けた医療、処置、失禁の対応など)
- 心身の状態に関する意見(日常生活の自立度、認知症の中核症状・周辺症状、身体の状態など)
- 生活機能とサービスに関する意見(移動、栄養・食生活、サービス利用による生活機能の維持や改善の見通しなど
- 特記すべき事項
コンピューターによる一次判定
認定調査員による訪問調査と主治医の意見書の一部の項目をコンピューターで分析します。
要介護認定には「介護の手間に係る審査判定」と「状態の維持・可能性に係る審査判定」の2つにわけられ、一次判定ではそのうち「介護の手間に係る審査判定」を行います。つまり、介護にどれくらいの時間がかかるかを判定します。
介護認定審査会による二次判定
コンピュータによる一次判定の結果と主治医の意見書をもとに、介護認定審査会で最終的な介護認定度を決定します。
介護認定審査会は保険や医療、福祉の専門家で構成されており、要介護区分の妥当性について検討します。具体的には、以下の点について審査判定を行います。
- 要介護状態、要支援状態に該当するのか
- 該当する場合、要介護区分はどれか
- 第2号被保険者の場合、要介護状態が特定疾病によるものか
審査会による二次判定での結果が市区町村から申請者に通知されます。要介護区分と判定された場合、介護保険サービスを利用できます。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
要介護認定の審査結果に不服があるとき
判定基準が不明瞭であったり、申請者の状態が適切に反映されていなかったりなどの理由で思いがけない判定結果を受ける事例もあります。認定結果に不服がある場合はまずは市区町村の介護保険課に問い合わせ説明を受けましょう。それでも納得できない場合は以下の方法が可能です。
- 介護保険審査会に審査請求(不服申し立て)を行う
- 区分変更
不服申し立てが認められると、介護保険審査会が介護認定が適切なものであったか審査します。審査請求は要介護認定結果通知を受け取ってから3ヵ月以内に行う必要がありますので、注意しなければなりません。
区分変更は、本来は認定後に状態が変わった場合に再調査して行いますが、認定結果に不服がある際にも申請可能です。担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに相談するといいでしょう。
介護保険の区分変更を行うタイミングは?入院中の場合も併せて解説!
実際に介護保険サービスを受ける方法
実際に介護保険サービスを受ける方法は、対象者が居住している地域や要介護認定による区分によって異なります。
ここでは以下の3つを解説します。
- 居宅サービスを受ける
- 施設サービスを受ける
- 介護予防サービスを受ける
居宅サービスを受ける
居宅でのサービスを希望する場合は、まずは居宅介護支援事業者を選びます。担当のケアマネジャーが決定したあとに、ケアプランが作成され、そのケアプランをもとにサービスが利用できます。サービスの内容は以下の通りです。
- 訪問サービス(訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーションなど)
- 通所サービス(通所介護、通所リハビリテーションなど)
- 短期入所サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護など)
- そのほかのサービス(福祉用具貸与、特定福祉用具販売など)

施設サービスを受ける
特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院などの介護施設に入所して受けられるサービスの内容は以下の通りです。
- 介護老人福祉施設入居者生活介護(食事や排泄の介護、リハビリテーション、レクリエーションなど)
- 介護老人保健施設入居者生活介護(医療処置、食事や排泄の介護など)
- 介護医療型施設入居者生活介護(医学管理下におけるリハビリ、食事や排泄の介護など)
- 介護医療院(医療的なケアや介護など)
施設で受けられるサービスは、施設にかかわるケアマネジャーがケアプランを作成し、そのケアプランをもとに必要なサービスが利用できます。
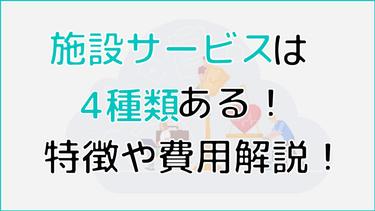
施設に入るならどこが良いかわからないという方はケアスル介護で相談するのもおすすめです。入居相談員にその場で条件に合った施設を提案してもらえるので、初めてでも安心して相談することが出来ます。
後悔しない老人ホーム探しがしたいという方はぜひ利用してみてください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
介護予防サービスを受ける
要支援の方が、要介護状態に悪化しないために受けられるサービスです。サービスを受けるためには、まず地域包括支援センターに連絡し、介護予防プランの作成を依頼します。受けられるサービスは、以下の通りです。
- 訪問サービス(介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーションなど)
- 通所サービス(介護予防通所リハビリテーション、介護予防デイサービスなど)
- 泊まりのサービス(介護保予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護など)
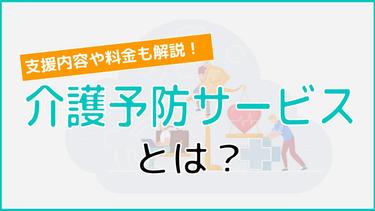
要介護認定を理解し、介護サービスを利用しよう
要介護認定の理解は、介護保険サービスを利用するための始めの一歩といえるでしょう。介護の必要性を測る客観的な制度であり、要介護認定の区分により受けられる給付の金額やサービスの内容が異なります。
要介護認定の申請から介護保険サービスの利用までは様々な手続きが必要になります。しかし、要介護認定を受けられると介護者の負担を軽減できるため、制度を正しく理解し早期に申請するようにしましょう。





