介護保険の施設サービスを利用するうえで、負担する費用は想像以上に大きくなります。食費や居住費の負担をできるだけ最小に抑えるためには「介護保険負担限度額認定証」制度を理解し活用するのが重要です。
この記事では介護サービスを受けるうえで利用を検討すべき「介護保険負担限度額認定証」について解説します。
利用要件や申請方法、対象施設についても紹介するので、今後の参考資料の一つとしてお役立てください。
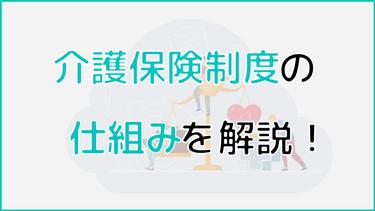
介護保険負担限度額認定証の減免要件
介護保険4施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)の入所およびショートステイを利用する場合、居住費・食費の費用は自己負担になります。介護をサポートするご家族にとっては、自己負担額に対して将来的な不安を抱える場合もあるでしょう。
そんな時に利用を検討したいのが「介護保険負担限度額認定証」です。この制度は、所得の低い方が介護保険4施設及びショートステイを利用する際の居住費及び食費を軽減できる制度を指します。
ただし、利用するには3つの要件を満たさなければ補足給付(軽減措置)の対象にはなりません。ここでは具体的な要件について詳しく説明します。
対象者の要件
介護保険負担限度額認定証は、所得が低い方が負担を抑えるために利用する制度です。利用するには以下の条件(要件)のとおり「住民税非課税世帯が対象」となります。
- 生活保護受給者
- 世帯全員(本人含む)が住民税非課税
- 本人と配偶者が住民税非課税
申請する際は、介護を受ける方が住民税非課税世帯に該当するかを確認する必要があるので注意してください。
所得の要件
所得の要件は「本人を含む世帯全員が住民税非課税」でなければなりません。本人の配偶者が別世帯になっている世帯もありますが、この場合も同様に、配偶者も住民非課税世帯であれば該当します。
なお、特定入所者介護サービス費の利用には、負担限度額認定を受ける必要がありますので、お住まいの自治体に申請をしてください。
| 設定区分 | 対象者 | 資産額 (カッコ内は夫婦の場合) |
|---|---|---|
| 第1段階 | 老齢福祉年金受給権者・生活保護受給者 | 1000万円(2000万円) |
| 第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金年収入額(※)+その他の合計所得金額が80万円以下 | 650万円(1,650万円) |
| 第3段階① | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金年収入額(※)+その他の合計所得金額が80万円超~120万円以下 | 550万円(1550万円) |
| 第3段階② | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金年収入額(※)+その他の合計所得金額が120万円超 | 500万円(1,500万円) |
| 第4段階 | 市区町村民税課税世帯 | 要件はないが、軽減措置もなし |
※課税年金だけではなく、障害年金や遺族年金などの非課税年金も含む
資産の要件
資産の要件は、対象者の所得と預貯金などの資産によって、段階的に負担限度額が決められています。預貯金とは「資産性があり・換金性が高く・価格評価が容易なもの」です。銀行預金だけではなく、株式や投資信託などの有価証券、国債や金なども資産に含めて考えます。
いっぽう、借金や住宅ローンなどの負債は、資産額から差し引かれます。対象者の負担段階ごとの預貯金は以下の通りです。
| 設定区分 | 単身 | 夫婦 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 1000万円以下 | 2000万円以下 |
| 第2段階 | 650万円以下 | 1650万円以下 |
| 第3段階① | 550万円以下 | 1550万円以下 |
| 第3段階② | 500万円以下 | 1500万円以下 |
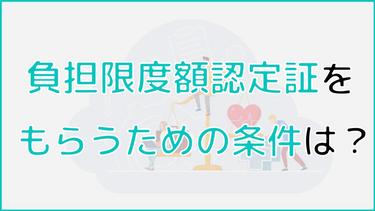
費用の安い老人ホームを探しているという方はケアスル介護がおすすめです。
全国で約5万件以上の施設情報を掲載しているので、幅広い選択肢からピッタリの施設を探すことが出来ます。
予算内で施設を探したいという方はぜひ利用してみてください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
介護保険負担限度額認定証の取得方法
ここでは「介護保険負担限度額認定証」に必要な申請書類や取得方法について説明します。
必要な申請書類
「介護負担限度額認定証」の必要書類は「介護負担限度額認定申請書」のほかに「同意書」「預貯金等の証明のための添付書類」「身元確認書類」が必要です。
- 介護負担限度額認定申請書介護負担限度額認定申請書とは?
申請書には被保険者氏名および配偶者に関する事項、それぞれの収入や預貯金に関する事項を記入します。また、入所した介護保険4施設及びショートステイの所在地、名称、入所年月日、課税(非課税)状況なども記入が必要です。入手方法:お住まいの自治体HPから申請書のPDFデータをダウンロードできます。ダウンロードが困難な場合は、書類を自治体から郵送してもらうことも可能です。- 同意書とは?
申請内容の課税状況や保有財産の残高について、自治体から報告を求められることや金融機関などが自治体に報告することに同意するものです。入手方法:お住まいの自治体のサイトから申請書のPDFデータをダウンロードできます。ダウンロードが困難な場合は、書類を自治体から郵送してもらうことも可能です。
※「介護負担限度額認定申請書」と「同意書」は一緒になっている場合がほとんどです。
- 同意書とは?
「預貯金等の証明のための添付書類」
| 預貯金等に含まれるもの (資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものが対象) |
確認方法(添付書類) (価格評価を確認できる書類の入手が容易なものは添付を求めます) |
|---|---|
| 預貯金(普通・定期) |
※インターネットバンクであれば口座残高ページの写し |
| 有価証券(株式・国債・地方債・社債など) | 証券会社や銀行の口座残高の写し ※ウェブサイトの写しも可 |
| 投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し ※ウェブサイトの写しも可 |
| 金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 | 購入先の口座残高の写し ※ウェブサイトの写しも可 |
| 負債(借入金・住宅ローンなど) | 借用証明書や残高証明書等の写し ※預貯金額等から差し引きます |
| 現金(いわゆるタンス預金) | 自己申告 |
なお、身元確認書類も「介護保険負担限度額認定証」を申請する際、マイナンバー(個人番号)の記入と、申請する方の身元確認書類が必要になります。身元確認書類は運転免許証などの顔写真があるものは1点、顔写真のない健康保険証などは2点必要です。
身元を確認できる書類が分からない場合は、事前にお住まいの自治体に問い合わせるとよいでしょう。
申請手順
提出先は各市区町村の担当窓口で、提出方法は郵送または持ち込みに対応しています。提出書類等に不備がなければ、申請後一週間程度で結果が通知されます。今一度、各書類に不備がないか確認するとよいでしょう。
第1~第3段階に該当した場合には、各自治体の担当部署から「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。また、第4段階であれば、補足給付に該当しない旨が通知されるので届いた書類は細かく確認してください。

申請時に注意すべきポイント
注意すべきポイントは以下の2つです。
| 申請時に注意すべきポイント | |
|---|---|
| 不正申告 | 偽の申告により不正に特定入所者介護サービス費等の支給を受けた場合には、介護保険法第22条第1項の規定に基づき、支給された額及び最大2倍の加算金を返還することになる可能性があるので、くれぐれも虚偽の申告、不正受給はやめましょう。 |
| ショートステイの場合 | 介護保険施設の所在地及び名称欄は、ショートステイの場合は記入不要です。申請者は、被保険者本人の名前を記入し提出しましょう。 |
これらの留意点を視野に入れながら申請するよう努めてください。
介護保険負担限度額認定証の対象施設
介護保険負担限度額認定証の対象施設は以下の通りです。
- 特養(特別養護老人ホーム)
- 老健(介護老人保健施設)
- 介護療養型医療施設
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 地域密着型介護老人福祉施設
それぞれの施設が持つ特徴について解説していきます。
特養(特別養護老人ホーム)
特養は、在宅での生活が困難になった要介護の高齢者が入居できる公的な「介護保険施設」の一つで、「特養」と呼ばれるのが一般的な施設です。
【対象】
- 65歳以上で要介護3以上の高齢者
- 40歳~64歳で特定疾病が認められた要介護3以上の方
- 特例により入居が認められた要介護1~2の方
【メリット】
- 公的な施設のため、老人ホームの中では比較的安価に入居できる
- 原則として終身にわたり入所できる
- 24時間介護が受けられる
【デメリット】
- 地域によっては入居までに待機期間がかかる場合もある
- 医療体制に限界がある
- 入居できるのが原則要介護3以上
- 資産額が多かったり、介護保険の自己負担割合が多いと、民間施設と変わらないくらいの負担になる
特養の特徴は、老人ホームの中では比較的安価に入居でき、原則として終身にわたりサービスを受けられるのが大きなポイントとなっています。
その反面、入居までの待機期間が長く発生する場合や、医療体制には限界があるので検討する際には注意してください。
老健(介護老人保健施設)
医師による医学的管理の下、看護・介護のほか、作業療法士や理学療法士等によるリハビリテーション、栄養管理・食事・入浴などの日常サービスまで併せて提供する施設です。「ろうけん」との呼称が一般的です。
【対象】
- 原則65歳以上で「要介護1」以上の介護認定を受けている方
- 40歳から64歳の特定疾病による要介護認定を受けている方
- 伝染病などの疾患がなく、病気での長期入院などを必要としない
※施設によって条件が異なります
【メリット】
- 機能訓練が充実している
- 病院から直接家に帰らずに、見守られながら暮らせる
- 手厚い医療ケアが受けられるケースもある
【デメリット】
- 内服薬が制限される
- 生活支援サービスやレクリエーションがやや少ない
- 多床室はプライバシーの確保が難しい
- 入居期間が原則3ヵ月
「ろうけん」は、医師による医学的管理の下、医療ケアや機能訓練が充実しており、家庭復帰に向けた手厚いサービスを受けられるのが、大きなメリットです。デメリットとしては、入所期間が原則3ヶ月となっており、現実には契約を更新したまま入所している方もいますが、長期間の入所ができない点です。一定期間の利用であっても質の良いサービスを受けたい方は検討されるとよいでしょう。
介護療養型医療施設
介護療養型医療施設とは、比較的重度の要介護者であり、医療的な措置が必要な方に対し、充実した医療処置とリハビリを提供する施設です。「介護医療院」とも呼びます。
【対象】
- 医学的な措置が必要な要介護1以上の高齢者(65歳以上)
- 「感染症など、他者への影響がある疾患を持っていない」など
- 65歳以下でも介護認定がある場合には入居の相談可※詳細は施設に問い合わせる必要があります
【メリット】
- 医療ケアが充実している(「インスリン注射」や「痰の吸引」、「経管栄養」など)
- 機能訓練が充実している
- 入居一時金が必要ない(保証金が必要なケースもある)
【デメリット】
- 施設の数が少ない
- 人工透析ができない施設もあるなど、すべての医療措置に対応しているわけではない「
- 多床室が多い
- レクリエーションなどは少ない
介護療養病床は、入居一時金がない点では入所しやすいと言えますが、数が少ないため入所難易度が高くなっているのが実情です。入所入居を検討している方は入所入居期間を正しく調整する必要がありそうです。
短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所生活介護(ショートステイ)とは、利用者が可能な限り自己の生活している居宅において、能力に応じた日常生活を営めるよう、短期間入所によって入浴、排泄、食事などの介護や日常生活上の世話及び機能訓練を行うサービスです。
【対象】
- 要介護1以上の認定を受けた方
【メリット】
- 自宅介護をしている家族の負担を軽減できる
- 老人短期入所施設、特養等で短期間入所をしてサービスを受けることが可能(連続使用日数は30日)
【デメリット】
- 施設の予約が取りづらい
- 期間が短いため、友人づくりがしづらく要介護者の心身状態を悪化させるリスクがある
短期入所生活介護(ショートステイ)は、自宅介護をしている家族の負担軽減や、まだ入所経験のない要介護者や家族が「短期間であっても施設に預ける」選択肢を持てるのがポイントです。短期間のため利用者が多く、予約が取りづらい状況となっているので、施設に空き状況を確認の上、検討を初めてはいかがでしょうか。
短期入所療養介護(ショートステイ)
短期入所療養介護(ショートステイ)とは、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る目的で提供されるサービスを指します。何らかの事情により一定期間自宅での介護ができない時に利用できます。
老健、療養病床のある病院や診療所等に短期間入院し、看護、医学的管理の下で、介護、機能訓練、医療処置、日常生活上の世話を提供するサービスです。
【対象】
- 要介護1以上の認定を受けている方
【メリット】
- 短期間入所をして介護サービスが受けられる(連続利用日数は30日)
- リハビリテーション専門職が配置されている(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士など)
- 要介護者の孤独感を解消できる
- 要介護者及び介護者の緊急時に対応してもらえる
- 認知症患者への対応も可能
- ターミナルケア(終末医療)を実施してもらえる
【デメリット】
- 要介護者が慣れない環境に戸惑ってしまい、心身状態を悪化させるリスクがある
- 施設の予約が取りづらい
- 利用しすぎて介護保険の利用限度額に達してしまい、ほかの介護サービスの利用に影響が出る
- 滞在費・食事などは介護保険適用外となっている
短期入所療養介護(ショートステイ)は、「医療型ショートステイ」として、老健や病院、診療所などに入所ができます。短期入所生活介護(ショートステイ)と大きく変わるのは医療サービスの手厚さにあります。短期間でも医療サービスを手厚くして欲しい方は検討してみてはいかがでしょうか。
地域密着型介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設とは、入所定員が29人以下の特養であって、「地域密着型施設サービス計画」に基づいてサービスを提供する施設をいいます。
【対象】
- 事業所のある地域に住所がある
- 65歳以上で要介護認定を受けている方
- 40歳~64歳で国の定める特定疾病によって要介護認定を受けている方
【メリット】
- さまざまな利用時間に対応してくれる
- アットホームな雰囲気
- 少数制のため個別性を持った機能訓練やレクリエーションが可能
【デメリット】
- 地域密着型介護老人福祉施設がある市町村でないと利用できない
- 一部の居宅サービス(訪問介護、デイサービス、ショートステイ)が受けられなくなる
- 担当のケアマネージャーが変わる
地域密着型介護老人福祉施設は、住み慣れた地域で暮らしたいと考えている方たちにとってはありがたいサービスになっています。
居住地の施設にしか入所できない制限がある反面、ご家族は面会に行きやすく、入所者の寂しさや負担感は軽減しやすい環境です。
規模が小さいため、居住地に施設がなかったり、担当ケアマネージャーが変わってしまったりするデメリットもありますので、まずは、ご自身が居住する市区町村に施設があるのかを調べるところから始めましょう。
地域密着型介護福祉施設への入所を検討しているという方はケアスル介護がおすすめです。
入居相談員にその場で条件に合った施設を提案してもらえるので、初めてでも安心して相談することが出来ます。
初めての施設探しで後悔しない老人ホーム探しがしたいという方はぜひ利用してみてください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
介護保険負担限度額認定証の更新制度
原則、介護保険負担限度額認定証の期間は8月1日から翌年7月31日までの1年間です。毎年更新が必要ですが、一度目に認定されたあとは、翌年以降は自動的に更新書類が送付されます。
ただし、介護保険負担限度額認定証の有効期限については、地域の実情に応じて市町村の判断により設定可能であるため、お住まいの自治体の担当窓口に確認すると安心です。スケジュールに余裕を持って更新しましょう。
介護保険負担限度額認定証の利用範囲について学び、かしこい利用を検討しよう
ここまで、「介護保険負担限度額認定証」について解説してきました。大事なポイントは以下の3つです。
- 「介護保険負担限度額認定証」は非課税世帯が対象
- 「介護保険負担限度額認定証」の申請には各自治体窓口にて郵送で申請可能
- 介護保険4施設(介護老人福祉施設、老健、介護療養型医療施設、介護医療院)の入所およびショートステイを利用したときの居住費・食費の費用を減額可能
上記3つのポイントを把握しておくと、介護保険負担限度額認定証の利用検討がしやすくなります。まずは細かな要件を確認し、自分やそのご家族は対象範囲かをチェックしましょう。
介護保険負担限度額認定証に関するよくある質問
Q:介護保険負担限度額認定を持っている方が転居、子どもとの同居 等により課税世帯に属することになった場合は申し出る必要がありますか。
A:介護保険負担限度額認定の所得要件は、世帯が課税であるかで判定します。
世帯状況に変更が生じた場合は、お住まいの自治体の担当窓口に確認してください。
Q:介護保険負担限度額認定証を持っていたが、提示を忘れてしまった場合、その期間の返金は可能ですか。
A:利用した事業所に、後日、介護保険負担限度額認定証を提示すると、自己負担額が調整されます。
もし事業所で調整ができない場合には、お住まいの自治体の担当窓口に申請すると、介護保険負担限度額までの差額について返金(償還払い)が受けられます。
ただし、「国の定める基準費用額」を超える金額(各サービス事業者が定める食費と部屋代など)を支払った場合は、負担限度額までの差額について返金を受けることはできません。詳しくは、お住まいの自治体にお問い合わせください。
そのほか介護保険の仕組みや、実際の利用負担額について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。





