「特別養護老人ホーム(特養)の費用は安いと聞いていたけど、それでも金銭的に余裕がない……」
「サービスを受けるために必要な料金を、さらに安くする方法はないの?」
特別養護老人ホーム(特養)は、低価格で手厚い介護サービスを受けられる施設として知られていますが、必要な費用に不安を感じる世帯も少なくありません。
特養への入所費用にお悩みの場合には、多床室がある従来型特養を選んだり公的な減免制度の活用によって、負担を抑えることができます。
今回は特別養護老人ホーム(特養)の費用を安くする方法や、減免制度の適用条件、申請方法まで詳しく解説していきます。

特養(特別養護老人ホーム)の費用を安くする方法はある?
結論から言うと、特別養護老人ホーム(特養)の費用を安くする方法はあります。
多床室がある従来型特養を選んだり公的な減免制度を活用することにより、金銭面でお悩みを抱える方々も安心して介護を受けていただけます。
特別養護老人ホーム(特養)の費用を抑える方法としては、以下の内容が挙げられます。
- 多床室を利用する
- 減免制度を利用する
- 生活保護を受ける
次項からは、それぞれについて詳しく解説していきます。
特別養護老人ホーム(特養の月額費用)の月額費用の内訳は、以下の通りです。
- 介護サービス費(介護保険適用)
- 介護サービス加算(介護保険適用)
- 居住費
- 食費
- 日常生活費
このうち、介護サービス加算と日常生活費は個別で費用が変わるため、以降では、「介護サービス費」「居住費」「食費」の軽減方法を見ていきます。
特養への入居を検討しているという方は、ケアスル介護がおすすめです。ケアスル介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができるためご希望に沿った施設探しが可能です。
「プロに相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
特養(特別養護老人ホーム)の費用を安くする方法①多床室を利用する
特別養護老人ホーム(特養)の居室は、主に下記の4タイプに分かれています。
- 従来型多床室
- 従来型個室
- ユニット型個室
- ユニット型個室的多床室
介護サービス費は介護保険が適用され、介護度で決まっています。また、収入によって自己負担割合が1〜3割となります。
また、従来型かユニット型かで料金が違い、ここでは個室と多床室での違いはありません。
●「介護サービス費」介護度・居室タイプ別自己負担額(30日・1割負担)
| 従来型 個室/多床室 | ユニット型 個室/個室的多床室 | |
| 要介護1 | 17,190円 | 19,560円 |
| 要介護2 | 19,230円 | 21,600円 |
| 要介護3 | 21,360円 | 23,790円 |
| 要介護4 | 23,400円 | 25,860円 |
| 要介護5 | 25,410円 | 27,870円 |
※特別養護老人ホームは要介護3以上の人が入所できる施設ですが、特例として要介護1.2の人が認められる場合があるため掲載しています。
居住費は4つの居室タイプで料金が変わり、食費は全国一律料金(1445円/1日)となります。こちらは介護度による違いはありません。まとめると下記の表になります。
●「居住費」「食費」居室タイプ別自己負担額(30日)
| 居住費 | 食費 | |
| 従来型多床室 | 25,650円 | 43,350円 |
| 従来型個室 | 35,130円 | |
| ユニット型個室的多床室 | 50,040円 | |
| ユニット型個室 | 60,180円 |
「介護サービス費」「居住費」「食費」すべてをまとめると下記の表になり、結論として従来型多床室が一番安いことがわかります。
●「介護サービス費」「居住費」「食費」合計費用 居室タイプ・介護度別(30日・1割負担)
| 従来型多床室 | 従来型個室 | ユニット型個室的多床室 | ユニット型個室 | |
| 要介護1 | 86,190円 | 95,670円 | 112,950円 | 123,090円 |
| 要介護2 | 88,230円 | 97,710円 | 114,990円 | 125,130円 |
| 要介護3 | 90,360円 | 99,840円 | 117,180円 | 127,320円 |
| 要介護4 | 92,400円 | 101,880円 | 119,250円 | 129,390円 |
| 要介護5 | 94,410円 | 103,890円 | 121,260円 | 131,400円 |
これにより、一番安い従来型多床室と一番高いユニット型個室では4万円近い差があることがわかります。
ユニット型は、10部屋ほどの居室がリビングを囲むように配置され、少人数のユニットケアを実施しています。一人ひとりに寄り添った個別ケアを実現する新しいタイプで、現在新築で建てられている特養はユニット型となります。
ユニット型個室は、建物が新しく、プライバシーが守られ、個別ケアを実施するためスタッフの数も多くなります。
一方、従来型多床室とは、1つの部屋をカーテンなどで仕切り通常4人で利用する居室で、病院などに近いイメージです。古くからあるタイプのもので建物も古いところが多いです。
また、従来型は、建物の造りがユニット型と違い細かい空間に分かれていないため、声かけや夜間の見守りなどがしやすく、部屋の移動が少なくてすむなど、介護士はケアの効率化を図ることができます。
建物が古くプライバシーの確保が難しいという入居者が不都合に感じる理由だけでなく、介護サービスの提供に必要な人件費を抑えることができることから、従来型多床室は低価格な費用での利用が可能となっています。
実際にはどれくらい安くなる?
特別養護老人ホーム(特養)で必要となる月額費用は、居室タイプと介護度で変わることがわかりました。さらに、次に説明する特定入所者介護サービス費の減免制度により、市町村民税非課税世帯は費用が安くなります。
具体的には下記の表になります。市町村印税非課税世帯の段階分けの具体的な要件については、次の章の「特定入所者介護サービス費」で説明していますので、参考になさってください。
●従来型多床室を利用する場合 約2.6万〜9.4万円
| 市町村民税非課税世帯 | 課税世帯 | ||||
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階(1) | 第3段階(2) | 第4段階 | |
| 要介護1 | 26,190 | 39,990 | 47,790 | 69,090 | 86,190 |
| 要介護2 | 28,230 | 42,030 | 49,830 | 71,130 | 88,230 |
| 要介護3 | 30,360 | 44,160 | 51,960 | 73,260 | 90,360 |
| 要介護4 | 32,400 | 46,200 | 54,000 | 75,300 | 92,400 |
| 要介護5 | 34,410 | 48,210 | 56,010 | 77,310 | 94,410 |
●ユニット型個室を利用する場合 約5.7万~13.1万円
| 市町村民税非課税世帯 | 課税世帯 | ||||
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階(1) | 第3段階(2) | 第4段階 | |
| 要介護1 | 53,160 | 55,860 | 78,360 | 99,660 | 123,090 |
| 要介護2 | 55,200 | 57,900 | 80,400 | 101,700 | 125,130 |
| 要介護3 | 57,390 | 60,090 | 82,590 | 103,890 | 127,320 |
| 要介護4 | 59,460 | 62,160 | 84,660 | 105,960 | 129,390 |
| 要介護5 | 61,470 | 64,170 | 86,670 | 107,970 | 131,400 |
以上より、特別養護老人ホーム(特養)の費用を安くしたい場合は、従来型多床室を利用することがおすすめです。
またそのほかの居室タイプを利用する場合も、本人の介護度や、世帯の所得状況など把握し、必要となる費用をしっかりと確認しておきましょう。
特別養護老人ホーム(特養)の居室のそれぞれのタイプについて、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
多床室の特養を知りたいという方は、ケアスル介護がおすすめです。ケアスル介護は、約5万件の施設情報を掲載しているため幅広い選択肢から検討することが可能です。
「施設選びで失敗したくない」という方は、ご気軽に活用ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
特養(特別養護老人ホーム)の費用を安くする方法②減免制度を利用する
収入や資産に応じて介護費用の負担を抑える公的な減免制度があります。理解を深め、無駄なく活用しましょう。
利用できる減免制度は以下の通りです。
| 減免制度名 | 減免される費用項目 | 概要 | 申請方法 |
| 特定入所者介護サービス費 | 居住費・食費 | 4段階の所得ごとに、居住費と食費を減免される制度 | お住いの市区町村の役所にて申込 |
| 高額介護サービス費 | 介護サービス費用の自己負担額 | 1ヶ月の利用者負担額が所得ごとの区分限度額を上回った場合に払い戻される制度 | お住いの市区町村の役所にて申込 |
| 高額医療・高額介護合算療養費制度 | 医療費と介護サービス費用の自己負担額 | 医療費と介護サービスの自己負担額の1年間の支払額が基準を超えた場合に払い戻される制度 | お住いの市区町村の役所にて申込 |
| 社会福祉法人などの利用者負担軽減制度 | 介護サービスの自己負担額、居住費および食費 | 市区町村税非課税世帯で特定の条件を満たした場合は、利用者負担の1/4が軽減される制度 | お住いの市区町村の役所にて申込 |
| 医療費控除 | 介護サービスの自己負担額・居住費・食費 | 所定の費用項目について確定申告を行うことで所得税から医療費控除を受けることができる制度 | 確定申告にて申請 |
それぞれの制度の概要や適用条件、減免額、申請方法などについては、別途こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
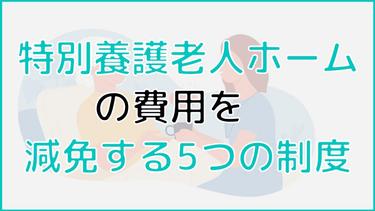
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
特養(特別養護老人ホーム)の費用を安くする方法③生活保護を受ける
あらゆる制度を検討したうえで、それでも介護にかかる費用が払えない場合、生活保護を受けるという手段があります。
特別養護老人ホーム(特養)は、生活保護を受けている方も入所が可能となっており、必要となる費用は支給される保護費のなかでまかなうことができます。
しかし、生活保護を受けたら、すべてのサービスが制限なく利用できるというわけではありません。
あくまで健康で文化的な最低限度の生活を保障するため、利用できるのは指定の介護支援事業者が作成する計画書に基づく介護サービスとなるので、理解しておきましょう。
生活保護の受給対象となる方は、以下の条件を満たした方です。
- 世帯収入が厚生労働省の定める最低生活費に満たない方
- 高齢や障害などのやむを得ない事情で、働いて収入を得ることができない方
- 生活の援助をしてくれる三親等以内の親族がいない方
- 持ち家や車など、資産を所有していない方
- 公的融資制度や公的扶助の対象外になること
次項ではそれぞれについて詳しく解説していきます。
世帯収入が厚生労働省の定める最低生活費に満たない方
世帯収入が厚労省の定めた基準額を下回っている場合、生活保護を受給対象となります。
基準額については、居住している地域と世帯人数によって金額は異なるため、お住まいの自治体に確認してみましょう。
ちなみに東京都の基準額は単身で月13万円と定められており、年収に換算して156万円以下の収入である場合は生活保護の受給対象となっています。
また年金を受給中の場合、この年金は収入と見なされるため注意が必要です。
高齢や障害などのやむを得ない事情で、働いて収入を得ることができない方
生活保護には年齢制限は設けられておらず、0歳から100歳まで誰でも受給可能です。
高齢や障害によって働けない場合は、生活保護の受給対象となります。
そのほか怪我や病気、精神疾患などで思うように働けなくなってしまった場合も、生活保護の対象者となり、給付を受けることができます。
生活の援助をしてくれる親族がいない方
三親等以内の親族から生活の援助を受けられない場合、生活保護の受給が可能です。
生活保護を受けようとする際には、配偶者や子供、兄弟など扶養義務のある三親等の親族から、できる限り援助を受けることが求められます。
しかし、親族から扶養の意思が得られない場合や、金銭面の問題で親族に扶養能力がない場合など、どうしても援助を受けることが難しい場合は、生活保護を受けることができます。
資産を所有していない方
生活費に換金できる資産を持っていない方は、生活保護の受給対象となります。
換金できる資産がある場合は、すべて売却して生活費に充てることが求められます。
資産として見られるのは、10万円以上の現金や預貯金だけでなく、土地不動産、生命・医療保険、自動車などが含まれます。
「生活保護受給者は特養に入居できるのか知りたい」「生活保護受給者が特養に入居する際の流れが知りたい」という方は、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
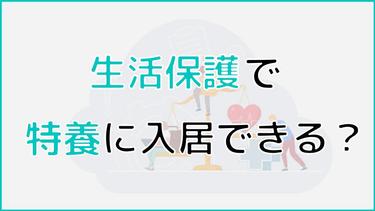
まとめ
特別養護老人ホーム(特養)の費用が払えない場合は、使用するサービスの見直しや公的な減免制度を活用することにより、負担する費用を安くすることができます。
必要となるサービスや、世帯の状況に応じて適切な手段をとることで、金銭面において大きな助けとなるでしょう。
また、「介護サービスやお金の制度の話は、難しくてよく分からない」という方は、地域包括センターに相談してみることがおすすめです。
介護についてはもちろん、医療、福祉などの内容について相談することができ、高齢者の家族の方々にとっても安心して計画を立てることができます。
特別養護老人ホーム(特養)の費用を安くしたい場合には、実際の申請で必要になる手続きや、お住まいの地域で担当窓口はどこになるのかを確認しながら、ひとつひとつ手続きを進めていくことが大切です。
そのほか特別養護老人ホーム(特養)についてや、費用が払えないときの対処法について知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
特別養護老人ホーム(特養)の費用を安くしたい場合には、実際の申請で必要になる手続きや、お住まいの地域で担当窓口はどこになるのかを確認しながら、ひとつひとつ手続きを進めていくことが大切です。
特別養護老人ホーム(特養)の費用を抑える方法としては、「多床室を利用する」「減免制度を利用する」「生活保護を受ける」などが挙げられます。詳しくはこちらをご覧ください。
特別養護老人ホーム(特養)は、生活保護を受けている方も入所が可能となっており、必要となる費用は支給される保護費のなかでまかなうことができます。詳しくはこちらをご覧ください。





