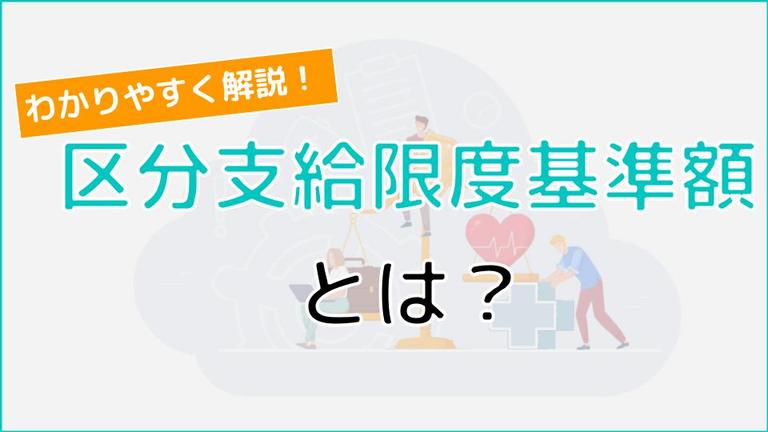介護保険サービスを利用したときの費用は、利用者の所得によって1~3割の自己負担だけで済ませることができます。しかし、介護保険にももちろん財源があるので自己負担が安いからと言って際限なく介護サービスを利用することはできません。
そこで、要介護・要支援度ごとに月の上限額が単位数として区分ごとに定めているのが「区分支給限度基準額」なのです。似ている言葉として「支給限度基準額」もありますが、厳密にはこれらは違います。
本記事では、介護保険を利用したことがない人に取っては難しい言葉である「区分支給限度基準額」についてわかりやすく解説します。単位と円の違いや、「支給限度基準額」との違いも解説します。
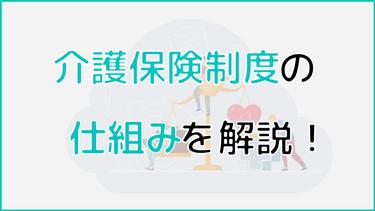
区分支給限度基準額とは
まず初めに区分支給限度基準額の意味についてわかりやすく解説していきます。単位と円の違いなどの細かい用語の違いまで解説するので、初めて聞いたという方は注意深く読んでいきましょう。
区分支給限度基準額とは区分ごとの限度額
区分支給限度基準額とは、要支援・要介護度ごとに設定された介護保険サービスの月の上限を単位数として設定しているものです。
もう少しわかりやすく説明すると、そもそも介護保険を利用する際は所得によって自己負担は1~3割の少額で利用することができます。そのため、介護を必要としている方は積極的に介護保険が適用されるサービスを利用しますが、介護保険にも財源があります。
財源とは、全国民が40歳以上になると強制加入する介護保険の保険料と税金[高橋1] のことです。財源が無くなれば介護保険制度の仕組みが崩れてしまうので、一人がつかいすぎないように要介護認定を受けた一人一人に月の利用上限を設定しているのです。したがって、上限を超えた分は全額自己負担となるのです。
ただこれではわかりづらいので、基本的には円換算して原則として1単位=10円で換算します。よって100単位であれば1,000円です。
そもそもなぜ「円」で上限を設定しないかというと、介護サービスによってかかる人件費等が異なることや地域間の人件費の差を考慮しているからです。つまり、人件費等が高い東京の一等地や訪問介護・訪問看護などのサービスの場合は1単位が最大で11.40円になったりします。
そのため、サービス提供者側からすると同じサービスを受けるにしても東京の一等地と地方部では単位数は同じでも、支払われる報酬額(円)は異なるのです。それに伴って、区分支給限度基準額の単位数が同じでも東京の一等地で介護サービスを受ける時と、郊外で受ける時では上限単位は同じでも上限金額が異なることがあるのです。
区分支給限度基準額と自己負担額の一覧
要支援・要介護度ごとに設定されている区分支給限度額と自己負担1~3割だった場合の自己負担額の一覧は以下の通りです。
| 区分 | 区分支給限度基準額(単位) | 自己負担割合1割の場合(円) | 自己負担割合2割の場合(円) | 自己負担割合3割の場合(円) |
|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 5032 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |
| 要支援2 | 10531 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |
| 要介護1 | 16765 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
| 要介護2 | 19705 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
| 要介護3 | 27048 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
| 要介護4 | 30938 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
| 要介護5 | 36217 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |
※1単位当たり10円として計算した場合
区分支給限度額の上限は重度の被保険者が手厚いサービスを受けることができるように、介護度が上がるごとに自己負担額の上限額も上がっています。
例えば、自己負担額1割の被保険者が要介護4だった場合、30,938円までは自己負担1割で介護保険サービスを利用することができます。
区分支給限度額に応じた老人ホーム・介護施設をお探しの際には、ケアスル介護で相談してみることがおすすめです。
ケアスル介護では全国で約5万もの施設から、入居相談員がご本人様にぴったりの介護施設を紹介しています。
「幅広い選択肢から納得のいく施設を探したい」という方は、まずは無料相談をご利用ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
区分支給限度基準額と支給限度基準額の違い
区分支給限度基準額は、被保険者に設けられた4つの支給限度基準額のうちの一つで、要介護・要支援などの区分ごとに基準額を設定したものとなります。したがって、4種類ある支給限度基準額のうちの一つが区分支給限度基準額となるのです。
ここでは、残り3種類の支給限度基準額について解説していきます。
福祉用具購入費支給限度基準額
福祉用具購入費支給限度基準額とは、介護保険で認められているポータブルトイレや浴槽などの福祉用具の購入についての上限で、1事業年度、10万円の上限が設定されています。(1事業年度とは4月1日から翌年3月31日までの一年間を指します)
また、福祉用具についてはレンタルできるもの[高橋4] もあり、要介護度ごとに自己負担額1~3割でレンタルすることもできます。
住宅改修費支給限度基準額
住宅改修費支給限度基準額とは、手すりを付けたり、段差をスロープに変えるなどのバリアフリー工事である住宅改修を実施したときに同一の住宅で20万円の上限が定められている基準額となります。
種類支給限度基準額
種類支給限度基準額とは、市区町村によって利用できる特定の介護サービスが制限されている場合に、一人当たりが月に利用できる回数を制限している限度額のことです。
例えば、定員20名の通所介護しかない地域において、毎日利用したいという人が100人いたとするとすぐに全員が利用することはできなくなります。したがって、すべての人に公平にサービスを提供することができなくなります。
そこで、条例によって不足する可能性がある特定の介護サービスによって「月○○回まで」のように上限を設けることができるのが種類支給限度基準額なのです。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
区分支給限度基準額の対象となるサービス
区分支給限度基準額は介護保険サービスを利用する際の要支援・要介護度ごとの上限ですが、区分支給限度基準額の対象となるサービスと対象とならないサービスがあります。
それぞれについて紹介していきます。
対象サービス
区分支給限度基準額の対象となるサービスの一覧としては以下のサービスとなります。
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 福祉用具貸与
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 特定施設入居者生活介護(短期利用に限る)
- 定期巡回・随時対応サービス
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用に限る)
- 複合型サービス
通所サービスや短期入所サービスなどを利用した際の食費やそのほかオムツ代や歯ブラシ代などの雑費は自己負担となることに注意しましょう。
対象外のサービス
区分支給限度基準額の対象外となるサービスとしては以下の介護サービスが挙げられます。
費用が安く人気な施設である特別養護老人ホームやそのほか老健などの施設サービスでは居室のタイプや要介護度、入所する施設によって費用が異なり、自己負担額は1~3割で負担します。
- 居宅療養管理指導
- 特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型を除く)(短期利用を除く)
- 認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老健)
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
- 福祉用具購入費・住宅改修費
これらの施設サービスと対象となる居宅サービスなどの併用はできないことに注意しましょう。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
区分支給限度基準額を超過した場合どうなる?
区分支給限度基準額を超過した場合は、超過した分を全額自己負担で支払う必要があります。通常であれば1~3割の自己負担で支払う必要がありますが、10割の自己負担で支払わないといけないことに注意しましょう。
ただし、1割から3割の自己負担額の合計が高額になった場合は、高額介護サービス費支給制度などの軽減制度を使えば所得ごとに定められた負担の上限額を超えた分の費用は返還してもらえます。具体的には以下の表のように区分が設けられています。
| 区分 | 区分 | 負担の上限額(月額) |
|---|---|---|
| 市町村民税課税世帯 | 課税所得690万円(年収約1160万円) | 140,100円(世帯) |
| 課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1160万円)未満 | 93,000円(世帯) | |
| 市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) | |
| 市町村民税非課税世帯 | 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 24,600円(世帯) |
| ・合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方・老齢福祉年金を受給している方 | 24,600円(世帯)15,000円(個人) | |
| 生活保護を受給している方 | 15,000円(世帯) |
利用料が自己負担額を超えている場合は、自治体から届く「介護保険高額介護サービス費支給申請書」を提出して下さい。一度申請されますと、以降の申請は不要です。
区分支給限度標準額を理解して介護保険を利用しよう
本記事では介護保険を利用する際の要支援・要介護度ごとに設定されている上限である、区分支給限度基準額について解説しました。
単位と円の違いや地域によっても自己負担額は少しずつ変わってくるので介護保険を利用する際は自分の介護度ごとの自己負担額を把握して利用するようにしましょう。
区分支給限度基準額とは、要支援・要介護度ごとに設定された介護保険サービスの月の上限を単位数として設定しているものです。詳しくはこちらをご覧ください。
区分支給限度基準額は、被保険者に設けられた4つの支給限度基準額のうちの一つで、要介護・要支援などの区分ごとに基準額を設定したものとなります。したがって、4種類ある支給限度基準額のうちの一つが区分支給限度基準額となるのです。詳しくはこちらをご覧ください。