要介護認定の申請をすると、そのときの身体状態に応じて介護等級(要介護度)が決まります。ここでは、介護等級の違いで何が変わるのか、介護等級の示す状態の目安について解説し、認定された後の流れもご紹介します。本記事を読み「要介護度」関連についての理解を深め、いざとなったときに向けて介護サービスを利用できるよう備えましょう。

要介護度の区分(介護等級)は8段階
要介護度(介護等級)は全部で8つの区分で構成されています。
- 自立・非該当
- 要支援1、2
- 要介護1、2、3、4、5
なお、自立・非該当を含めず、7段階と紹介するケースもあります。
要介護認定を受ける方の多くは、全国一律に定められた基準をもとに、要支援または要介護のどの区分になるか判断されます。
要支援よりも要介護の方が介護の必要度合が高く、そして、数字は大きければ大きくなるほど重度が上がり、要介護5が最も重度の状態です。
もし、要介護認定の申請をしたとしても、要支援や要介護の基準に当てはまらず「非該当」と判定される方もいます。そのため、自分たちとしては支援が必要だと思っても、介護や支援の必要性がなく一人での生活が可能な状態と判断されるケースもあるのです。
要支援と要介護の境は何で決まる?
要介護認定の区分の中でも、多くの方が疑問に感じるのは要支援と要介護の違いでしょう。似ている2つの言葉ですが、使えるサービスの種類や量は異なるため、自宅で生活を続けたい方やその家族にとっては、大きな影響が出る場合があります。
まずは、それぞれの定義について確認しましょう。
【要支援状態の定義】
「身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要支援状態区分)のいずれかに該当するものをいう。」
※厚生労働省令で定める期間:原則6ヵ月
引用:『要介護認定に係る法令』
【要介護状態の定義】
「身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要介護状態区分)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。」
※厚生労働省令で定める期間:原則6ヵ月
引用:『要介護認定に係る法令』
この定義によってわかるのは、要支援と要介護の分かれ目は、「常時介護」が必要かどうかという点です。どちらの状態も日常生活には何らかの支障はあるものの、要支援の場合は状態の悪化や防止が必要な状態、要介護は常時介護が必要な状態であると整理できます。
要支援と要介護の違いで何が変わる?
要支援と要介護とでは、使えるサービスの種類やその量(頻度)が変わります。ほんの少しの違いだと思うかもしれませんが、介護保険サービスを利用したい方にとっては大きな境い目です。
介護保険サービスには次のような種類があります。
- 自宅訪問のサービス(訪問介護、訪問入浴など)
- 施設に通うサービス(通所介護、通所リハビリテーションなど)
- 短期間施設に宿泊するサービス(短期入所など)
- 施設に入所して生活するサービス(特別養護老人ホームなど)
- 生活に便利な道具をレンタル・購入するサービス(福祉用具貸与、福祉用具販売)
要支援と要介護とでは、これらのサービスの使える範囲と頻度(量)が異なるため、要支援の場合は要介護よりも限定的になります。
「要支援、要介護で利用できるサービス」
| サービスの種類 | 要支援 | 要介護 |
| 訪問介護 | ◯ | ◯ |
| 訪問看護 | ◯ | ◯ |
| 訪問入浴 | ◯ | ◯ |
| 訪問リハビリテーション | ◯ | ◯ |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ✕ | ◯ |
| 夜間対応型訪問介護 | ✕ | ◯ |
| 通所介護 | ◯ | ◯ |
| 通所リハビリテーション | ◯ | ◯ |
| 認知症対応型通所介護 | ✕ | ◯ |
| 地域密着型通所介護 | ✕ | ◯ |
| 小規模多機能型居宅介護 | ✕ | ◯ |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | ✕ | ◯ |
| 短期入所生活介護 | ◯ | ◯ |
| 短期入所療養介護 | ✕ | ◯ |
| 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | ✕ | △
原則要介護3以上 |
| 介護老人保健施設 | ✕ | ◯ |
| 介護療養型医療施設 | ✕ | ◯ |
| 介護療養院 | ✕ | ◯ |
| 認知症対応型共同生活介護
(グループホーム) |
◯ | ◯ |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | ✕ | ◯ |
| 福祉用具貸与 | ◯
※介護度によりレンタル対象品が異なる |
◯
※介護度によりレンタル対象品が異なる |
| 特定福祉用具販売 | ◯ | ◯ |
| 住宅改修費支給 | ◯ | ◯ |
上記の表に記載した介護サービスを、必要性に応じて組み合わせて利用します。
入居できる施設が知りたいという方は、ケアスル介護がおすすめです。ケアスル介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができるためご希望に沿った施設探しが可能です。
「プロに相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
要介護度を決めている目安
要介護度を決める目安や要介護度ごとにおける状態の目安を見てみましょう。ここで紹介するのはあくまでも目安のため、たとえ同じ介護度でも身体の状態や必要な介護内容は異なります。
「要介護度ごとの状態の目安」
| 介護度 | 状態の目安 |
| 要支援1 | 基本的な日常生活は1人でできるが、手段的日常生活動作(買い物・金銭管理・内服管理・電話の使用)のいずれかに見守りや介助が必要な状態。 |
| 要支援2 | 要支援1の状態に加え、下肢の筋力低下による歩行不安定が見られる。今後、介護が必要になる可能性がある。 |
| 要介護1 | 日常生活動作(食事・排泄・入浴など)のいずれかに介助が必要で、手段的日常生活動作のどれかにも毎日介助が必要な状態。 |
| 要介護2 | 日常生活動作・手段的日常生活動作の一部に毎日の介助が必要。日常生活動作はできても認知症の症状によって日常生活にトラブルが起こる可能性がある場合も含まれる。 |
| 要介護3 | 歩行が不安定で杖や歩行器、車椅子が必要。日常生活動作や手段的日常生活動作の何かに毎日全面的な介助が必要な状態。 |
| 要介護4 | 常時、介護なしでは日常生活を送るのが困難。全面的な介護を要するが、会話は行える。 |
| 要介護5 | ほとんど寝たきりの状態で、意思の伝達が困難。自分で食事ができない。日常生活すべてに全面的な介助が必要な状態。 |
要介護度ごとに支給金額が決められている
介護保険サービスを利用した場合に支払う料金(自己負担額)は、1割〜3割となります。その差額の7割〜9割は、介護保険からの給付となり、要介護者の費用負担が軽減されています。
しかし、この介護保険からの給付は無制限ではありません。要介護度別に、給付される限度額が決められており、これを介護保険支給限度額といいます。
介護保険支給限度額が重要なワケ
介護保険支給限度額は、要介護度が高いほど高額となります。つまり、介護度が高い方ほど1割〜3割の負担で使える介護保険サービスが増える仕組みです。
1ヶ月あたりの介護保険支給限度額
| 要介護度 | 介護保険支給限度額 |
| 要支援1 | 5,032単位 |
| 要支援2 | 10,531単位 |
| 要介護1 | 16,765単位 |
| 要介護2 | 19,705単位 |
| 要介護3 | 27,048単位 |
| 要介護4 | 30,938単位 |
| 要介護5 | 36,217単位 |
実際の支給限度額は、「円」ではなく「単位」で決まっています。1単位いくらになるのかは、サービスの種類やお住まいの地域によって多少の差があり、1単位10円〜11円程度が目安です。
支給限度額がいくらかまで覚える必要はありませんが、ここでは介護度によって支給限度額が変わってくることを把握しておきましょう。
支給限度額を超えてしまったら
介護保険サービスを利用する際、支給できる費用は介護度によって決められています。支給限度額内であれば、利用したサービス費の1割~3割の自己負担割合で利用可能です。自己負担割合(1割~3割)は、所得の状況によって変動します。自分の自己負担割合は、介護保険負担割合証が発行され、送られてくるためそちらで確認しましょう。
また、支給限度額を超えた分は、全額自己負担する必要があるため注意が必要です。支給限度額を超えないよう、利用する介護保険サービスを担当のケアマネージャーが調整します。優先的に利用したい介護保険サービスがあれば、事前に相談しておくとよいです。
支給限度基準額について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
使えるサービスの種類や量で生活は変わる
要介護度ごとに使えるサービスの種類は異なります。また、要介護度に応じて支給限度額が決められているため、自己負担額1〜3割で利用できるサービス内容や頻度も変わってきます。
例えば、デイサービスを利用しながら家族の介護を受けて生活をしている方の場合、デイサービスの利用回数が週1回増えるだけで、家族の休息時間や安心して仕事に出掛けられる日が月4日も増えます。
つまり、要介護度が一段階異なるだけで、自己負担割合1〜3割で受けられるサービス内容や頻度(量)が増え、介護負担や本人の生活に変化を及ぼすのです。
認定された要介護度が、実際の介護の必要性と比較して不足していると感じた場合、不服申し立てを検討しましょう。
施設への入居を検討しているという方は、ケアスル介護がおすすめです。ケアスル介護なら、見学予約から日程調整まで無料で代行しているためスムーズな施設探しが可能です。
「プロに相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
要介護度の認定を受けるのはどんな人?
ここからは要介護度の認定が受けられる対象者と、要介護認定を受けたあとの流れをご紹介します。
第一号被保険者と第二号被保険者
介護保険の加入者は、65歳以上の「第1号被保険者」と40~64歳までの「第2号被保険者」です。
40歳以上になると、介護保険料の支払い義務が生じますが、基本的に介護保険のサービスが利用できるのは65歳以上の「第1号被保険者」がメインとなります。
ただし、40~64歳の「第2号被保険者」のうち、老化に起因する病気(特定疾病)で介護が必要になった場合は、要介護認定を受け、介護保険サービスの利用が可能です。
申請してから要介護度が決まるまでの流れ
介護保険サービスを受けるには、まず要介護認定の申請を行う必要があります。手続きの流れは、以下の通りです。
- 申請書の提出
- 認定調査
- 結果通知
要介護認定の申請は、お住まいの地域の役場にある介護保険担当窓口で行えます。ほかにも、お近くの居宅介護支援事業所や在宅介護支援センター、地域包括支援センターでも可能です。
申請してから後日、市区町村から任命された認定調査員の訪問を受け、身体機能の状態の把握や日常生活の状況などのチェックが行われます。調査結果と、かかりつけ医の意見書をもとに要介護度が決まり、要介護認定の結果がわかるのは、調査からおよそ「1ヶ月後程度」になります。
結果は、自宅に郵送される介護保険証で知らされます。その後の手続きについては案内が同封されているため安心です。

要介護度が決まったあとの流れ
要介護度が決まったら、その次は介護保険サービスの利用に向けた調整や手続きが行われていきます。その手続きは、地域包括支援センターの職員や居宅介護支援事業所のケアマネジャーと一緒に行っていきます。
サービス利用に向けた段取りは、本人や家族で行うことも可能ですが、介護保険制度の知識が不可欠で簡単なものではありません。ほとんどの方がケアマネジャー等と一緒に進めているのが現状です。
- 要支援→地域包括支援センターに相談
- 要介護→居宅介護支援事業所に相談
- ケアマネジャーによる面談とケアプランの作成
- 介護保険サービス事業所との調整
- サービス利用開始
要介護認定の結果が出て担当のケアマネジャーがつくまでは、慣れない手続きで大変かもしれませんが、そのあとは介護のプロに色々と相談しながら進められるため安心です。
ケアマネジャーは、本人の話や要望だけでなく、家族や本人を支える周囲の人々の意見にも耳を傾けてくれます。ケアプランは一度作成すれば終わりではなく、必要に応じて随時変更されるものでもあるため、困り事や要望があれば相談してみましょう。
要介護度に不満があるときはどうすれば?
要介護度の認定結果について不満があるときは、不服申し立てが可能です。また、申請をしてから結果が出るまでの間に状態が変わった場合は、区分変更申請手続きを行って、もう1度調査のやり直しも可能です。
不服申し立ては、都道府県が設置する介護保険審査会に対して行います。不服申し立てができる期間は、要介護認定の結果の通知を受けた翌日からおよそ3ヶ月までです。
区分変更申請は、市区町村の介護保険を担当する窓口で申請をします。認定結果への不満ではなく、本人の状態に変化があった時のみ区分変更は認められます。
介護認定の申請方法について、更に詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
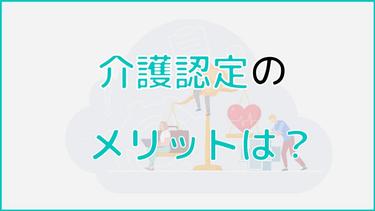
分からないことがあれば相談しよう
要介護度(介護等級)は、申請時や更新時の本人の状態によって変わるケースもあります。2回目以降の認定で、前回と介護度が変わっても慌てないように、仕組みを知っておくと便利です。
介護保険制度やサービスの利用については、分からない部分もたくさんあるでしょう。不安をできるだけなくすためにも、困ったことは早めに介護保険の窓口やケアマネジャーに相談してはいかがでしょうか。
介護等級に関するよくある質問
Q.介護等級と障害等級は違うの?
A.障害等級は、障害者福祉サービスを利用する方々の障害の程度を表す指標です。そのため、要介護度(介護等級)とは違い、障害者の方々がサービスを利用する上で必要となります。
Q.介護等級はサービスを利用しないうちから認定してもらえる?
A.要介護認定を受けたからといって、すぐにサービスを利用する必要はありません。しかし、実際にサービスを利用するときに要介護認定を受けた時と状態が変わっているかもしれません。場合によっては区分変更申請が必要となる可能性があります。




