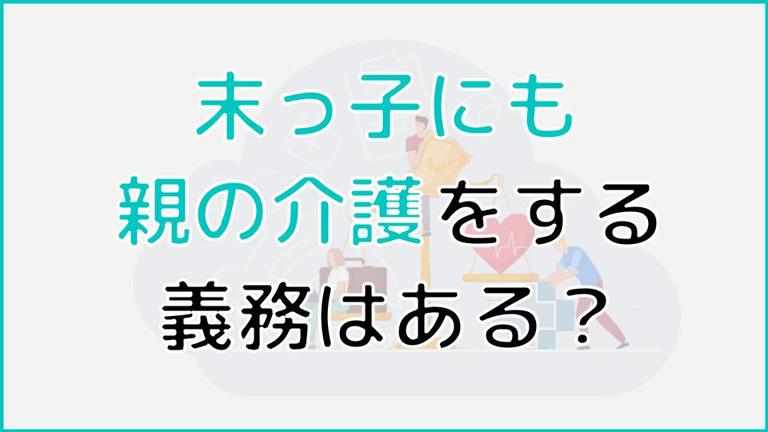末っ子にも親の介護義務はある?兄弟で協力して介護をやり遂げるには
一昔前は、長男の妻が介護を担うケースが多くありましたが、現代ではそうとも限りません。最近は末っ子が介護を担うケースも少なくないようです。
しかし、「末っ子なのに自分ばかり親の介護をしている」「ほかの兄弟姉妹に意見しにくい」などと悩みを持つ方も少なくはありません。
この記事では、末っ子に介護の義務はあるのか、兄弟間で協力して介護をするにはどうしたらよいかを解説します。また、トラブルに発展しやすい金銭トラブルを解消する方法も紹介しているため、ぜひ最後までご覧ください。
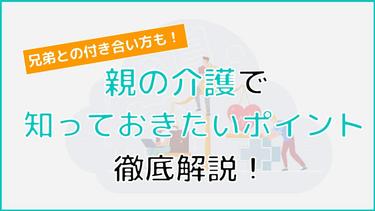
末っ子が親の介護をするときに大変なこと
末っ子に限らず親の介護は大変なものです。しかし、末っ子であるが故に大変な一面もあります。具体的には以下のような事例です。
- 親が長男に頼りたがる
- 自分の意見が通りにくい
- 親から受けた兄弟格差により不仲になる
これらが介護にどのように影響するのか、詳しく解説していきます。
親が長男に頼りたがる
一昔前の日本では長男が家を継ぐものとされていました。その名残が残っており、親が長男に頼りたがる、期待してしまう事例もあります。
末っ子の自分が介護しているのに、自分の言うことよりも長男の言うことを聞くケースも珍しくはありません。酷い場合は、介護は末っ子、遺産はすべて長男にと話す親もいます。
報われない介護はとても辛いものです。その結果、親や長男と不仲になってしまうかもしれません。
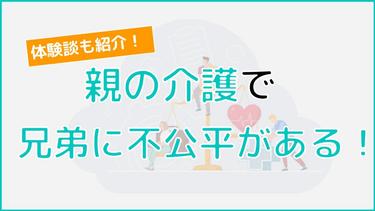
自分の意見が通りにくい
末っ子は子ども扱いされるケースが多くあります。「もういい歳なのに……。」と不満に思う方も多いでしょう。そんななか、兄姉に意見しにくい、意見をしても通りにくいと感じている方もいます。
介護は1人の力では成り立ちません。しかし、意見しにくいがゆえに自分1人で抱え込んでしまうと、体調を崩したり、介護鬱になったり、親子共倒れになってしまう可能性があります。
親から受けた兄弟格差により不仲になる
子どもの頃から兄弟間に格差があった場合、親の介護をきっかけに不仲になってしまうケースもあります。長男が優遇されていた、末っ子が1番可愛がられていたなど、格差の形はさまざまです。
どのような形であれ、心にわだかまりが残っていると、「一番優遇されたのだから介護をすべき」「自分が介護をしているのに、親が違う兄弟ばかり可愛がる」など、不満として現れてしまいます。その結果、取り返しのつかないレベルの大喧嘩をしたり、遺産について疑心暗鬼になったりしてしまう可能性があります。
「自宅ではもう親の面倒を見切れない」「施設を探したいが、何から始めれば良いのかわからない」と悩んでいる方は、ケアスル 介護での相談がおすすめです。
ケアスル 介護なら、土日を含む毎日10:00〜19:00まで入居相談員が対応しており、約5万件の施設情報から条件にあった施設を教えてもらえます。
「条件にあった施設を幅広い選択肢から見つけたい」という方はまずは無料で相談してみましょう。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
末っ子が親の介護をするときにおこるトラブル3選
親の介護問題はとてもセンシティブな問題です。なかなか、親の現状を受け入れられない方もいるでしょう。
また、介護に前向きになれても、人それぞれ意見や対応できる範囲は異なります。そのため、親の介護をどうするか、兄弟間で揉めるケースも少なくはありません。
ここでは起きやすいトラブル3選を紹介していきます。具体的にどのような事例があるのか確認していきましょう。
ケース1.兄弟のいずれかが介護をしようとしない
介護は自分たちの生活に大きな影響を及ぼします。そのため、兄姉が親の介護を嫌がるケースも少なくはありません。立派だった親が弱った姿を見たくないと介護を拒否する方もいます。
特に女性の独身者は、家庭を持たないことを理由に介護の負担が大きくなりがちです。しかし、そうなると負担が偏ってしまい、兄弟間に格差が生まれてしまいます。その結果、不仲になったり、追い詰められた末に手を挙げるようになってしまったりするケースも見受けられます。
ケース2.親の介護にかかる費用を押し付ける
介護において、金銭的なトラブルは特に多いと言われています。
親の預貯金が元々少なく、子どもたちがその負担をしなくてはいけないケースも少なくはありません。しかし、「住宅ローンが残っているから」「子どもに教育資金がかかるから」と負担を押し付ける方や、介護には全く手を出さず遺産の話だけしてくる方もいます。
少額でも親の介護が長引けば金額は大きくなります。最初は大丈夫でも、後々になって喧嘩になる事例も少なくありません。
ケース3.兄弟間で意見が合わない
介護に関する意見は人それぞれです。時には意見が分かれる場合もあります。
特に意見が分かれやすいのが、親を施設に入れるか否かです。大切な両親の老後に大きな影響を与えるため、自宅で過ごす方がよいのではと思う方も少なくはありません。
しかし、実際に介護をしているとだんだん自宅で介護できなくなっていきます。そのときに、身近で見ている方と普段介護には関わらない方の意見が食い違い始めます。介護に直接関わろうとしないのに、口だけ出すケースも少なくはありません。
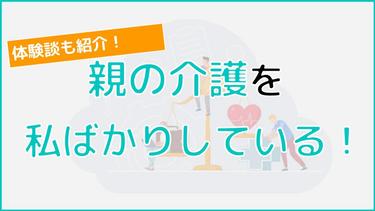
末っ子に親の介護をする義務はあるか
一昔前は、長男の妻や長女が介護をするケースが多くありました。そのため、末っ子には介護義務がないと誤解している方もいるでしょう。しかし、末っ子にも介護義務はあります。
介護義務は日本の民法では“扶養義務”と呼ばれています。「一定範囲の親族同士で経済上や心身上の理由などにより自力で生活できない親族がいるときには、支援をしなければならない」義務です。
この扶養義務を負うのは、“直系血族”と“兄弟姉妹”であると民法第877条に定められています。直系血族とは、具体的に、父母、祖父母、子ども、孫です。そのため、兄弟姉妹全員に介護する義務はあり、程度の差はありません。
また、民法第752条により、本人の配偶者にも同居及び協力、扶助の義務があります。特別な事情がある場合は、三親等以内の親族が扶養義務を負うケースもあります。しかし、どのような場合であっても子の妻には介護義務は発生しません。
親の介護をしないとどうなるか
扶養義務があると判断されたにもかかわらず、親の介護を放棄するのは「保護責任者遺棄罪」に当たり、3ヶ月以上5年以下の懲役に科せられる可能性があります。
加えて、親の介護を放棄した結果、親が死亡もしくは傷を負った場合には、「保護責任者遺棄致死罪」や「保護責任者遺棄致傷罪」が適用される場合もあります。
では、どうすれば扶養義務を果たしたとみなされるのか、気になる方も多いでしょう。扶養義務には、心身の世話をする扶養と経済的な支援をする扶養の2種類があり、片方だけでも義務を果たしたと認められます。
扶養義務を負っている方自身が、生活ができる範囲で支援すればよいため、生活に困っている場合はしなくても大丈夫です。介護義務が発生するかは、家庭裁判所が生活保護の受給の有無を判断するときの生活水準を目安に判断します。
親の介護にまつわる兄弟間のトラブルの解決法
親の介護にはトラブルがつきものです。すでにトラブルの渦中にいる方もいるのではないでしょうか。そんな方々のために、次は兄弟間のトラブルの解決方法を紹介します。
親の介護は兄弟姉妹みんなが納得できる役割分担が非常に重要です。どうしたら納得してもらえるのかを意識して、対応していきましょう。それでは、具体的にどう対応したらよいのか、解説していきます。
話し合いを行う
どんな状況でも、まずは話し合いを行う必要があります。「話し合いは今まで散々やってきた」「話し合いをどう進めればいいのかわからない」そんな方もいるでしょう。話し合いは
“何を”“どのように”伝えるかが非常に重要です。以下のような流れで進めていきましょう。
- 親の状況を伝える
- 介護に対する本音を聞く
- 介護に参加できる範囲を確認する
- 主介護者を決める
- それぞれの役割を決める
話し合いがうまくいかなかった方もぜひ参考にしてください。
親の現在の状況を伝える
まずは、親の現状を伝えましょう。
- 親にどの程度介護が必要なのか
- 経済的な状況はどうなのか
- 将来的にどのような介護を希望しているのか
- 将来的にどのような介護が必要になりそうか
上記の項目を中心に伝えると要点がわかりやすいです。
現状を伝えても、理解できない、理解しようとしない場合もあります。その場合は、数日間一緒に過ごしてもらうと効果的です。押し付けようとする場合は、扶養義務は兄弟みんな等しくあり、放棄すると不利益があると伝えてみましょう。
介護に対する本音を聞く
現状を理解してもらったあと、それぞれの意見を確認します。その際、介護ができるかできないかではなく、まずは親の介護に対する気持ちを確認しましょう。
介護できるかを中心に話し合うと、介護を避けるために「私は仕事があるから」「腰が悪いから」「ローンがあるから」などと大変さを比較する場になってしまいます。そうではなく、まずは自分から親の現状にショックを受けている、昔はあんなに元気だったのに、と正直な気持ちを話してみましょう。
多少話が脱線しても構いません。親に対しても気持ちを再確認してもらうことが重要です。親に対して否定的な内容を話しても、その気持ちを受け入れるよう心がけましょう。
介護に参加できる範囲を確認する
お互いの気持ちがわかってきたら、介護に参加できる範囲を確認します。
まずは、月々どれくらい費用が必要か、どれだけ介護の手が足りないかなどを再度伝えましょう。そのうえで、“何ならできるか”に焦点を当てて確認していきます。できないことに焦点を当てると話を進めにくくなるため注意が必要です。
兄弟のなかには、親と不仲で介護に積極的になれない方もいるかもしれません。その気持ちを受け入れつつ、具体的に何ができて、何が絶対に嫌なのかを話し合いましょう。顔を合わせるのが嫌なら、手続き関係を行ってもらったり、経済的な負担をしてもらったりするとよいでしょう。
主介護者を決める
主介護者とは簡単にいうと一番近くで身の回りの世話などを行う人です。キーパーソンとも呼ばれます。身の回りの世話だけではなく、各種手続きを行ったり、体調を崩した時の連絡先になったりするため、負担は誰よりも重くなります。
また、主介護者は今後の介護の方針を決める中心的な人物です。自宅でもう介護できないと判断したり、施設を探したりは原則主介護者が行います。今後の介護をトラブルなく進めるためには、主介護者の負担は誰よりも重いと兄弟姉妹みんなが認識し、主介護者の意向を尊重することが重要です。
「主介護者になったけど自宅での介護は難しい」「施設の探し方がわからない」と悩んでいる方は、ケアスル 介護での相談がおすすめです。
ケアスル 介護なら、土日を含む毎日10:00〜19:00まで入居相談員が対応しており、約5万件の施設情報から条件にあった施設を教えてもらえます。「施設選びで後悔したくない」という方はまずは無料相談を。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
それぞれの役割を決める
主介護者を決めたあと、それぞれの役割を決めます。その際、介護の負担が1人に集中しないよう注意しましょう。介護費用の援助をする、週末や終業後に手伝う、定期的に電話で親の安否確認をするなど、少しでも協力する姿勢が大切です。
また、会社の介護休暇や介護休業を使えるか、会社独自の支援がないか確認し、協力し合うとよいでしょう。介護休暇や介護休業は育児介護休業法で認められた法律上の制度です。そのため、会社に制度は必ずあり、介護休暇や介護休業を取得できます。
参照:『介護休業制度 – 厚生労働省』
話し合いで解決できない場合は調停も可能
兄弟姉妹間の事情や考え方の違いにより、自分たちだけの話し合いで解決できない場合は家庭裁判所に「扶養請求調停」を申し立てられます。
裁判所と聞くと大袈裟かもしれませんが、調停は裁判ではありません。裁判所が選任した調停委員を交えた“話し合い”です。
不要請求調停では、兄弟姉妹それぞれの客観的な状況や介護に対する考え方などを調停委員が聞き取り、経済状況を確認したうえで、調停委員が解決策を提示します。この解決策に合意すれば調停成立です。
そのあと、裁判所が合意内容の調停調書を作成します。もしも、調停調書の内容を果たさない場合は、強制執行にて債務者の財産を差し押さえできます。
「費用がかかるのでは……」と不安になる方もいるかと思いますが、扶養請求調停の費用は裁判と違って少額です。扶養権利者1人につき収入印紙1200円、連絡用の郵便切手のみ必要です。そのほかにも必要な書類等ありますが、詳しくは裁判所のホームページを確認してください。
参照:『扶養請求調停 – 裁判所』
経済的に不安がある場合は制度を活用
金銭に関する問題は介護する側の不安感も強く、トラブルになりやすい問題です。しかし、そんな不安を和らげる制度も存在します。
- 特定入所者介護サービス費
- 高額介護(予防)サービス費
- 高額介護合算療養費制度
親の預貯金や収入が心許ない場合、これらの制度を利用できるかもしれません。経済的な不安が軽減できれば、兄弟姉妹みんなの介護に対する不安が和らぐはずです。ぜひ活用ください。
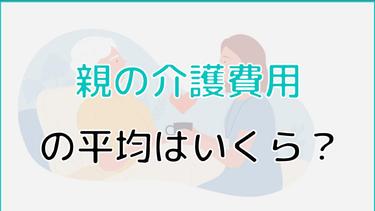
●特定入所者介護サービス費
特定入所者介護サービス費とは、住民税非課税世帯の人が、介護保険施設やショートステイなどの利用時に、居住費、食費などの負担限度額を超えた支払い分の支給が得られる制度です。
対象となるサービスは以下の通りです。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
- 地域密着型介護老人福祉施設
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護(ショートステイ)
「特定入所者介護サービス費」の給付を受けるには、住まいのある市区町村に申請し、負担限度額認定証を交付してもらう必要があります。
詳細は下記の通りです。
| 利用負担段階 | 預貯金等の資産の状況 | 居住費(日) | 食費(日) | ||||||
| ユニット型個室 | ユニット型多床室 | 従来個室
(特養など) |
従来個室
(老健など) |
多床室 | ショートステイ | 施設 | |||
| 第1段階 | 生活保護等を受給している方 | 単身:1000万円以下
夫婦:2000万円以下 |
820円 | 490円 | 320円 | 490円 | 0円 | 300円 | |
| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で
年金収入等(※)が80万円以下の方 |
単身:650万円以下
夫婦:1650万円以下 |
420円 | 370円 | 600円 | 390円 | |||
| 第3段階1 | 世帯全員が住民税非課税で
年金収入等が 80万円超120万円以下の方 |
単身:550万円以下
夫婦:1550万円以下 |
1,310円 | 1,310円 | 820円 | 1,310円 | 370円 | 1,000円 | 650円 |
| 第3段階2 | 世帯全員が住民税非課税で
年金収入等が 120万円超の方 |
単身:500万円以下
夫婦:1500万円以下 |
1,300円 | 1,360円 | |||||
参照:「特定入所者介護サービス費(補足給付)」介護サービス情報公表システム 厚生労働省
●高額介護(予防)サービス費
高額介護サービス費とは、介護保険の利用時に自己負担額の合計が限度額を超えた場合に、超えた分の金額が戻ってくる制度です。
月の負担限度額は下記の通りとなっています。
| 適用区分 | 負担上限額 |
| 年収1160万円以上 | 140,100円(世帯) |
| 年収770万円〜年収1160万円 | 93,000円(世帯) |
| 年収770万円未満 | 44,400円(世帯) |
| 世帯の全員が市町村民税非課税 | 24,600円(世帯) |
|
24,600円(世帯)
15,000円(個人) |
| 生活保護受給者 | 15,000円(世帯) |
対象者は、要介護(要支援)認定を受けて、介護保険を利用している方です。
なお、介護サービスの中にも対象にならないものもあるので注意しましょう。
- 特定福祉用具購入や住宅改修にかかる負担
- 施設における居住費(短期入所の場合は滞在費)および食費
- 理美容代などの日常生活に要する実費
上記は高額介護サービス制度の対象外の一例です。
●高額介護合算療養費制度
高額介護合算療養費制度は、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)にかかった医療保険と介護保険の自己負担額が高額になった方の負担を軽減する制度です。
被保険者の年齢や所得に応じて限度額が設定されており、限度額を超過した金額分が還付されます。
<限度額>
| 75歳以上 | 70〜74歳 | 69歳以下 | |
| 後期高齢者医療保険+介護保険 | 被用者保険または国民健康保険+介護保険 | ||
| 年収約1,160万円〜 | 212万円 | 212万円 | 212万円 |
| 年収約770〜約1,160万円 | 141万円 | 141万円 | 141万円 |
| 年収約370〜約770万円 | 67万円 | 67万円 | 126万円 |
| 〜年収約370万円 | 56万円 | 56万円 | 67万円 |
| 市町村民税世帯非課税等 | 31万円 | 31万円 | 60万円 |
| 市町村民税世帯非課税(年金年収80万円以下等) | 19万円 | 19万円 | 34万円 |
該当する方は翌年の2月、3月に市役所から申請書が届きます。届き次第、申請を行いましょう。
親の介護は長子から末っ子までみんなで協力する必要がある
親の介護は想像以上の困難を伴います。そのため、介護を避けようとする兄姉もいるかもしれません。
しかし、親の介護義務は兄弟姉妹みんなにあります。公平に介護に携わり、みんなが納得して介護を行うことが重要です。兄弟姉妹みんなで協力して介護を行うために、まずは話し合いから始めてみてはいかがでしょうか。
その際はぜひご紹介した方法を試してください。
民法第877条により、扶養義務を負う親族は、“直系血族”と“兄弟姉妹”であると定められています。具体的には、父母、祖父母、子ども、孫です。特別の事情がある場合は、三親等以内の親族が扶養義務を負う場合もあります。また、民法第752条により、夫婦間にも扶養義務(同居、協力および扶助の義務)があります。長男の妻には扶養義務はありません。詳しくはこちらをご覧ください。
金銭関係はトラブルになりやすい問題です。親の預貯金や収入が心許ない場合、経済的な負担を緩和する制度を利用できるか確認するとよいでしょう。介護に対する不安が和らぐはずです。①特定入所者介護サービス費②高額介護(予防)サービス費③高額介護合算療養費制度 上記3つの制度について、市役所に問い合わせてみましょう。詳しくはこちらをご覧ください。