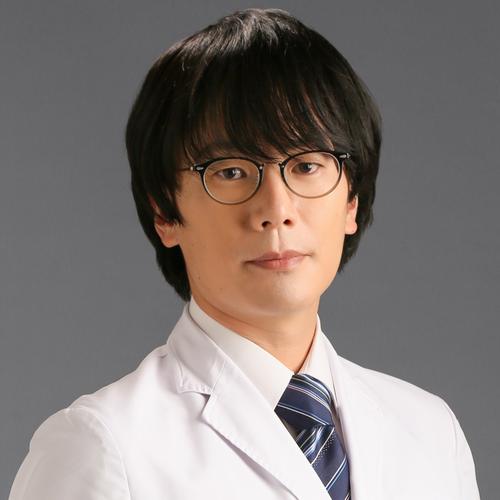認認介護という言葉を耳にしたことはあるでしょうか?介護する側とされる側、両者が認知症の状態を言います。
65歳以上の高齢者同士で介護を行う老老介護が社会的に問題視されていますが、認知症同士の認認介護はより深刻化した状態です。
通常でも介護の実態は社会的に孤立することが多いなか、認認介護が抱える問題とはどういったものでしょう。
ここでは認認介護とは何か、具体的な問題やその解決策について紹介します。
認認介護の定義とは
認認介護の定義は、65歳以上の高齢者世帯において、認知症の方が同じく認知症の方を介護している状態です。
老老介護は65歳以上の高齢者が同じく65歳以上の高齢者を介護している状態を表しており、認認介護はさらに介護者も要介護者も認知症を発症していることが前提になります。
近年認知症を発症する高齢者は増加の一途をたどっています。また夫婦やパートナー、兄弟などの同世代の介護だけではなく、75歳以上の親世代の方を介護している方、お互いが75歳以上である超老老介護も年々増加している状態です。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
認認介護と老老介護の関係
認認介護は、老老介護の進行により起こってくるものです。介護の始まった頃は自分たちの手に負えると頑張っていたものの、徐々に体力的にも精神的にも辛くなり、認知症を発生するまでに至るケースが多々見られます。
老老介護の一因に、世帯の核家族化が進み子ども世帯も独立して家を構える事が多いため、介護の助けを求めにくいという現状があります。定年まで仕事に打ち込んでいた方のなかには、町内や周囲との人間関係も希薄で頼る術を知らない人も少なくありません。
責任感の強さから頑張り続ける方も多く、気力・体力ともに限界を超えるまで助けを求めることができずにいます。結果、認知症の方が認知症の方を介護する、認認介護になってしまいます。
認認介護の背景にあるものとは
ようやく会社を定年退職し、悠々自適な老後を考えていたのに、なぜ認認介護の状況にまで陥ってしまうのでしょうか。そこには健康であれば楽しいはずの社会背景や福祉制度が原因となっている現実があります。
認認介護や老老介護は、問題点が山積みです。中でも健康寿命と平均寿命の相違による長期間の老後問題や、便利なはずの介護保険制度の矛盾点、かさむ医療費による経済的なリスクなどが顕著になっています。
平均寿命と健康寿命
平均寿命とは、平均的な寿命年齢を表しています。2019(令和元)年の調査によると、平均寿命は男性で81.41歳、女性で87.45歳と緩やかながら右肩上がりに伸びており、男性と女性の差は約6歳です。
健康寿命は日常生活が制限なく生活できる期間を表し、2019(令和元)年の調査では、男性72.68歳、女性75.38歳です。つまり男女共に健康寿命を過ぎた約10年間は、何らかの病を発症し介護生活に入る可能性があることを示しています。
今後医療技術の発達により、増々平均寿命が延びていくでしょう。そのため健康寿命を押し上げ、平均寿命との差を縮小していくことが、老老介護や認認介護の問題解決の糸口になるといわれています。
介護保険制度
介護保険制度とは、介護を必要とする人が誰でも使える保健制度です。介護申請し、認定が下りた方なら誰でも使える公的サービスで、以下の6つのサービスが受けられます。
- 訪問介護
- 訪問看護
- 通所介護(デイサービス)
- 通所看護(デイケア)
- 短期入所(ショートステイ)
- 福祉用具貸与(介護・福祉用具のレンタル・購入)
6つのサービスのどれを利用するかなどは、専門家のアドバイスやサポートによって決定します。サービスを受けられる範囲は介護度によって決定します。
皮肉なことですが、介護者の負担を減らす便利なサービスが、平均寿命を伸ばす要因にはなっても健康寿命には影響しません。
金銭問題
高齢者世帯の主な収入はほとんどの場合年金だけになり、医療が必要な状態や介護サービスを受けている年数が長引くほど、経済的なリスクは上がります。
月々に貰える年金は、ほとんど医療と介護の費用に消えるという方も多いのではないでしょうか。
年金額は明らかに現役時代よりも金額が少ないため、より長い期間の老後に備えて細々と暮らしている方は多いです。そのため、サービスを受けたいと思いながら、金銭的な理由で断念している方もいます。
また、お金を払って家族以外に介護を任せることに、抵抗がある方も少なくありません。他人に頼れないという思いから、老老介護や認認介護へとつながり高齢世帯が孤立する要因になっています。
認認介護の抱えるリスクとは
さまざまな社会背景によって、老老介護から認認介護へとつながるリスクが高まっています。特に、深刻な認認介護に陥ったときに起こりうるリスクは、誰もが知っておく必要があります。
認認介護は、介護者と要介護者に認知症の症状がある場合を指しますが、必ずしも受診して認知症と診断を受けた方ばかりではありません。
そのため、無自覚のまま認知症の方が介護者として日々を過ごしている例も多く、いつどんな事故が起きてもおかしくない状態です。認認介護によるリスクとはどんなものなのか、事前にチェックしておきましょう。
共倒れのリスク
要介護度が上がると、介護の負担も比例して大きくなります。最初は声掛け程度で済んだものが、着替えや入浴、トイレの付き添いと生活面全てにおいて介助が必要となります。
老老介護では、介護者も体がままならない中で介護をしなければならず、体力的にも精神的にも苦しい思いをしているでしょう。ましてや認認介護の場合、介護者も日々できないことが増えていく中で、介護を手伝ってくれる方がいない現実に置かれています。
認知症は、ストレスが症状悪化の一因になるといわれています。介護者の認知症が悪化していけば、どちらも介護が必要な状況となり、共倒れになってしまいます。
介護にかかる時間のリスク
高齢になり体力が落ちてくると、動作が緩慢になるため介助に時間がかかります。介助動作に時間がかかると、要介護者の体勢も不安定となり負担がかかった部分を痛めることになりかねません。
介護者自身も、一つひとつの介助動作によって体力を消耗し疲労が溜まっていきます。認知症の方は、身体や精神的疲労も症状の悪化に繋がる場合が多く、事故につながるケースも考えられます。
特に、介助の頻度が高いトイレや移動・移乗の介助、入浴介助では足腰への負担が大きくなり、要介護者の身体を上手く支えられずに、介護者・要介護者共に転倒し動けなくなってしまうといった最悪のケースもあり得ます。
社会的に隔離されるリスク
介助により外に出る時間が少なくなっていくと、密室介護になりやすく周囲も状況を把握できない悪循環に陥るでしょう。
認認介護では介護者も要介護者も認知症のため、脳機能の障害によってコミュニケーションを上手く取ることができなくなってきます。特に、認知症の初期症状は周囲の方も気付かないことが多く、自覚のないまま認認介護になることもすくなくありません。
他人に迷惑をかけることを恐れて社会的なコミュニケーションを自ら断つ方も多く、より孤立した状態の中で介護が行われることになります。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
認認介護の問題点は管理能力の低下
認認介護の1番の問題点は管理能力の低下です。管理能力とは、物事を管理し運営する能力のことで、生活においてなくてはならないものといえます。特に、介護の場面ではさまざまなシーンで、管理能力の高さが病状の回復・維持に繋がります。
老老介護では加齢による体力面の低下で介護がままならないという問題点がありますが、認認介護では管理能力の低下が最大の問題点として挙げられます。
服薬管理ができない
認知症の方は、服薬管理ができません。薬を飲んだ行為自体を忘れてしまうため、飲んでいないと思い指定された量以上の服薬をしてしまったり、薬を飲むこと自体を忘れてしまったりして理想的に治療が進みません。
薬によっては服薬をしない状態が続いたり、用法容量以上の薬を飲んだりすることで健康維持に大きく影響します。また、処方された薬の使用方法を理解することも難しく、適正な服薬ができないのは、深刻な問題です。
薬の飲み間違いを防ぐために、曜日や日付が入ったお薬ポケットやケースなどのアイテムもあります。しかし、認知症が進むと数字や文字の理解も困難になってくるため、認認介護は適正な服薬ができない状況になってくるのです。
体調管理ができない
認知症が進むと気温に合わせた衣服の調整が難しくなり、体調管理ができなくなります。寒暖の感覚が鈍くなるため、真夏に防寒具を着こんだり、冬の寒い日にコートも着ずに外出してしまったりして体調を崩しやすくなります。
また、自ら適切な水分補給ができないため、熱中症や脱水症状を起こしやすい特徴もあります。そのため、いつも目に入る場所に経口補水液などを置くなど、常に水分補給を意識してもらうようにする対策を講じる必要があります。
また、体の不調を言葉にして上手く伝えられないため、周囲が分からないまま体調が悪化することも多いです。認認介護では、お互いの体調不良に気づかず悪化させることがあります。
食事管理ができない
認知症になると、自分で食事を作ることも難しくなってきます。調理の手順さえ分からなくなるため、栄養を考えた献立の組み立ても困難でしょう。
また、認知症の症状が進むと、空腹感を感じにくくなり食事を摂ること自体忘れたり、食事を拒否したりします。一方で、満腹感を感じにくくなると、食事を摂ってもすぐに忘れて過食傾向に走りがちです。お互い食事の管理ができないので、さらに悪循環になりかねません。
また、買ってきた食材を使用せずに冷蔵庫に入れたまま管理されず、何度も同じものを買ってくることもあります。賞味期限の切れたものをわからずに食べてしまうことも珍しくないため、体調を壊しやすい状況です。
金銭管理ができない
認知症になると金銭の管理能力が低下するため、複数の口座を使い分けることは困難でしょう。支払用口座と貯蓄用口座を分けている場合もありますが、認認介護の状態では管理ができません。
銀行は、名義人が認知症であることが分かると、トラブル防止の観点から利用制限や口座凍結の措置を取ることがあります。銀行への対応もできないまま、困窮状態になるのも認認介護の問題点です。銀行からお金を引き出せず、毎月の支払いが滞りトラブルの原因になることもあるでしょう。
認認介護での介護者の現状
2019(令和元)年に厚生労働省が行った国民生活基礎調査によると、要支援1から要介護2では、全体の約半数の方が必要な時に手を貸す程度の介護量であると答えています。介護度3以降になると半日以上介護が必要と答える方が5割を占めており、要介護度4、5の方はほぼ終日介護が必要です。
しかし、認認介護での現状は、要介護1や2の方であっても、ほぼ終日の声掛けや付き添いが必要です。要介護度3になると身体介護を必要とし、昼夜を問わず問題行動が発生するため、介護者の負担は数字以上のものになります。
また、介護者の認知症の症状が進んでいくと、介護状況はさらに悪化します。
認認介護の解決策とは
認認介護の解決策としては、早期段階での専門家の介入が必須です。認知症にはさまざまなタイプがあるので、症状に見合った適切な対応が必要となります。
家族が介護を行う場合でも、間違った対応を行っていると認知症の症状悪化を招き、トラブルを引き起こしかねません。まずは、かかりつけ医や認知症専門医に関与が必要です。
専門家への相談が難しい場合には、地域の役所や包括支援センターの早期対応が必要でしょう。
在宅介護サービスの利用
認知症の方が利用できる在宅介護サービスを紹介します。
- 訪問介護介護福祉士やホームヘルパーが自宅に訪問し、介護や生活援助を行うサービス
- 訪問入浴介護自宅で入浴するのが困難な利用者の元へ介護福祉士やホームヘルパーが訪問し、入浴の手伝いを行うサービス
- 訪問看護看護師や保健師等が利用者の自宅に訪問して、医師の指示に基づいた医療処置や医療管理機器の管理などを行うサービス
- 通所介護(デイサービス)通所施設で食事や入浴などの生活支援や生活行為向上のための支援や機能訓練等を提供するサービス認知症対応のデイサービスもある
- 通所リハビリテーション介護老人保健施設や医療施設で日常生活向上のためのリハビリテーションを提供するサービス食事や入浴などを提供している場所もある
- 短期入所生活介護介護老人福祉施設などに短期間入所し、日常生活の支援や機能訓練等を提供するサービス
- 短期入所療養介護介護老人保健施設や医療施設に短期間入所し、医学的な管理の下で医療上のケアを含む日常生活における支援などを提供するサービス特に老人性認知症疾病療養病棟では、重度の要介護者の対応が可能
介護施設での同居
夫婦2人での生活を継続したい場合、夫婦が同居できる2人部屋を用意している介護施設がおすすめです。
しかし、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの公的な施設は2人部屋の設置がないため、民間が運営している老人ホームなどの施設に限ります。
民間運営の老人ホームとは、有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅のことです。特定施設として認定されていれば、介護保険で外部の在宅サービスを利用できるので、自宅にいるように専門家の助けを借りて生活できます。
また、認知症状が進み通常の施設では生活が難しいと思われる方には、認知症専門のグループホームがおすすめです。認知症専門のスタッフにより24時間生活援助が受けられるので、安心して生活できます。
地域包括支援センターへ相談
地域包括支援センターとは、介護サービスに関わる相談事を受けてくれる公的な専門機関です。
高齢者の生活をサポートしてくれる施設として、全国に3000ヵ所の設置があり、主任ケアマネージャーや社会福祉士、保健師などの介護や福祉の専門家が相談者の悩みを聞いて対応してくれます。
日常生活の困りごとの相談から、介護保険サービスの申請まで行っています。自分の地域にあるセンターの連絡先が分からない場合は、役所に連絡すれば教えてくれます。
主な利用対象者は65歳以上の高齢者の方ですが、認知症が進み自分で状況の説明ができない場合には、家族や近しい方からの相談も受け付けています。相談する方と対象者の住んでいる地域が異なる場合は、対象者が住む地域のセンターに連絡を入れましょう。
地域の人たちとの交流
高齢者の見守り活動を行っている地域もあります。地域の民生委員は、一人暮らしの高齢者宅に定期的に見守りを行う心強い存在です。また、近所の人に関して気になったことを気軽に相談でき、異変があったらすぐに対応してくれるといったシステムを作っている自治体もあります。
民間の事業者と連携して高齢者の見守りを行っている地域もあります。特に新聞や電気・ガス・水道などのライフラインは異変に気が付きやすく、おかしいなと感じたら誰かが地域の担当センターに連絡することも重要です。
高齢の両親と離れて暮らしていて心配な方は、自分の両親の住んでいる地域にどんなサービスがあるか確かめておきましょう。
また認知症の方でも入れる老人ホーム・介護施設をお探しの際には、ケアスル介護での相談がおすすめです。
ケアスル介護では施設の紹介だけではなく、見学予約から日程調整も無料で実施しています。
「後悔しない施設選び」がしたいという方は、まずは無料相談をご利用ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
まとめ:脱認認介護に向けて
家族構成の変化や医療技術の発達で、老後の生活は大きく変わりつつあります。平均寿命が伸びる中、これからも老老介護や認認介護は増加し、より大きな社会問題となっていくでしょう。
認知症はほとんどの場合、進行を遅らすことはできるものの、症状の画期的な改善は期待できません。そのため、もし夫婦で認知症になったら、自分たちだけで何とかしようと思わずに周囲に助けを求めることが重要です。
家族や夫婦の問題として抱え込まずに、積極的に専門家の助けを借りましょう。介護する側も介護される側もより楽に自分らしく生活できるよう、早めの対応を心掛けることが大切です。
認認介護の定義は、65歳以上の高齢者世帯において、認知症の方が同じく認知症の方を介護している状態です。老老介護は65歳以上の高齢者が同じく65歳以上の高齢者を介護している状態を表しており、認認介護はさらに介護者も要介護者も認知症を発症していることが前提になります。詳しくはこちらをご覧ください。
認認介護では管理能力の低下が最大の問題点として挙げられます。例えば、服薬管理ができません。薬を飲んだ行為自体を忘れてしまうため、飲んでいないと思い指定された量以上の服薬をしてしまったり、薬を飲むこと自体を忘れてしまったりして理想的に治療が進みません。詳しくはこちらをご覧ください。