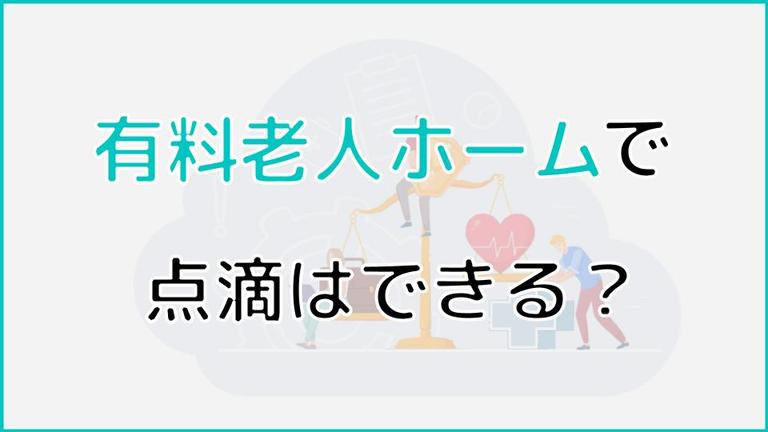「有料老人ホームで点滴ができるか不安」「点滴ができる有料老人ホームがあるか知りたい」・・・
このような疑問のある方はいませんか?有料老人ホームはいろいろな種類があり、点滴が可能な施設がどれなのか分かりにくいかもしれません。
本記事では点滴ができる有料老人ホームを選ぶコツを紹介します。また、医療が必要な場合に、施設を選ぶときの注意点を紹介します。安心した施設生活を送れるように、ぜひ本記事を参考にしましょう。
有料老人ホームでは一部施設で点滴が可能
有料老人ホームで点滴ができるかどうかは、施設によって異なります。点滴は医療の専門的な技術が必要な行為なので、医師や医師の指示を受けた看護師しかできません。そのため、点滴ができるのは、医師や看護師が配置されている施設です。
有料老人ホームは以下の3つに大きく分けられます。
- 介護付き有料老人ホーム
- 住宅型有料老人ホーム
- 健康型有料老人ホーム
それぞれの施設で特徴や人員基準が違います。そのため、点滴が可能かどうかも異なるので、施設ごとに詳しく解説します。
介護付き有料老人ホーム
介護付き有料老人ホームは、介護を必要とする方が入居して、食事や洗濯などの生活の支援、排泄や入浴などの介助、リハビリなどが受けられる施設です。
ほかの有料老人ホームと違い、都道府県から「特定施設入居者生活介護(以下特定施設)」と指定された施設だけが介護付き有料老人ホームと呼ばれます。
特定施設は、要介護認定をされた高齢者に生活の支援や介護、機能訓練などを提供する施設で介護保険の対象になります。看護師や介護スタッフの配置義務があり、以下のような基準になっています。
| 介護付き有料老人ホーム(特定入居者生活介護)における看護・介護スタッフの配置基準 | |
|---|---|
| 要支援の入居者の場合 | 要介護者の入居者の場合 |
| 入居者10人に対して1人以上の配置が必要 | 入居者3人に対して1人以上の配置が必要 |
| ただし看護師は要介護者が30人までは1人、30人を超える場合は50人ごとに1人
夜間は看護もしくは介護スタッフが1人以上 |
|
以上のように看護師は必ず1人以上の配置がされているので、介護付き有料老人ホームでは医師の指示があれば点滴ができます。しかし夜間の配置は必須ではなく、施設によって点滴などの医療行為に制限があるため確認が必要です。
ただし、医師の配置は必須ではありません。そのため医師の指示を受ける場合は、施設独自に医師を配置しているか、往診や協力医療機関など外部のサービス利用が必要です。
参照:特定施設入居者生活介護

住宅型有料老人ホーム
住宅型有料老人ホームは、自立した方から介護が必要な方まで幅広い高齢者を受け入れる施設です。食事や掃除などの生活支援や生活相談、緊急時の対応などは実施されますが、介護が必要な状態になると個人で外部の介護サービスを利用する必要があります。
介護付き有料老人ホームのような特定施設ではないため、施設長以外に人員基準は定められておらず、医療行為に対応するような基準は設けられていません。
ただし、施設によっては看護師や介護スタッフなどを手厚く配置をしており、外部の医療(往診、訪問看護ステーションなど)、介護サービスと連携しながら、点滴が可能な場合もあります。
参照:特定施設入居者生活介護
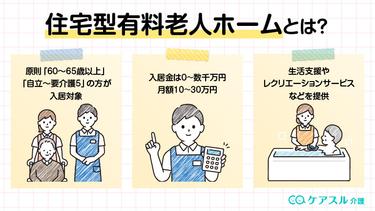
健康型有料老人ホーム
健康型有料老人ホームは、健康で自立した生活ができる方が入居する施設です。食事や清掃などの生活支援はありますが、ほかの有料老人ホームに比べて、介護などのサービスは提供されません。
元気な方が充実した生活が送れるように、アクティビティやレクリエーション、行事などのイベントが充実しており、設備も整っている施設が多いです。
看護師の配置義務はなく、施設での医療行為を想定していないため、点滴が必要な場合は外部の医療機関(病院、医院、クリニックなど)を自分で受診する必要があります。また、入退院を繰り返す、常時点滴が必要な状態になれば、施設によっては退去を求められる可能性もあるので、事前に確認をしておきましょう。
点滴を受けることができる施設を検討しているという方は、ケアスル 介護がおすすめです。ケアスル 介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができるためご希望に沿った施設探しが可能です。
「プロに相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
点滴が可能な有料老人ホームを選ぶ5つのポイント
有料老人ホームでも点滴が実施できる施設があります。そのような施設を選ぶために、以下の5点を確認しましょう。
- 介護付き有料老人ホームを選ぶ
- 看護師が常時配置されている
- 医療機関に隣接している
- 訪問看護ステーションが併設されている
- 医師の往診が充実している
それぞれのポイントについて、詳しく解説します。
介護付き有料老人ホームを選ぶ
介護付き有料老人ホームは看護師の配置が義務付けられているので、医師の指示があれば点滴を実施できます。医師の指示は以下の形で出されます。
- 医師が施設に配置されている
- 主治医や協力医療から往診に来る
- 病院やクリニックを受診する
夜間に看護師を配置する義務はないため、常時点滴が必要な場合は、介護付き有料老人ホームであっても点滴が不可能な可能性が高いです。ただし、夜間にも看護師を配置している施設(看護師:24時間配置)もあるので、入居を検討する場合は事前に確認しましょう。
看護師が常時配置されている
看護師が24時間配置されている有料老人ホームでは夜間の点滴に対応できます。また、通常の人員配置以上に看護師を配置している、経営母体が医療法人である、病院と隣接している、病院との連携を特徴としている時点で、手厚い医療サービスの提供を強みにしている施設といえます。
前述のように看護師のみでは医療行為ができないのは変わりありませんので、医師との連携をしっかり取れる体制になっているかは確認が必要です。往診や協力医療機関との連携、施設医師や併設医療機関の有無は忘れずにチェックしましょう。
また、人員配置や医療サービスが手厚い場合、費用が高額になる可能性があります。常時の点滴などの医療行為は通常の有料老人ホームでは想定されていないため、希望する場合は費用面も検討する情報に加えましょう。
医療機関に隣接している
施設に医療機関に隣接していると、その医療機関から医師や看護師が来て、点滴などの医療行為が可能な場合があります。急変時なども迅速に対応可能で、優先的に入院もできる場合があるので、安心感があります。
特に医療法人が運営している有料老人ホームは、法人内の医療機関が対応できる体制を整えている場合が多いのが特徴です。そのため、有料老人ホームの運営主体がどのような法人なのかもチェックするとよいでしょう。
訪問看護ステーションが併設されている
住宅型有料老人ホームや外部サービスに委託している介護付き有料老人ホームでは、訪問看護を利用すれば点滴などの医療行為が可能です。特に施設に訪問看護ステーションが併設されていれば、常時対応しやすく、夜間でも訪問看護ステーションからのサービスを受けることも可能です。
訪問看護ではかかりつけ医や主治医の指示が必要になります。介護保険サービスで訪問看護を利用する場合は介護サービス計画に位置づけられていなければいけません。担当のケアマネジャーに相談して利用を進めることになります。
また、訪問看護と小規模多機能型居宅介護が一緒になった「看護小規模多機能型居宅介護」や24時間の訪問介護や訪問看護に対応する「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」などのサービスでも訪問看護が利用できます。
いずれにしても担当のケアマネジャーに相談して、点滴を含めた医療ニーズに対応できるサービスを活用しましょう。
医師の往診が充実している
医師の往診が十分な場合、施設内の看護師や外部の訪問看護と連携して、点滴を受けられます。施設が医療機関と提携あるいは、法人内の医療機関と隣接していると、24時間の医師による対応が可能な場合もあります。
医師の頻回の訪問は難しいため、実際の医療行為は看護師が実施するケースが多いです。医師の往診だけでなく、医師と看護師との連携がどのように行われるのか確認しましょう。
点滴だけではない!有料老人ホームで可能な医療
有料老人ホームで可能な医療行為は点滴だけではありません。看護師が配置されている場合、さまざまな医療行為の提供が可能です。
また、介護スタッフは医療行為の提供はできませんが、専門的な技術や知識を必要としない「医療的なケア」を実施することができます。そこで、各職種がどのような医療が提供可能か具体的に紹介します。
看護師が提供可能な医療
看護師は医師の指示があれば点滴以外の医療行為も提供できます。しかし、すべての医療行為が可能なわけではなく、手術や処方など医師にしか許されていない医療行為は実施できません。看護師が可能なのは以下のような行為です。
- 痰の吸引
- 褥瘡(じょくそう)の処置
- 在宅酸素を使用されている方の管理
- 人工呼吸器の管理
- インスリンの注射
- 導尿
- 中心静脈栄養(心臓に近い静脈から点滴による栄養補給)
- 経管栄養(胃や腸からチューブを使用して栄養剤を注入)
- バルーンカテーテルの管理
- ストーマ装置の取り替え
ただし、看護師が配置されているからといって、すべての有料老人ホームで医療行為が提供されるとは限りません。医師の指示がないと実施できません。また、施設の方針にもよります。入居前にどのような医療行為が受けられるか(可能か)を詳しく確認をしましょう。
介護スタッフが提供可能な医療
介護スタッフは医療行為が原則できません。しかし以下の内容は医師や看護師などの免許を持っていないスタッフでも可能な行為とされています。
- 水銀体温計や電子体温計で腋窩の体温を測定する
- 自動血圧測定器で血圧を測定する
- 入院治療の必要がない方の酸素飽和度を測定するためにパルスオキシメータを装着する
- 汚物で汚れたガーゼを交換する
- 絆創膏を貼るなど軽い傷に対して簡単な処置をする
- 皮膚への軟膏を塗る(褥瘡の治療を除く)
- 湿布を貼る
- 点眼薬を注す
- 爪や爪周辺に異常がない場合に爪を切る(ヤスリをかける)
- 重度の歯周病などがない場合に口腔内を清掃する
- 耳垢を取り除く
- ストーマ装置にたまった汚物を捨てる(肌に装着したパウチの取り替えは不可)
介護付き有料老人ホームでは夜間に介護スタッフまたは看護スタッフの配置が義務付けられているため、これらの行為に対応可能です。
また、介護スタッフでも指定の研修を受けた場合に限り以下の医療行為が実施できます。
- 喀痰吸引(吸引装置を使用して口や鼻、気管切開後に装着する管から痰を吸引する行為)
- 経管栄養(自力で食事ができない方の胃や腸にチューブを挿入して栄養剤を注入する行為)
実施するためには医師の指示や看護師との連携、本人・家族の同意が必要といった条件があります。希望する有料老人ホームで対応できない場合もあるので注意しましょう。
点滴が必要なときに有料老人ホームを選ぶ際の3つの注意点
「5つの勘所」を踏まえて施設を検討すれば、点滴が可能な有料老人ホームを探せるかもしれません。しかし、施設の種類や人員配置を確認するだけでは見落とす部分もあります。
そのため、点滴を優先して有料老人ホームを選ぶ場合でも、「注意したい3つのポイント」を紹介します。
人員配置だけでなく、サービス内容をチェックする
人員配置が充実していても点滴などの医療行為に対応できるとは限りません。施設によって提供されるサービスが違うため、必ず事前に確認しましょう。例えば看護師が夜間配置されていても、常時の点滴が不可能な場合もあります。
逆に人員配置で夜間の看護師を配置していなくても、隣接している医療機関や訪問看護ステーションの利用で点滴に対応できる施設もあります。
また、介護スタッフの配置が充実していても、常時の介護に対応しておらず、夜間は見守りのみといった場合もあります。
そのため、入居前に施設の相談員や管理者と面談して、点滴が受けられるかどうかをしっかり説明を聞きましょう。
点滴以外に「どこまで対応できるのか」をチェックする
有料老人ホームへ入居して必要になるのは点滴だけではありません。ほかの医療行為や重度の介護が必要になった場合に対応できるか確認をしておきましょう。
対応が難しい状態になると退去を求められるケースもあります。見学のときに直接相談したり、重要事項説明書や契約書に目を通し、具体的に確認しましょう。
また、終末期における「看取り」が可能かも、大切な要素です。かならずチェックしましょう。看取りとは症状の改善が見込めない方に対して、できるだけ身体的・心理的な苦痛を緩和し、人生の最期まで尊厳を保って、医師や看護師および介護スタッフが連携しながらケアを提供します。「人生会議」(ACP:アドバンス・ケア・プランニング)を行っているかどうか、施設としてどのように考えているのか、も施設選びの選択基準に加えるのもよいでしょう。
本人や家族でしっかり意志を確認して、希望の対応をしてもらえる有料老人ホームを選ぶようにしましょう。
施設の雰囲気や設備の充実度も忘れずにチェック
点滴などの医療への対応が優先される場合でも、施設を選ぶときには、施設の雰囲気や設備の充実度を確認するようにしましょう。入居される方が安心して生活を送るためには、ただ点滴ができればよいわけではありません。
施設の雰囲気を知るためには、資料に目を通すだけでなく、実際に施設を見学するのが大切です。見学では入居者とスタッフの両方の様子を確認するようにしましょう。
そのために、できるだけレクリエーションや食事など人が多く集まる時間帯に見学するのがポイントです。
また、有料老人ホームには施設によって、さまざまな特色のある設備が備わっています。例えば、趣味のための専用ルームがあれば入居後も楽しく生活できるでしょう。
介護度が上がったときに使いやすい工夫(介護ベッド、移動用車いす、移動・移乗リフト、特殊浴機器)がされている点も大切です。廊下の幅やトイレの広さ、手すりなどの設置状況を確認しましょう。
施設選びで失敗したくないという方は、ケアスル 介護がおすすめです。ケアスル 介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができるためご希望に沿った施設探しが可能です。
「プロに相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
希望の有料老人ホームで点滴ができない場合の対策を紹介
希望して入った有料老人ホームで点滴が必要になっても、施設で対応が難しい場合があります。その場合、点滴が可能な施設に移らなければいけません。
急に施設を探す必要になっても困らないように、具体的に候補になる施設を紹介します。点滴以外にもニーズに合った施設を選ぶために各施設のサービス内容も参考にしましょう。
介護医療院や特養(特別養護老人ホーム)に移る
医師や看護師が配置されており点滴が可能な介護施設として、介護医療院や特養(特別養護老人ホーム)があります。
介護医療院は長期間の治療が必要な方が介護を受けながら生活をする施設です。病気の治療も想定された施設ですので点滴やほかの医療行為も対応できます。
特養は病状が落ち着いた介護が必要な方が入居する施設で、原則要介護3以上の方しか入居できません。看護師の配置が義務付けられているため、点滴などの医療行為が実施できます。
しかし、医師は非常勤でも可能で、看護師は夜間の配置は必須ではないため、常時の点滴は難しい場合があります。その分、特養は有料老人ホームや介護医療院に比べると費用が安いのが特徴です。
医療が充実した有料老人ホームに移る
有料老人ホームの中には、医師や看護師を常時配置したり、隣接した医療機関と密に連携をとったりして、手厚い医療を提供する施設があります。点滴はもちろん、末期がんや人工呼吸器を使用する方の受け入れが可能な施設もあります。
有料老人ホームの生活を継続したまま、点滴が受けたい場合は、このような施設を探してみましょう。ただし、費用が高額になる可能性があるため注意しましょう。
有料老人ホームでも点滴が可能な場合も!施設によって異なるためしっかりチェックしよう
有料老人ホームでも点滴を受けられる施設はあります。しかし、施設の種類や人員配置、利用できるサービスなどによって対応が異なるため事前の確認が大切です。本記事で紹介した施設選びのコツや注意点を確認して、点滴が可能な施設を探してみましょう。
また、入居中に点滴が受けられない場合、別施設の検討が必要になります。施設の種類はさまざまですので、本記事を参考にしながら、家族が安心して生活できるような施設を選びましょう。
有料老人ホームでも医師や看護師が配置されている、外部の訪問看護を活用する、往診をしてもらう、などで点滴が受けられる場合があります。これらは施設によって異なるので、事前にしっかり確認しましょう。詳しくはこちらをご覧ください。
点滴以外の医療に関しては、配置されているスタッフや施設の取り決めによって受けられるものが異なります。入居する前に人員配置や施設の決まりを確認しましょう。また、点滴と同様に外部の訪問看護ステーションや協力医療機関との連携で受けられる医療もあります。合わせて確認しましょう。詳しくはこちらをご覧ください。