特養はほかの施設に比べて月額費用が安いうえに終身利用もできますが、そのぶん人気もあり1年以上入所を待たされるというケースは決して珍しくありません。そんな特養ですが、じつは世帯分離をすれば安い費用をもっと抑えられる可能性があります。本記事では、特養の入所で世帯分離をするメリット・デメリットについてご紹介します。

世帯分離を知れば特養(特別養護老人ホーム)の費用対策にもなる?
世帯分離とは、同じ住所で登録している住民票を親と子の2世帯に分けることです。世帯を分けるだけでもじつはいくつかのメリットが得られます。
そもそも特養に入所すると、多くの方が住民票を施設の住所に移されます。しかし、転居後の市区町村によって介護保険料や受けられる高齢者サービスが異なるため、人によっては特養に入所したあとも住民票を移さずに施設生活を過ごす方もいるのです。
ですが、世帯分離によって世帯の合計所得額が変わるため、結果的に介護保険料や国民健康保険料が安くなる可能性があります。特養はほかの老人ホームに比べて費用が安いのが特徴ですが、それでもなるべく費用を抑えたいものです。
ここからは、特養の費用対策にもなる世帯分離について解説します。
世帯分離には費用面においてメリットがある
前述したとおり、世帯分離によって親と子の世帯がわかれると、それまで合計されていた年間の所得額の計算が変わります。そのため、所得税や国民健康保険料の自己負担額が減り、金銭的な負担を大きく減らせる可能性があるのです。
老人ホームは、施設やサービスの利用料として月額数万円以上のお金が必要になります。施設を利用している間は毎月数万円以上の出費が続くので、それが長期的に続くとなると大きな負担になってしまうかもしれません。
ですが、世帯分離によって所得の合計額が少なくなると、高額介護サービス費支給制度を利用できるようになります。高齢介護サービス費支給制度とは、介護保険を利用してサービスを受けた場合、自己負担額が1ヵ月の上限額を超えると、超過した費用の一部が返還される制度です。
特養に入所したあとも費用面の対策をしていきたいという方は、世帯分離を活用してみてもよいでしょう。
特養(特別養護老人ホーム)の入所者が世帯分離をすると減らせる5つの費用負担額
これから特養に入所される方にとって、世帯分離は金銭的な負担を減らすためにとても有効的な方法です。毎月の自己負担額をすこしでも減らしたいなら、世帯分離をするだけですぐに費用負担が減っていると実感できるかもしれません。
ここでは、世帯分離のメリットを費用負担という点に着目してご紹介します。すこしでも特養の金銭的な負担を減らしたいとお考えでしたら、これからご紹介する内容をぜひ参考にしてみてください。
1.所得税
高齢の親と同居している方の場合、世帯を一緒にしているとより収入額の高い方の所得で計算されてしまうため、所得税が高くなってしまいます。所得税が高くなると支払う税額が高くなってしまうので、金銭的な負担が大きくなってしまうのです。
ですが、世帯分離によって世帯の収入額が減ると、それに応じて所得税が減るので、介護を受ける親の支払い税額も減ります。今まで高齢の親を扶養していたという方は老人扶養控除が受けられなくなるので負担は増えるかもしれませんが、高齢の両親側の負担は減るのです。
収入が公的年金だけになった場合、65歳に満たない方は受給額が108万円以下、65歳以上の方は受給額が158万円以下の場合、所得税を払う必要がありません。
課税対象となる所得は、年金受給額から基礎控除と公的年金等控除を差し引いた金額で計算されます。しかし、年齢に応じて設定されている受給額を下回った場合、課税対象となる所得が0円になるので支払いが発生しません。
世帯分離によって、それまで高齢の親を扶養していた方にとってはデメリットとなる部分もありますが、所得税の点で考えるとお得になります。
2.特養(特別養護老人ホーム)の自己負担額
公的介護保険の利用による自己負担の合計額が1ヵ月あたりの上限額を超えた場合、市区町村に申請すれば、費用の一部が払い戻される高額介護サービス費支給制度が利用しやすくなるので、介護費用の自己負担額が減ります。
また、特養に入所される場合は介護保険を適用して費用の負担を軽減するのが一般的ですが、介護保険の自己負担額は所得金額によって異なります。
【65歳以上の人が世帯に1人の場合】
| 1割負担 | 本人の合計所得金額が160万円未満、もしくは本人の年金収入とその他の
合計所得が280万円未満 |
| 2割負担 | 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で年金収入とその他の
合計所得が280万以上、もしくは本人の合計所得金額が220万円以上で年金収入 とその他の合計所得が340万円未満 |
| 3割負担 | 本人の年金収入とその他の合計所得が340万円以上 |
【65歳以上の人が世帯に2人の場合】
| 1割負担 | 本人の合計所得金額が160万円未満、もしくは本人の合計所得金額が
220万円未満で本人と同一世帯の65歳以上の方の年金収入とその他の 合計所得が346万円未満 |
| 2割負担 | 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で本人と同一世帯の
65歳以上の方の年金収入とその他の合計所得が346万円以上 、もしくは本人の合計所得金額が220万円以上で本人と同一世帯の65歳以上の 方の年金収入とその他の合計所得が463万円 |
| 3割負担 | 本人の合計所得金額が220万円以上で本人と同一世帯の65歳以上の方の
年金収入とその他の合計所得が463万円以上 |
このように、世帯分離によって所得金額が減ると介護保険料の自己負担額が減るのです。
3.国民健康保険料の負担額
国民健康保険料の負担額は、前年の所得の合計額によって異なります。
前年度の合計所得額が高いほど国民健康保険料の負担額も大きくなるという仕組みなので、収入が年金収入のみの高齢者が収入の多い方と世帯を一緒にしていた場合、国民健康保険料の負担額が増える可能性があります。
ですが、世帯分離は所得税と同様に世帯収入をわけるので、結果的に世帯の総収入が減り、国民健康保険料の負担額が減るのです。
高齢になり身体機能や認知機能が低下すると、働いてお金を稼げなくなったり、働ける場所がほとんどなくなったりするので収入が年金収入のみとなる場合が多いです。自立した生活が難しくなって特養に入所した場合、ほかの老人ホームに比べて費用は安いとしても、毎月数万円程度の自己負担額が発生します。
特養に入所してから支払いができなくなってトラブルの原因にならないように、世帯分離によって国民健康保険料の減額を検討してみてもよいでしょう。
4.公的施設の負担額
世帯収入によって、公的施設での自己負担額を軽減できる介護保険負担限度額認定制度を利用できる可能性があります。一般的な介護保険サービスの自己負担額は1~3割程度ですが、介護保険負担限度額認定制度によって自己負担総額を減らせる可能性があります。
介護保険負担限度額認定制度には4段階の世帯収入の条件が設定されています。特養に入所した際のそれぞれの条件を表にまとめて解説します。なお、食費カッコ内はショートステイの金額となります。
| 段階 | 適用条件 | 食費 | (個室・ユニット型) | 個室的多床室・ユニット型 | 従来型個室 | 多床室 | 多床室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者
・本人の資産が1000万円以下(夫婦の資産が合計2000万円以下) |
300円
【300円】 |
820円 | 490円 | 320円 | 0円 | 0円 |
| 第2段階 | ・本人の前年の年金収入金額等が80万円以下の者・本人の資産が650万円以下(夫婦の資産が合計1650万円以下) | 390円
【600円】 |
820円 | 490円 | 420円 | 370円 | 370円 |
| 第3段階
(1) |
・本人の前年の年金収入金額等が80万円超120万円以下の者・本人の資産が550万円以下(夫婦の資産が合計1550万円以下) | 650円
【1000円】 |
1310円 | 1310円 | 820円 | 370円 | 370円 |
| 第3段階(2) | ・本人の前年の年金収入金額等が120万円を超える者・本人の資産が500万円以下(夫婦の資産が合計1500万円以下) | 1360円
【1300円】 |
1310円 | 1310円 | 820円 | 370円 | 370円 |
| 第4段階 | ・市区町村民税課税者がいる世帯・別世帯の配偶者が市区町村民税課税者・第1段階から第3段階(2)までの各判断基準を超えている | 施設設定額 | 施設設定額 | 施設設定額 | 施設設定額 | 施設設定額 | 施設設定額 |
このように、世帯収入によって負担段階・負担限度額が異なります。施設によって居室タイプの利用料金に差があるので、不明な点があればケアマネジャーもしくは施設にお問い合わせください。
5.後期高齢者医療制度の保険料
後期高齢者医療制度とは、75歳以上のすべての高齢者および前期高齢者にあたる65〜74歳のうち一定の障害があると認定された方が加入する医療保険制度です。それまで適用されていた老人保健制度に代わり、2008年(平成20年)4月から施行が開始された制度です。
75歳を超えた時点で後期高齢者医療制度の保険対象者となり、新たに後期高齢者医療制度の保険証が交付されます。後期高齢者医療制度を適用すれば、医療機関での自己負担額を1割程度に抑えられますが、そのためには保険料を納付する必要があります。
ほかの税金制度と同様に、後期高齢者医療制度の保険料も世帯の合計所得額によって変動するので、世帯分離によって世帯の合計所得額が減ると保険料の負担額も減る可能性があるのです。
※出典 厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
特養(特別養護老人ホーム)の入所者が世帯分離をすると費用に影響はでる?
「特養に入所している人が世帯分離をすると特養にかかる費用に影響はあるのかな?」と疑問に思った方もいらっしゃるかもしれません。
特養へ入所している方が世帯分離をすると、じつは手当の面で影響が出てしまいます。また、税金の支払い額に影響が出る場合もあるのです。
どのような手当てに影響が出てしまうのか、また手当以外にも何か影響が出てくるのかなど世帯分離におけるデメリットをご紹介します。
1.手続きに手間と時間がかかってしまう
世帯分離をするためには必要な書類を揃えてお住いの市区町村に申請をする必要があり、この手続きが人によっては手間となります。
世帯分離をするためには、市区町村の窓口で「世帯変更届」を提出する必要がありますが、届け出ができるのは、本人・世帯主・同一世帯の方あるいは委任状を持った代理人だけです。同一世帯の方や代理人が申請する場合は、たとえ親族の方であっても委任状が必要なのでご注意ください。
必要な書類は、以下のとおりです。
- 本人確認書類
- 国民健康保険証
- 世帯変更届
- 印鑑
※本人確認書類は以下のいずれか
・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート・写真付き住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書のいずれか1枚
・写真なしの住民基本台帳カード、健康保険証、・年金手帳、国民年金、厚生年金または船員保険の年金証書などのいずれか2枚
このように、世帯分離をするためには所定の手続きと書類が必要になり、お住いの市区町村の担当窓口で手続きを行う必要があります。
2.扶養手当などの各種手当が受けられなくなる
世帯分離をすると、高齢の親が扶養から外れることになるため、毎月支給されていた扶養手当や家族手当を受け取れなくなる可能性があります。
扶養手当や家族手当が受け取れなくなると、それまで扶養控除を受けていた分の費用が給与から引かれてしまうので、高齢の親を扶養に入れていた方にとってはデメリットになります。また、扶養を外れてしまうと、保険組合のサービスを受けられなくなるため、扶養から外れたご家族は健康保険料を自分で支払わなければなりません。
もしも高齢の親を扶養に入れていた場合、会社から支給されている各種手当や保険組合のサービスを利用した方が、結果的にお得なケースがあるので、世帯分離をする前にしっかりと確認しましょう。
もしも扶養手当などについてわからない点があれば、会社で経理を行っている方、もしくはお住いの市区町村の担当窓口で対応してくれるので、手続きの前に一度ご相談ください。
3.国民健康保険料が高くなるケースがある
人によっては世帯分離によって国民健康保険料の自己負担額が増えてしまうケースがあります。
世帯分離をした場合それぞれの世帯主が国民健康保険料を納める必要があるので、世帯主が2人になる方は両世帯の金額を合計すると以前よりも高くなってしまう可能性があるためです。
このように、人によっては世帯分離をした結果、損をしてしまう可能性もあります。ですが、税金関係は難しい用語ばかりで、計算方法も決められているのでとても難しいイメージがあるかもしれません。
国民健康保険料を含めて税金関係でわからない点があれば、年金機構が運営している全国の年金事務所で対応を行っています。人によって世帯構成や経済状況が異なりますが、その人に合った対応をしてくれるので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
特養(特別養護老人ホーム)へ入所する場合世帯分離をして費用を抑えられる場合もある
税金関係の話は専門用語ばかりなので、とても難しく感じるかもしれません。また、支払額などは決められた計算方法があるのですが、計算方法が分からずにそのまま手続きをしてしまう方もいます。
とはいえ、人によっては損をしてしまう場合もあるので、必ず専門の機関などに相談してから手続きを行うとよいでしょう。
上手に活用すれば、介護保険料や国民健康保険料の支払いが安くなる可能性があるので、本記事でご紹介した内容をぜひ参考にしてください。特養を安く利用する方法についてさらに知りたいという方は、こちらもご覧ください。
関連記事
 特養(特別養護老人ホーム)の費用を安くする方法はある? お金がない場合の対処法や、5つの減免制度まで詳しく解説カテゴリ:特養(特別養護老人ホーム)の費用更新日:2025-08-07
特養(特別養護老人ホーム)の費用を安くする方法はある? お金がない場合の対処法や、5つの減免制度まで詳しく解説カテゴリ:特養(特別養護老人ホーム)の費用更新日:2025-08-07関連記事
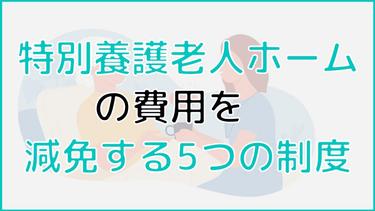 特別養護老人ホーム(特養)の費用を安くする減免制度6つを徹底解説!カテゴリ:特養(特別養護老人ホーム)の費用更新日:2025-08-07
特別養護老人ホーム(特養)の費用を安くする減免制度6つを徹底解説!カテゴリ:特養(特別養護老人ホーム)の費用更新日:2025-08-07
すべての方がそうなるとは限りませんが、場合によっては可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
親と子どもの世帯所得を分けるので、親の所得税が安くなります。詳しくはこちらをご覧ください。





