介護が必要な家族を老人ホームへ入居させたいと思っているにもかかわらず、何らかの理由で入居できない状態になってはいませんか?
自身の両親や祖父母といった大切な家族とはいえ、常に介護をするのは大変なものですし、それぞれの生活を考えると自宅での共同生活は現実的ではありません。
そこで本記事では、老人ホームに入居できず困っている方へ向けて施設に入れない理由を解説します。入りやすくするコツについても併せて紹介するので、老人ホームに断られ続けている方は参考にしてください。
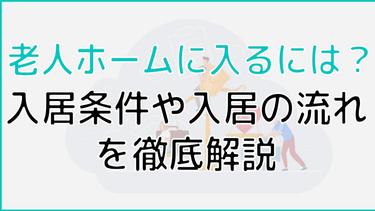
老人ホームに入れない理由
高齢者の増加とともに、老人ホームへの入居を希望する方も増加しています。しかし、全国各地で多くの方が入居待ち状態になっているのが現状です。ここでは、老人ホームに入居待ちが増えている理由について解説していきます。
要介護度による入居者の優先度がある
老人ホームの中でも特に入居希望者が多いのが、社会福祉法人などが運営する「特別養護老人ホーム」です。そして、この特別養護老人ホームに受け入れてもらえずに困っている方が多くいるとされています。これは、介護度が規定のラインまで達していないのが大きな原因となっているようです。
介護度とは介護を必要としている度合いを数値化したもので、要支援1~2、要介護1~5の7段階に分かれています。数字が大きくなればなるほど、重度であることを指しています。
| 要支援1 | 基本的な日常生活は1人でこなせるが、掃除や調理など家事の一部に手助けや見守りが必要な状態。 |
| 要支援2 | 基本的な日常生活は1人でこなせるが、入浴時に浴槽をまたいだり高いところから物を取れなかったりなど特定の動作が困難な状態。軽度の認知症が見られる場合もある。 |
| 要介護1 | 起立や歩行が不安定で、排泄や着替えといった日常生活上必要な動作を1人で行えない状態。 |
| 要介護2 | 起立や歩行が難しく、食事・排せつ・着替えといった日常生活全般で介護が必要な状態。 |
| 要介護3 | 自力での起立や歩行が難しく、食事・排せつ・入浴といったすべての動作に介助が必要な状態。 |
| 要介護4 | 自力での起立や歩行がほぼ不可能で、食事・排せつ・入浴といったすべての動作に介護が必要な状態。認知機能の低下によって理解力に乏しく、コミュニケーションも取りづらい。 |
| 要介護5 | 寝たきり状態で、食事や排せつ・寝返りまで24時間全面的にサポートが必要な状態。認知機能も大きく低下しており、コミュニケーションを取るのも困難なケースが多い。 |
「特別養護老人ホーム」に入居するためには、上記に挙げた要介護3以上の認定が必要です。そのため、要介護2以下の方を介護していて自宅での面倒は見切れないために、特別養護老人ホームを探していても入れる施設が見つからない可能性が高いといえます。
老人ホームの数が足りていない
生活インフラの安全性の向上や医療技術の発展によって人々が長寿化した影響により、介護を必要とする高齢者が増えています。介護需要の高まりに合わせて老人ホームの建設数も増加傾向となっているのですが、実際に入居できる老人ホームの数は不足しているといわれています。
これは、空間的な空きはあっても入居者の介助や生活サポートに回せるスタッフの手が足りていないため、新規の入居者を制限している施設があることや、医療ケアや看取り対応が必要な利用者を受け入れる体制ができないなどにより、入所が難しいのが現在の老人ホームの現状です。
空室のある老人ホームを探しているという方はケアスル介護で探すのがおすすめです。
入居相談員にピッタリの施設を提案してもらえるので、初めての施設探しでもスムーズに探すことが出来ます。初めての老人ホーム探しで何から始めればよいかわからないという方はぜひ利用してみてください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
老人ホームに受け入れを拒否される主な理由
ここからは、老人ホームへの入居を断られる主な理由について詳しく解説します。
入居に必要な条件を満たせていない
老人ホームでは、それぞれ入居要件が決められています。
| 特別養護老人ホーム | 原則要介護3以上 |
| 介護老人保健施設 | 要介護1以上 |
| グループホーム | 入居希望者の住所と施設の所在地が同一市町村である
65歳以上かつ要支援2~要介護5の方 など |
上記に挙げたのは、あくまでも一例です。老人ホームにはほかにもさまざまな種類があるうえ、施設ごとに細かい規定を設けているケースが多くあります。条件を満たせていないと、入居申請しても許可してもらえないので、施設を選ぶ際には事前に条件の確認をしておくとよいでしょう。
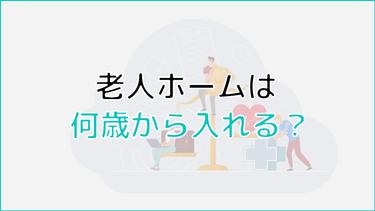
継続的な医療行為が必要である
持病によって医療行為を継続的に受ける必要がある場合、施設側から入居を断られる可能性が高いとされています。これは、病気が悪化した場合のリスクを考えて慎重になっているためです。
例えば糖尿病を抱える方であれば定期的なインスリン注射が必要であったり、呼吸器の病気を患っている方であれば日常的に在宅酸素吸入器を使用しなければならなかったりするケースが多いでしょう。このような方が施設内に増えてしまうと、スタッフが業務過多となり入居者の安心な生活サポートができなくなってしまう可能性があります。そのため、医療行為が常に必要となる方の受け入れは拒否する施設が多いのです。
暴力的な言動や行動がみられる
認知症を患っていて暴力的な言動の症状が出ており、ほかの入居者の方や老人ホーム施設のスタッフに危害が及ぶと判断された場合、対応困難と判断されて受け入れを拒否されてしまうケースもあります。
ただし、暴力的な言動を取る高齢者を受け入れるかどうかの基準は施設によって異なるため、1つの施設で断られたとしてもほかの施設であれば入居を許可してくれる場合もあります。そのため、暴力的な言動や行動が本人に見られる場合には施設へ相談するとよいです。
感染症がある
インフルエンザやノロウィルス、結核といった感染症を患っている方は入居を断られる場合が多いです。これは、施設内で感染症が蔓延してほかの入居者を命の危険にさらす可能性があるためとされています。実際、結核は過去に高齢者施設で集団感染を発生させている事例があります。
そのため、感染症に関しては施設側も慎重になっているのです。しかし感染症の中でもすでに明確な対処や対策がある者に関しては入居を受け入れてもらえる場合があります。どうしても施設へ入居させたいからといって施設側へ感染症があることを伝えないでいると、集団感染でほかの入居者の健康状態が悪化したり訴訟問題に発展したりと大きな問題に発展してしまう可能性が高いので、申し込む際に必ず伝えましょう。
比較的入居しやすい老人ホームとは
老人ホームと一言でいっても、その中には数多くの種類があります。前項では「特別養護老人ホーム」は入居が難しいケースが多いと紹介しましたが、それ以外では入居しやすい施設もあるのです。ここからは、比較的入居しやすい老人ホームを紹介します。
利用料を払って入れるサービス付き高齢者向け住宅
「サービス付き高齢者向け住宅」は、老人ホームでありながら住宅に位置づけられている施設です。
「サービス付き高齢者向け住宅」には「一般型」と「介護型」の2種類の施設があり、「介護型」を選択した場合は専門の介護職員が必要な介護のサービスを提供します。
「一般型」「介護型」ともに通常の賃貸物件同様に「賃貸契約」の締結が必要で、利用中は月額で賃料を支払う必要があります。個々が利用したサービスによって料金は加算されるので、月額費用は入居者ごとに異なるのが特徴です。
外出や外泊がしやすい自由度の高さも特徴で、老後を悠々自適に過ごしたい方に最適といえます。
共同生活が人を選ぶため入りやすいケアハウス
「ケアハウス」は利用者の経済的な負担が小さい「軽費老人ホーム」にあたる施設です。家族のサポートを受けられない方や、単身生活に不安を感じている方が安心して暮らせるサービスを展開しています。
「ケアハウス」は「一般型」と「介護型」の2つに分かれており、「一般型」では家事などの日常生活サポートが受けられるようになっています。「介護型」では日常生活のサポートに加え、介護を受けることが可能です。
ただし入居希望者が多く、一定の入居待ち期間が発生する点が難点となっています。
老人ホームに受け入れを拒否された際の対処法
本人の状態に合う施設を選んだとしても、受け入れを拒否されるケースもあるかもしれません。ここでは、受け入れ拒否をされた場合の適切な対処法を紹介します。
拒否の理由を聞く
まずは、どういった理由で受け入れを拒否しているのかを確かめるのが大切です。施設側がネックに感じている部分を取り除ければ、入居を許可してくれる可能性があるためです。
例えば施設側で対応困難な医療行為がネックになっているのであれば、主治医に相談すると簡単な医療処置に変更してもらえるケースもあります。処置が簡単なものに変更されれば、施設側の負担も減るため受け入れてもらえる可能性が高いでしょう。
老人ホーム側から納得できない理由を説明された場合には、役所などに話すと解決に向かう可能性があるので諦めずに相談してみるとよいです。
ほかの施設を検討する
1つの老人ホームで断られたとしても、受け入れ基準が異なる別の老人ホームでは入居が許可される場合もあります。ネックになっている部分に対処が可能な施設を探してみるとよいです。
また、選択肢を限定するのではなく可能な限り多くの老人ホームへ入居の問い合わせをするのも重要な点です。数を撃てば当たるわけではありませんが、多くの施設へ問い合わせると、入居の活路が開けるケースも往々にしてあるので気になる施設には積極的にアプローチをかけていくとよいでしょう。
金銭的な問題で老人ホームに入れない場合
金銭的な理由によって、老人ホームへの入居が困難になっている方もいるかもしれません。しかし、そのような方もここで紹介するポイントを押さえれば、入居が可能になる可能性があります。以下に紹介する方法の中から、活用可能なものがないかチェックしてみましょう。
介護保険負担限度額認定制度を活用する
経済的負担を減らすために、まずは「介護保険負担限度認定制度」の利用を検討するとよいでしょう。「介護保険負担限度認定制度」は特別養護老人ホームや介護老人保健施設をはじめとした、介護施設を利用する場合にかかる食費や居住費の負担を軽減してくれる制度です。
いくつかの条件をクリアする必要がありますが、受理されると「介護保険負担限度額認定証」が発行され割安で利用できるようになります。
地域包括支援センターに相談する
各地域の行政には、高齢者の生活支援を行っている「地域包括支援センター」が設置されています。
「地域包括支援センター」は、介護予防支援及び包括的支援事業を担っている場所です。介護予防ケアマネジメント業務や包括的・継続的ケアマネジメント支援業務のほか、老人ホームや高齢者介護についての相談を受け付けています。
「地域包括支援センター」は市町村だけでなく社会福祉法人や医療法人などが運営していたり、「特別養護老人ホーム」といった介護事業所に併設されていたりするケースもあります。
老人ホーム施設に入居するまでのサポートや介護についてのアドバイスが受けられるので、施設入居について悩みんでいる方は一度相談してみるとよいかもしれません。
生活福祉資金(長期生活支援資金)を利用する
入居資金が不足している場合には、社会福祉制度の1つである「生活福祉資金」を利用するのも一つの手です。
「生活福祉資金」は高齢者や障害者といった収入に問題を抱えている方々を経済的に支えるための制度で、これを利用すれば金銭的に困っている方も老人ホームへ入居できる可能性が高くなります。支援として用意されているのは、以下の4つです。
- 総合支援資金
- 福祉資金
- 教育支援資金
- 不動産担保型生活資金
この中で、老人ホーム入居に利用できるのは「福祉資金・不動産担保型生活資金」になります。利用には65歳以上かつ市町村民税が非課税世帯である必要がありますが、入居に困っている方の中には該当する方も多いでしょう。利用したい方は、まず市役所などの行政機関に問い合わせるとよいです。
老人ホームに入れない理由と対処法を把握しよう
常に介護が必要な方を、家族だけで支えるのはとても大変なものです。老人ホームへ入居の申し込みをしても断られてしまった場合には、まず受け入れ拒否の理由を施設側に聞いてみましょう。ネックになっている内容を取り除けない場合には本人の状態や予算・希望条件などの情報を整理したうえで、ほかの施設へアプローチをかけてみるとよいです。
経済的な理由から入るのが困難になっている方は、生活福祉資金などといった制度の活用を検討してみるとよいかもしれません。どうしたらよいか分からない場合は、地域包括支援センターなどに相談し必要なタイミングでスムーズに施設へ入居できるようにしましょう。
お住まいの市町村の窓口から申請できます。お近くの市役所、または地域包括支援センターへご相談ください。詳しくはこちらをご覧ください。
まずは、受け入れ拒否をする理由に正当性があるか確認してください。そのうえで、受け入れられない原因を見極めるようにしましょう。例えば受け入れ拒否の理由が継続的な医療行為の場合、主治医に相談してスタッフの負担が軽減するような医療行為に変更となれば入居できる可能性があります。性別によって部屋の空きがない場合は、空きができるまで待っていれば受け入れてくれる場合もあります。そのため、まずは受け入れ拒否の理由を聞いて施設側と条件のすり合わせをしていくのが大切です。詳しくはこちらをご覧ください。





