認知症の症状の1つである「帰宅願望」には、以下の流れで対応してみましょう。
- 話を聞く
- 「帰りたい」気持ちを受け止める
- 安心できる環境を提供する
この記事のまとめ
-
「帰宅願望」のある方に対応する際は、
①話を聞こうとするところから始めてみましょう
②相手の「なぜ帰りたいのか」を知り、その気持ちを受け入れてあげましょう
③どうしても落ち着かない場合は、少し環境を変えてみて、安心できる環境を探してみましょう
①話を聞く
まずは、帰宅願望を訴える方を避けるのではなく、話を聞こうとするところから始めてみましょう。
【実際の介護職員の方の声】
帰宅願望の強いご利用者がいて、 声をかけられるのを避ける職員。
最終的に私のところに『ちょっと聞きたいんだけど、私帰るにはどうしたらいい?』と。
帰宅願望の強い方に対して適当にあしらうほど、その症状は酷くなり、対応が大変になる。
避けるより『踏み込む』のがとても大事。
参考:Xの投稿より引用
②「帰りたい」気持ちを受け止める
話を聞いても、相手の「帰りたい」という気持ちを理解し、受け止めようとする姿勢がなければ、相手は「帰りたいのに何で止めるのか」「自分の邪魔をするな」と怒ってしまうこともあります。
【実際の介護職員の方の声】
放置されてて帰宅願望出て不穏、話し方が威圧的すぎて介護拒否される、説明を高音早口で行うから誰も理解できずレクリエーション失敗、駄弁ってて転倒やら徘徊見落とす等々…
こんなにやらかしててなんで自信満々なのうちの介護士達
参考:Xの投稿より引用
- コミュニケーションのスピードはゆっくりと
- 「主人の御飯が気になった」「子どもが帰って来る時間だ」など、相手の「なぜ帰りたいのか」という理由を聞くようにする
- 間違った感情や現実的に起こりえない話をしていても否定はしない
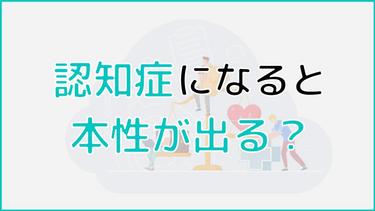
③安心できる環境を提供する
帰宅願望を訴える方と丁寧にコミュニケーションを取っても、徘徊が始まりウロウロしたり、扉を叩いたりと、何をしても落ち着かないこともあるでしょう。
そんな時には、今いる環境を変えてみて、相手が安心できる環境を探してみましょう。
【実際に帰宅願望のある方の介護をされている方の声】
午前中から高齢者の帰宅願望がマックスだったので、高齢者の実家までドライブ。親戚の皆様、ありがとうございました
ファミリーマートのカフェラテ(ヘーゼルナッツシュガートッピング)でご満悦。明日は雪の予報なので、暖かいうちに活動量を増やします
参考:Xの投稿より引用
また、帰宅願望のある方の安心できる環境として、介護施設への入居を検討したい方は、ケアスル介護での相談がおすすめです。ケアスル介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことが可能です。
自分一人だけで対応しようとせず、まずはケアスル介護で無料相談をしてみてはいかがでしょうか。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
帰宅願望対応のケーススタディ
ケース①:Aさんの場合
夕方なるとソワソワする専業主婦だったAさん。夕方以外の時間は落ち着いて過ごしています。夜もトイレ以外は徘徊もなく、よく眠れており、不安の訴えはありません。帰宅願望が強くなる時間は夕方です。毎日夕方になると、「帰りたい」と荷物をまとめます。
どのような声掛けが望ましいでしょうか?
行動は毎日夕方になると始まります。ゆっくりAさんの話を聞くと、ご主人や息子さんが帰ってくるからその前に自宅に戻って食事の用意をしたいから帰りたい気持ちが強いです。
実際、ご主人は昨年亡くなっており、息子さんは隣町で家庭を持って過ごしています。
現実を説明してもAさんは納得がいかないでしょう。認知症の症状の1つである見当識障害があるため、時間や場所などの感覚が薄れているからです。
この場合、まずは話を聞いてAさんの気持ちを受け入れましょう。受け入れたうえで、ご主人や息子さんは仕事中のため、こちらで過ごしてほしいと頼まれている旨を伝えます。ここでは「仕事中だから待ちましょう」など「○○だからすぐは難しい」事実を正しく伝えるのが重要です。
一方で正しいとはいえ直接、「ご主人は昨年亡くなりました」など、事実を伝えると混乱してしまいます。また、信じてもらえず、怒りっぽくなる、攻撃的になる恐れもあります。「仕事中なので終わったら連絡をもらって食事の用意をしましょう」と声を掛けると不安なく過ごせ、ご家族は安心されるでしょう。
ケース②:Bさんの場合
毎日帰らなければ…と尋ね歩いているBさん。自営で果樹園をご主人と経営されていました。ご主人が亡くなり、現在は息子さんが跡を継いでいますが、認知症で忘れています。
果樹園が気になって仕方がない様子です。口を開けば「いつ家に帰れる?」「誰が迎えに来る?」の繰り返しが多くなりました。
どのような声掛けが望ましいでしょうか?
ご主人が亡くなった事実は認識できているため、あえては触れません。息子さんについては、ご主人の跡を継いで果樹園をやっているのを伝えても大丈夫です。Bさんの「帰りたい」「果樹園が忙しいから手伝いに行きたい」という思いについては、「帰る」「手伝う」の言葉は使用せず、果樹園での仕事など話題を変えて聞きましょう。
果樹園のがんばった話や苦労話を聞くことに徹します。話しているうちに帰りたい気持ちから自分のがんばった事実を知ってほしい、見てほしい、聞いてほしいに変わっていくでしょう。
また、「帰宅願望のある方の対応に悩んでいるため、介護施設への入居を検討したい」という方は、ケアスル介護での相談がおすすめです。
ケアスル介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことが可能です。
自分一人だけで対応しようとせず、まずはケアスル介護で無料相談をしてみてはいかがでしょうか。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
まとめ
認知症の症状の1つである「帰宅願望」に対応する際には、その場しのぎ的な対応ではなく、相手の気持ちを受け入れながら丁寧に対応することが大切です。
困ったときには、改めて以下のステップに立ち返ってみてくださいね。
- 話を聞く
- 「帰りたい」気持ちを受け止める
- 安心できる環境を提供する




