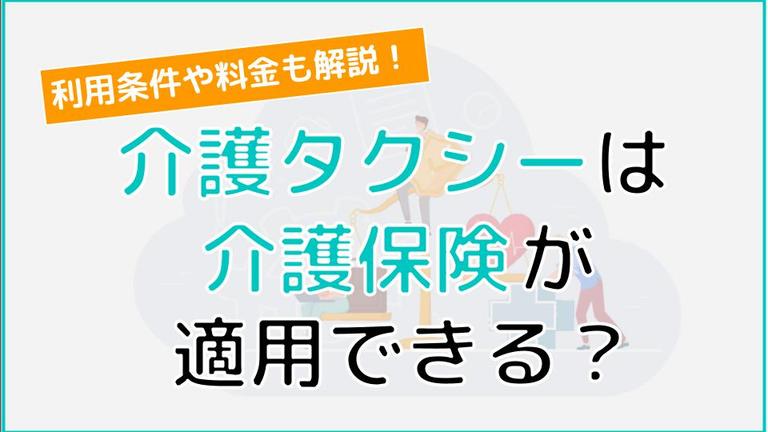介護タクシーは、介護を必要とする高齢者の方が外出する際に非常に便利なサービスです。
利用者を目的地まで送ってくれるだけでなく、介護職員初任者研修以上の資格を保有する運転手により乗降時の介助を受けることもできます。
介護タクシーには介護保険が適用されるものと、適用されないものがあり、利用にあたっての条件や料金についてよく知っておくことが重要です。
「介護タクシーって聞いたことはあるけど、そもそもどんなサービス?」
「介護保険を適用して利用するには、どうすればいいの?」
そんな疑問をお持ちの方々のため、今回は介護タクシーのサービス内容や介護保険の適用条件、料金の仕組み、利用方法まで詳しく解説していきます。

介護タクシーには介護保険が適用される
結論から言うと、介護タクシーを利用する際には介護保険の適用が可能です。
介護保険の適用対象となるのは要介護1以上の認定を受けた方で、利用の目的としては、通院や選挙投票などの「日常生活または社会生活に必要な行為に伴う外出」に限られます。
運転手は介護職員初任者研修以上の資格を保持しており、移動だけではなく乗降時の介助を受けられることは大きなメリットと言えるでしょう。
しかし、介護タクシーのなかには2種類があり、介護保険を適用できるものと、適用できないものがあります。
次項では、介護タクシーの種類について詳しく解説して行きます。
介護タクシーには2つの種類がある
介護タクシーには2つの種類があり、介護保険の適用が可能なものを「介護タクシー」、介護保険が適用されないものは「福祉タクシー」と呼ばれています。
保険が適用される「介護タクシー」は、ケアプランに含まれていれば自己負担額を軽減することができ、経済的な負担を抑えることができます。
一方で保険が適用されない「福祉タクシー」は、利用額が全額自己負担となるため、費用面での負担が大きくなる傾向にあります。
また「介護タクシー」という名称はあくまで通称であり、正式に言えば訪問介護に含まれるサービスのひとつです。
地域や行政によっては呼ばれている名前が異なる場合があるため、利用を検討する際にはケアマネージャーに尋ねてみましょう。
次に、それぞれの特徴を解説して行きます。
介護タクシーと福祉タクシーの違い
介護タクシーと福祉タクシーの違いを表で表すと、以下のようになります。
| 名称 | 介護タクシー | 福祉タクシー |
| 介護保険 | 適用できる | 不可 |
| 利用対象者 | ・要介護1以上 ・1人で交通機関を利用できない方 |
誰でも利用できる |
| サービス内容 | ・乗降介助 ・移動介助 ・外出準備介助など |
一般的には目的地への移送のみ |
| 利用目的 | 日常生活または社会生活に必要な行為に伴う外出のみ | 制限なし |
| 利用方法 | ケアプランを作成 | 福祉タクシー業者に連絡 |
介護タクシーと福祉タクシーの最大の違いは、介護保険の利用が可能であるかどうかです。
介護タクシーは介護保険の利用が可能で、要介護1以上の認定を受けた方が利用対象となっています。
1人でバスや電車などの交通機関に乗ることが困難な方のために、目的地までの移送や乗降介助を提供してくれることは大きな魅力と言えるでしょう。
利用にはケアマネージャーに相談し、ケアプランに介護タクシーの利用を含めてもらうことが必要です。
一方、福祉タクシーには介護保険が適用されないため、自己負担の金額は大きくなる傾向にあります。
しかし福祉タクシーの利用対象者に条件はなく、福祉タクシーの業者に連絡すれば誰でも気軽に目的地まで移送してもらうことが可能です。
介護タクシーは利用対象者や目的が制限されていますが、介護保険を利用し、自己負担額を抑えることができます。
福祉タクシーには介護保険が適用されませんが、利用条件などに制限がなく、自由度が高いことが特徴と言えるでしょう。
介護タクシーと福祉タクシーの違いについて、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
関連記事
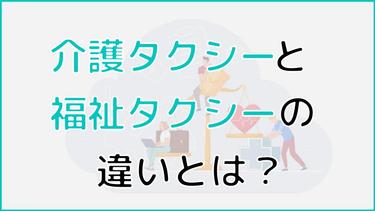 介護タクシーと福祉タクシーの違いとは?目的から対象者、料金の違いを解説!カテゴリ:在宅介護更新日:2023-02-24
介護タクシーと福祉タクシーの違いとは?目的から対象者、料金の違いを解説!カテゴリ:在宅介護更新日:2023-02-24
次項では、介護保険が適用される介護タクシーの利用条件や、サービス内容について詳しく解説して行きます。
介護施設や老人ホーム探しを検討している方は、ケアスル 介護での相談がおすすめです。
ケアスル 介護なら、約5万を超える施設の中から、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができます。
老人ホーム探しを始めた方は、ぜひケアスル 介護で相談してみてはいかがでしょうか。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
介護保険適用で介護タクシーを利用する方法①利用条件
介護保険が適用できる介護タクシーには、利用対象者や条件が厳密に定められています。
利用上のルールを正しく理解すれば、費用の自己負担を抑えながらサービスを受けることができるため、大きなメリットとなるでしょう。
介護タクシーの利用対象となる人
介護タクシーの利用対象となるのは、以下の条件を満たした方です。
- 要介護1~5の認定を受けている
- ひとりで公共交通機関に乗ることが困難
- 自宅・有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)に住んでいる
介護タクシーの利用対象となるのは、要介護1~5の認定を受けており、ひとりで公共交通機関に乗ることが困難な方です。
「要支援」の方は利用対象とならないため、注意しておきましょう。
また、介護タクシーは一般的に自宅で生活している方のためのサービスとなっています。
そのため、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの施設に入居している方も利用対象外となっているため、理解しておきましょう。
介護タクシーの利用目的
介護保険タクシーの利用目的は、「日常生活・社会生活に必要な行為に伴う外出」に限られています。
たとえば介護保険が適用される目的としては、以下のようなものが挙げられます。
- 通院(受診やリハビリなど)
- 預金の引き下ろし
- 役場での申請などの手続き
- 選挙での投票
- 補聴器やメガネの作成・調整など本人が出向かなければできない買い物
以上のように介護タクシーを利用して外出する場合は行き先が定められており、仕事や趣味、旅行など目的では利用できないことを理解しておきましょう。
受けられるサービスの内容
介護タクシーは、目的地までの往復の移送のほかにも、乗降時の介助や着替えの介助といった外出準備まで多岐に渡るサービスを提供しています。
具体的なサービスの内容を解説すると、以下のようなものが挙げられます。
出発時
- 介護タクシーが利用者の自宅まで迎車
- 着替えをはじめとする外出準備の介助
- タクシーまでの移動や乗車の介助
目的地に到着
- 降車の介助、目的地までの移動介助
- 通院の場合、受付または受診科までの移動介助・病院スタッフへの声かけ (病院内の介助は病院スタッフが対応)
- 受診後の支払い、薬の受取
帰宅時
- 降車時の介助、自室までの移動介助
- 必要な場合は着替え・おむつ交換など
以上のように介護タクシーは乗降時の介助に限らず、外出前の身支度や、帰宅から自室までの移動もサービスに含まれています。
一般的に歩行が困難な方が車まで移動する場合は懸念点がいくつもあり、安全性に配慮したりとサポートする家族の負担が重くなるケースも多いです。
しかし、介護タクシーの運転手は介護職員初任者研修以上の資格を保有するプロのため、利用者の移動や外出を安心して任せることができます。
また乗降時には車イスやストレッチャーを使用することもでき、利用者の身体的負担も最小限に抑えられると言えるでしょう。
車椅子やストレッチャーはレンタルも可能となっており、普段外出することが少ない方にとっても便利です。
サービスを利用する際の注意点
介護タクシーを利用する際には、意点があるためよく確認しておきましょう。
家族の同乗が認められていない
原則として介護タクシーには、家族が同乗することができません。
保険適用ができる介護タクシーは正式には「通院等乗車介助」という、介助を受けることが前提のサービスとなっています。
そのため介助をしてくれる家族が同乗できるのであれば、サービスを利用する必要はないとみなされてしまうのです。
原則として、介助を必要とする利用者本人のみ乗車することになるため、よく注意しておきましょう。
しかし、認知症や精神疾患といった特別な事情がある場合は家族同乗が認められることがあるため、事前にケアマネージャーに相談しておくことが大切です。
そのほか介護タクシーに家族が同乗するケースについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
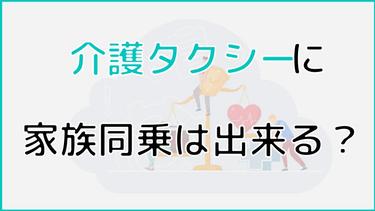
乗車介助以外のサービス扱いになる場合がある
実際に必要となった介助の度合いによっては、乗降介助以外のサービス扱いになることがあります。
以下のような状況では「身体介護」「生活援助」であると判断される場合があるため、注意しておきましょう。
- 要介護4・5の方で、外出前後の介助に20分~30分以上の時間を必要とするとき
- 外出の前後で食事や入浴、排泄の介助などで30分以上の身体介護が必要となるとき
- 外出中に日常生活品の買い物などの生活援助を行うとき
例外として、介護タクシーに運転手の以外のヘルパーがに同乗している場合は、介助内容によって「通院等の乗降介助」となるのか「身体介護」となるのかの判断が変化します。
判断の基準は介護タクシーの業者によって異なり、どのサービスとして判断されるかでサービスの単位数が変化するため、事前に細かくケアマネージャーと相談することをおすすめします。
運転手は病院内の付き添いができない
病院の中での介助は、原則として病院のスタッフが対応することになるため、運転手は病院内まで付き添いをすることはありません。
ただし、次のようなケースでは例外として運転手の付き添いが認められることがあります。
- 病院内の移動に介助が必要になる場合
- 認知症や精神疾患といった症状のために見守る必要がある場合
- 排泄介助を必要とする場合
そのほか要介護度が高く、そもそも1人では移動や手続きをすることができない状態でも、運転手の付き添いが認められます。
付き添いが認められる基準は地域の方針によって異なるため、自治体の担当窓口まで確認してみましょう。
介護保険適用で介護タクシーを利用する方法②利用料金
介護タクシーの料金は、以下の3つの要素で構成されることになります。
- 運賃
- 介助サービス費用
- 車いすなどのレンタル費用
このうち介護保険の適用対象となるのは、介助サービス費用のみとなっています。
運賃と器具のレンタル費用に関しては全額自己負担となるため、理解しておきましょう。
細かい料金はタクシー業者によって異なるため、利用前によく確認してみることをおすすめします。
次項では、それぞれの料金について詳しく解説して行きます。
運賃
運賃は、一般のタクシーと同じようなメーター料金で計算されていることが多いです。
例としては「初乗り料金2キロ750円+以降1キロごとに400円」といった計算になります。
そのほか30分ごとに1000円といった「時間制運賃」を導入している事業者もあるため、よく確認してみましょう。
また前述のとおり運賃は自費となりますが、通常の相場の半額程度で済む場合もあるため、比較的負担は少ないと言えます。
介助サービス費用
介助サービス費用には介護保険を適用することができ、「通院等乗降介助」の自己負担額は1割・1回あたり約100円での利用が可能です。
往復の場合は2回とカウントされるので、約200円ほどかかることを覚えておきましょう。
そのほか介護保険が適用されない場合は全額が自己負担となり、乗降時や外出の準備以外の介助では、以下のように費用が発生します。
- 室内介助:1,000円
- 外出付き添い:1,200円
- 病院内介助 :900円(30分)
車いすなどのレンタル費用
車いすやストレッチャーなどをレンタルする場合は、レンタルの費用がかかります。
料金は業者によって異なりますが、おおよその目安としては以下のようになっています。
- 車いす:無料~1,000円
- リクライニング車いす:1500円~2000円
- ストレッチャー:4,000円~6,000円
そのほか酸素吸入器などの医療機器のレンタルを実施しているケースもあるため、利用前によく確認してみましょう。
関連記事
 介護タクシーは料金が高い?料金の仕組みや実際の金額シミュレーションまで詳しく解説カテゴリ:介護タクシー更新日:2025-02-25
介護タクシーは料金が高い?料金の仕組みや実際の金額シミュレーションまで詳しく解説カテゴリ:介護タクシー更新日:2025-02-25関連記事
 介護タクシーの料金はいくら?利用条件から金額のシミュレーションまで詳しく解説カテゴリ:介護タクシー更新日:2025-05-07
介護タクシーの料金はいくら?利用条件から金額のシミュレーションまで詳しく解説カテゴリ:介護タクシー更新日:2025-05-07
介護施設や老人ホーム探しを検討している方は、ケアスル 介護での相談がおすすめです。
ケアスル 介護なら、約5万を超える施設の中から、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができます。
老人ホーム探しを始めた方は、ぜひケアスル 介護で相談してみてはいかがでしょうか。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
介護保険適用で介護タクシーを利用する方法③利用手続き
介護タクシーで介護保険を利用するには、要介護認定を受けたあとケアマネージャーに相談することが必要です。
ケアマネージャーはケアプランを作成するだけでなく、業者を選ぶ際のアドバイスもしてくれるため、まずは気軽に相談してみることが大切です。
次項では要介護認定を受けることから、介護タクシーの利用までの手順を解説して行きます。
要介護認定を申請する
介護タクシーの利用には、要介護1~5の認定を受けていることが必要です。
まずはお住まいの自治体の窓口や地域包括センターで、要介護認定の申請を行いましょう。
要介護認定を受ける
要介護認定を申請したあとは、自治体の職員やケアマネージャーなどが自宅を訪問し調査を行います。
この際に本人の状態や家族構成、生活環境などを確認し、当日の結果と医師の意見書などをもとにして、コンピュータが1次判定を行います。
医師の意見書はかかりつけ医でも作成が可能となるので、頼みやすい人がいれば早めに相談してみましょう。
その後、審査会によって2次判定が行われ、ここで要支援や要介護度が決定します。
結果の通知までにかかる期間は地域によって異なりますが、申請からおおよそ30日程度となっています。
ケアプランを作成する
要介護認定を受けると、自治体からケアマネージャーを紹介されることになります。
ケアマネージャーは、本人の身体状況や生活ニーズに最適な介護計画を作成してくれるプロフェッショナルです。
今後の介護計画である「ケアプラン」の作成時に、介護タクシーのサービスである「通院等乗降介助」を利用したい旨を伝えましょう。
ケアマネージャーの了承のうえ、「通院等乗降介助」が含まれたケアプランを作成してもらうことにより、保険適用で介護タクシーを利用することができるようになります。
介護タクシー事業者と契約する
最後に介護タクシーの事業者と契約します。
事業者は自分で選ぶこともできますし、ケアマネージャーからアドバイスを受けることもできます。
契約する業者が決まったあとはケアマネージャーの仲立ちのもと、事業者と契約を結びます。
契約が終わった段階で、介護タクシーのサービスが利用開始となります。
介護タクシーを探す際のポイント
一口に介護タクシーと言っても、事業者はさまざまです。「どう選べばいいのか分からない…」とお悩みの方もたくさんいます。
そんな方々のために、次項では介護タクシーを選ぶ際に知っておきたいポイントを4つ紹介します。
ケアマネージャーに相談する
まず何よりもおすすめしたいのは、迷ったらケアマネージャーに相談することです。
介護のプロフェッショナルであるケアマネージャーは、サービス料金が適正か介護保険適用にあたっての注意点など、さまざまなアドバイスをしてくれます。
1から10まで自分で調べることも不可能ではないですが、手間と時間が掛かってしまうかもしれません。
信頼できる事業者の紹介や、そのほか役立つ情報を提供してくれるケアマネージャーは大きな助けとなるでしょう。
そのほかご自身で調べる際には、以下のようなポイントを確認してみることをおすすめします。
- 車いすやストレッチャーなどの乗車時のスタイル
- 付き添いは運転手のみか、別に介護士がいるか
- どのような介助に対応しているか
- 医療機器を取り扱っているか
- リフトやスロープなどの車両装備
料金設定が分かりやすいか
2つ目は利用料金を確認しておくことです。
介護タクシーでは、事業者によって運賃の計算方法が異なったり、介助の度合いによって追加料金が発生したりします。
契約してみてから予想外の料金が発生してしまうことのないように、事前に見積もりを貰うようにしましょう。
費用項目の確認や追加料金となる項目の確認をしたうえで、さらに適正な価格どうかをケアマネジャーと相談してみることもおすすめです。
運転者の技量・人柄
3つ目は、運転手の技量・人柄を見ておくことです。
本人を安心して任せられる介護スキルや運転技術があるのか、実際に本人との相性はどうか細かく確認してみることが大切と言えます。
実際に事業所でお話を聞くことも良いですが、情報収集にはインターネットの口コミを活用することも効果的です。
ウェブサイトのなかには、地域の介護タクシーをまとめて紹介しているサイトも存在します。
気になった業者があればインターネット上の情報を活用しながら、よく比較検討してみると良いでしょう。
本人が利用したいと思うか
最後は、本人が利用したいと思うかです。
事業者を選ぶときは料金やサービス内容を気にしてしまいますが、利用する本人の意思も尊重しなければなりません。
通院の際などは、基本的に本人と運転手は2人になることも多いです。
利用者のなかには、運転手との会話が生活の楽しみになるという方もいます。
長期間の付き合いになる可能性もあるため、本人と運転手の相性を考えることはもちろん、本人自身の気持ち大切にすることは忘れてはなりません。
まとめ
介護タクシーの利用に、介護保険を適用することは可能です。
介護タクシーには2種類あり、介護保険が適用可能な「介護タクシー」と、介護保険が適用されない「福祉タクシー」と呼ばれるものが存在しています。
介護保険の適用により、自己負担額を抑えて移送サービスを利用したい場合は「介護タクシー」を選ぶことがおすすめです。
利用条件には、本人が要介護認定を受けており1人で交通機関に乗ることが困難であることなどが挙げられます。
また、原則として家族の同乗は認められていないため、注意しておきましょう。
介護タクシーの料金は、運賃+介助サービス費+車いすなどのレンタル費用で計算されます。
事業者を選ぶ際は、ケアマネジャーに相談しながら進めることをおすすめします。
サービスの内容や料金が分かりづらい、運転手が信頼できるかといった諸々の不安を相談し、安心したうえで介護タクシーを利用することが大切です。