車椅子でもそのまま乗ることのできる「介護タクシー」。介護を必要とする方が増加するなかで、この介護タクシーの利用も増加傾向にあります。
介護を必要とする方やその家族の介護や移動が、介護タクシーの誕生によって実現が可能になったともいえるでしょう。
ここでは介護タクシーの利用を検討する方をはじめ「どんな人が利用できるの?」と疑問を抱える方へ、介護タクシーの特徴や介護保険での利用方法を福祉タクシーとの違いを織り交ぜながらご紹介します。
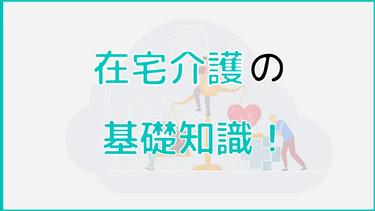
介護タクシーとは
介護タクシーは、介護が必要な方の外出をサポートしてくれる便利な社会資源です。しかし「福祉タクシー」と近藤されることが多く、違いについては分かりにくいものとなっています。
その分かりにくさゆえ、利用しようとしてもどちらを選んだらいいのか迷ってしまい、結局利用できなかったという経験をされた方も多いのではないでしょうか。
そこで介護タクシーの概要について、福祉タクシーのサービスを交えながらご紹介します。
訪問介護事業が実施する介助サービスのひとつ
介護タクシーのサービスについては、介護保険の範囲に含まれていません。一般的には訪問介護に含まれるサービスであり、通常のタクシーとは異なります。
一般的なタクシー会社が運行する「車イスが乗るようなタクシー」は、車両が特別という点を除き通常のタクシーと同様に利用できます。これが「福祉タクシー」であり、介護タクシーと線引きされているのが通例です。
つまり、介護保険が適用になるタクシーを「介護タクシー」、介護保険を使わずに乗る福祉車両を「福祉タクシー」と呼ぶのです。
しかし介護タクシーという名称は介護保険上定義されておらず、福祉タクシーとの明確な違いも法律上位置付けられているわけではありません。
行政によってはこれらの表現が異なる場合も少なくないため、介護保険サービスを利用中の方は、担当のケアマネジャーに問い合わせてみるとよいでしょう。
介護保険を利用する場合はあらかじめ確認する必要がある
介護タクシーは「介護保険の利用によって乗車可能な訪問介護が実施するサービス」です。
日常で使うタクシーのように、走行中のタクシーをつかまえて即座に乗車できるものではありません。また、利用には介護保険が適用されるため、利用条件が満たされている点や、ケアプランに組み込まれているかなどを確認のうえ、計画的な利用が必要です。
したがって、「どのような場面でどのように使えるのか」について十分に理解した上で、介護タクシーを利用する必要があります。一般的なタクシーや福祉タクシーのように使えるものではないので、利用方法について細かく把握しておくと利用時のトラブル防止にもつながるでしょう。
福祉タクシーはタクシー会社が運営する福祉車両
一般的なタクシーと同様に運行するものの、その内容は福祉車両を指すケースが多いのが福祉タクシーです。内容や名称が類似しているために介護タクシーと混同する方も少なくありません。
介護保険での介護タクシーの利用を希望していない方からすると、呼び名が違っても大きな問題にはならないでしょう。しかし、介護保険適用のタクシーを使いたい方は、誤解がないようにこの違いを知っておくと安心です。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
介護タクシーの利用対象者とサービス内容
介護タクシーと福祉タクシーの違いが理解できたところで、次は介護タクシーはどのような方が利用できるのか、どんなサービスを受けられるのかについてご紹介します。介護タクシーの利用を検討している方は、ご家族が対象となるかを確認しながら読み進めてください。
介護保険サービスで利用できる人とは
ここでいう介護タクシーとは、訪問介護のサービスの一部である「介護保険適用のもの」を指します。まずは対象者について見ていきましょう。
要支援や非該当の方は利用不可
介護タクシーは介護保険サービスの一部です。そのため要介護認定を受けた方以外の利用はできません。さらに、利用対象は「要介護1以上の方」に限定されているので注意が必要です。
また「1人で公共交通機関を使うことができない状態」である点も利用において重要な条件です。たとえば、要介護1の認定がおりていても、1人でバスに乗れる方であれば利用できません。介護タクシーの利用対象者は、自分では公共交通機関に乗車できない方である点に留意してください。
特別養護老人ホームなどの施設入居者は対象にならない
要介護認定1以上の方の中には、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などに入所している方もいますが、施設に入居される方であっても利用対象外となります。その理由は介護タクシーの利用条件は自宅で生活をしている方が利用できる訪問介護サービスの一部であるためです。
なお、長期的に泊まって利用できる施設の中には住まい扱いの場合もあります。たとえばサービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム、ケアハウスなどです。
このような施設はあくまでも住居としての位置付けであり、自宅で暮らしている方と同じように在宅サービスを使って生活しています。そのため、ケアプランに介護タクシーの利用が反映されていれば利用可能です。
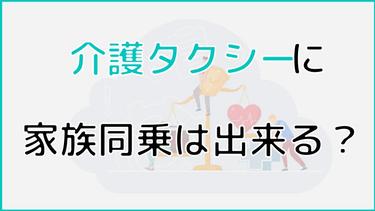
詳しい利用条件
介護タクシーの利用においては、一般的なタクシーのように好きな時間・好きな場所に移動できるものではない点に注意しなければなりません。
また、利用には介護保険法で決められた目的に合致しなければならない点やケアプランに組み込む必要があるなど、いくつかの段取りが必要です。
ここでは介護タクシーの利用において定められた条件について解説します。
日常生活ならびに社会生活上必要な行為に伴う外出のみ適用
介護タクシーの利用によって向かえる場所はある程度限定されます。一般的な利用ルールとしては「日常生活上または社会生活上必要な行為にともなう外出」に該当するかどうかです。
例えば以下のような場面において介護タクシーの利用が認められています。
- 通院
- 預金の引き下ろし
- 役場での申請などの手続き
- 選挙での投票
- 補聴器やメガネの作成・調整など本人が出向かなければできない買い物
このように介護タクシーを利用して外出する場合は行き先が限られ、仕事や趣味、旅行などにはできない点を視野に入れておきましょう。
訪問介護サービスのひとつなために移動における自由度は低い傾向にある
単なる移動手段としてではなく、外出の準備やタクシーまでの移動、乗り降り時の介助、帰宅後の着替えや排泄の介助なども介護タクシーの支援に含まれます。
受診のための利用であれば、薬の受け取りや会計も必要に応じてサポートされるため、要介護状態にある方にとっては心強いサービスといえるでしょう。
ただし、あくまでもケアマネジャーが計画するケアプランに基づいて行われる訪問介護サービスのため、計画に組み込まれない内容のサポートや介護タクシーの目的にそれることまでは対応できない点にも注意してください。
例えば、受診のために介護タクシーを利用し、その帰りにどこかに寄るといった使い方はできません。また、利用者の家族の同乗は原則不可といった決まりもあります。家族の同乗が不可な理由は、家族が介助するのであれば、乗務員が介助する必要性がないためです。
介護タクシーの利用で得られるメリット
ここまで解説したルールや利用条件などを考慮すると、介護タクシーに対する印象は人それぞれかもしれません。中には利用におけるハードルの高さを感じる方もいるでしょう。しかし、1人での外出が難しい方にとってはメリットもたくさんあります。
介護タクシーの利用によって得られるメリットは以下の4点です。
- 外出前と後の支援も受けられる
- 車への乗り降りの介助が受けられる
- 場合によっては外出先でのサポートも受けられる
- 外出に必要な車イスなどもレンタルできる
介護タクシーの乗務員は、介護職員初任者研修以上の資格を持ったスタッフに限られます。外出前の身支度や、帰宅後の着替えなどもサービスに含まれるため、ふだん外出する機会がなく不安な方も安心です。
自力での起立や歩行が困難である方が自家用車に乗車する場合、介助があっても懸念点がたくさんあります。また、介助に慣れていない家族がサポートする場合、危険性もともなう点に配慮しなければなりません。
介護タクシーを利用すれば、介護のプロが安全に配慮してサポートし、無理なく車イスやストレッチャーを使って乗り降りできるため、介助する家族の不安を最小限に抑えられるといえるでしょう。また、車椅子やストレッチャーは必要に応じてレンタルも可能であるため、特に外出頻度が少ない方にとっても便利です。
福祉タクシーは自由度が高く急ぎでの利用にも対応
ここからは、介護タクシーと混同されやすい福祉タクシーについても理解を深めていきましょう。
福祉タクシーは「介護保険関係なく利用できる、福祉車両のタクシー」です。乗務員に介護資格はなく、取得の義務もありません。外出前後や外出中の介助は受けられないものの、普通のタクシーと同様に自由に利用できるのがメリットです。
足腰が不自由で車椅子を使用する方であっても、福祉車両であるため楽に乗り降りできます。友人と会う約束をしていたり、お茶に出掛けたり、趣味の場に参加したりといった自由な使い方が可能です。ほかにも、冠婚葬祭や美容院、病院の入退院時、日用品以外の買い物、旅行など幅広く使えるのが福祉タクシーです。
介護タクシーの利用対象者であっても、急いで外出しなければならない場合やケアプランに組み込んでもらう時間がない場合は、福祉タクシーの利用も視野に入れましょう。
介護タクシーにおける基準料金
介護タクシーの利用費用は、基本的に以下の3つを合わせたものとなります。
- 運賃
- 介助サービス費用
- 車イスなどのレンタル費用
運賃は通常のタクシーと同じく距離制運賃の事業者が多いです。そのほかに、30分1,000円などの時間制になっているところもあります。
介助サービス費用に関しては、車への乗り降りやその前後、行き先での介助をどこまで依頼するかによって異なります。介護保険が適用されるのはこの部分で、自己負担割合に応じて1割~3割の費用負担で済ませることが可能です。
車椅子やストレッチャーのレンタルをする場合、各事業所が定めるレンタル料金を支払います。車椅子の場合500円程度で済むケースが多いですが、ストレッチャーになると2,000円を超える料金設定も珍しくありません。
介護保険を使用する場合
介護認定などの条件をクリアする方が、介護保険を使って介護タクシーを利用する場合、保険が適用となるのは介助サービス費用の部分です。
どこまでの介助を希望しケアプランに反映されるかは人それぞれですが、おおまかに説明すると以下のような費用が発生します。
- 通院時乗降介助(自己負担額100円~300円程度)
- 身体介護(自己負担額200円~2,000円程度)
これらの費用に、運賃と車椅子などのレンタル費用を足して最終的な金額を計算します。
介護保険を使用しない場合
介護保険を利用せずに介護タクシーを利用することも可能です。この場合、介助サービス費用が全額自己負担となりますが、福祉タクシーとは違い移動前後や移動先でのサポートを受けることができます。
- 通院時乗降介助(自己負担額1,000円~3,000円程度)
- 身体介護(自己負担額2,000円~20,000円程度)
これを見てわかるように、介護保険が適用にならない部分の費用負担が重くなるため、事前によく確認をして検討するとよいでしょう。
自治体から配布されたタクシー券の使用は事業所に要確認
お住まいの地域によっては「福祉タクシー券」が配布されるケースもあります。助成内容やその金額は障害の程度により異なり、自治体が契約するタクシー事業者のみ利用が可能です。
そのため、介護タクシーの利用時には福祉タクシー券は利用できないかもしれませんが、一般のタクシー会社が運行する福祉タクシーなら割引が受けられる可能性があります。
関連記事
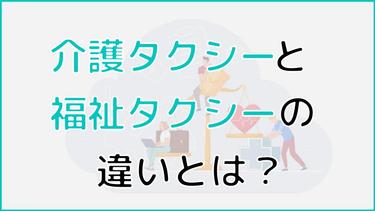 介護タクシーと福祉タクシーの違いとは?目的から対象者、料金の違いを解説!カテゴリ:在宅介護更新日:2023-02-24
介護タクシーと福祉タクシーの違いとは?目的から対象者、料金の違いを解説!カテゴリ:在宅介護更新日:2023-02-24関連記事
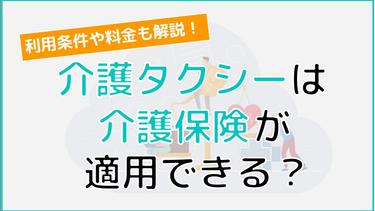 介護タクシーには介護保険が適用される?料金や利用方法まで詳しく解説カテゴリ:介護タクシー更新日:2025-05-07
介護タクシーには介護保険が適用される?料金や利用方法まで詳しく解説カテゴリ:介護タクシー更新日:2025-05-07関連記事
 介護タクシーの料金はいくら?利用条件から金額のシミュレーションまで詳しく解説カテゴリ:介護タクシー更新日:2025-05-07
介護タクシーの料金はいくら?利用条件から金額のシミュレーションまで詳しく解説カテゴリ:介護タクシー更新日:2025-05-07
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
介護タクシーを利用する際はケアマネジャーに相談すると安心
本記事では介護タクシーの特徴や福祉タクシーとの違い、利用条件などをご紹介しました。要介護者にとって外出が安心して行える点でとても便利なサービスですが、サービスの利用にはいくつかの条件を満たす必要もあります。
こうした条件に当てはまるかどうかは、要介護者本人やその家族が調べて判断するのは難しいものです。詳しくは、担当のケアマネジャーさんに問い合わせてみるとよいでしょう。
介護タクシーに関するQ&A
Q.介護タクシーで病院に受診したあと、帰り道で買い物に寄ることは可能ですか?
介護タクシーを使った買い物は、生活必需品に限って認められています。受診の帰路で水分補給を目的とした飲料水の購入は可能ですが、その場合の通院等乗降介助は介護保険で算定することができないため注意が必要です。
Q.認知症があり家族がそばにいた方が安心ですが、その場合も1人で乗らなければなりませんか?
原則、家族の同乗は認められませんが、市区町村から特別な事情があると認められた場合は同乗も可能です。事前に相談されることをおすすめします。




