親の介護をしている人の中には兄弟間で分担をしなくてはいけないとわかっていつつも、親の介護をしない兄弟がいるという方も少なくないというのが実情です。
例えば、「長女なのだからあなたがすべて介護は担当してほしい」「遠方に住んでいるから親の介護はできない」など、さまざまな理由で親の介護を一方的に押しつけられてしまっているような状況の方もいると思います。
そこで、本記事では親の介護をしない兄弟とのコミュニケーションとして、親の介護をしない兄弟の言い分から説得の方法、最後に介護をした場合に相続は有利になるのかなどについて解説していきます。
親の介護をしない兄弟の言い分
親の介護をしない兄弟の言い分として多くあるのは「長男なんだから貴女ばやるべき」というような長男・長女に押し付けてくる場合、弱っている親を真正面から受け入れることができない度量の問題や、物理的に遠方に住んでいる等が考えられます。
それぞれの親の介護をしない兄弟の言い分について考察していきます。
長男・長女に押し付ける場合
親の介護をしない兄弟の言い分として先ず最初に考えられるのは、あなたが長男や長女の場合は、年上なのだからあなたがやりなさい、というような長男・長女への押し付けです。
また、長男や長女に押し付ける場合はほかの兄弟だけではなく介護を受ける親が「あなたが長女なのだからやってほしい」「長女がやるのが当たり前」というような感覚から介護を頼まれるという場合があります。
しかし考えてみれば、法的には親の扶養義務は子供全員にあるため兄弟の順番はもちろん関係ありませんし、相続のことを考えても長男・長女だからと言って優遇されることはなく等分で分けられます。
とはいえ、親の介護をしない兄弟の言い分としてまず考えられるのは長男・長女だからという理由で押しつけている理由だと考えられます。
介護をする度量が無い
親の介護をしない兄弟の言い分として次に考えられるのは、長男長女や次男次女に限らず弱っている親を受け入れることが出来ないという度量の無さや認知症などを患っている場合に精神的に親の介護に耐えることが出来ないということです。
確かに若年性認知症の場合や比較的若くして介護が必要になった場合は元気な親を見慣れているので衰弱している姿を見るのは確かにつらいことです。
しかし、弱っている親の面倒を見るのがつらくなるのはほかの兄弟でも同様に起こるため、親の介護をしない兄弟がいる場合は介護が大変なのは自分も同じであることなどを真摯に伝えてみましょう。
以上より、親の介護をしない兄弟の言い分として2つ目に考えることが出来るのは弱っている親の介護をする度量が無いことでしょう。
遠方に住んでいて物理的に介護ができない
親の介護をしない兄弟がいる場合で最も多いのが、遠方に住んでいて親の介護をそもそも物理的にできないというものです。
というのも、メインで親の介護をしている方が親の実家に住んでいる場合などにおいては、親の介護をしない兄弟は「親の貯金で生活をしているのだから、親の介護をすることに文句を言うな」などと心無いことを言ってくるような場合もあります。
しかし、介護は介護士やケアマネジャーなどの専門職がたくさんある立派なプロの仕事です。したがって、一つの仕事を親の介護という形で一人の兄弟が請け負っているともいえるため、他の兄弟が物理的に介護をすることが出来ない場合は経済的な援助を提案するなどしてバランスをとることが重要です。
親の介護をしない兄弟が遠方に住んでいる場合でも、金銭的な援助を頼むなどしてバランスをとるようにしましょう。
親の介護をしたくないという方はこちらの記事もご覧ください。
また親の介護や兄弟とのやりとりで限界を迎えてしまう前に、介護施設に入居するのもひとつの手です。
ケアスル介護では入居相談員が予算感や施設ごとに実施するサービス、立地情報などをしっかりと把握した上で、ご本人様に最適な施設をご紹介しています。
「幅広い選択肢から後悔しない施設選びがしたい」という方は、まずは無料相談をご利用ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
親の介護をしない兄弟を説得する方法
親の介護をしない兄弟を説得する方法としては、役割分担を徹底することや自身がまず介護サービスについて熟知しておきどのような分担方法があるか考えるという方法があります。
役割分担を徹底する
親の介護をしない兄弟を説得する方法として先ず最初に挙げることが出来るのは役割分担を徹底するということです。
というのも、親の介護をしない兄弟の言い分として遠方に住んでいるため介護をすることが出来ないというケースが非常に多くありますが、そういった場合などに親の介護をする代わりに施設に入所する際は金銭的に援助をお願いするなどの役割分担をしておくことが重要です。
そのほかにも、在宅介護をする場合はレスパイトケアと言って介護者自身の休息の時間が非常に大切となります。レスパイトケアとして介護者が旅行などで介護をできないときは必ず代わりに介護をしてもらうなどのルールをあらかじめ作っておくことが必要です。
以上より、親の介護をしない兄弟を説得する方法として最初に考えることが出来るのは役割分担の徹底だと言えるでしょう。
親を施設に入れたいがお金がない時の対処法について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
介護サービスについて熟知しておく
親の介護をしない兄弟を説得する方法として次にあげることが出来るのは介護サービスについて熟知しておくことです。
というのも、兄弟間の議論となった際に金銭的にどれくらい援助をしてほしいのかを伝えることは非常に重要ですが、自身が介護保険サービスについて理解していなかったリ施設に入所する際の費用がわかっていないとなかなか説得するのは難しくなります。
例えば、特別養護老人ホームやケアハウスなどの費用の安い老人ホームを知っておくことで、兄弟に出来るだけ少額で援助を提案することが出来るので資金援助してくれる可能性も高くなります。
したがって、親の介護をしない兄弟を説得する次の方法は自身が介護サービスについて熟知しておくことであると言えるでしょう。
親の介護費用について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
介護に対する考え方を整理しておく
親の介護をしない兄弟を説得する最後の方法は、話し合いの際に兄弟の親の介護についての考え方を整理しておくことです。
というのも、仮に親の介護をしない兄弟の言い分として年老いている親の面倒を見るのがつらいという場合では、実際問題として在宅介護の手伝いをしてもらうのは難しいと言えます。
したがって、親の介護をしない兄弟を説得する最後の方法はまず兄弟の親の介護についての考えを整理することであると言えるでしょう。
親の介護をしている際のストレスとの向き合い方について知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
親の介護をしない兄弟との役割分担はどうする?
親の介護をしない兄弟との役割分担としては以下のようなパターンが考えられます。
- 在宅介護を一人が行う代わりに他の兄弟は経済的な援助をする
- 在宅介護は一人の兄弟に任せるが、施設に入所する場合は入居一時金を全額出す
- 在宅介護は一人の兄弟に任せるが、レスパイトケアとして休息をとるタイミングで必ず介護を担当する
- 在宅介護は一人の兄弟に任せるが、施設探しの際はすべて他の兄弟が分担し月額費用もすべて出す
以上のようにやはり物理的に離れた場所に住んでいることも考えられますので、役割分担をする場合は一人が介護をしたうえで他の兄弟は金銭的な援助をするというパターンが考えられます。
役割分担の方法は家族形態や住んでいる場所、兄弟の人数から親の貯蓄によって様々なので話し合った際に最適な役割分担は何か考えながら議論をしましょう。
親を施設に入れる手順について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
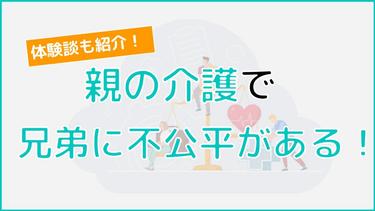
親の介護をしない兄弟を説得できない時の対処法
親の介護をしない兄弟を説得できない時の対処法として考えることが出来るのは、地域包括支援センターへの相談や家庭裁判所での民事調停が選択肢となります。
地域包括支援センターで相談する
親の介護をしない兄弟を説得できない時の対処法としてまず考えられるのは地域包括支援センターでの相談です。
地域包括支援センターとは地域の介護・福祉・保険・医療の相談窓口が集約されている総合的な相談窓口と言える施設で、中学校と同じ数だけ設置されている機関です。介護に関わらず家族の介護に対する取り組みなどについても相談することが出来るので親の介護をしない兄弟がいる際は有効な相談窓口となるのは間違いありません。
したがって、親の介護をしない兄弟を説得することが出来ない場合の最初の対処法としては、地域包括支援センターでの相談と言えるでしょう。
家庭裁判所で扶養請求調停を申し立てる
親の介護をしない兄弟を説得する際の最後の手段は家庭裁判所で「扶養請求調停」という形で民事調停を申し立てることです。民事調停として申し立てた場合、家庭裁判所の調停委員は以下の事項について確認します。
- 生活状況
└介護に必要な身体的負担はどの程度必要かを把握 - 経済状況
└親や兄弟の源泉徴収票や所得証明書などを提出し、経済状況を把握
生活状況や経済状況に加えて、当事者から介護についての考え方やこれまでの議論の流れなどを確認し、主観的な情報なども踏まえたうえで調停委員は解決策を提示します。
解決策の提示後、双方が合意を摂ることが出来れば、裁判所が合意した内容の書面(調停調書)を作成し、当事者は書面の内容を履行しなくてはなりません。支払いなどが遅れた場合は強制執行が可能となるので、債務者の財産の差し押さえが可能です。
仮に当事者間が民事調停員の解決策に合意できない場合は「審判」として調停で合意が取れていない事項について裁判官が判断し、決定事項に当事者は従う必要があります。
親の介護をしない兄弟よりも相続は多くもらえる?
親の介護をメインでした兄弟は親の介護をしない兄弟よりも相続は多くもらえるのでしょうか。本章では相続観点で親の介護について考えてみましょう。
一人で親を介護しても多く相続してもらえる法律はない
親を一人で介護したとしても親の介護をしない兄弟より相続で多く資産をもらえるという法律は現状ありません。
介護した分財産を多くもらうには「寄与分」という考え方に基づいて決まりますが、介護における寄与分の判断はほかの兄弟がすることになります。したがって、他の兄弟が認めない限り多くもらうことはできないので、一人で親を介護しても多く相続してもらうのは難しいのです。
例として裁判となった場合について検討してみますが、どのくらいの額を認定してもらえるのか判例を見てみると認知症の親を10年間一人で介護をしていた人の相続分は1日数千円程度の寄与分を認めてもらう程度だったことがわかっており、その期間介護をせずに働いていた方と比較すると多くはないことがわかっています。
したがって、親の介護を一人でしたからといって親の介護をしない兄弟よりも多く相続してもらうのは現状難しいと言えるでしょう。
介護した分を多くもらうには遺言状を書いてもらおう
親の介護をしない兄弟よりも多く相続でもらうにはやはり親から遺言状を書いてもらうのが一番と言えるでしょう。
介護をしている人に取っては親に対して遺言状を書いてほしいと伝えるのは気がひけるかもしれませんが、「親の責任として書いてほしい」と伝えることで遺言状を書いてもらえる可能性もなくはありません。
したがって、口約束で多く相続してもらえないという事態を防ぐためにも親に対して介護をしている際に遺言状を書いてもらうのが一番良いと言えるでしょう。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
親の介護をしない兄弟との向き合い方
ここまで親の介護をしない兄弟をどう説得するべきかについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
親の介護をしない兄弟と向き合う際は相手の立場に立ってみて、なぜ親の介護をしたくないのか相手の言い分を聞くことも重要です。
場合によっては衰弱している親を見るのがつらいということも考えることはできるので、親の介護の役割分担をする際は兄弟の介護についての気持ちも踏まえたもので円満に解決するのが一番と言えるでしょう。
親の介護をしない兄弟を説得する方法としては、「役割分担を徹底する」「介護サービスについて熟知しておく」「介護に対する考え方を整理しておく」などが挙げられます。詳しくはこちらをご覧ください。
親の介護をしない兄弟を説得できない時の対処法としては、「地域包括支援センターで相談する」「家庭裁判所を利用する」などが挙げられます。詳しくはこちらをご覧ください。





