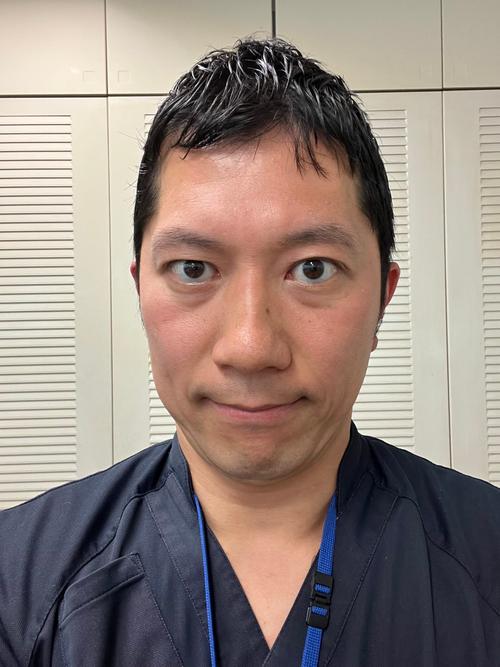レビー小体型認知症を患った家族に対する介護の方法に悩んでいないでしょうか?介護のやり方を知るには、まず原因を作り出している「レビー小体型認知症」について学ぶ必要があります。
本記事では、レビー小体型認知症について詳しく解説するとともに、治療法や対処法も併せて解説します。レビー小体認知症の家族への介護に悩んでいる方はご覧ください。
レビー小体型認知症ってそもそもどういう病気?
レビー小体型認知症とは、「レビー小体」と呼ばれる変性したタンパク質が脳に蓄積して発症する認知症です。
認知症患者の約20%を占めており、アルツハイマー型認知症の次に多い認知症として知られています。また、レビー小体型認知症の発症率は男性が女性の2倍と言われており、男性の発症率が高いです。
レビー小体が脳に生じて発症する病気には、レビー小体型認知症のほかにパーキンソン病があります。パーキンソン病とは、手足の震えや便秘、立ち眩みなどの症状が引き起こされる病気です。「黒質」と呼ばれる脳幹の一部にレビー小体が生じる場合があります。
レビー小体型認知症を発症する原因は何?
レビー小体型認知症の発症原因は、加齢による脳の変化だとされています。脳は加齢と共に、神経細胞が徐々に減少していきます。
中でも神経細胞の減少は、側頭葉と後頭葉が顕著です。脳の記憶の処理をしている「側頭葉」と視覚情報の処理をしている「後頭葉」が脳の加齢で萎縮し、幻覚が出るのです。
運動などによって、神経細胞の減少するペースを緩やかにすることは可能ですが、減少自体を止めるのは難しいとされています。つまり、レビー小体型認知症の予防方法としては、できるだけ神経細胞が減少するペースを緩やかにするしか今のところないのです。
どのようにレビー小体型認知症とわかるの?
レビー小体型認知症は、下記の症状のうち2つに該当するとともに、脳画像検査、心臓の画像検査、睡眠検査のいずれか1つで条件を満たす異常な所見がみられた場合、レビー小体型認知症と診断されます。
- レム睡眠行動異常症
- 繰り返し出現する幻視
- 認知機能の明らかな変動(低下)
- 動作緩慢、寡動、静止時振戦、筋強剛のうち1つ以上の症状がある
参照:『7章 Lewy小体型認知症』
認知症と聞くと、物忘れや物事の認識不足が多いイメージがありますが、レビー小体型認知症の初期で主にみられる症状は、睡眠障害や幻覚、体の不調です。
ただ、中期になると認知機能の変動が大きくなり、改善と悪化を繰り返しながら次第に症状が悪化する傾向にあります。認知機能の変動以外にも、記憶障害や見当識障害も徐々に低下していきます。
後期になると、パーキンソン病によく似ている症状が強くなり、ちょっとしたことでの転倒や転落、ふらつき、立ちくらみが発生するような状態になります。
以上のように、初期から後期に進むにつれて生活上でのリスクが大きくなるため、レビー小体認知症を家族が発症した場合は、できるだけ早い段階で治療を行い、進行の抑制が求められます。
レビー小体型認知症の主な症状7つ
ここでは、レビー小体型認知症の特徴的な症状を7つ解説します。レビー小体型認知症を患っている家族の介護のためにも、主な症状を把握しておきましょう。
妄想
レビー小体型認知症では、次の3つの「妄想症状」が見られる場合があります。
- 被害妄想:他人からさまざまな嫌がらせを受けていると感じる など
- 誤認妄想:目の前に誰もいないのに、あたかもいるかのように認識する など
- 替え玉妄想(カプグラ症候群):近くにいる家族を「偽物」で、本物はどこか別の場所にいると主張する など
3つの中でよく見られるのは「被害妄想」です。特に、側頭葉の萎縮によって記憶力が低下しているため、もの忘れを起因とした被害妄想が多くなっています。
「物はあるよ」と言葉で説明しても理解は得られず、見つかるまで主張を繰り返すのが特徴です。
また、替え玉妄想に関して発症する原因は明確ではありませんが、脳内の機能が低下しているため、親しい人かそうでないかの識別をできないからだと考えられています。
本当の家族なのにもかかわらず、突然偽物扱いされてしまってはショックも大きくなってしまいます。レビー小体認知症の妄想の症状を明確に把握しておくと、病気が原因だと理解できるため、自身が受けるショックを軽減し対応もしやすいでしょう。
幻視
幻視とは、視覚を司る後頭葉が障害を受けてしまい、実在しないものが見えるようになる症状です。
レビー小体型認知症の方のうち約80%の方に幻視を生じるとされています。幻視が発症する理由は明らかになっていませんが、後頭葉に血流が少なくなることで生じているのではないかと考えられています。
幻視が生じると、現実にはいないはずの動物や人物が実際にいるように見えてしまい、それを追い返そうとする行動に出るようです。このような現象を繰り返すのもレビー小体型認知症の特徴になります。
また、「幻覚」に分類される症状の中では、幻視が最も多いものの、幻聴や幻触、体感幻覚なども見られます。幻視が発症する病気はレビー小体認知症だけでなく、うつ病や統合失調症の場合にも見られる症状のため、医師による明確な診断が必要です。
抑うつ症状
レビー小体型認知症になると、初期から抑うつ症状がよく見受けられます。
抑うつ症状は、物事に対して悲観的な感情を抱いたり、気分がふさぎ込んだりして何事にも意欲が沸きにくくなる症状です。
「抑うつ症状」と「うつ病で生じる症状」との違いがよくわからないと思います。抑うつ症状は、先述したように気分の落ち込みを指した言葉です。一方で、うつ病で生じる症状に抑うつ症状に加え、疲れやすさ、不眠または過眠などの症状が総じて現れる状態を指します。
つまり、抑うつ症状はうつ病で現れる症状の1つなわけです。
レビー小体型認知症で抑うつ症状は見られやすいため、認知症に伴って気分の落ち込みなども見られた場合は、医師に相談して対処しましょう。
パーキンソン症状
「パーキンソン病」と呼ばれる病気では、手足の震えや筋肉のこわばり、動作緩慢などの症状が生じます。
これらの症状が、パーキンソン病とは別の原因によって生じたものを「パーキンソン症状」と呼びます。症状が似ているため、パーキンソン病またはレビー小体型認知症のどちらが原因か判断が難しいです。そこで、手足の震えや筋肉のこわばりなどのパーキンソン症状が生じてから1年以内に「認知症」が現れた場合はレビー小体型認知症、1年後に現れた場合は「パーキンソン病」と判断するよう、ガイドラインによって推奨されています。
パーキンソン症状は、日常生活を送るうえで転倒リスクにつながるため、住宅内の環境整備や福祉用具の活用などが求められます。
自律神経症状
レビー小体型認知症では、自律神経症状を発症する場合もあります。自律神経症状とは、立ちくらみや多汗、便秘など、自律神経に関連する体の不調が発生する症状です。
自律神経は、交感神経と副交感神経の2つの神経で構成され、無意識にバランスを上手く調整しています。交感神経は、血圧や脈拍の上昇、瞳孔を開くなどの「興奮作用」があるのに対し、副交感神経は、血圧や脈拍の低下、瞳孔の縮小、腸の活動促進などの「リラックス」作用があります。運動をするときは「交感神経優位」、休むときは「副交感神経優位」といったイメージがわかりやすいです。
しかし、レビー小体型認知症では交感神経と副交感神経のバランスが乱れ、体の不調を起こしやすくなります。
睡眠障害
レビー小体型認知症を発症すると、個人によっては睡眠障害が発症する場合があります。
レビー小体型認知症で引き起こされる睡眠障害の特徴は、「眠りの浅い時間帯(レム睡眠)」に、突然大声を出したり暴れたりする「レム睡眠障害」です。レム睡眠障害の原因は、睡眠をコントロールしている脳の部位の障害だとされています。本人だけでなくご家族に危害が加わる可能性があるため、早めに何らかの対処をする必要があります。
本人が意図して暴れていたりするわけではないため、睡眠時の行動が気になる場合は、本人を傷つけないように配慮した声かけを行うようにしましょう。また、介助者であるご家族がケガをする前に、早めに病院を受診するようにしてください。
認知機能の変動
レビー小体認知症になると、日によって認知機能が大きく変化します。
病状が次第に進行してくると記憶障害も併発してくるものの、レビー小体認知症の初期は記憶障害が目立たないため、調子のよい状態を見ていると病気であると判断が付きにくい傾向にあります。
また、レビー小体認知症初期に注意力の低下、今まであまり間違えなかったのに見間違いや道の間違えが頻出する場合が多いです。
ただ、認知機能の変動差の大きさは個人によって大きく変わるため、アルツハイマー型認知症やうつ病、パーキンソン病と間違えられることも珍しくありません。そのため、初期には中々見分けがつきにくい病気といえるでしょう。
レビー小体型認知症の治療法
2022年現在では、レビー小体型認知症を根本から解決する治療方法がないため、経過の進行に応じて、症状の緩和を図る薬物療法を中心に行います。
レビー小体型認知症の薬物療法は、抗認知症薬の「ドネペジル」や「リバスチグミン」などの投与が主です。認知症の症状などで衝動が激しい場合は、抗精神病薬を用いる場合もあります。しかし、レビー小体型認知症の特徴として薬剤への過敏性があるため、少量の服用で様子を見ながら調整していきます。
自宅で薬を服用する場合は、服薬管理を入念に行い、副作用の症状が発症した場合は担当医に相談しましょう。
レビー小体型認知症の家族への対応法を紹介
ここでは、レビー小体認知症のご家族への対応方法を解説します。対応方法を参考にし、レビー小体認知症を患っている家族への介護を実践しましょう。
幻覚症状:否定しない
レビー小体型認知症で幻視症状が出ている場合には、ご家族の発言を決して否定しないようにしてください。
実際に存在しないものであっても、レビー小体型認知症を患っている本人にとっては現実のものに感じるため、否定されるとより興奮してしまいます。
本人の不安や興奮を落ち着かせるためにも、見えているものがどのようなもので、どこにあるのかを聞き、幻視の実態を理解したうえで対応しましょう。
幻視は自分から近づいたり離れたりすると消える場合が多いので、あえて自分たちから近づいて触れてみるかその場から一度離れてみるとよいかもしれません。
ちなみに部屋が暗い場合は幻視が見えやすくなるため、「〇〇が見えた」と本人が興奮状態で言ってきたら、一度明かりをつけてそれでも見えるか否かを尋ねてみるとよいでしょう。
レム睡眠障害:様子を見守る
レム睡眠障害が発生した場合は、事前に対策をしたうえで本人の様子を静かに見守るのが最適です。
レム睡眠障害では、本人が夜中に大声をあげ、起きて歩き回るなどの行動が考えられます。これに備えて、ベッドから落ちて怪我しないように低床にしておき、移動の妨げになる物をどけておくなどの対策をしましょう。また、様子を見守るだけでなく、本人が外に出ないように十分注意しておくことも大切です。
レム睡眠障害は不安やストレスが蓄積した状態で生じやすい傾向にあります。本人に合ったストレス解消を行ったり、環境を整えたりなどを日頃から心がけるとよいでしょう。
認知機能低下:状態がよいときにリハビリ実施
認知機能の低下に対して、リハビリの実施が推奨されています。
実際に、リハビリで行われる「運動療法」が認知機能の改善に効果があるとわかっているのです。
注意点として、レビー小体型認知症の認知症症状は、1日の中で良い状態と悪い状態の差が大きい特徴があります。
そのため、悪い状態のときにリハビリを行っても思うようにリハビリを行えず効果が期待できません。夕方から夜にかけて悪化する傾向にあるため、比較的良い状態の場合が多い「朝方」にリハビリを実施するのが良いとされています。
個人によって認知症の症状の現れる周期は異なるため、どのような周期で症状が出やすいか記録を取っておくのも一つの手です。
転倒しにくい環境づくり
レビー小体型認知症になると、パーキンソン症状や注意力の低下などにより、つまづいて転びやすくなるため、転倒しにくい環境づくりが大切です。
例えば、スロープを付けて段差をなくしたり、手すりや照明を付けて視認性を確保したりすると転倒リスクを下げられます。
また、移動する際にはできるだけ見守りまたは介助を行いましょう。一人にするのは非常にリスクが高まるため、常に目が届く範囲にいるのが重要です。
専門家(ケアマネージャーや医師など)に相談する
レビー小体型認知症の方への対処方法で困ったら、ケアマネージャーや医師などの専門家に相談するとよいです。
特に、自宅でレビー小体型認知症の方の介護に充てる時間がない方や負担が大きいと感じている方はケアマネージャーに相談しましょう。レビー小体型認知症の方が入居可能な介護施設もあるため、介護施設への入居を調整してもらえます。介護施設は、介護に関する専門知識を豊富に備えたプロが多く在籍しているため、安心して介護を任せられます。
仕事で忙しい方や介護疲れで困っている方は専門家に相談し、介護施設への入居を検討するとよいでしょう。
まとめ|対応に困ったら専門家に相談しよう
レビー小体型認知症を患っている場合、妄想や睡眠障害などの症状で意味不明な発言、いきなり暴れ出すといった行動をする傾向にあります。
しかし、彼らの行動をやみくもに否定しては逆効果になってしまうため注意が必要です。彼らの発言を否定せず受け入れ、レビー小体型認知症の家族が過ごしやすい環境づくりを心がけましょう。
対応に困ったら、かかりつけ医や要介護認定を受けている場合はケアマネージャー、地域包括支援センターなどに相談が可能です。自身の負担を軽減するためにも、遠慮せずに相談します。
レビー小体型認知症は、パーキンソン病・うつ病・アルツハイマー病と誤診されることが多い病気です。そのため、違和感を感じた場合は早めに認知症の専門医を受診することがおすすめです。詳しくはこちらをご覧ください。
レビー小体型認知症は、内科・神経科・脳神経外科で診察可能です。詳しくはこちらをご覧ください。