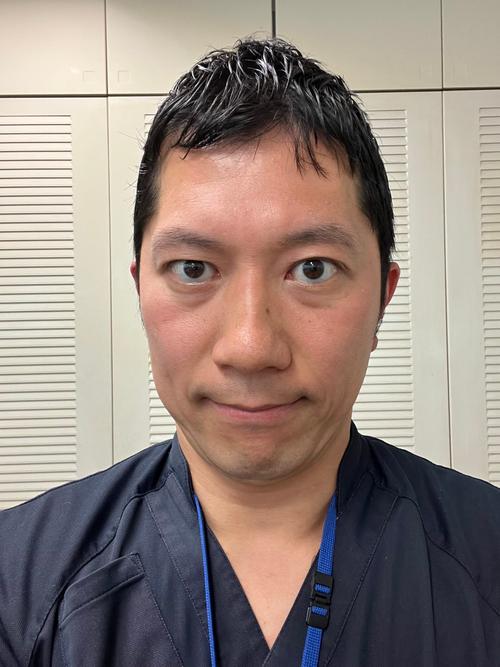自宅に認知症のご家族がいる方の悩みとしてもっとも多いのが、夜間の対応ではないでしょうか。「昼間は静かなのに夜になるとうるさくて休めない」「夜に叫ぶから近所の目が気になる」などの悩みを抱えている方は多いかと思います。
この記事では、認知症の方が夜に活発になる理由や、夜間眠ってもらうための方法について解説していきます。認知症の方が夜間うるさいときの対処方法について紹介していきますので、参考にしてください。
認知症の方が夜にうるさい6つの理由
認知症の方は、理由もなく夜に大声を上げたり、叫んだりされているわけではありません。
主に以下のような理由があるといわれています。
- 夜間せん妄
- レム睡眠行動障害
- 不眠障害
- 見当識障害
- 不安感
- 活動量の低下
夜になるとうるさくなる理由が分かれば、対処方法を考える際の参考になります。ご家族に当てはまるものはどれか確認しながら、それぞれを詳しくみていきましょう。
1.夜間せん妄
夜間せん妄とは、夜に発現するせん妄症状を指します。せん妄とは、幻覚や興奮、不安感をともなう精神症状です。
人の体は、朝起床して、夜に眠る「サーカディアンリズム」と呼ばれる生活リズムを形成しています。しかし、認知症の方、特にアルツハイマー型認知症の方の場合は、サーカディアンリズムが崩れやすいといった特徴があります。サーカディアンリズムが崩れると、睡眠ホルモンである「メラトニン」の分泌が低下してしまうため、夜間なかなか寝付けず、夜間せん妄につながる傾向があります。
ほかにも、「夜は暗く周囲が見えづらいため、恐怖心や不安感が増強しやすい」「1日の疲れによる脳の機能低下」などが理由で、せん妄症状が出現しやすいです。
夜間せん妄は、夜間にだけ出現し、周囲が明るい昼間には現れません。また、中には「近くに蜂がいる」「泥棒が入った」などと叫ぶ方もいます。このような幻視は、認知症の方以外には見えないため、つい否定してしまう場合もあるでしょう。しかし、認知症の方にとっては現実で起こっている出来事だというのを、忘れてはいけません。
2.レム睡眠行動障害
レム睡眠行動障害は、レビー小体型認知症の方によく出現する睡眠障害や昼夜逆転症状の一つです。
睡眠とは、眠りの深い「ノンレム睡眠」と、眠りの浅い「レム睡眠」を繰り返しています。夢を見ているのは、レム睡眠のときになります。
通常入眠中は、脳からの指令はほとんど体へ届かないため、体が動かせません。しかし、レム睡眠行動障害の場合は、入眠中でも脳からの指令が体へ届くようになります。そのため、レム睡眠中に見ている夢の中の動きと同じ行動をしてしまうといわれています。
例えば、一見眠っているにもかかわらず、叫んでいるようであれば、夢の中でも叫んでいるのかもしれません。
ほかにも、突然起きだしたりしてしまうのも、夢の中でそのような行動を起こしている可能性があります。
3.睡眠障害
睡眠障害とは、夜間に眠れなくなる症状です。
朝に起きて、夜に眠る「サーカディアンリズム」という生活リズムを形成しているのは、脳の一部である「松果体」や「視床下部」です。さらに、睡眠ホルモンの「メラトニン」は、松果体で合成しています。
脳の機能は加齢とともに低下していくため、生活リズムを形成しているサーカディアンリズムが崩れやすくなります。高齢者から「早朝に目が覚める」「昼夜逆転が起こる」などといった睡眠障害の訴えがよく聞かれるのは、このためです。
認知症は、脳の機能低下により生じる疾患です。そのため、認知症になると、よりサーカディアンリズムが崩れてしまい、睡眠障害を生じやすくなります。
4.見当識障害
見当識とは、日時や場所、目の前にいる人などから、総合的に判断し、自分自身が置かれている状況を把握・理解できる能力をいいます。つまり、見当識障害とは、「ここはどこで、今は何月何日なのか」「目の前にいる人は誰なのか」「自分は今どこにいるのか」などが分からなくなる障害です。見当識障害が出現する代表的な疾患として、認知症があります。
見当識障害は、症状があらわれる順番が以下のように決まっています。
- 時間
- 場所
- 人間関係
見当識障害が現れると、一番はじめに時間の把握が困難になるため、昼夜逆転が起こりやすいです。例えば、深夜0時とお昼の12時を間違えてしまい、深夜に昼食を作り出すなどといった行動もみられます。
5.不安感
認知症の方に限らず、寝る前に過去の嫌な出来事を思い出したり、嫌な夢を見て起きてしまう経験があるでしょう。
通常であれば、過去の出来事は過去のものとして認識できますし、夢も夢だと判断ができます。しかし、認知症の方の場合、見当識障害によって、過去の出来事や夢の中の話を現在起こっている出来事として捉えてしまう傾向にあります。
また、認知症の方は、自身の感情を言葉にして伝えるのが苦手です。そのため、寝る前に嫌な出来事を思い出したり、嫌な夢を見たりした際に、大声を出して叫ぶ行動で、自身の不安感を伝えようとしている場合があります。
さらに、不安感によって興奮してしまうと、寝付けなくなってしまう負のループに陥る場合も多いです。
6.活動量の低下
脳の機能低下が原因で生じる認知症は、体内の生活リズムを形成しているサーカディアンリズムが崩れやすいため、昼夜逆転が起こりやすいといった特徴があります。また、認知機能の低下によって社会との関わりが少なくなり、外出の機会が減り、陽の光を浴びる機会が減ると、さらに昼夜が悪化してしまう傾向にあります。
だからといって、昼間に外出をせず、長時間の居眠りやベッド上で生活を送るのは、昼夜逆転をさらに悪化させる原因です。昼夜逆転の生活を長期間続けると、本来の生活リズムである夜間に眠る生活に戻すのが困難になります。そのため、昼夜逆転の生活が長い方こそ、夜間に起きてしまう傾向にあります。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
認知症の方に夜間眠ってもらう方法3選
認知症の方は、意味もなく夜に声を出しているわけではありません。夜になると起きだし、大声を出したりするのには、必ず理由があります。理由がわかれば、夜間眠ってもらうための方法を試せるでしょう。
ここでは、認知症の方に夜間眠ってもらう以下の3つの方法について詳しく説明していきます。
- 眠りやすい環境づくり
- 睡眠日記の活用
- 日中の活動量アップ
どれも普段の生活に取り入れやすい方法ですので、一つずつ試してみるとよいでしょう。
1.眠りやすい環境づくり
眠りやすい環境づくりには、以下のような方法があります。
- 寝室の室温や明るさなどを整える
- 足浴をする
- ホットココアやチョコレートなどでリラックスする
- 不安の解消に努める
朝までしっかり眠ってもらうためには、入眠までの環境や睡眠中の環境を整えられるかがポイントです。明るさや室温、時計の音が気になるかどうかなど、眠りやすい環境は人それぞれ異なります。認知症の家族が眠りやすい環境を、探してみるとよいでしょう。
また、人は、一度高くなった体温が下がるときに眠たくなります。入浴は寝る2~3時間前に済ませる、1時間前に足浴をすると、入眠する頃には体温が下がり、入眠しやすくなります。眠る前にホットココアやホットミルクを飲んだり、一粒のチョコレートを食べながらリラックスするのも、眠りやすい環境作りの一つです。
「眠らなきゃ」「朝まで眠れるかな」などと考えすぎてしまうと、余計に眠れなくなってしまいます。
トイレで起きてしまう方はトイレを済ませる、痛みで起きてしまう方は痛みのある部位に湿布を貼っておくなど、不安要因を解消したら、あとはリラックスして入眠環境を整えましょう。
2.睡眠日記の活用
睡眠日記とは、睡眠状況を客観的に評価する方法で、以下のような内容を日記に記していきます。
- 睡眠時間
- 睡眠時の環境
- 日中の様子
一定期間睡眠日記をつけてみると、「寝る直前にテレビを見ていた」「午睡の時間が長かった」など、夜間眠れない原因が見えてくる場合があります。夜間眠れない原因が分かったら、その原因を改善するよう努めていくとよいでしょう。
また、睡眠日記は、夜間の睡眠状況が一目で分かるため、医師へ相談する際に非常に役に立ちます。ショートステイの利用や、施設入所の際にも、スタッフへ説明しやすくなるため、睡眠日記を付けておくとよいでしょう。
3.日中の活動量アップ
日中の活動量アップは、昼夜逆転の改善になります。
認知症は脳の機能低下によって生じます。そのため、体内の生活リズムを形成している「サーカディアンリズム」が崩れやすく、昼夜逆転が起こりやすいです。
体内の生活リズムを整えるうえで重要なのが、「太陽の光を浴びる」行動です。日中の活動量が増やせれば、自然と太陽の光を浴びられるでしょう。
また、散歩やデイサービスの利用などで、適度な運動ができれば、疲労感から夜間はよく眠れるようになります。日中活動する習慣のない方は、朝一番にカーテンを開けて、太陽の光を取り入れるところから始めてみてもよいかもしれません。
午睡に関しては、寝すぎなければ特に問題はありません。眠たいときには、10~30分間眠ると睡眠障害にも効果があるとされています。
認知症の方が夜にうるさいときの対処法
認知症の家族が夜間眠ってくれない状況が連日続くと、介護する方は身体的にも精神的にも参ってしまうでしょう。つい、認知症の家族に対して怒ってしまう場合もあるのではないでしょうか。
しかし、大声を出すなどの興奮状態にある方に対し、怒ってしまうのは逆効果です。怒られ、さらに興奮してしまうと再度眠るまでに時間を要します。
例えば、夜間せん妄による幻聴や幻視は、介護者には聞こえたり見えたりしていなくても、認知症の方には現実に起こっているものです。見当識障害によって、自身がどこにいるか分からなければ叫んでしまっても、無理はないです。
気持ちを完全に理解するのは難しくても、認知症の方が現在置かれている状況に寄り添い、まずは優しく声をかけてみましょう。気持ちに寄り添ったうえで、「なぜ大声を出したのか」を聞いてみると、理由が分かるはずです。気持ちが聞けたら、否定するのではなく「怖かったね。もう大丈夫だよ」などの優しい声掛けをしましょう。
睡眠薬は効果がある?
現在、認知症の方の睡眠障害に対する効果的な薬物療法はないといわれています。
ただし、一口に睡眠薬といっても、薬の構造や薬効にはいくつもの種類があるため、絶対に効果がないとは言い切れません。また、昼夜逆転を改善する方法の一つとして、睡眠薬を内服する場合もあります。しかし、睡眠薬に限らず、薬全般に言えるのですが、薬効がある分、副作用もあるのが薬です。
睡眠薬の副作用には、種類によって異なりますが、主に以下のようなものがあります。
- 精神神経系症状
- 消化管症状
- 翌日の眠気
- 皮膚症状
- 薬物依存
- 内分泌症状
そのため、初めから睡眠薬に頼るのではなく、まずは、昼夜逆転を改善する方法などを試してみるとよいでしょう。アメリカのアルツハイマー病協会でも、認知症の睡眠障害に対しては、薬物療法ではなく、生活リズムの改善を勧めています。
ただし、絶対に睡眠薬を使用してはいけないわけではありません。生活リズムの改善を心がけていても、昼夜逆転が改善しない場合には、かかりつけ医に相談すれば、その方に合った睡眠薬の処方をしてくれるでしょう。
認知症の症状を理解し、睡眠環境を整えよう
認知症の方は、理由なく夜間寝なかったり、大声を出したりしているわけではありません。夜間せん妄による幻聴や幻視、見当識障害、脳の機能低下による昼夜逆転の進行など、さまざまな要因が重なり合って、夜間の睡眠障害を引き起こしています。
幻聴や幻視、見当識障害などは、認知症のない方には想像がしにくく、理解も難しいでしょう。しかし、認知症の方にとっては現実に起こっている問題です。否定はせず、不安感や幻聴・幻視への共感をし、認知症の方が安心できる声掛けを行うのが大切です。また、夜間眠れるように、睡眠環境を整えたり、日中の活動量を増やしたりなども実践してみるとよいでしょう。