日中は寝て夜に起きている“昼夜逆転”の状態で、夜は活発になっている。そのため、家族を起こしてしまい、介護者は寝る時間がない……と介護疲れを感じている方も多いのではないでしょうか。
認知症末期の方は活動能力が低下し、ほとんどベッドの上で過ごしているため、日中でも眠くなってしまうのは仕方がない面もあると思います。
そんな認知症末期の睡眠障害にお困りの方へ、本記事ではなぜ夜に眠れなくなってしまうのか、睡眠障害の対処法をご紹介します。
認知症末期で睡眠状況はどうなる
認知症には初期、中期、後期といった段階があり、睡眠状況も大きく変化していきます。では、どのように睡眠状況が変化していくのか段階別でみていきましょう。
初期の状態
認知症の始まりでは、単なる物忘れの状態と変わりありません。しかし、認知症が進み初期といわれる段階になると、記憶障害が起こります。たとえば、「直前の出来事を忘れてしまう」「忘れてしまったことでさえ忘れてしまう」など。同じ動作を繰り返すため、普段行っている日常生活がスムーズにいきません。
症状が進行すると時間や場所などの認識ができなくなり、不安感ばかり強くなっていきます。やがて、根拠のない不安感は気がかりへと変化し、眠れない状況を作ってしまいます。
中期の状態
認知症中期に進むと、記憶や判断能力が著しく低下します。中期まで進行した方は、一人で生活することは難しくなっているでしょう。たとえば、「ご飯を食べたのに、ご飯を食べていない」というのも中期の症状です。
直前の記憶がすっぽりと抜けた状態で、自己判断もできなくなります。それによって、着替えや掃除、お買い物、トイレや入浴といった日常的なことでさえも介護が必要になってきます。
昼夜の区別もできなくなり、日中に入眠してしまうことも多くなります。そのため、夜間は寝つきが悪くソワソワしてしまい、夜中ずっと徘徊してしまうといった状態に陥りやすいです。
それだけではなく、周辺症状といった本人の性格や環境によってあらわれる「せん妄」「幻覚」「暴力」「興奮状態」が頻発します。
末期の状態
認知症末期になると、認知機能の低下だけではなく身体機能も低下します。歩くことが難しくなり、寝たきりの状態になっていきます。そのため、排泄、入浴、食事などの日常的な動作すべてに介助が必要です。
発語も少なくなり、コミュニケーションも困難な状態になります。こちらからアクションを起こしてあげないと、生活リズムが崩れ、睡眠はもちろん身体的にも悪い方向へ進行してしまいますから、予防や対策が重要な時期です。予防や対策をしないと、免疫力の低下によって感染症を起こしやすい状態となってしまいます。
また、機能が急激に低下しますが心は動いている状態です。そのため、これまでの経験から雰囲気によって状況を察知します。周囲の環境によって睡眠状態も大きく変化することがあります。
認知症末期で睡眠状況が悪化する原因について
睡眠状況の悪化には、日常的な生活からおこる身体的要因と、精神面に関わっている心理的要因などがあります。また、治療のために使用している薬が日中に活動を抑制する原因になっている場合があります。
身体的要因が睡眠状況を悪化させている
認知症末期は、体を動かすことが難しくなり、1日をベッドの上で暮らすようになっていきます。体を動かさなくなると筋肉が萎縮するだけでなく、脳への刺激も減り脳が萎縮していくのです。
また、体を動かさなければ萎縮だけでなく、拘縮といって固まった状態になります。筋肉に柔軟性がないと疲労が溜まりやすく、気怠さを感じたり、痛みの原因にもなるのです。
痛みが強くなっていくと、臥床しているだけで痛みを感じてしまいます。常に痛みを感じていますから、とても寝られる状況ではないことがわかると思います。痛みはとても不快なものです。不快感はストレスを増加させていき、夜中も眠れず認知機能もさらに低下していくのです。
精神的要因も睡眠状況を悪化させている
施設に入居して環境が変わったり、活動能力が低下し自分の思い通りにならない場合もストレスは蓄積していきます。できないことが増えてもどかしくなったり、介護者に怒られたりもしますから、フラストレーションが溜まっていく一方です。
ストレスは血流を低下させてしまうため、脳に充分な栄養が行き渡らず、思考を鈍らせていきます。うつ病のように精神的なダメージを与えますから、日中は一点を見つめてぼーっとしていたり、突然大きな声を上げたりするようなことがあるので、夜間も眠れなくなってしまう場合があります。
薬が逆効果になることもある
夜間に眠れず睡眠薬を服用している認知症の方もいますが、実は逆効果になっていることがあります。
認知症末期は、認知機能が著しく低下しているため、状況の判断ができません。場所も介助してくれる人も分からないため、常に不安がたくさんある状態だから眠れないのかもしれないです。
なぜ寝ないのか原因を追求しないまま、薬の用量が増えていったりすると、効き過ぎている場合もあり、朝に睡眠を促している可能性も考えられるのです。
また、薬によっても副作用で眠気を誘ってしまうものもあります。睡眠薬を使用していない方で日中に眠ってしまっているのであれば、他の薬が原因となっている場合があります。一度、医師へ確認をとって見直してみるとよいでしょう。
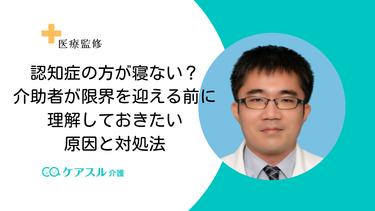
認知症は睡眠による関係性も高い
睡眠不足は、海馬という記憶を司る脳の一部が破壊されてしまうため、認知症が進行していくともいわれています。
睡眠不足によって、脳内にアミロイドβと呼ばれる不要なタンパクを蓄積させてしまいます。アミロイドβは、脳の細胞を破壊していく物質だといわれています。それだけではなく、同じく脳内の細胞を破壊してしまう「タウたんぱく質」という物質も睡眠不足によって脳内に蓄積されていきます。
しかし、これら不要な物質は睡眠不足を解消することで、取り除かれることも研究によりわかっているのです。
認知症による体内時計の乱れで睡眠障害が起こる
認知症の方が体内時計を乱しやすい理由として、意欲が低下してしまい、活動が減ってしまうことが考えられます。
通常の場合、日中に日の光を浴びる機会があると思います。しかし、認知症末期の方はベッドで過ごすことが増えるため、室内だと日の光を浴びる機会が減ります。日の光は、人のホルモン分泌に大きく関わっていて、睡眠のONとOFFを切り替える役割があるのです。それがないと体内時計が乱れてしまい、体が昼夜の区別ができなくなってしまいます。これらが昼夜逆転や夜間の不眠を引き起こす原因となるのです。
体内時計を乱さないために、朝はしっかりと日の光を室内に入れてあげましょう。
高齢者の体内時計が乱れる理由
高齢になると体内時計が乱れる理由として、もう一つあります。体力の低下や老眼などの身体機能が低下するのと同じで、体内時計も自然と乱れてきます。
年齢を重ねるにつれてメラトニンの分泌量も低下するのです。昼夜の切り替えが上手くできないので、昼間に眠気がでたり、早朝に目が覚めたり、眠りが浅くなってしまいます。
身体機能が低下し、さらに昼間に眠気が出てしまう。この状態では、活動が億劫になる一方なため、生活にメリハリがなく体内時計が乱れたままだという訳です。
認知症末期が家族の日常生活に与える影響
認知症の方が夜間に何かを訴えて叫んだり、覚醒してベッドで暴れるということはよくあります。そうなると家族も心配で眠れなくなり、肉体的にも精神的にも疲労感が増して、介護が辛くなるでしょう。
では、認知症末期の方が睡眠障害を起こすとどうなってしまうのか、具体的な介護状況についてお伝えします。
夜間の介護状況
認知症末期の方は寝たきりの状態が多くなります。寝たきりになると、日常生活のすべてにおいて介護が必要となるでしょう。
そこに、昼夜逆転が加わると、夜間に目がさえて活発になります。寝るはずの夜間に、食事や痛みなどを訴えます。発語が追いつかなくなり、上手くコミュニケーションが取れませんが、本人は伝えているつもりです。聞き手は、「何かを伝えようとして叫んでいる。どうしてほしいのかわからない」「夜だから寝るように話すが伝わらない」といった状態になってしまいます。
奇声を上げたり排泄物などをいじってしまうため、介助者も眠れず体力的にも限界を迎えてしまう家族が多くいるのです。
介護者が限界を迎える前に
認知症の方の介護に限界を迎えてしまうと、介護うつや虐待に発展します。
人は睡眠がとれないと、健常者でも心身へ支障をきたしてしまいます。適切な判断ができなくなったり、精神疾患へ発展したりするのです。介護疲れは誰にでもあり、限界を迎える前に先を見据えて手を打つことが必要なのです。
これらを解決させる手段として、介護サービスの利用や専門家に相談することが必要になります。介護は、相手の生命に強く影響しますので当然休みはありません。しかし、介護者が自ら休息の時間を作ることも重要だということを覚えておきましょう。
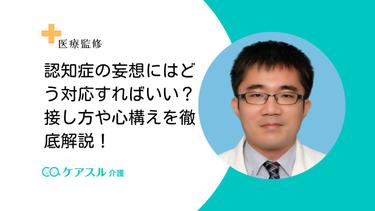
認知症末期でも穏やかに生活が送れる方法
認知症で寝たきりであっても、穏やかに暮らしている方もいます。穏やかに暮らしている方は、ルーティンが整っているのです。寝たきりの方にとって、時間の管理をしてあげることが穏やかに過ごす重要なポイントとなります。
認知症末期の人へおすすめする1日の過ごし方
体内時計を整えて穏やかな生活を送るためには、規則正しい生活を過ごすための工夫が必要となります。朝から夜のおすすめの過ごし方を紹介します。
- 朝:起床と朝ご飯、歯磨き
- 昼:昼ご飯と歯磨き
- 夕:夕ご飯と歯磨き
- 食事以外の時間→レクリエーション
朝は、カーテンを開けて朝陽を浴びることが大切です。食事時間は30分程度を目安にします。無理に食べさせないことが重要です。食事以外の余暇時間は、本人が興味のあることをしてあげます。また、ベッド上でできるストレッチなどをして、体を動かすことも積極的に行うのも有効です。食後の歯磨きは、口腔内の雑菌を除去して誤嚥性肺炎を防ぐだけではなく、生活リズムを整える有効的な手段にもなります。
日中に家族ができること
認知症末期でも喜怒哀楽の感情や意思はあります。日中に入眠しないように声をかけ、アイコンタクトも積極的にしていきましょう。そうすることで、適度な疲労感が与えられるので、夜間は快適な睡眠がとれるようになります。
- アイコンタクトをする
- 声かけをする
- 入浴・排泄・食事・着替えなどのお世話をする
- ラジオやテレビの鑑賞をする
- 家族で過ごすときも参加させてあげるなど
また、日常的な活動の入浴やオムツの交換、食事の介助なども睡眠を促すためのよい活動になります。本人が好きだったラジオや音楽なども刺激になります。もちろん、家族で一緒に過ごしているだけでも、雰囲気から落ち着いて過ごせる機会になるのです。
認知症末期の睡眠状況が改善しない場合の選択肢
規則正しい生活を心がけてみたものの、睡眠状態に改善はみられなかったなんてこともあります。規則正しい生活習慣から、よい睡眠にしていくには長い期間がかかるので、数か月繰り返し対応することが重要です。それでも夜間の睡眠状況が改善されなかった場合は、サービスを利用して専門家の意見を聞くことをおすすめします。
家族の負担を軽減して状況に合わせたサービスを選択
サービスには、居宅サービス、施設サービス、地域密着型があります。主なサービスを、下記に記載します。
居宅サービス:自宅に足を運んでくれるタイプのサービス。
施設サービス:施設に入居した人へ提供するサービス。
地域密着型サービス:訪問や通所型、認知症対応型、特定施設型などの市区町村が提供するさまざまなサービス。
居宅サービスは、訪問・通所・短期入所サービスがあります。施設サービスは、老人ホームなどの施設入所型の身の回りのお世話を行ってくれるサービスになります。そして、地域密着型サービスは、他の2つのサービス内容と変わりはありませんが、市区町村が地域に合わせた介護事業所を設定してくれるサービスとなっています。
これらサービスを使用する場合の窓口は、地域包括支援センターや市区町村の役所などです。
専門家へ相談する
認知症末期の睡眠状況がよくないことにより、本人も家族にも大きなストレスや負担をもたらします。
本人が眠れないのには理由がありますので、まずはなぜ眠れないのかをしっかり把握することが重要です。しかし、本人は訴えることが難しいので、家族が眠れない理由を知るのはかなり時間がかかります。
もし、行き詰まってしまったら、認知症の専門家に相談することがよいでしょう。専門家に相談することで、眠れない理由を知るヒントになるかもしれません。
相談先は、全国の認知症疾患医療センターや日本認知症学会などにて、地域の医療機関を調べられます。
まとめ|認知症末期の生活を理解して介護にあたり、負担が大きいようであればサービスを検討しよう。
睡眠障害が起きる原因は日常の生活による影響が強いです。睡眠障害を解決するには、まずは規則正しい生活が重要です。しかし、解決には「しらみつぶし」のように要因を探っていくことが大切なのです。もちろん、試行錯誤します。
介護に疲れてしまった場合は、一人で悩むのは禁物です。必ず、サービスなどを利用し、誰かに協力を依頼するのがポイントになります。
もし、変化がなく悪化してしまうのであれば、サービス内容を変更して環境を変えてみたり、認知症専門医に相談してみるとよいでしょう。
必ずしも改善するとは限りません。昼夜逆転の大きな原因は、体内時計の乱れや不安から起こります。まずは、日中の活動を見直すことや睡眠の環境を整えることが重要となります。詳しくはこちらをご覧ください。
お住まいの「地域包括支援センターによる高齢者の総合相談窓口」や「市区町村の役所」「かかりつけの医療機関(医療ソーシャルワーカー)」「最寄りの市区町村社会福祉協議会」「地域に住む民生委員」「在宅介護支援センター」などで相談ができます。出向くことが不可能ならば、自治体のホットラインなど電話で気軽に相談もできます。詳しくはこちらをご覧ください。








