介護保険サービスの提供を日常的に受けていると、サービス費の負担額の大きさに、不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。実は、自己負担額の大きさに悩みを抱えている方は、多くいます。
そこで利用すべきなのが、サービスの利用で支払った自己負担額の一部が返金される「高額介護サービス費」という制度です。
しかし、この制度を利用すると、どの程度まで返金してもらえるのか、仕組みがわからない方のかもいるでしょう。
そこで、この記事では、高額介護サービス費の計算方法について詳しく紹介説明しています。サービス別の自己負担上限額についても解説説明していますので、ぜひ参考にしてください。
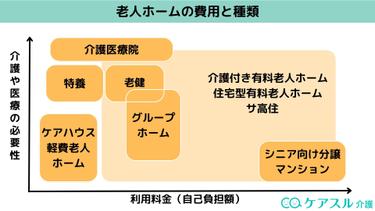
高額介護サービス費とは
高額介護サービス費とは、介護保険制度の提供サービスにかかる1カ月間で支払った支払金額が負担上限額を上回った際に、上回った分の支払金額が戻ってくる制度です。
介護サービスにかかる支払額は、一般的には1割負担ですが、一定額以上の所得がある方は2割、現役と同じくらいの所得がある方は3割負担になります。
介護サービスの量が増えると、支払う金額も高額になります。
高額介護サービス費は、1カ月間の自己負担の上限額を上回った際、上回った部分については払い戻しをしてもらえる制度です。
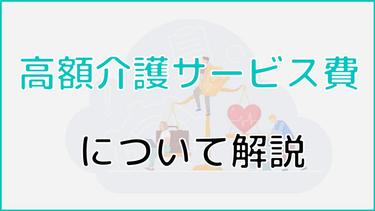
高額介護サービス費の算出方法
介護サービスの提供を受ける方が、ひとつの世帯で「ひとりなのか、複数人か」により、2通りの算出方法にわかれます。
- 利用者がひとり
- 利用者が複数人
具体的な事例を交えながら一緒に見てみましょう。
単身利用者の場合
単身でサービス提供を受けている方の算出方法は、「自己負担額-負担上限額」です。
例えば、1カ月の自己負担額が24,600円、提供サービスに40,000円を支払ったと設定し、上記の計算式に当てはめます。
「40,000円ー24,600円=15,400円」
払い戻してくれる金額は15,400円です。
複数人利用者の場合
複数人でサービス提供を受けている時の算出方法は、「(利用者の合計負担額-世帯の上限額)×個人の負担額÷利用者の合計負担額」です。
サービスの提供を受けた方が複数人の場合は、少し複雑になります。わかりやすく具体例をあげますので、一緒に見ていきましょう。
具体的な世帯情報を以下に設定して算出
- 父母2人にサービス提供
- 世帯の上限額は24,600円
- 父の支払金額は30,000円
- 母の支払金額は25,000円
上記で算出すると父と母の支払金額は55,000円です。
父と母の個人負担を計算式に当てはめてみます。
個人の割合を求めた金額が払い戻される額です。父と母の口座に計算で算出した金額がそれぞれ振り込みされます。忘れずに確認しておきましょう。
第2段階の利用者負担上限額とは
第2段階の利用者負担上限額の算出方法は、多少複雑です。具体的な例を交えながら一緒に見ていきましょう。
第2段階の利用者負担上限額に当てはまる方は以下の段階に当てはまる方です。
- 非課税世帯
- 個人の上限額は15,000円
- 世帯の上限額は24,600円
例えば、家族でサービスの提供を受け、提供月の利用が1人であれば「個人の上限額は15,000円」2人以上であれば「世帯の上限額24,600円」と考えます。
具体的な例を挙げて算出してみましょう。
「父の支払額14,000円、母の支払額11,000円」
(14,000円+11,000円)-24,600円=400円
- 個人の上限額の15,000円は上回っていない
- 世帯の上限額24,600円を上回っている
上記を算出すると払い戻しの対象金額は400円です。
「父の支払額16,000円、母の支払額7,000円」
16,000円-15,000円=1,000円
- 2人が支払った金額の合計が世帯の上限額を超えていない
- 父が個人の上限額の15,000円を上回っている
上記を算出すると払い戻しの対象金額は1,000円です。
細かい計算を覚えるのが苦手でも、自治体がしっかりと算出し報告してくれますので安心してください。
「介護施設への入居を検討している」「介護施設を探したい」という方は、ケアスル介護での相談がおすすめです。
ケアスル介護なら、全国5万を超える施設の中から、入居相談員に相談しながらあなたに合った施設を選ぶことが可能です。
初めて介護施設探しをするという方は、ぜひ一度相談してみてはいかがでしょうか。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
高額介護サービス費の負担上限額
高額介護サービス費の負担上限額は、所得により異なる6つの段階に分けられます。
令和3年8月に課税世帯の負担上限額の変更があり、所得の高い方の負担上限額が引き上げられました。ご自身の負担上限額を確認してください。
引用:厚生労働省「令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます」
世帯、個人の負担上限額を上回った部分が高額介護サービス費の対象となる金額です。
ただし、介護サービスの提供を居宅で受ける方は、介護区分により利用できる介護サービスの上限額も異なります。
居宅でサービスの提供を受ける場合
介護サービスの提供を居宅で受ける方は、介護区分で介護サービスの量の上限が決まっています。1カ月で提供が可能なサービスの量を以下の表にまとめました。
| 介護区分 | 1カ月に利用できるサービスの上限単位 |
| 要支援1 | 50,320単位 |
| 要支援2 | 105,310単位 |
| 要介護1 | 167,650単位 |
| 要介護2 | 197,050単位 |
| 要介護3 | 270,480単位 |
| 要介護4 | 309,380単位 |
| 要介護5 | 362,170単位 |
1単位の単価は10.90円や11.40円のように、サービス内容や地域によって異なります。注意点としては、上限額を超えて提供を受け発生した部分の利用料金は全額自己負担と考えておきたい点です。
サービス提供に関してはケアマネジャーが利用計画表を作成し、調整をおこなってくれますので相談してください。
施設で介護サービスの提供を受ける場合
施設で介護サービスの提供を受けている方は以下の2通りがあります。
- 多床室の利用
- ユニット型個室の利用
厚生労働省のサイトに1カ月の自己負担の目安が掲載されていました。居住費や食費などサービス以外の負担部分も参考になります。
なお、以前は所得だけで利用額が算出されていましたが、現在は資産基準が導入されているため、年金などの所得は少なくても、資産が一定額を超えていると補足給付が受けられなくなっている点には注意しましょう。
高額介護サービス費の申請方法
高額介護サービス費は、以下の手順で申請ができます。
- 自動的に郵送される申請書に記入
- 各自治体の窓口に書類を提出する
- 審査後、口座へ入金される
手続き自体は、各自治体から郵送された申請書に記入して提出するだけですので、難しくありません。
申請から振り込みまでの流れを詳しく見ていきましょう。
3ヶ月以内|自動的に郵送される申請書に記入
高額介護サービス費の対象者には、各自治体から自動的に申請書が郵送されます。
月の自己負担額を上回った場合、自治体が細かい計算をしたうえで申請書を送付してくれますので、必要事項を記入しましょう。
記入箇所などがわからない場合は、各自治体の窓口で相談できますので、次に紹介する必要なものを持って各自治体の窓口にいくだけなので心配ありません。
ただし、申請書の郵送時期は各自治体によって異なりますので、気になる方は問い合わせをしてください。
各自治体の窓口に提出する
郵送されてきた申請書に必要事項を記入できたら、申請に必要なものを準備して各自治体の窓口に提出しましょう。
申請に必要なものは以下のとおりです。
- 高額介護サービス費支給申請書
- 介護保険被保険者証
- 印鑑
- 振込先の口座情報などが確認ができるもの(本人名義)
申請自体は時間もかかりません。申請が終われば各自治体から発行される通知書を待つだけで、それほど手間はかからないでしょう。なお2回目以降は、自動的に手続きがおこなわれるため、利用者側が申請をしなくても、1回目と同じ流れで、自己負担上限額を超えた金額が払い戻されます。
2ヶ月以内|審査後に口座へ入金される
申請書を含めた書類を提出し審査に通ると、各自治体が発行する「支給決定通知書」が届きます。そのあと、申請時に記入した本人名義の口座に入金される予定です。
なかなか入金されない場合は自治体に問い合わせてみましょう。申請時に前もって、入金される時期を確認しておくと安心して振り込みを待てるでしょう。
「介護施設への入居を検討している」「介護施設を探したい」という方は、ケアスル介護での相談がおすすめです。
ケアスル介護なら、全国5万を超える施設の中から、入居相談員に相談しながらあなたに合った施設を選ぶことが可能です。
初めて介護施設探しをするという方は、ぜひ一度相談してみてはいかがでしょうか。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
高額介護サービスの支給方法
高額介護サービス費の支給には、以下の2通りの方法があります。
- 本人償還
- 受領委任払い制度
本人が手続きする「本人償還」と事業所側が手続きを負担してくれる「受領委任払い制度」です。どちらの方法も各自治体で手続きが必要ですので覚えておきましょう。
本人償還で支給される手続きが通常ですが、受領委任払い制度も自治体や事業所によって利用できる場合があります。それぞれ詳しく解説していきますので、自分に合った方法を選んでください。
本人償還
本人償還とは、自己負担額を上回った分の金額が後日支給される方法です。原則、この「本人償還」で支給されることになっています。
まず、サービスを受けている事業所に毎月、自己負担額を全額支払います。あとで自治体から郵送される申請書で手続きをし、支給される流れです。
そのため、払いすぎたお金が自分の口座に払い戻されるまで一定の期間がかかります。
受領委任払い制度
受領委任払い制度とは、介護を提供してくれる事業所や施設の窓口で自己負担上限額のみの支払いだけで済むようになる制度です。
月の負担上限額以上の支払い部分は介護サービス事業所が本人に代わり、あとに自治体に請求をしますので、この制度を利用すれば毎月支払う高額な自己負担を軽減できます。
支払う自己負担額が定額になり、安心して介護サービスを受けられるでしょう。
ただし、この制度を利用できる介護サービス事業所は限られていますので、気になる方は利用している事業所に問い合わせてみましょう。
長期化する介護期間に費用がかさむことが不安に感じる人も多い
厚生労働省の調査によると、平均的な介護期間と、1人あたりの介護費用額は、以下の表の通りです。
●平均的な介護期間(=平均寿命-健康寿命)
| 男性
8.73年 |
女性
12. 07年 |
平均で男性で約9年、女性では約12年の介護期間があるとも考えられ、介護にかかる費用もかさんでいきます。
●1人あたりの介護費用額
生命保険文化センターの調査によると、在宅介護にかかる費用は月額4万8000円、施設介護では月額12万2000円の介護費用がかかるとされています。
介護度が重くなるほど、かかる費用も増えていきます。たとえば要介護1では月額5万3000円ですが、要介護5になると月額10万6000円の介護費用がかかります。
| 要介護度 | 介護費用(月額) |
| 要支援1 | 4.1万円 |
| 要支援2 | 7.2万円 |
| 要介護1 | 5.3万円 |
| 要介護2 | 6.6万円 |
| 要介護3 | 9.2万円 |
| 要介護4 | 9.7万円 |
| 要介護5 | 10.6万円 |
参照:生命保険文化センター「令和3年度生命保険に関する全国実態調査」
高額介護サービス費は、所得に合った自己負担上限額まで軽減してくれる制度です。
しかし、初回は申請手続きをしない限りは適用されません。サービスの提供を受けてから2年以内に手続きをしておく必要があります。
各自治体から郵送された申請書は忘れずに手続きをしておきましょう。
高額医療・高額介護合算療養費制度とは
医療費と介護費用の両方がかかっているご家庭の場合、医療費と介護費用の両方を合算して、上限を超えたら払い戻してもらえる制度です。負担の上限額は、申請する人や世帯の所得などで決まっています。
介護が必要な方は、医療費がかかっていることも多いので、さらなる負担軽減制度があるのは、心強いですね。
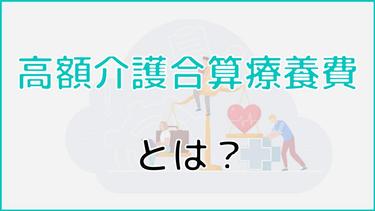
「介護施設への入居を検討している」「介護施設を探したい」という方は、ケアスル介護での相談がおすすめです。
ケアスル介護なら、全国5万を超える施設の中から、入居相談員に相談しながらあなたに合った施設を選ぶことが可能です。
初めて介護施設探しをするという方は、ぜひ一度相談してみてはいかがでしょうか。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
高額介護サービス費の計算方法を理解して一度算出してみよう
高額介護サービス費は、1カ月間で支払ったサービス費の自己負担額の合計が負担上限額を上回った際に、上回った分の金額が戻ってくる制度です。
高額介護サービス費の算出方法は1人で利用する場合と、2人以上で利用する場合で異なります。紹介した算出方法で一度算出してください。
また、所得の額によって自己負担額も異なります。ご自身の負担上限額と高額介護サービスに適用される金額がわかれば、必要以上に介護サービスの量を抑えなくてもよい場合もあるでしょう。
今後のために、ぜひ当記事で紹介した算出方法を試してください。
1カ月あたりの公的介護保険の自己負担額が高額になる場合、所得に応じた限度額の超過分を払い戻してもらえる制度です。第2段階の区分に該当する方は「個人」「世帯」両方の限度額の設定があり、負担を軽減できます。詳しくはこちらをご覧ください。
立て替えるのも難しい場合は、自己負担額を上回った部分を直接自治体から施設に支払われる制度です。利用できる自治体や事業所が限られていますので、一度問い合わせをしてください。詳しくはこちらで解説しています。





