要介護認定を受けた方の中には、「要介護2の認定を受けたけれど、調べてみると実際には3の気がしている」「要介護2と3で結局何が違うのかわからない」という方も少なくないと思います。
要介護認定は、認定調査員が自宅を訪問して被介護者の状態を調査したのち、主治医の意見書などを参考にして結果が出ますが、やはり認定調査員や当日の被介護者の状態によって結果にブレが生じるということも考えられなくもありません。
そこで、要介護2と3の状態にどのような違いがあるのか、またどのような判断基準に基づいて要介護2と3の違いは生まれるのかについて解説していきたいと思います。

要介護2と3の違い
要介護2と要介護3の違いは、主に身体状態と介助時間の2つです。
身体状態については、要介護2が家事や入浴、排せつ・食事などに部分的な介護が必要であるのに対し、要介護3ではそれらの生活動作全般に介護が必要な状態であるという違いがあります。
介助時間については、要介護3の方が介護が必要になる場面が多いため、介助時間が長くなる傾向にあり、終日の介護が必要になる割合が高いと言えます。
以下では、要介護2と3の状態、またその違いについて解説していきます。
要介護2の状態
要介護2の状態としては、日常生活を一人で送ることが難しい状態とされており、一人で家事や入浴、排せつ、食事などでも部分的に補助が必要になる状態のことを指しています。
具体的には、
- 立位保持や立ち上がる際に支えが必要な状態
- 食事や排せつ、入浴などの日常生活動作において見守りや部分的に手助けが必要
- 認知機能の低下(思考力や判断力など)が見られており、手助けが必要
などの状態であるとされています。したがって、要介護2の方が日ごろから見守りや介助が必要とされています。
以上より、要介護2の状態としては全面的に介助が必要な状態ではありませんが、立ち上がりや食事、排せつ、入浴などの日常生活において見守りが必要な状態であると言えるでしょう。
要介護3の状態
要介護3の状態としては、自分で立ち上がったりスムーズに歩行することが難しく、食事や排せつ、入浴などの日常生活においても介護が必要な状態を指します。また、認知機能の低下も進んでくるタイミングであり、見当識障害や実行機能障害があらわれる方も増えてくるタイミングとなっています。
具体的には、
- 排せつや入浴、服の着替えなどで全面的な介助が必要な状態
- 身の回りのことや家事全般を一人で出来ない
- 立位保持や立ち上がりを自力で行うことが出来ない
- 認知機能の全般的な低下が見られることがある
などが要介護3の具体的な状態と言えるでしょう。
したがって、要介護3の状態としては全面的な介助が必要になっている状態と言えるでしょう。
要介護2と3の介助時間の違い
内閣府の「令和元年版 高齢社会白書(全体版)」によると、要介護2の方と同居している介護者の介護時間としては、全体の約半数である50.2%が「必要な時に手を貸す程度」となっている一方で、要介護3の方と同居している介護者の介護時間としては、全体で最も多いのは「ほとんど終日」で32.5%であることがわかっています。
| ほとんど終日 | 半日程度 | 2~3時間程度 | 必要な時に手を貸す程度 | その他 | 不詳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護2 | 15.70% | 12.20% | 15.80% | 50.20% | 3.70% | 2.40% |
| 要介護3 | 32.50% | 17.60% | 13.10% | 27.70% | 5.90% | 3.30% |
上述したように要介護2の状態としてはに日常生活の一部で介助が必要な状態とされている一方で、要介護3は日常生活で全面的な介助が必要となっているだけに、実際の介護時間も長くなっていることがわかっています。
要介護2・3で入れる施設を探しているという方はケアスル介護で探すのがおすすめです。
入居相談員にピッタリの施設を提案してもらえるので、初めての施設探しでもスムーズに探すことが出来ます。
初めてで何から始めればよいかわからないという方はぜひ利用してみてください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
要介護2と3の違いが生まれるポイント
要介護2と3の違いが生まれるポイントは、厚生労働省によって定められている要介護認定等基準時間です。
本章では、具体的にどのような流れに沿って要介護2と3の違いが生まれているのかについて解説していきます。
要介護認定等基準時間によって違いが生まれる
要介護2と要介護3は厚生労働省によって定められている要介護認定等基準時間に沿って決められています。
| 要支援1 | 要介護認定等基準時間が25分以上32分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
|---|---|
| 要支援2要介護1 | 要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
| 要介護2 | 要介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
| 要介護3 | 要介護認定等基準時間が70分以上90分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
| 要介護4 | 要介護認定等基準時間が90分以上110分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
| 要介護5 | 要介護認定等基準時間が110分以上又はこれに相当すると認められる状態 |
(出典:厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」)
要介護認定等基準時間は、訪問調査員が訪問調査をした際に直接生活介助、間接生活介助、BPSD関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為の5つの観点で収集したデータをもとに、特養や介護医療院に入院・入所している3500人の実際の介護時間と照らしてどの程度の介護時間が必要になるのか算出したものとなります。
そのため、要介護2と要介護3は上述の基準時間が異なっているので、訪問調査及び主治医の意見書を参考にどの程度時間が必要と判断されるかによって違いが生まれる仕組みになっているのです。
なお、「1分間タイムスタディ・データ」と呼ばれる実際の介護施設におけるデータをもとに時間を算出しているので、実際に自宅で行われる介護時間とは異なることに注意しましょう。
違いに納得できない場合は?
要介護2と3の違いが生まれる理由について紹介しましたが、違いに納得することが出来ない場合は不服申し立てもしくは区分変更申請をすることで認定結果を変更することが出来る可能性があります。
不服申し立て(介護保険審査会への審査請求)をすると、要介護認定の再調査依頼をすることが出来るので場合によっては認定結果が変わる可能性があります。
ただし、不服申し立ては2カ月程度結果がわかるまでに時間がかかる可能性があるため、すぐに再申請をしたい場合は区分変更申請をするのも選択肢の一つです。
区分変更申請とは本来ケガや病気の進行で介護度が明らかに変わったと言える場合できる申請手続きですが、納得できない場合は本人の身体状況と介護度があっていない状態と言えるので不服申し立ての代わりに区分変更申請をするのも少なくありません。
要介護2と3の介護保険サービスの違い
要介護2と3で使える介護保険サービスの違いとしては、居宅介護サービスは要介護2と3で使えるサービスに違いはありませんが、施設サービスは要介護3の方から特別養護老人ホームに入所できる※のが違いです。
※要介護1、2の方でも特例入所が出来る場合があります。
居宅介護サービス
介護保険サービスのうち居宅介護サービスに位置付けられているサービスにおいては要介護2と3で利用できるサービスに違いはありません。
具体的には、要介護2であっても3であっても以下の介護保険サービスを利用することが出来ます。
| サービス分類 | 名称 | 概要 |
|---|---|---|
| 訪問サービス | 訪問介護 | 訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護や掃除や洗濯、買い物から調理までの生活支援を行う |
| 訪問入浴 | 利用者の身体の清潔の維持や心身機能の維持回復を図り、看護職員と介護職員が自宅に訪問し、持参した浴槽で入浴の介護を行う | |
| 訪問看護 | 看護師などが疾患のある利用者の自宅を訪問して、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の援助を実施する | |
| 訪問リハビリテーション | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが自宅を訪問し、心身機能の回復や日常生活の自立に向けたリハビリテーションを実施する | |
| 通所サービス | 通所介護(デイサービス) | 利用者が通所介護施設に通い、施設で食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練などを実施する。 |
| 通所リハビリ | 利用者が通所リハビリテーション施設に通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や生活機能向上のための機能訓練などを行います。 | |
| 短期滞在サービス | 短期入所生活介護(ショートステイ) | 介護老人福祉施設などの施設で常に介護が必要な方を短期間で受け入れ、食事や入浴などの日常生活上の支援、機能訓練などを提供する。 |
| 短期入所療養介護(医療型ショートステイ) | 医療機関や介護老人保健施設、介護医療院で日常生活上の世話や医療、看護、機能訓練などを提供。 |
※参考:厚生労働省「公表されている介護サービスについて」
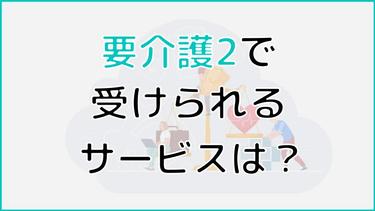
施設サービス
要介護2と3の方で利用することが出来る施設サービスの代表的な違いとしては、要介護3から特別養護老人ホームに入所できるという点があります。
特別養護老人ホームとは、要介護3以上の方を受け入れている公的な介護保険施設です。食事・入浴・排泄の介助や生活支援、リハビリ、レクリエーションから看取りまで対応しています。
公的な施設である特養は、他の介護施設よりも比較的安価で入所できることが特徴です。
ただし、安価で人気の高い施設であることから、地域によっては入所待ちが発生していることもあります。細かい状況はエリアごとに異なりますが、入所までに待機期間を要する場合もあることは理解しておきましょう。
基本的には要介護3以上の人が特養の入所対象となりますが、特例として要介護1~2の人でも利用対象となる場合があります。要介護1~2のうち、認知症や知的障害、精神障害などによって、日常生活がスムーズに送れない人は特養の利用対象です。
特別養護老人ホーム以外の公的施設である介護老人保健施設、介護医療院は要介護1から入所することが可能であるため、要介護2と3の違いはありません。
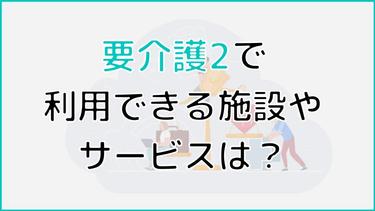
その他の介護保険サービス
居宅介護サービス、施設サービス以外にも地域密着型介護サービスや福祉用具の貸与・購入費用の支援や住宅改修の資金援助などを介護保険サービスとして利用することが出来ますが、要介護2と3で利用できるサービスに大きな違いはありません。
要介護2と3の区分支給限度基準額の違い
要介護2と要介護3で利用することが出来る介護保険サービスの種別に大きな違いはありませんが、利用できる介護保険サービスの量には違いがあります。
具体的には、要介護度ごとに設定されている区分支給限度基準額に違いがあるので、要介護3になると今まで利用することが出来なかった介護保険サービスも現在のものに加えて利用することが出来るようになる可能性があります。
| 区分 | 区分支給限度基準額(単位) | 自己負担割合1割の場合(円) | 自己負担割合2割の場合(円) | 自己負担割合3割の場合(円) |
|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 5032 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |
| 要支援2 | 10531 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |
| 要介護1 | 16765 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
| 要介護2 | 19705 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
| 要介護3 | 27048 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
| 要介護4 | 30938 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
| 要介護5 | 36217 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |
※1単位当たり10円として計算した場合
※出典;厚生労働省「区分支給限度基準額について」
以上の表のように、要介護2と3では基準となる単位数が異なりますので利用できる介護保険サービスの量が異なることを覚えておきましょう。

要介護2と3の違いのまとめ
要介護2は日常生活を一人で送ることが難しい状態とされており、一人で家事や入浴、排せつ、食事などでも部分的に補助が必要になりますが、要介護3は自分で立ち上がったりスムーズに歩行することが難しく、食事や排せつ、入浴などの日常生活においても介護が必要な状態を指します。
また、要介護2と3では利用できる介護保険サービスの種類に大きな違いはありませんが、利用できる介護保険サービスの量には大きな違いがあることが特徴と言えるでしょう。
要介護2は日常生活を一人で送るのが難しく部分的に介助が必要な状態ですが、要介護3は全面的な介助が必要な状態です。内閣府の調査のように、実際の家庭での介護時間も異なることがわかります。詳しくはこちらをご覧ください。
要介護2と3の違いが生まれるポイントは、厚生労働省によって定められている要介護認定等基準時間です。詳しくはこちらをご覧ください。
VOICEVOX:四国めたん





