グループホームは、介護サービス費は要介護度によって定額となっています。
他のサービス同様に費用の1〜3割の自己負担で利用できますが、住居費、管理費・共益費、食費には介護保険は適用されません。また、日用品やおむつ代など、雑費が使った分だけかかってきます。
近年、年金支給金額の引き下げや物価上昇による施設の住居費(賃料)、食費の値上げで、今まで支払えていた費用でも難しくなってくる場合もあるでしょう。
もし、グループホームの費用が払えないとなった場合どうすればいいのでしょうか?
強制退去になり追い出されてしまうのではと、不安に思っている方もいるかもしれません。
本記事では、グループホームの費用が払えない場合どうすればいいのか、利用できる制度はあるのかなどを紹介していきます。
関連記事
 グループホームの費用はいくら?費用を抑え、年金で賄うためのコツも伝授!カテゴリ:グループホームの費用更新日:2025-12-18
グループホームの費用はいくら?費用を抑え、年金で賄うためのコツも伝授!カテゴリ:グループホームの費用更新日:2025-12-18関連記事
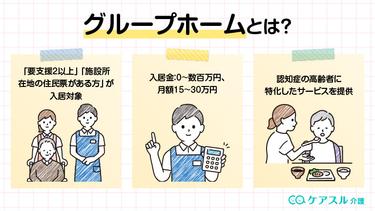 グループホームとは|入居条件からサービス内容、デメリットまで解説カテゴリ:グループホーム更新日:2025-12-18
グループホームとは|入居条件からサービス内容、デメリットまで解説カテゴリ:グループホーム更新日:2025-12-18
グループホームの費用が払えない時はまず相談
グループホームの費用が払えない、支払いがかなり厳しいと思った場合には施設のスタッフや施設に所属するケアマネジャーに相談しましょう。
ここで最もやってはいけないのは、相談もせず支払いを放置することです。
無断で放置をしてしまうと、施設側との信用問題に関わります。
今後もお世話になると考えれば、信用がなくなる事態はできるだけ避けましょう。
スタッフやケアマネージャーに相談をすると、さまざまな提案や制度の紹介をしてもらえます。
今よりも費用負担の軽い施設に移ったり、今の施設のまま費用を抑える工夫を行ったりと相談に乗ってもらえるでしょう。
短期的な理由で支払いができない場合は、一時的に支払いを見送り分割で少しずつ支払っていくなど方法はさまざまです。
ただし、どのような対策が可能なのか、どれくらい負担を減らせるのかなどは、現在のサービス利用状況や責任者の判断などによって変わります。
またグループホームの費用が払えない場合は、費用の安い施設に移り住むのもひとつの手となります。
介護施設・老人ホームをお探しの際には、ケアスル 介護で相談してみることがおすすめです。
ケアスル 介護ではご本人様の身体状況や必要となる介護サービスをお伺いしたうえで、入居にどれくらいの費用が掛かるのかもご案内します。
「分からないことを相談して安心して施設を選びたい」という方は、まずは無料相談からご利用ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
グループホームの費用が払えなくなったらすぐに退去させられる?
もしグループホームの入居中に費用が支払えなくなったとしても、すぐに退去させられるわけではありません。
ほとんどの場合、グループホームなどの施設では月々の費用は本人が支払うようになっていますが、もし本人が何らかの事情で支払えない場合は、入居時に登録した身元引受人や連帯保証人に請求が行われます。
ここで、身元引受人が支払ってくれれば、特に問題はありません。
しかし、身元引受人も支払えない場合、支払の猶予期間があります。
猶予期間は3〜6か月程度用意されていますが、施設によって違います。
場合によっては1〜2か月程度とかなり短い場合もあるので、注意してください。
猶予期間に関しては、入居時に交わした「重要事項説明書」に記載されているはずです。
支払いができなかった場合、この猶予期間に費用を支払う方法を見つけるのか、施設移動するかなど対応を決める必要があります。対応が決まらないまま、猶予期間が過ぎれば契約解除となり強制退去となります。
グループホームの費用が支払えないときの制度9選
グループホームの費用が支払えなくなった場合の対処法は、受けるサービスを減らす、施設を移るなどさまざまです。それだけではなく、国や自治体が行っている制度を利用すれば、滞り無く支払いができる可能性があります。
ここで支払いが難しい時に利用できる制度を9つご紹介します。
- 生活保護の受給
- 特定入所者介護サービス費制度
- 介護保険料の軽減
- 高額介護(予防)サービス費制度
- 高額医療・高額介護合算療養費制度
- 自治体独自の助成制度
- 社会福祉法人の軽減制度
- リバースモーゲージ
- マイホーム借り上げ制度
国や自治体が行っている制度を利用するためには、家族の経済状況や住んでいる地域などによって条件をクリアする必要があります。ケアマネージャーや施設スタッフの方は、地域の制度や最新の制度にも詳しいのでぜひ相談してみましょう。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
1.生活保護の受給
生活保護とは、生活が困窮している方に向けて国が行っている制度です。文化的で最低限な生活を保証するために現金が支給されますが、金額に関しては地域や世帯状況で変わります。
生活保護を受ける際の条件は以下の通りです。
- 世帯全体の収入が月13万円以下(年収156万円以下)
- 身内から資金的援助を受けられない
- 働けない
- 預貯金や土地などの財産を持っていない
身内から資金的援助を受けられず、土地などの財産を持っていなければ生活保護の受給は可能です。
また、生活保護で支給されたお金は、使用用途が生活を行うためと定められており、グループホームへの支払いなどの介護費用も生活保護の補助対象です。そのため、生活保護で受給したお金を施設の支払いに充てても問題ありません。
参考:厚生労働省
2.特定入所者介護サービス費制度
所得の低い人の居住費や食費を軽減する制度です。これらの費用は、介護保険の適用外となっていますが、所得によって負担限度額が決まっており、差し引いた分は介護保険から支払われます。
特定入所者介護サービス費制度の負担限度額は所得や施設の種類によって変動し、該当する施設は以下の通りで、グループホームは含まれません。つまり、この制度を活用するには、以下のような施設に移ることが不可欠となります。
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 短期入所療養介護
対象となるのは以下の条件をすべて満たしている方です。
- 介護認定を受けている
- 別世帯の配偶者を含む世帯全員が住民税非課税
- 預貯金などが一定金額以下
特定入所者介護サービス費制度の申請方法は、住んでいる市区町村に介護保険負担限度額認定申請書などを記入し申請を行います。
3.介護保険料などの軽減
介護保険は40歳になってから毎月納付を行い、要介護認定を受ければ介護サービス費が1割負担になります。
ただし、一定の条件を満たせば、介護保険料や介護サービス費の軽減が受けられます。
詳しい条件は市区町村によって異なり、条件をすべて満たしている方が市区町村へ申請を行います。
大まかな条件は以下の通りです。
- 世帯年収が1人世帯150万以下である(世帯が1人増えるごとに+50万円)
- 世帯の貯蓄額が1人世帯350万以下である(世帯が1人増えるごとに+100万円)
- 居住用以外の土地や建物を所有していない
- 親族などに扶養されていない(証明書が必要になる場合もある)
- 介護保険料を滞納していない
減免の内容や申請に必要な書類は市区町村や個々のケースによって変わるため、まずは市区町村へ問い合わせましょう。
4.高額介護(予防)サービス費制度
高額介護(予防)サービス費制度とは、対象になる1か月分の介護保険サービス費用のうち一定金額は自己負担となり、超えた分を支給してもらえる制度です。自己負担となる一定金額は所得に応じて変動します。
この制度は自分から申請する必要はなく、高額介護(予防)サービス費制度の対象となった場合は市区町村から申請書が送られてくるでしょう。
送られていた申請書に必要事項を書き込み提出をすれば、上限金額を超えた月は自動で登録した口座に還付されます。
こちらは一度申請すれば、上限を超えた月は自動で還付されるため、申請を更新する必要などはありません。
5.高額医療・高額介護合算療養費制度
高額医療・高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険における1年間の自己負担額の合計が高額の場合自己負担額を軽減してくれます。
高額医療・高額介護合算療養費制度における1年とは、8月1日〜7月31日で計算されるため注意が必要です。
高額医療・高額介護合算療養費制度の対象者は以下の条件に該当する世帯です。
- 国民健康保険などの各医療保険における世帯内である
- 1年間の医療保険と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えている
自己負担額の限度額に関しては、各所得区分ごとに設定されています。申請方法は、高額医療・高額介護合算療養費制度の対象となれば、市区町村から申請書が送られてくるので、必要事項を記入し提出をします。
高額医療・高額介護合算療養費制度の対象となるのは、医療保険と介護保険の自己負担額のみであり、食費や居住費、保険診療外費用は対象外です。
6.自治体独自の助成制度
こちらは、どこに住んでいるのかによって利用できるかどうか大きく変わります。
高齢者支援の一環として、各自治体が独自に行っている助成制度であり、一定の条件を満たせば介護サービス費用の助成が受けられます。
助成制度の例を一部ご紹介していきましょう。
- 緊急通報システム:装置をレンタルし24時間いつでも駆けつけてくれる
- おむつ類:おむつやおしりふきの現物支給やおむつ代の助成
- 住宅修繕:介護保険制度とは別に用意できる場合がある
- 外出支援:タクシーの利用券やバスの乗車料金に対する助成
- 宅食サービス:食事を届ける場合と民間サービスを利用する際の料金に対する助成
- 介護予防教室:要介護状態にならないように又は悪化防止を目的とした教室の実施
- 生活支援:介護保険ではカバーされない洗濯など
ほかにも、T字杖の無料支給などが用意されています。また、これらの制度はすべての自治体で行われているものではなく、似た名前であっても条件などが違う場合もあります。
どんな制度があるのか、詳しい条件や申請方法などは、各自治体に問い合わせるか、担当のケアマネージャーに聞いてみましょう。
7.社会福祉法人等による軽減制度
社会福祉法人等が運営する施設を対象とした軽減制度(社会福祉法人等による低所得者に対する利用者負担軽減制度)は、入居しているグループホームが社会福祉法人の場合、実施されている可能性があります。
一定以下の所得の方に対して、介護サービスの自己負担額や食費、居住費が1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)まで軽減されます。ただし、現段階ではグループホームは対象外となっており、この制度を活用するには、施設を移ることが必要となります。
社会福祉法人の軽減制度を受けるための条件は以下の5つの条件を満たしている必要があります。
- 単身世帯で年間収入150万円以下である(1人増えるごとに+50万円)
- 単身世帯で預貯金などの合計が350万円以下である(1人増えるごとに+100万円)
- 日常生活に必要な資産以外に活用できる資産がない(居住目的以外の土地や建物など)
- 親族などに扶養されていない
- 介護保険料を滞納していない
申請に関しては、自治体の担当窓口で申請書類をもらい、必要事項を記入し提出します。条件を満たしており、書類に不備が無ければ「社会福祉法人の利用者負担軽減確認証」が届きます。こちらが届いたら必ず利用している施設へ提示してください。
社会福祉法人の利用者負担軽減確認証が手元に届いただけでは、軽減は受けられません。この点のみ注意してください。
8.資産価値で融資限度額が決まるリバースモーゲージ
リバースモーゲージとは、自宅などの資産価値があるものを担保にして生活資金を借り入れる方法です。社会福祉協議会や金融機関が借入先となりますが、貸付金額の限度や対象物件が違う場合があるので、注意してください。
借りられる金額は、担保の資産価値に左右されます。返済に関しては、借り入れた方が死亡すれば、担保物件を処分して返済に充てられます。
金融機関借入先の場合、主に2つの種類があります。
- 住宅金融支援機構と連携して借り入れを行う
- 金融機関独自で行う
どちらも借り入れた方が生きている間は利息のみを支払い、借り入れた方が亡くなったあとに相続人が自宅を売却し返済します。
リバースモーゲージで担保にした住宅に、2世帯(子ども夫婦が住んでいるなど)は住めません。金利や詳しい条件などは、どこからリバースモーゲージを行うのかによって変わります。複数の場所で金利や条件を聞き、最も納得できたところと契約を結ぶようにしましょう。
9.住んでいない自宅を貸すマイホーム借り上げ制度
マイホーム借り上げ制度とは、50歳以上の方でマイホームを持っている方が利用できる制度です。空室になっているマイホームを、ほかの方へ転貸を行います。
そうすると月々の賃料が発生し、その賃料を受け取れます。
事前に貸出期間を決めるので、その期間が終了すれば売却したり、もう一度住むのも可能です。
貸し出す家には以下の条件を満たしておく必要があります。
- 単独所有または共同所有する日本国内の住宅
- 建物診断が実施されている
- 建物診断の結果に応じた必要な工事が行われている
- 居住用の住宅である
また、1人目の入居者が決まれば、それ以降は空き家となっても既定の賃料が保証されます。
そのほか老人ホームの費用が払えない場合の対処法について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
グループホームの費用が払えない場合はまず相談
もし、グループホームの費用が払えなくなっても、すぐに追い出されることはありません。必ず猶予期間が存在するため、その期間内に費用負担の軽い施設へ移動したり、国などが行っている制度を利用したりしましょう。
利用できる制度や、申請方法などは役所や施設スタッフやケアマネージャーが教えてくれます。困ったときは一度相談してみましょう。
すぐに退去させられる心配はありません。基本的には3〜6か月程度の猶予があります。この猶予期間に費用を工面するか、施設移動するかなど対応を決めなければなりません。対応が決まらないまま、猶予期間が過ぎれば契約解除となり、強制退去となります。猶予期間は基本的には3〜6か月程度用意されている場合が多いです。しかし、施設によっては1〜2か月程度とかなり短い場合もあるので、注意してください。詳しくはこちらをご覧ください。
利用できる制度は以下のようなものがあります。①生活保護 ②高額介護(予防)サービス費制度 ③高額医療・高額介護合算療養費制度 ④自治体独自の助成制度 ⑤社会福祉法人の軽減制度 ⑥リバースモーゲージ ⑦マイホーム借り上げ制度自治体によって詳細な条件などは変わるため、ケアマネジャーに相談してみるといいでしょう。詳しくはこちらをご覧ください。





