介護は長期間にわたり行う必要があり、多くの費用がかかります。ご本人やご家族の方には、どうしても経済的な心配と先が見えない不安がついてまわるでしょう。
そんな不安と経済的な負担を減らすのが「介護保険負担割合」です。すでに介護サービスを受けていても、聞き慣れない方も多いと思います。
本記事では、介護保険負担割合について解説し、経済的な負担を軽くする耳寄り情報もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
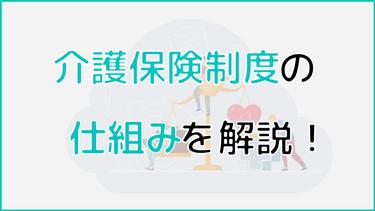
介護保険の仕組みと対象者
介護保険制度は市区町村が保険者として運営している公的な社会保険制度です。介護が必要な方の経済的な負担を軽減し、適切なサービスを受けられるよう支援しています。
40歳になると加入する義務が生じ、保険料を納め始めます。義務の生じた40〜64歳の方を「第2号被保険者」といいます。65歳以上の方は「第1号被保険者」と呼ばれ、介護保険サービスの利用が可能です。しかし、65歳になったからといってすぐにサービスを受けられるわけではありません。介護保険サービスを利用するには、市区町村の窓口で申請し、要介護・要支援認定を受ける必要があります。必要性を認められて初めて利用できるのです。
しかし、40歳から64歳までの方もサービスを受けたい場合もあるでしょう。リウマチやパーキンソン病など「特定疾病」に該当する病気を患っている方はサービスの対象になります。
介護保険に対応している施設への入居を検討しているという方は、ケアスル介護がおすすめです。ケアスル介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができるためご希望に沿った施設探しが可能です。
「プロに相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
介護保険の負担割合は収入によって異なる
介護保険サービスを利用した場合、自己負担は基本1割です。この自分が負担する割合を、介護保険負担割合といいます。残りの9割は介護保険が「介護給付」として保険料や税金より負担します。
しかし、すべての方が1割の負担でサービスを受けられるわけではありません。収入が高く支払い能力があるとみなされた方、条件を満たした方など一部の方は、介護保険負担割合が2〜3割になります。
この介護保険負担割合は収入に応じて決定されるため、貯蓄が多く収入の少ない方は1割、貯蓄が少なく収入が多い方は2〜3割になるケースもあります。

介護保険の負担割合
介護保険負担割合は「前年度の所得」をベースに、「年齢」「65歳以上の方の世帯人数」などの状況に応じて決定します。具体的にはどのような条件で負担割合が上がるのか確認していきましょう。
引用:『平成30年8月から現役並みの所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が3割になります』
介護保険の自己負担割合を判定するための「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、所得金額調整控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また、長期・短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。
「その他の合計所得金額」とは、この合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
例えば、夫婦ともに年金収入のみ、合計所得金額が夫200万円、妻150万円、合計350万円の世帯があったとします。この場合、夫は合計所得金額が160万円以上220万円以下、夫婦の所得が346万円以上なので自己負担は2割です。妻は合計所得金額が160万円未満のため1割負担です。
自身の合計所得金額を知る機会がないという方は、年末調整や確定申告を行っている場合、お住まいの市区町村の役所・役場で合計所得金額を確認できます。気になる方は一度確認してもいいかもしれません。
介護保険負担割合は毎年見直され、そのときの状況や収入に応じた変更がなされます。「本人名義の土地を売ったら、介護保険負担割合が上がってしまった……」といった例もあるため注意しましょう。
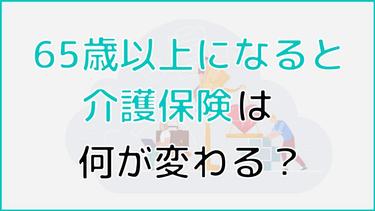
介護保険負担割合証とは
市区町村により決定された負担割合は「介護保険負担割合証」として交付されます。更新時期はいつなのか、いつ使うのかなど介護保険負担割合証の特徴をこれから解説していきます。
有効期限は1年間
介護保険負担割合証の適用期間は、毎年8月1日から翌7月31日までです。原則、更新の申請などは必要ありません。毎年6〜7月に新しいものが市区町村より郵送されます。ただし、5月末時点で要介護認定を受けていなかった方は自動更新ではないため、申請を忘れないように注意しましょう。
初めて介護保険サービスを利用する方や要支援者などの総合事業の対象者は、認定に合わせて決定および交付されます。介護保険負担割合証が送られてきたときに初めて自己負担割合を把握できるため、チェックを忘れず行いましょう。
ケアマネや各種サービス事業所に提示が必要
介護保険負担割合証は利用料金に直接関わる大切なものです。交付されたタイミングで必ずケアマネジャーや利用している介護サービス事業者に提示しましょう。新しくサービスを利用開始する場合は、介護保険被保険者証と合わせて提示が必要です。介護保険負担割合証を提示せずにいると、本来は軽減されるはずだった料金がそのまま請求される可能性があるため注意してください。
7月は医療保険証や負担限度額認定証なども更新される時期です。まとめて提示すると、ケアマネジャーの負担が低くなります。また、介護保険被保険者証や医療保険証などはセットにして保管おくと必要なときに慌てる心配がありません。
紛失した場合は再発行可能
介護保険負担割合証は重要な証書ですが、うっかり無くしてしまう場合もあるでしょう。実は介護保険割合証は再発行が可能です。市区町村の役所・役場にある再交付申請書を記入し提出するだけで、再発行してもらえます。市区町村のホームページからダウンロードできる自治体もあるので、調べてみてもいいかもしれません。
比較的容易に再発行は可能ですが、発行まで1週間ほどかかる場合もあります。タイミングによっては料金の軽減が受けられない可能性があるため注意しましょう。
介護保険の負担割合が変わるタイミング
更新時期以外にも負担割合が変わるタイミングが大きく分けて3つあります。
- 65歳になった場合
- 世帯構成に変更があった場合
- 住民税の所得更正があった場合
適用期間中に65歳になる場合は、交付される負担割合証にあらかじめ65歳到達前後の負担割合が記載されます。今まで1割負担で利用していたサービスが2割、3割となる可能性があるため事前にチェックしておくといいかもしれません。
家族の「転入・転出」「死亡」「65歳到達」によって世帯構成が変更になる場合は、該当日の翌月初日から変更になります。ただし、該当日が月の初日の場合はその月から変更になるため注意しましょう。
また、所得更正により所得等が変更された場合にも介護保険負担割合が変わる可能性があります。
所得更正とは、確定申告に関わる手続きです。納める税金が多い場合や還付される税金が少なすぎた場合に、正しい額に訂正を求める申請を指します。こちらが適用された場合、適用期間開始月の8月まで遡って負担割合が変更になる可能性もあります。その場合は各サービス事業所に事情の説明を行い、過誤申請と呼ばれる差額調整の手続きが各事業所より必要です。
介護保険の負担割合で困ったときに活用できる制度
介護保険負担割合により経済的負担は大きく軽減されますが、長期にわたる介護ではどうしてもご家族のお金の心配がついてまわります。実はそんなとき利用できる制度がいくつかあるため、ご紹介していきます。
負担上限額から超えた分が対象になる制度
1〜3割の自己負担で介護サービスを利用できますが、家庭の事情やご本人の状態によって必要なサービスや頻度はそれぞれです。多くのサービスを利用すれば、その分毎月の利用料も高くなってしまいます。そんな方々にご紹介したいのが「高額介護サービス費制度」です。
高額介護サービス費制度を利用すると、1か月間に支払った介護サービス費が一定額を超えた場合、超えた分が戻ってきます。あくまで介護保険サービス費のみが対象で、食費や雑費等はこの料金に含まれませんが、申請の手間も少なく、介護サービス利用者とその家族に寄り添った制度といえるでしょう。この制度は各世帯の収入によって、以下のように上限額が決められています。
1ヶ月間の世帯ごとの上限額(令和4年9月時点)
| 区分 | 負担上限額(月額) |
|---|---|
| 年収約1160万円以上 | 140,100円(世帯) |
| 年収約770万円以上約1160万円未満 | 93,000円(世帯) |
| 年収約770万円以下 | 44,400円(世帯) |
| 世帯全員が住民税非課税世帯
(前年の課税年金+その他の合計所得金額が80万円以下) |
24,600円(世帯)
15,000円(個人) |
| 生活保護受給者等 | 15,000円(世帯) |
参照:『高額介護サービス費-厚生労働省』
上記の額を超えた場合、超えてから数ヶ月後に市区町村から自動で通知書が届きます。忘れずに申請を行いましょう。
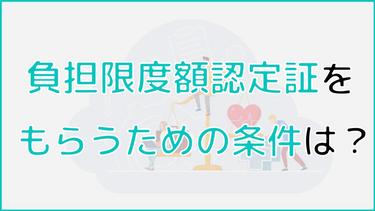
医療・介護保険の負担軽減に使える制度
ご本人の体調に変化があると、医療も介護もより多くのサービスが必要になりがちです。そんなときは「高額医療・高額介護合算費療養制度」を利用しましょう。
高額医療・高額介護合算費療養制度は1年間の負担を少なくする制度です。毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間にかかった介護保険サービスの自己負担額と医療費の自己負担額を合計し、上限額を超えた場合に超えた金額分が払い戻されます。
1年間の上限額(令和4年9月時点)
| 区分 | 70歳以上 | 70歳未満 |
|---|---|---|
| 年収1,160万円以上 | 212万円 | 212万円 |
| 年収770万円以上1,160万円未満 | 141万円 | 141万円 |
| 年収370万円〜770万円未満 | 67万円 | 67万円 |
| 年収156万円〜370万円 | 56万円 | 60万円 |
| 世帯全員が住民税非課税者 | 31万円 | 34万円 |
| 住民税非課税者かつ年金収入80万円以下 (所得が一定以下) |
19万円 | 34万円 |
参照:『高額介護合算療養費制度の限度額-公益財団法人長寿科学振興財団』
世帯に70歳以上と70歳未満がいる場合、まず70歳以上の自己負担合算額に限度額を適用したあと、残る負担額と70歳未満の自己負担合算額を合わせた額に限度額を適用します。また、所得が一定以下の住民税非課税世帯かつ70歳以上で介護保険サービスを利用している方が複数いる場合には、上限額は31万円です。
こちらも該当者には市区町村からお知らせが届きます。翌年の2〜3月に届くため、必ず申請を行いましょう。
住環境整備のためのお得なサービス
在宅で介護をしていると、ご本人が安心安全に過ごせるよう手すりをつけたり、自宅を改修したりする必要が出てきます。そんなときに1度だけ支給を受けられるのが「居宅介護住宅改修費」と「介護予防住宅改修費」です。要介護か要支援かによってどちらを利用できるか決まります。
- 手すりの設置
- 段差の解消
- 滑り防止および円滑な移動のための床材の変更(畳・じゅうたん・板材等)
- 引き戸等への扉の取り替え
- 洋式便座等への便器の取り替え
- 上記の住宅改修に付帯して必要となる改修(下地補強、給排水設備工事、壁・柱・床材の変更等)
※玄関から道路までの屋外の工事も対象
上記の改修を対象に、最大20万円分、改修費の7〜9割を介護保険で負担してもらえます。支給は原則1回限りですが、要介護区分が3段階上昇した場合や引っ越し等の理由で改めてリフォームする場合は再度支給申請が可能です。
この給付金は、自分たちで勝手に改修しても支給の対象になりません。以下のような手順を踏む必要があります。
- ケアマネジャーや理学療法士等に相談
- 相談を受けた専門職が本人の状態や希望に合わせ改修の提案を行う
- 住宅改修事業者を選択
- 住宅改修事業者が見積書を作成
- ケアマネジャーもしくは利用者が着工2週間前までには事前申請を行う(申請書類)
① 支給申請書
② 住宅改修理由書
③ 工事費見積もり書
④ 住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単な図を用いたもの)※住宅改修理由書の作成者は介護支援専門員、地域包括支援センター担当職員、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上そのほかこれに準ずる資格等を有する者に限られる - 市区町村から保険給付の許可を得て着工
- 住宅改修事業者へ支払いを行う
- 市区町村に改修費の領収書や費用の内訳、改修前と後の写真等を添えて提出
- 市区町村が書類を確認し、住宅改修費の支給が必要であると認めた場合、住宅改修費を支給
新築や増改築と合わせての改修は対象外です。また、領収書はご本人の名前でもらう必要があるため注意してください。

医療費控除は支払った医療費等が対象
確定申告で「医療費控除」の文字を見た方も多いのではないでしょうか。医療費控除は、自分や家族が1年間で一定以上の医療費を支払った際に、確定申告によって、翌年の税金を安くできる制度です。窓口で支払った自己負担額が対象となります。
一部の介護保険サービスの自己負担分や、特定の入所施設での介護サービス費や食費、居住費やおむつ代なども計上できます。居宅サービス事業者等の領収証には医療費控除の対象額が記載されているため、一度確認してみるといいかもしれません。
ただし、確定申告の際には医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付してください。医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。控除の請求を行いたい年の(1月1日〜12月31日分)の領収書が必要になるので、保管し忘れないようにしてください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
介護保険負担割合は介護サービス費に影響するため把握しよう
介護保険負担割合は介護費用に大きく関わるものです。どのような条件で変更になるのか、負担割合が上がる可能性はあるのかを知るだけでも、介護における費用の不安を和らげられるかと思います。上手に活用し、安心した介護ライフを送りましょう。
介護保険負担割合に関するよくある質問
Q.生活保護を受給していますが対象ですか?
A.対象です。生活保護を受給している場合は1割負担になります。
Q.介護保険負担割合証の更新手続きは必要ですか?
A.更新手続きは不要で自動的に自宅へ届きます。届いたら、ケアマネジャーや各サービス事業所への提示を忘れずに行いましょう。





