会社で働きながら親の介護をする、という方は近年多くいらっしゃいます。
休みの日に介護をするだけなら問題ありませんが、平日や出勤日に介護が必要になったら介護休暇を取って介護をする必要があります。そうなると気になるのは、介護休暇中に給与が出るのかどうかという点でしょう。
この記事では、「介護休暇中に給与が出るのかどうか」「休暇中に給与を支給してもらうにはどうすればよいのか」といったことについて解説していきます。
介護休暇では給与はもらえないことが多い
介護休暇は、要介護状態にある家族を介護するために取ることができる休暇であり、制度として定められています。
介護休暇は国によって定められている制度ですが、給与が出るかどうかは会社によって異なり、給与が出ないケースが多いです。
ここでは、介護休暇制度の概要や給与の仕組みについて解説していきます。
介護休暇とは
介護休暇とは、要介護の方が家族にいる場合に、その介護のために一時的に休暇を取ることができる制度です。育児介護休業法という法律で定められており、労働者の権利として定められています。
一時的な介護を目的とした休暇制度であり、ケアマネージャーや介護サービス担当者との打ち合わせや、通院の付き添いなどで活用することができます。なお、休暇取得可能な日数は、
- 要介護者1人に対して年間5日まで
- 要介護者2人に対して年間10日まで
となっています。会社側が定めていない場合は4/1~3/31の間が対象期間となっており、繰越はできません。
時間単位で取得できる
2021年1月1日に育児介護休業法が改正され、介護休暇を1時間単位で取得できるようになりました。
これまでは、1~2時間の介護をするためだけでも1日分の介護休暇を取る必要があったため、時間に「一時的な介護」という制度の目的と実態が釣り合っていないという状態が続いていました。
今回の法改正によって時間帯で所得できるようになり、「午前中は介護をするので3時間だけ介護休暇を取得し、13時からは勤務する」といったような働き方ができるようになったため、柔軟に介護休暇を活用できるようになりました。
介護休暇の給与規定は会社によって異なる
介護休暇中の給与に関して、会社側に支払いの義務はなく、会社の規定や就業規則によって異なります。原則無給となっている企業が多く、有給となっている場合は就業規則等に記載があります。
また、介護休暇に関しては国からの補償や補助金等もありません。
介護休暇を取る条件
介護休暇は、介護のためなら誰でも使えるのかと言われるとそうではありません。そのうえ、介護する相手にもある程度の条件があり、もしこれらの条件を満たしていない場合は、ただの欠勤になってしまう可能性があります。
ここでは、介護休暇を取る条件を見ていきましょう。
労働者側の条件
基本的に、対象となる要介護者を介護する立場にある労働者は皆、介護休暇を取得することが可能です。ただ、下記の場合は対象外となります。
- 入社6か月未満の労働者
- 1週間の労働日数が2日以下である労働者
- 日雇い労働者
- 半日・時間単位での介護休暇取得が困難な業務に従事している労働者
なお、正社員・パート・アルバイト・派遣社員といった勤務体系は問わず、上記4つの労働者でなければ皆が介護休暇を使うことが可能です。
介護相手側の条件
介護休暇を取る際は、介護する相手にも条件があります。本人とは見ず知らずの人の介護のために休暇を取られては会社としてはどうしようもないため、この条件が設定されています。
介護対象となるのは、基本的に本人の家族です。父や母、子、孫、配偶者、配偶者の父や母、祖父母、兄弟、姉妹が当てはまります。
また、介護対象の家族は要介護状態である必要があります。具体的には、「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」のことを指します。要介護状態の判定基準は、下記2つです。
- 要介護2以上であること
- 下記表の状態(1)~(12)のうち、2が2つ以上または3が1つ以上該当し、かつその状態が継続すると認められること
| 項目\状態 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| (1)座位保持(10分間一人で座っていることができる) | 自分で可 | 支えてもらえればできる | できない |
| (2)歩行(立ち止まらず、座り込まずに5m程度歩くことができる) | つかまらないでできる | 何かにつかまればできる | できない |
| (3)移乗(ベッドと車いす、車いすと便座の間を移るなどの乗り移りの動作) | 自分で可 | 一部介助、見守り等が必要 | 全面的介助が必要 |
| (4)水分・食事摂取 | 自分で可 | 一部介助、見守り等が必要 | 全面的介助が必要 |
| (5)排泄 | 自分で可 | 一部介助、見守り等が必要 | 全面的介助が必要 |
| (6)衣類の着脱 | 自分で可 | 一部介助、見守り等が必要 | 全面的介助が必要 |
| (7)意思の伝達 | できる | ときどきできない | できない |
| (8)外出すると戻れない | ない | ときどきある | ほとんど毎回ある |
| (9)物を壊したり衣類を破くことがある | ない | ときどきある | ほとんど毎日ある |
| (10)周囲の者が何らかの対応をとらなければならないほどの物忘れがある | ない | ときどきある | ほとんど毎日ある |
| (11)薬の内服 | 自分で可 | 一部介助、見守り等が必要 | 全面的介助が必要 |
| (12)日常の意思決定 | できる | 本人に関する重要な意思決定はできない | ほとんどできない |
「ケアハラスメント」とは?
ケアハラスメントとは、介護をしながら働いている人を、上司や同僚が不利益に取り扱うことをいいます。
介護休暇を取得するには上述の条件を満たす必要がありますが、介護を理由に休暇を申請したり残業ができないことなどを伝えたときに、「周りに迷惑がかかるから控えてほしい」などとして、申請を拒否されるといったケースは、ケアハラスメントに該当する場合があります。
ケアハラスメントに遭った場合は弁護士への相談が有効です。
参考:弁護士保険STATION
またもしも老人ホーム・介護施設をお探しの際には、ケアスル介護で相談してみることがおすすめです。
ケアスル介護では全国約5万もの施設から、入居相談員がご本人様のニーズに合った施設をご紹介しています。
「納得のいく施設選びをしたい」という方は、まずはぜひ無料相談をご利用ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
介護休業給付金なら、給料の約67%を支給してもらえる
介護休暇は原則無給であり、休暇中の給与収入はありません。ただ、雇用保険上の介護休業給付金制度を使えば、介護のために休んでいる間でも、給料の支給の代わりに介護休業給付金を雇用保険から支給してもらうことが可能です。
ただ、この制度は上で紹介した介護休暇とは少し異なるため、ここでは、介護休業給付金の制度や支給額について詳しく解説していきます。
介護休業給付金とは?
介護休業給付金とは、家族の介護のために仕事を休業する場合に給料の67%を受給することができる制度です。
介護休業給付金は、雇用保険上で規定されている介護休業に該当すると受け取ることができます。つまり、企業ではなく雇用保険で定められており、雇用保険から支給される給付金となっています。
なお、介護休暇上の給料と同様、企業が給与を支払ってくれるかどうかは就業規則上に記載されているので、確認してみましょう。
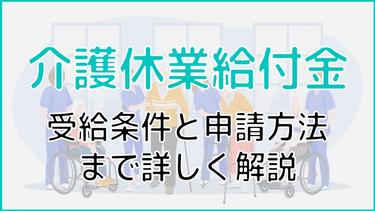
介護休業とは
介護休業とは、要介護状態の家族を介護するために取る休業です。介護休暇よりも長い間の休暇期間が設定されており、対象者1名につき93日間の休暇を取得することができます。
なお、この93日間は連続で取得する必要はなく、3回を上限として分割することが可能です。
介護施設を検討したり、施設に入居するまでの短期間だけ自分で介護をしたりなど、比較的長い間介護に携わる必要がある場合に、介護休業を利用することが多いです。
介護休業と介護休暇の違い
介護休業と介護休暇は、言葉としては似ていますがそれぞれ異なる制度です。それぞれ、どんな休業制度なのかを見ていきましょう。
| 介護休暇 | 介護休業 | |
|---|---|---|
| 特徴 | 家族の介護を目的とした、一時的な休暇 | 家族の介護を目的とした、長期的な休暇 |
| 上限日数 | 1年で5日間(対象が2名の場合は10日間) | 対象者1名につき、93日間。(3回を上限として分割可能) |
| 給付金額 | 原則なし | 給料の67% |
| 対象者 | 要介護状態の家族 | 要介護状態の家族 |
| 申請方法 | 当日口頭でも問題なし | 事前の申請が必要 |
長期的な介護が必要な場合は介護休業が、短期的な介護の場合は介護休暇の利用が向いています。なお、介護休業の場合は事前に申請が必要になるため、あらかじめ計画的に休暇を取る準備をしておきつつ、周りにも伝えておくようにしましょう。
介護休業給付金の支給額
介護休業給付金の支給額は、給料の67%と定められています。具体的には、「賃金(日額)×休業日数×67%」が給付額になります。
なお、介護休業給付金は非課税所得です。また、介護休業中に賃金が発生していなければ、雇用保険料も免除されます。
介護休業給付金の支給期間
介護休業給付金は、介護休業終了日の翌日から2か月後の月の末日までの間に企業側が申請することで受給することができます。
例えば、6月10日から介護休業をした場合は、6/11~8/31までの間に申請することで、その1か月ほど後に給付金を受け取ることができます。
休業終了日後に申請することになるため、介護休業中は受け取ることができません。
介護休業給付金を支給する条件
介護休業給付金を支給する条件として、労働者に関する条件と被介護者に関する条件の2つの条件があります。介護休暇と被っている部分もあるので、それぞれ比較しつつ見ていきましょう。
労働者側の条件
雇用形態を問わず、入社から1年以上経っていることが条件になります。
なお、パートやアルバイトなどの有期雇用契約の社員の場合は、「介護休業取得日から起算して93日を経過する日から、6か月を経過するまでに契約が満了し、更新されないことが明らかでないこと」が条件になっています。
介護相手者側の条件
介護相手の条件は、基本的に介護休暇と同じです。要介護状態にある家族が対象となります。
なお家族とは、父や母、子、孫、配偶者、配偶者の父や母、祖父母、兄弟、姉妹が当てはまります。
介護休業給付金の申請方法
まず、介護休業の申請を出します。介護休業取得日の2週間前までに申請書を提出する必要があり、企業の担当者に渡すケースと直接自分でハローワークに持っていくケースと2通りがあるので、企業側に確認するとよいでしょう。
その後実際に休暇を終えたのち、介護休業給付金を受け取るための申請を再度出す必要があります。これは、介護休業終了日の翌日から2か月後の月の末日までの間に提出する必要があります。
なお、介護休業給付金の申請の際には、
2. 会社に提出したものと同一の介護休業申出書
3. 出勤簿や出勤記録、タイムカード
4. 住民票
5. 賃金台帳、源泉徴収等給料がわかるもの
の5つの種類を用意しておく必要があります。企業によって申請前・申請後に出す書類が異なるので、注意しておきましょう。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
「給料を下げたくない!」介護休暇以外にどんな方法がある?
「一時的に休みたいけれど、介護休暇は給料が出ないので嫌だ。。」「介護休業を使うほどではないが、給料をもらいつつ介護休暇を取りたい」という方も中にはいらっしゃいます。
ここでは、介護休暇以外に取れる方法を紹介するので、参考にしてみてください。
有給休暇を使う
有給休暇を取得し、給料を得つつ介護のための休暇を取るという方法が一番に思い浮かぶでしょう。
ただ、もちろん人によって有給休暇の所持日数は異なります。また、人によっては有給休暇は旅行や遊ぶ際に使いたいという方もいるでしょう。
そのため、「介護休暇を使って無給で休む」か「介護のためだけど、給料を下げたくないので有給休暇を使う」のいずれかで、有休を選択する考え方もあります。
要介護認定を受けて、ケアマネージャーに依頼する
対象となる家族がまだ要介護認定を受けていない場合は、要介護認定を受けるためにケアマネジャーに依頼するという手もあります。
各市区町村にある地域包括支援センターや役所の高齢者福祉課に相談することで、要介護認定のための申請手続きをおこなえます。無事に要介護認定を受ければ、担当のケアマネージャーを決めることができるので、そのケアマネージャーに介護サービスや介護に関する相談をするのもよいでしょう。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
介護休暇に関するまとめ
介護休暇は、一時的に介護をするために休暇を取ることができる制度のことを指しており、原則無給となっています。中には介護休暇中も有給にしてくれる企業もあり、就業規則で確認することはできますが、実際にはほとんどの企業が無給としています。
そのため、介護をしつつも給料を受け取りたいという方は、有給休暇を取得したり、ケアマネージャーに依頼してヘルパーを派遣してもらい、介護を手伝って貰うという方法もあるでしょう。なお、長期的な介護が必要な場合は介護休業も視野に入れつつ、介護休業給付金で給料の67%を受けとるのも手です。
介護休暇中の場合は給与が発生しない可能性が高いです。ですが、介護休業給付金制度であれば給与をもらうことができます。詳しくはこちらをご覧ください。
介護休業給付金制度であれば、給与の67%に当たる額が支給されます。詳しくはこちらをご覧ください。




