要介護3とは身体能力の低下・認知症の進行などが見られ、日常生活のほとんどに家族の見守りや介助が必要な状態です。
食事や入浴、排泄などにもサポートが必要となり、移動には方向機や車いすが必要となることが多くなってきます。
24時間体制での介護を行うことになるため、ほとんどの方々が介護サービスを利用することになります。
「要介護3の人はどんな介護サービスを使っているの?」
「要介護3の人のケアプラン例を知った上で、将来の親の介護に備えたい」
そんな思いをお持ちの方々のため、今回は要介護3の方のケアプランの事例、利用できるサービス一覧、気になる費用まで詳しく解説して行きます。

要介護3の方のケアプラン例
本章では要介護3の方が利用するサービス・週間ケアプラン例についての具体例を紹介していきます。
おおよそ要介護3の方は、デイサービスを週に2~3回、訪問介護を週に5回ほど利用することが一般的です。
しかしひと口に「要介護3」と言っても身体状況や生活環境は人によって異なります。
そのため今回はそれぞれのケース別にケアプランを解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
- 家族が介護を行うことが難しいケアプラン例
- 本人が一人暮らしをしているケアプラン例
- 脳梗塞の後遺症から生活機能の改善を目指すケアプラン例
- 施設サービスを利用するケアプラン例
家族が介護を行うことが難しいケアプラン例
【Aさん・80歳・女性・要介護3/夫と2人暮らし】
1年程前から物忘れが始まり、専門医受診したところ認知症の診断が出る。
これまでは夫や地域のサポートによって自宅での暮らしを継続できていたが、夫が腰椎圧迫骨折を患い介護を行うことが難しくなる。
次男は同市内に在住しているが自営業と息子の世話で頻繁な訪問が困難な状況。
夫婦2人での生活を続けるため、見守り・サポートが必要となる。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00~9:00 | |||||||
| 9:00~10:00 | 通所介護 (デイサービス) |
通所介護 (デイサービス) |
通所介護 (デイサービス) |
||||
| 10:00~11:00 | |||||||
| 11:00~12:00 | |||||||
| 12:00~13:00 | 訪問介護 | 訪問介護 | |||||
| 13:00~14:00 | |||||||
| 14:00~15:00 | |||||||
| 15:00~16:00 | |||||||
| 16:00~17:00 | |||||||
| 17:00~18:00 |
その他:住宅改修(浴室・廊下に手すりを取り付け)
平日に訪問介護もしくは通所介護(デイサービス)が入ったケアプランとなりました。
老人ホームではなく「自宅で夫婦2人で暮らしたい」と望んだAさんには、これらのサービスによって意欲的な自立支援を促します。
訪問介護では、スタッフが自宅を訪問し、安否確認の他、入浴・食事・排せつなどの身体介護や、洗濯・掃除・買い物・調理などの生活の支援をします。
息子がいない時間帯の生活支援をはじめ、顔なじみのヘルパーが日常の困りごとなどにも相談に乗ってくれるため、安心して親を任せることができます。
通所介護(デイサービス)では、施設に通いながら利用者の身体機能の維持・向上をはじめ、孤立感の解消を目的としたサービスを受けられます。
訪問介護で実施される身体介助などのほか、レクリエーションではほかの利用者との交流も魅力で、生活の楽しみになることも多いです。
サービス利用の料金
上記のケアプランの場合、毎月で必要な料金は以下のようになります。
※住宅改修・福祉用具購入に関しては月々の支払いではなく、区分支給限度額の範囲にも含まれないため除外
| 利用サービス | 利用頻度 | 利用回数/月 | 金額/回 | 金額/月 |
|---|---|---|---|---|
| 訪問介護(30分以上1時間未満) | 2/週 | 8 | 3,960円 | 31,680円 |
| 通所介護(5時間以上6時間未満) | 3/週 | 12 | 7,730円 | 137,040円 |
| 合計 | 168,720円 | |||
| 自己負担(1割の場合) | 16,872円 | |||
料金の出展:厚生労働省「介護報酬の算定構造」(令和3年)
本人が一人暮らしをしているケアプラン例
【Bさん・70歳・男性・要介護3/一人暮らし】
妻とは30年前に離婚。子供は居なく、両親や兄は死去。
2年前にパーキンソン病の診断を受けていたが、1月はじめ風邪を引いて寝込んだときから服薬ができなくなり、食事も思うように摂れないようになった。
「薬が決められたように飲めるか、食事が用意できるか心配」という本人の言葉を受けて、一人暮らしでも安心して生活できるような支援が必要となる。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00~9:00 | |||||||
| 9:00~10:00 | 通所リハビリテーション (デイケア) |
訪問看護 | 通所リハビリテーション (デイケア) |
訪問介護 | 訪問看護 | 通所リハビリテーション (デイケア) |
訪問介護 |
| 10:00~11:00 | |||||||
| 11:00~12:00 | |||||||
| 12:00~13:00 | |||||||
| 13:00~14:00 | |||||||
| 14:00~15:00 | |||||||
| 15:00~16:00 | 訪問介護 | 訪問介護 | 訪問介護 | 訪問介護 | |||
| 16:00~17:00 | |||||||
| 17:00~18:00 |
その他:住宅改修(玄関に手すりを取り付け、トイレドア取り換え)、介護ベッド貸与
全ての日に訪問介護や訪問看護、通所リハビリテーションが入ったケアプランとなりました。
「薬が飲めれば日常生活は問題ない」と診断されたBさんには、一人暮らしでも安心して生活を送れるよう、服薬の確認と基礎運動能力の維持を目的とした支援を行います。
訪問看護では服薬の管理のほか、血圧・脈拍・体温の測定を実施することにより、日ごろからBさんの体調を気に掛けることができます。
通所リハビリテーションではパーキンソン病の症状を考慮しながらも残存機能を活かし、自立した生活をサポートする目的があります。
要介護3は一般的には一人暮らしが難しい場合が多いですが、本人の症状によって利用するサービスをしっかりを考えれば一人暮らしの継続も可能な場合があると言えるでしょう。
サービス利用の料金
上記のケアプランの場合、毎月で必要な料金は以下のようになります。
※住宅改修・福祉用具購入に関しては月々の支払いではなく、区分支給限度額の範囲にも含まれないため除外
| 利用サービス | 利用頻度 | 利用回数/月 | 金額/回 | 金額/月 |
|---|---|---|---|---|
| 訪問介護(30分以上1時間未満) | 6/週 | 24 | 3,960円 | 95,040円 |
| 訪問看護(30分以上1時間未満) | 2/週 | 8 | 8,210円 | 65,680円 |
| 通所リハビリ(3時間以上4時間未満) | 3/週 | 12 | 6,380円 | 76,560円 |
| 合計 | 237,280円 | |||
| 自己負担(1割の場合) | 23,728円 | |||
料金の出展:厚生労働省「介護報酬の算定構造」(令和3年)
脳梗塞の後遺症から生活機能の改善を目指すケアプラン例
【Cさん・90歳・男性・要介護3/一人暮らし】
4ヶ月前に脳梗塞(小脳梗塞)を再発し、入院による治療・リハビリテーションを受けていた。
近隣に住む弟のサポート(通院時の付き添いなど)も受けているが、弟自体がすでに高齢(84歳)であり、自身の健康維持や今後の介護に不安を抱えている。
退院後に体力・気力を付けて一人暮らしを安心して営むために、生活上の支援・基礎能力の向上が必要となる。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00~9:00 | |||||||
| 9:00~10:00 | 訪問リハビリテーション | 訪問看護 | 訪問介護 | 訪問リハビリテーション | 訪問介護 | 訪問看護 | 訪問介護 |
| 10:00~11:00 | |||||||
| 11:00~12:00 | |||||||
| 12:00~13:00 | |||||||
| 13:00~14:00 | |||||||
| 14:00~15:00 | |||||||
| 15:00~16:00 | 訪問介護 | 訪問介護 | 訪問介護 | 訪問介護 | 訪問介護 | 訪問介護 | 訪問介護 |
| 16:00~17:00 | |||||||
| 17:00~18:00 |
その他:住宅改修(手すりの取り付け、段差の解消)、定期受診
全ての日に訪問介護や訪問看護、訪問リハビリテーションが入ったケアプランとなりました。
病院から退院したばかりのCさんには、まず自宅での生活リズムに慣れてもらうため訪問サービスが中心となっています。
訪問リハビリでは機能訓練の継続や定期的な身体状況の評価を行い、自立した生活を支援します。
また一見すると多めの支援ですが、身体状況の改善が見られれば徐々に訪問介護の回数を減らしていくことを見据えています。
あくまで退院直後で体力に不安がある時期をサポートするためのプランであり、できることを取り戻して安心の一人暮らしを目指します。
サービス利用の料金
上記のケアプランの場合、毎月で必要な料金は以下のようになります。
※住宅改修・福祉用具購入に関しては月々の支払いではなく、区分支給限度額の範囲にも含まれないため除外
| 利用サービス | 利用頻度 | 利用回数/月 | 金額/回 | 金額/月 |
|---|---|---|---|---|
| 訪問介護(30分以上1時間未満) | 6/週 | 40 | 3,960円 | 158,400円 |
| 訪問看護(30分以上1時間未満) | 2/週 | 8 | 8,210円 | 65,680円 |
| 訪問リハビリ(20分以上) | 2/週 | 8 | 3,070円 | 24,560円 |
| 合計 | 248,640円 | |||
| 自己負担(1割の場合) | 24,864円 | |||
料金の出展:厚生労働省「介護報酬の算定構造」(令和3年)
施設サービスを利用する場合のケアプラン例
5年ほど前に夫がなくなり一人暮らしをしていたが、脳梗塞で倒れてしまう。
病院で治療・リハビリを受けていたが、在宅復帰後も介護が必要となる。
しかし近隣には子供や親戚を含め頼りにできる人がいないため、遠方に住む家族と相談して特養へ入所することになった。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00~9:00 | 特養 | 特養 | 特養 | 特養 | 特養 | 特養 | 特養 |
| 9:00~10:00 | |||||||
| 10:00~11:00 | |||||||
| 11:00~12:00 | |||||||
| 12:00~13:00 | |||||||
| 13:00~14:00 | |||||||
| 14:00~15:00 | |||||||
| 15:00~16:00 | |||||||
| 16:00~17:00 | |||||||
| 17:00~18:00 |
特養(特別養護老人ホーム)に入居するプランとなりました。
要介護3以上の方が入居できる特養では、施設で暮らしながら食事や入浴、排泄などの介助をはじめ、たん吸引や胃ろうなどの処置も受けることができます。
認知症ケアにも対応しているほか、病気の後遺症などでほとんど全面的な介護を必要とする方も安心の環境です。
施設に入所することは遠方に住むDさんの家族にとっても、もっとも負担を軽減できる選択肢と言えるでしょう。
サービス利用の料金
特養の費用は入居一時金などの初期費用が0円、月額費用は要介護度や入居する居室タイプによっても異なりますが9~15万円が相場です。
そのほか要介護5のように重度の介護を必要とする方にとって入居の選択肢となるのは、以下のような施設が挙げられます。
| 名称【運営】 | 初期費用(入居一時金・敷金) | 月額利用料 |
|---|---|---|
| 特養(特別養護老人ホーム)【公的】 | なし | 5~15万円 |
| 介護医療院【公的】 | なし | 6~17万円 |
| 介護付き有料老人ホーム【民間】 | 0~数億円 | 15~40万円 |
要介護3で利用できるサービス一覧
本章では「要介護3」の方が利用できるサービスを一覧表で紹介します。
利用できるサービスの全体像を知ったうえで、今後の計画の参考になれば幸いです。
| サービスの種類 | サービス内容 | |
|---|---|---|
| 訪問サービス | 訪問介護 | 訪問介護員が自宅を訪問し、食事・排せつ・入浴などの介護や掃除・洗濯・買い物などの生活支援を行う |
| 訪問入浴介護 | 介護・看護職員が自宅を訪問し、持参した浴槽で入浴の介護を行う | |
| 夜間対応型訪問介護 | 24時間安心して過ごせるよう、夜間帯にも対応している訪問介護サービス。 安否確認や排せつの介助等を行う「定期巡回型」と、転倒した際や急な体調不良等の有事の際に介護をする「随時対応型」の2つに分かれている。 |
|
| 訪問看護 | 看護職員が疾患のある利用者の自宅を訪問し、主治医の指示に基づいた療養上の世話や診察の援助を行う | |
| 定期巡回・随時対応型訪問 介護看護 |
「定期巡回型」と「随時対応型」の両方に対応しており、訪問介護だけでなく訪問看護も組み込まれているサービス | |
| 訪問リハビリ | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等の専門スタッフが自宅を訪問し、心身機能の維持・回復や日常生活の自立に向けたリハビリを行う | |
| 居宅療養管理指導 | 医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士等の専門家が自宅を訪問し、療養上の管理・指導を行う | |
| 通所サービス | 通所介護(デイサービス) | 介護施設に通い、介護・生活援助・機能訓練等のサービスを受けることができる日帰りのサービス。自宅と施設までは送迎してくれる。 |
| 通所リハビリ(デイケア) | 病院・老健・診療所等に通い、専門スタッフによる機能訓練・日常生活動作等のリハビリを受けることができる。食事や入浴といった生活援助の提供もある。 | |
| 認知症対応型通所介護 | 認知症の方を対象とした通所介護サービス。 | |
| 地域密着型通所介護 | 定員18人以下の施設で、入浴や食事などの介護や機能訓練等のサービスを受けることができる。定員が少ないため、一人ひとりに寄り添った対応が可能。 | |
| 療養通所介護 | 常に看護師による観察が必要な方を対象にしたサービス。医師や訪問看護ステーションと連携して食事・入浴などの日常生活支援、機能訓練が提供される。 | |
| 短期入所サービス | 短期入所生活介護 (ショートステイ) |
介護施設に短期間入所し、介護・生活援助・機能訓練等のサービスを受けることができる。1度で最大30日までの利用が可能。 |
| 短期入所療養介護 (ショートステイ) |
老健や介護医療院といった医療体制が整っている施設に短期間入所し、介護・生活援助に加え、医療処置や看護等の医療サービスを受けることができる。1度で最大30日までの利用が可能。 | |
| 複合型サービス | 小規模多機能型居宅介護 | 施設への通いを中心として、訪問・短期入所サービスを組み合わせ、介護・生活援助・機能訓練等のサービスを受けることができる。 |
| 看護小規模多機能型 居宅介護 |
小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせたサービス。 | |
| 施設サービス | 老健(介護老人保健施設) | 利用者の在宅復帰を目的とした施設。介護・看護・生活援助・リハビリ等のサービスを受けることができるが、原則3~6か月で退所しなければならない。 |
| 特養(特別養護老人ホーム) | 常に介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などが受けられる施設。 | |
| ケアハウス | 自立した生活が難しい高齢者の方を対象とした、少ない費用で介護・生活援助等のサービスが受けられる施設。 | |
| 介護療養型医療施設 | 比較的重度の要介護者を対象とした、充実した医療処置・リハビリ等のサービスが受けられる施設。 | |
| 介護医療院 | 介護療養型医療施設で受けられるサービスに加え、介護や生活援助にも力を入れている施設。 | |
| 有料老人ホーム | 食事・介護・生活援助・健康管理のうち1つ以上を提供している施設。24時間介護サービスを受けることができる「介護型」、生活援助を中心に受けることができる「住宅型」等の種類がある。 | |
| サ高住(サービス付き高齢者向け住宅) | 「安否確認」「生活相談」等のサービスを受けることができるバリアフリー対応の施設。 | |
| グループホーム | 認知症の方を対象とした、少人数での共同住宅の形態でサービスを受けることができる施設。 | |
| 福祉用具の 利用サービス |
福祉用具の貸与 | 車いすや介護ベッド等の福祉用具をレンタルすることができるサービス。 |
| 福祉用具の販売 | 簡易浴槽や入浴補助用具等の福祉用具を購入することができるサービス。 | |
要介護3の人がよく利用するサービス
上記で紹介した介護サービスの中から、要介護3の方によく使われるサービスを詳しく紹介します。
訪問介護
訪問介護員(ホームヘルパー)などが自宅を訪問し、入浴や排せつ、食事などの介護サービス、そのほかの日常生活を送るうえで必要となる家事などの援助を行います。
自宅にいながら介護サービスを受けられるため、利用者は環境の変化に伴うストレスが少ないことがメリットとして挙げられます。
また介護保険サービスのなかでも比較的安価な部類に入るため、普段介護を行う家族が仕事などで見守ってあげられない時にも適していると言えるでしょう。
通所介護(デイサービス)
介護施設やデイサービスセンターなどに通い、食事や入浴、排せつなどの介助、機能訓練やレクリエーションを行います。
閉じこもりがちな利用者の孤独感の解消・身体機能の維持なども目的としており、ほかの利用者との交流などから生活の楽しみとなることもメリットです。
また自宅からの車での送迎サービスが付いていることも多く、在宅介護を行っている家族にとって大きな負担軽減になると言えるでしょう。
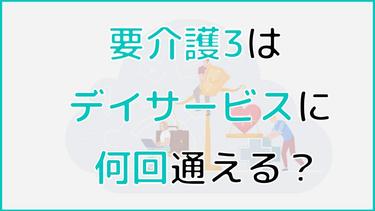
通所リハビリ(デイケア)
老健などの介護施設や病院に通い、医師や理学療法士などの専門スタッフによるリハビリテーション・医療ケアを行います。
日常生活機能の維持・向上、認知機能の改善などを目的としており、デイサービスよりも医学に基づいたリハビリテーションが受けられることがメリットです。
退院したばかりで生活が不安な方や、骨折・変形性関節症などをお持ちの方には適していると言えるでしょう。
また利用時には看護師による健康チェックも行われており、日々の安心にもつながっています。
短期入所生活介護(ショートステイ)
施設に一定期間入所し、食事や入浴、排泄などの介助をはじめ、日常生活上の世話やリハビリを行います。
数日間の宿泊ができるため、在宅介護を行う家族が外せない用事ができた場合にも適したサービスであると言えるでしょう。
連続の利用日数は最大30日まで行うことができ、本格的に施設へ入所する前の疑似体験としての利用も可能です。
また家族などにとっては、自分のためにまとまった時間が確保できるために、大きな負担軽減につながると言えます。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
要介護3の区分支給限度額は?
| 区分 | 区分支給限度基準額(単位) | 自己負担割合1割の場合(円) | 自己負担割合2割の場合(円) | 自己負担割合3割の場合(円) |
|---|---|---|---|---|
| 要介護3 | 27048 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
区分支給限度額とは、介護保険によって補填される金額の上限額のことです。
上記のように、要介護3の場合は区分支給限度額(単位)が27048と定められており、270,480円分までの介護サービスに保険が適用されることになります。
したがって自己負担割合が1割の方の場合は、最大で自己負担27,048円までのサービスを利用できることになるのです。
※1単位10円の場合。地域によって単位ごとの金額が異なる場合があります。
また区分支給限度額を超えて介護サービスを利用する場合は、超えた分のサービス料金は全額自己負担となるため注意しておきましょう。
介護リフォームでは補助金を受けられる
介護保険では自宅のバリアフリー化を行う方を対象に、「住宅改修費」として最大20万円の補助金を給付しています。
金銭的な補助を受けながら、手すりの取り付けや段差の解消、扉を引き戸に取り換えるなどの工事を行うことができ、介護への負担を軽減できるでしょう。
また、この「住宅改修費」は区分支給限度額には含まれません。
つまり毎月の区分支給限度額をオーバーすることを気にすることなく、自宅のバリアフリー化を行うことができるのです。
補助金を受けるには、工事の前にお住いの自治体で「住宅改修費」の申請が必要なため、窓口を訪ねてみるか、ケアマネジャーに相談してみましょう。
なお、工事の金額が20万円を超えた場合は自己負担となり、基本的に補助金支給は要介護者1人につき1度きりの支給となります。
また、要介護状態区分が重くなったとき、転居した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定されるなど、細やかな決まりもあるので注意が必要です。
要介護3で介護サービスを利用する流れ
要介護3で介護サービスを利用するには、ケアマネジャーと相談してケアプランを作成してもらうことが必要です。
要介護認定を受けたあとは、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼することでケアプランを作成することができます。(参考:厚生労働省「サービス利用までの流れ」)
ケアマネジャーは、要介護認定を受けた方が満足のいく介護サービスを利用できるよう、本人や家族と面談の上、「ケアプラン(介護サービス計画書)」を作成し、サービス事業者や市区町村などとの連絡調整を行ってくれます。
ケアプランの作成後は、ケアマネジャーの仲立ちのもと事業者と契約を結び、サービスの利用開始となります。
また「老人ホームに入居したいけど、入居前の手続きが大変そう…」という方は、ケアスル 介護で相談してみることがおすすめです。
ケアスル 介護では施設の紹介だけでなく、見学や体験入居の申し込みや日程調整の代行も実施しています。
「暮らしの雰囲気を知った上で、納得して施設を探したい」という方も、まずは無料相談からご利用ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
まとめ
おおよそ要介護3の方は、デイサービスを週に2~3回、訪問介護を週に5回ほど利用することが一般的です。
しかしひと口に「要介護3」と言っても身体状況や生活環境は人によって異なります。
生活の全てにおいて介助を行うだけが介護の在り方ではありません。
本人の意思や目標・生きがいをしっかりと把握した上で、その人に適した形で自立支援を行うのがケアプランです。
今回紹介したのは数例ですが、ケアマネジャーと実際に相談する際は本人の気持ちや家族の在り方をよく考えたうえで納得のいくケアプランを立てられるようにしましょう。




