特養(特別養護老人ホーム)は、低価格な料金ながら手厚い介護サービスを受けられると人気の施設です。
そのため多くの方々が入所を希望しており、いわゆる「入所待ち」が発生することも多くなっています。
しかし、実は特養の入所順は申し込み順ではなく、本人の「要介護度」「介護者の状況」「サービスの利用率」を加味して決まることになります。
「要介護度が考慮されるなら、要介護5だと優先的に入所できるの?」
そんな疑問をお持ちの方々のため、今回は要介護5であれば特養に優先的に入所できるのか、特養の判定基準、早く特養に入るための方法について解説して行きます。
関連記事
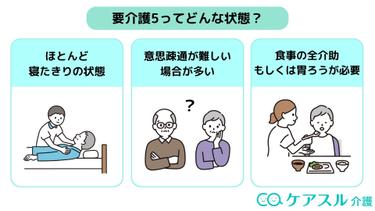 要介護5とは?要介護5で利用できるサービス・施設から給付金制度まで詳しく解説!カテゴリ:要介護5更新日:2025-12-18
要介護5とは?要介護5で利用できるサービス・施設から給付金制度まで詳しく解説!カテゴリ:要介護5更新日:2025-12-18
【この記事のまとめ】
- 要介護5であれば、特養への入所が優先される可能性は高いが、必ずしもすぐに入所できるわけではない。
- 特養の入所判定基準は、「要介護度」「介護者の状況」「サービスの利用率」などが挙げられる。
- 優先の判定基準は平たく言うと「緊急性が高いか」なので、要介護3であっても身寄りがなくて頼りにできる人がいない場合は入所が優先されることもある。
要介護5であれば特養に優先的に入所できる?
要介護5であれば、比較的早くに特養に入所できる可能性は高いと言えるでしょう。
しかし、前述のとおり特養の入所判定基準は「要介護度」だけではないため、必ずしもすぐに入所できるわけではないことに注意が必要です。
特養の入所判定基準は主に「要介護度」「介護者の状況」「サービスの利用率」などが挙げられます。
それら全項目の点数を計算し、合計の点数が高い方から優先的に入所ができるという仕組みになっているのです。
例えば「要介護5で同居する家族に介護をしてもらっている方」よりは、「要介護3でひとり暮らししており、身寄りがない方」の方が緊急性が高いと判断され、後者の入所を優先するケースもあります。
したがって、要介護5であれば特養に優先的に入所できる可能性は高いですが、特養の入所判定基準をしっかりと理解しておくことが大切と言えるでしょう。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
要介護5でも知っておきたい特養の入所優先順位の仕組み
本章では、特養の入所の優先順位を決めるための「判定基準」について詳しく解説して行きます。
前述のとおり主な判定項目としては、「要介護度」「介護者の状況」「サービスの利用率」などが挙げられます。
判定基準は、施設によって少々異なりますが、以下では、例として伊那市の特養の判定基準を紹介します。
<要介護度>
| 要介護5 | 30点 |
|---|---|
| 要介護4 | 25点 |
| 要介護3 | 20点 |
| 要介護2 | 15点 |
| 要介護1 | 5点 |
<居宅介護サービス利用率>
| 80%以上 | 15点 |
|---|---|
| 60%以上80%未満 | 12点 |
| 40%以上60%未満 | 9点 |
| 20%以上40%未満 | 6点 |
| 20%未満 | 3点 |
注)利用率=居宅介護サービスの利用費÷区分支給限度額×100
<介護者の状況>
| 30点 | 25点 | 20点 | 15点 | 10点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入所希望者 単身世帯 |
身寄りがなく介護者がいない | 定期的な介護可能者が、市町村内または近隣市町村に住んでいない | 定期的な介護可能者が、市町村内または近隣市町村に住んでいるが、病気や重複介護等の理由で十分な介護が困難 | 定期的な介護可能者が市町村内にまたは近隣市町村に住んでいる | |
| 入所希望者と 高齢者のみ世帯 |
主な介護者が、長期入院中など、事実上介護が不可能 | 主な介護者が、要介護・要支援状態、病気療養中など十分な介護が困難 | 主な介護者が、高齢のため、十分な介護が困難 | ||
| 入所希望者との 二人世帯 |
主な介護者が、長期入院中など、事実上介護が不可能 | 主な介護者が、要介護・要支援状態、病気療養中など十分な介護が困難 | 主な介護者が就業しているため、十分な介護が困難 | ||
| 入所希望者と子世帯及び親族世帯との同居 | 主な介護者が、就業、育児、病気療養中など、十分な介護が困難(協力者なし) | 主な介護者が、就業、育児、病気療養中など、十分な介護が困難(協力者あり) |
<要介護2以上に認定されてからの期間>
| 3年以上 | 10点 |
|---|---|
| 2年以上3年未満 | 8点 |
| 1年以上2年未満 | 6点 |
| 1年未満 | 4点 |
<認知症高齢者の日常生活自立度(主治医意見書)>
| ランクM | 10点 |
|---|---|
| ランクⅣ | 8点 |
| ランクⅢ | 6点 |
| ランクⅡ | 5点 |
| ランクⅠ | 3点 |
| 自立 | 0点 |
出典:伊那市「特別養護老人ホーム優先入所基準」
こちらの判定基準はあくまでも一例ですが、このような判定基準によって計算される点数が高いほど、優先的に入所する必要があると判断され、優先入所順位が上がることになります。
また、これらの判定項目以外にも、入所申込書の特記事項などの内容を基に、入所の必要性が高いと認められた場合には、点数が加算されることもあります。
このような判定基準の仕組みを理解しておくと、入所までの期間の目途も立てやすいのではないでしょうか。
介護放棄や虐待の事実があれば優先度は上がる
上記で解説した以外にも、介護放棄や虐待といった実態がある場合は優先順位が上がる傾向にあります。
客観的に見て要介護者に生命・身体に危険が生じているケースなどは、合計得点に関わらず入所できることがあると言えるでしょう。
入所優先順位は判定会議によって決定される
入所の優先順位は、施設内で定期的に開催される「判定会議」にて決定されることになっています。
判定会議は、施設長や生活相談員、その他職員などによって行われ、施設ごとに設けている判定基準に基づき、入所優先順位を決定するものとなります。
判定会議の開催頻度については、1月に1回、半年に1回など、施設によって大きく異なるため、事前に把握しておくといいでしょう。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
要介護5で特養に優先的に入る方法
本章では要介護5の認定を受けている方で、可能な限り特養入所の優先順位を上げる方法として下記の3つが挙げられます。
- 入所の緊急性を伝える
- 介護度の変化は細かく報告
- 職員と顔なじみになり、状況を理解してもらう
特養に入所するためには、前章で解説したように様々な評価基準があります。
要介護度や身寄りの有無を意図的に変えることはできませんが、、「入所判定」における優先順位を上げて、できるだけ早く入所するためには、おさえるべきポイントがあります。
この章では、特養入所の優先順位が上がる方法を、順に解説していきます。
入所の緊急性を伝える
特養(特別養護老人ホーム)の入所の緊急性が上がることにより、判定点数が上がります。
入所希望者の要介護を意図的に変えることはできませんが、例えば介護者が働いていると、緊急性が高いと評価され、優先順位があがります。
介護のために仕事を休んだり、収入が大きく減ったような実態があれば、もれなく伝えましょう。
前章でも解説したように、特養に優先的に入所するためには入居予定者の状況のみならず、介護者の就労状況も判定基準となります。
例えば、専業主婦(主夫)がいる家庭と、介護者が就労中の家庭とでは、日中の介護者が仕事で不在の家庭の方が、入所の緊急度が上がります。
逆に日中介護できる専業主婦(主夫)や身内が近くにいる場合は、緊急度がそれほど高くないと判断されます。
ここで言う「就労中」とは必ずしも正社員である必要はありません。判定基準の例にもあるように、週に何十時間以上働いているかが判断基準となることが多いです。
専業主婦(主夫)がいる家庭であれば、仕事に就くことを検討するのも良いかもしれません。もちろん同時に、不在中の見守り、介護をどうするかを検討することも不可欠となります。
介護度の変化は細かく報告
特養(特別養護老人ホーム)に入所申込をした後も、入居予定者や介護者の状況が変化した際には、細かく報告することが大切です。
特養の入所申込をしても、あとは入所決定まで放置してしまう方が多いです。
待機期間中に要介護度に変化があったり、認知症などの新たな症状が見られるなどの変化が生じることもあります。
基本的には入所判定会議が終わり次第連絡を入れるのが一般的であるため、入所待ち期間に「現状はいかがでしょうか?」といった特養からの問い合わせはありません。
施設によっては、要介護度や家庭環境に変化が生じた場合はご連絡を入れるよう入所申込書に記載している施設もあります。優先的に入所したいならば、こまめに連絡をすることが大切です。
体調や家庭環境に変化があった場合は、必ず報告しましょう。
職員と顔なじみになる
特養(特別養護老人ホーム)の職員に顔を覚えてもらうことで、特養入所の優先順位を上げてもらえるケースがあります。
入所判定会議には、介護スタッフの代表者が参加します。利用者を受け入れる側のスタッフも、全く知らない人よりはある程度事情を知っている方の方が受け入れやすいといえます。
また、利用者の在宅での状況(大変さ)をスタッフが把握していれば、入所の優先順位も上がるでしょう。
そのため、介護サービスや短期入所生活介護(ショートステイ)を行っている特養であれば、積極的に利用しましょう。
介護サービスをどれくらい利用しているかは入所の判断基準につながります。特養が実施しているサービスを利用すれば、入居予定者は施設の雰囲気を体感できて、介護者も介護の負担を下げることにもつながります。
ただし、職員に顔を覚えてもらうことにもデメリットがあります。たとえば、他の入居者に迷惑をかけるなど、施設職員に対して悪い印象を与えてしまうこともあります。
入所前に介護スタッフより厄介な利用者だと思われてしまうと、入所を断られてしまうケースも稀にあるため注意しておきましょう。
まとめ
要介護5であれば、比較的早くに特養に入所できる可能性は高いです。
しかし特養の入所判定基準は「要介護度」だけではないため、必ずしもすぐに入所できるわけではないことに注意が必要です。
例えば「要介護5で同居する家族に介護をしてもらっている方」よりは、「要介護3でひとり暮らししており、身寄りがない方」の方が緊急性が高いと判断され、後者の入所を優先するケースもあります。
したがって、要介護5であれば特養に優先的に入所できる可能性は高いですが、特養の入所判定基準をしっかりと理解しておくことが大切と言えるでしょう。
要介護5であれば、比較的早くに特養に入所できる可能性は高いと言えるでしょう。しかし特養の入所判定基準は「要介護度」だけではなく、「介護者の状況」「サービスの利用率」なども加味されるため、必ずしも優先的に入所できるわけではないことに注意が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
可能な限り特養入所の優先順位を上げる方法として下記の3つが挙げられます。①入所の緊急性を伝える ②介護度の変化は細かく報告 ③職員と顔なじみになり、状況を理解してもらう詳しくはこちらをご覧ください。




