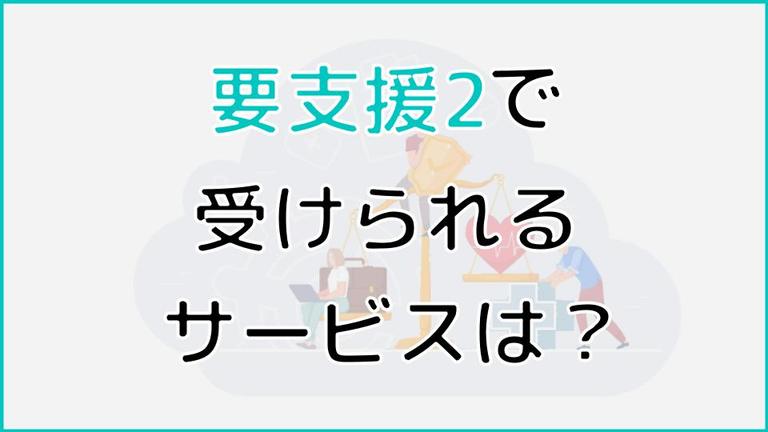要支援2は、日常生活の一部に手助けや見守りが必要な状態です。
まだ本格的な介護が必要な状態ではありませんが、少しずつ介護に時間や手間が取られるようになるため、ご家族の方は疲労やストレスが溜まってしまうこともあるでしょう。
そういった状況で利用したいのが、介護保険サービスです。介護保険サービスは、利用者の心身機能の維持・回復はもちろんですが、ご家族の方の負担を減らすことも目的としています。
しかし、要支援2ではどんな内容のサービスが受けられるのか分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、要支援2で受けられるサービスやその内容について解説します。
介護保険サービスを検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

要支援2で受けられるサービス一覧
要介護認定を受けた方であれば、介護保険サービスを利用することができますが、要支援の場合は、要介護状態への進行・悪化を防ぐことを目的とした介護予防サービスの提供が中心となります。
要支援2の認定段階も例外ではなく、介護予防サービスを中心に多くのサービスを利用することができます。
要支援2で受けられるサービスは、以下の通りです。
| サービス 分類 |
名称 | 概要 |
|---|---|---|
| 訪問型サービス | 介護予防訪問介護(ホームヘルパー) | 訪問介護員が利用者の自宅に訪問し、利用者が自立して行うことが困難である、掃除・洗濯・調理といった家事の代行や買い物の代行などの生活援助を行う |
| 介護予防訪問入浴介護 | 自宅の浴槽での入浴が困難な方向けに、簡易浴槽を積んだ訪問車で利用者の自宅へ訪問し入浴の介助を行う | |
| 介護予防訪問リハビリ | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などの専門家が利用者の自宅に訪問し、リハビリを行う | |
| 介護予防訪問看護 | 医師の指示に基づき看護師等が利用者の自宅に訪問し、療養上のお世話や診療の補助を行う | |
| 介護予防居宅療養管理指導 | 通院が困難な利用者に対し、医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが利用者の自宅を訪問し療養上の管理・指導・助言を行う | |
| 通所型サービス | 介護予防通所介護(デイサービス) | 施設に日帰りで通い、通い先の施設にて、食事の提供や入浴、生活援助、機能訓練などのサービスを受けることができる |
| 介護予防通所リハビリ | 要介護状態になることを予防するため、老健(介護老人保健施設)・病院・診療所・介護医療院に通い、リハビリを行う | |
| 介護予防認知症対応型通所介護 | 認知症の症状が明らかに見られる方に対し、心身機能の維持回復を目的とした専門的なケアを行う | |
| 短期入所型サービス | 介護予防短期入所生活介護 | 老人ホーム等に短期間入所し、入浴・排せつ・食事等の介助や機能訓練等のサービスを受けることができる |
| 介護予防短期入所療養介護 | 老健や介護医療院等の医療機関に短期間入所し、看護および医学的管理の下で介護や生活援助、医療ケア、機能訓練等のサービスを受けることができる | |
| 複合型サービス | 小規模多機能型居宅介護 | 利用者の選択に応じて「訪問」「通所」「宿泊」の3つを組み合わせて利用できるサービス |
| 施設サービス | グループホーム | 認知症の方を対象とした、少人数での共同住宅の形態でサービスを受けることができる施設。 |
| 有料老人ホーム | 食事・介護・生活援助・健康管理のうち1つ以上を提供している施設。24時間介護サービスを受けることができる「介護型」、生活援助を中心に受けることができる「住宅型」、食事等の生活援助のサービスを提供する「健康型」等の種類がある。 | |
| ケアハウス(自立型) | 経済的・家庭的な理由から自立した生活が困難な高齢者を対象とした施設。 少ない費用で生活援助・食事の提供などのサービスが受けられる。 |
|
| サ高住(サービス付き高齢者向け住宅) | 「安否確認」「生活相談」等のサービスを受けることができるバリアフリー対応の施設。 | |
| 福祉用具の貸与・販売 | 福祉用具の貸与 | 手すりや歩行補助杖などの福祉用具をレンタルすることができるサービス。 |
| 福祉用具の販売 | 入浴補助用具等の福祉用具を購入することができるサービス。 |
上記の表からも分かるように、介護保険で利用できるサービスは、それぞれのサービス内容によって訪問型や通所型、施設入所型といったような種類に分類されます。
以下では、サービスの種類ごとに1つずつ解説していきます。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
要支援2で受けられるサービス①訪問型サービス
訪問型サービスとは、文字通り、訪問介護員や看護師が利用者の自宅に訪問し、リハビリや生活援助、医療ケア等のサービスを提供するというものです。
担当の職員や看護師が利用者の自宅へ訪問しサービスを提供してくれるため、利用者は自宅から移動する必要がなく、利用者本人にかかる負担が少ないのが特徴と言えるでしょう。
以下では、訪問型サービスに該当するサービスを詳しく紹介します。
介護予防訪問介護
介護予防訪問介護とは、訪問介護員が利用者の自宅を訪問し、調理や洗濯、掃除、買い物といった日常生活上の支援を行うサービスとなります。
受けられるサービス内容は、要支援の方が行うのが難しいとされている洗濯や掃除をはじめとした家事の支援が主であり、入浴・排せつ・食事の介助といった身体介護を受けることはできないため、注意が必要です。
また、介護予防訪問介護は、介護保険法の改正によって、各自治体が主体となって行うサービス事業へと移行されたため、自治体によってサービスの費用や利用回数制限などが異なるため、把握しておきましょう。
介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護は、自宅の浴槽での入浴が困難な方向けに、簡易浴槽を積んだ訪問車で利用者の自宅へ訪問し入浴の介助を行うサービスです。
介護予防訪問入浴介護は、介護職員と看護職員それぞれ1人ずつの計2人が担当するのが一般的です。入浴の介助だけでなく、医療や介護の観点から全身症状のチェックも行ってもらえるため症状の変化にも対応しやすく、ご家族がなかなか自宅に通えない場合でも安心です。
介護予防訪問リハビリ
介護予防訪問リハビリは、利用者が要介護状態にならないよう予防するために、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などの専門家が利用者の自宅に訪問し、リハビリを行ってくれるサービスです。
現在の生活機能の維持・回復が主な目的であり、利用者が可能な限り自立した生活を送れるよう、リハビリのサポートを行ってくれます。
リハビリを行っている方のなかには、要支援区分から自立状態まで回復したという方もいるため、積極的に利用することをおすすめします。
介護予防訪問看護
介護予防訪問看護は、医師の指示に基づき看護師などが利用者の自宅に訪問し、療養上のお世話や診療の補助を行うサービスです。
要介護状態になることを予防する、また現在の身体状態の維持を目的としており、利用者が自立した生活を送ることができるよう支援してくれます。
サービス内容としては、以下の通りです。
- 病状・障害の観察といった健康管理
- 食事・排せつのケアなどの水分・栄養管理
- 医療ケア(傷や床ずれの処置、医療機器の管理など)
- 薬の管理
- ご家族の悩みの相談
- 療養生活に関する助言
ご本人のケアはもちろん、ご家族の方の悩みの相談にも対応してくれるため、悩みや不安がある場合は頼るようにしましょう。
介護予防居宅管理指導
介護予防居宅管理指導は、通院が困難な利用者に対し、医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが利用者の自宅を訪問し療養上の管理・指導・助言を行うサービスです。
要介護状態になることを予防する、また現在の身体状態の維持を目的としており、利用者が自立した生活を送ることができるよう支援してくれます。
介護予防居宅管理指導を利用することで、「医師の指導」「薬剤管理」「嚥下機能などを考慮した食事管理」等の指導を自宅で受けることができます。
要支援2で受けられるサービス②通所型サービス
通所型サービスは、利用者本人がサービスを提供している介護施設などに通いサービスを受ける形態を指します。
訪問型と異なり、利用者本人が自宅から移動する必要があるため多少の負担はかかりますが、他の方との交流の場になるなど、自宅では得られない効果をもあるため、必要に応じて利用するといいでしょう。
とはいえ、通い先の施設が利用者の自宅までの送迎も行ってくれるため、移動の負担というよりも環境の変化による負担が大きいと言えます。
なお、通所型サービスは日帰りでのサービスになっており、宿泊はできないため注意が必要です。
以下では、通所型サービスに該当するサービスを詳しく解説していきます。
介護予防通所介護(デイサービス)
介護予防通所介護とは、デイサービスセンターなどに通い、日常生活上の支援や機能訓練、レクリエーションなどを受けながら生活するサービスとなります。それらのサービスに加え、施設側が送迎も行ってくれるため、利用しやすいのもポイントです。
介護予防通所介護は、要介護状態への進行・悪化を予防するだけでなく、自宅に籠りがちの利用者の孤立感の解消も目的としています。
施設では、施設スタッフだけでなく他の高齢者との交流もあるため、自宅に籠りがちで気分が落ち込んでしまうという方は積極的に利用してみるといいかもしれません。
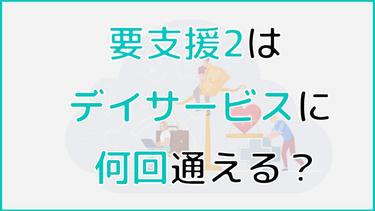
介護予防通所リハビリ
介護予防通所リハビリは、要介護状態になることを予防するため、老健・病院・診療所・介護医療院などに通い、リハビリを行います。
リハビリは、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などの専門家が担当しており、生活機能の維持・回復訓練や日常生活動作訓練などを行います。
介護予防通所リハビリでは、日常生活上の支援や生活行為を向上させるための共通的サービスに加え、運動機能の向上や栄養指導、口腔機能の向上などの選択的サービスを利用することができます。
必要なサービスをしっかりと把握したうえで選択することが重要です。
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護は、認知症の症状が明らかに見られる方に対し、心身機能の維持回復を目的とした専門的なケアを提供するサービスとなっています。
血圧測定や食事の提供、入浴・排せつの介助などのサービスが受けられるほか、レクリエーションやイベントなどに参加できる施設もあります。
認知症の症状が見られる場合には、病状の進行を防ぐためにも、介護予防認知症対応型通所介護のような専門的なサービスを利用してもいいかもしれません。
要支援2で受けられるサービス③短期入所型サービス
短期入所型サービスとは、文字通り短期間だけ施設に入所し生活するというサービスです。
一般的にはショートステイと呼ばれており、利用者が施設に宿泊し、サービスを受けながら生活を送ることができるため、やむを得ない理由で介護ができない場合やご家族が介護から離れリフレッシュしたい際に利用されることが多いサービスとなっています。
短期入所型サービスは、1日から利用することができ最大30日間宿泊することが可能です。
以下では、短期入所型サービスに該当するサービスを詳しく解説していきます。
介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護は、介護施設に短期間入所し、洗濯や掃除といった家事や着替えの手伝いといった生活支援、見守り、緊急時の対応といったサービスを受けながら生活することができるサービスです。
施設に入所できる期間は1日~30日までとなっており、30日を超えると超過分は全額自己負担となるため注意が必要です。
介護予防短期入所療養介護
介護予防短期入所療養介護は、老健や介護医療院などの医療面が充実した施設に短期間入所し、看護および医学的管理の下で生活支援や医療ケア、機能訓練などのサービスを受けながら生活することができるサービスです。
介護予防短期入所生活介護と異なる点としては、入所先の施設やサービスの違いが挙げられます。
介護予防短期入所療養介護では、老健や介護医療院の医療機関に入所することになります。介護予防短期入所生活介護と異なり、医療機関に入所するためサービス内容も異なっており、投薬やリハビリなどのより医療的専門性の高いサービスを受けることができます。
入所期間は、介護予防短期入所生活介護と同じく1日~30日となっており、30日を超過した分は全額自己負担となるため、注意が必要です。
短期入所型サービスを利用する際には、それぞれの違いを踏まえたうえで適切な方を選択するようにしましょう。
要支援2で受けられるサービス④複合型サービス
複合型サービスは、「訪問」「通い」「宿泊」等のサービスを組み合わせて利用することができるサービスです。
前述の3種類のサービスを1つの事業所が提供しているため、利用者の状況に応じて適切な種類のサービスが受けられるなど、柔軟に対応可能という特徴を持ちます。
また、利用手続きが1回で済むというメリットもあります。
以下では、複合型サービスに該当するサービスを詳しく解説します。
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護は、利用者の選択に応じて「訪問」「通所」「宿泊」の3つを組み合わせて利用できるサービスとなります。
利用者が可能な限り自立した生活を送れることを目的としており、家庭的な環境や地域住民との交流のもと、日常生活の支援や機能訓練と行うという特徴があります。
訪問・通所・宿泊の3つのサービスを同じ施設・職員が担当することから、連続性のあるケアを受けることができるため、安心感を得られやすいサービスとなっています。
要支援2で受けられるサービス⑤施設サービス
施設サービスは、介護施設に入居し生活する形態のサービスとなります。
施設へ入居すれば、専用の設備を用いた介護やリハビリなどのサービスを日常的に受けることができるため、自宅に比べると身体的には楽な生活が送れるでしょう。
施設の特徴により異なりますが、介護や生活支援、リハビリなど、多様なサービスを受けることができます。
以下では、要支援2の方が入居可能な施設について詳しく解説していきます。
グループホーム
グループホームとは、認知症の症状が見られる方を対象とした、5~9人の少人数からなる共同住宅の形態(ユニット)で生活する施設となっています。
認知症の進行を遅らせること、また生活機能の維持を目的とした施設であり、入居者同士のかかわりが深く慣れ親しんだ環境を作りやすいことから、認知症の改善に繋がる可能性が期待されています。
グループホームでは、入浴・食事・排せつの介助をはじめとした身体介護やその他の日常生活上の援助、リハビリなどのサービスを受けることができます。それに加えて、専門的な認知症ケアが受けられるため、認知症の症状が心配という方でも安心して入居できる施設と言えます。
認知症の症状が見られることが多く、専門的な認知症ケアを受けたいという方は入居を検討してみると良いかもしれません。
有料老人ホーム
有料老人ホームとは、「介護(入浴・食事・排せつ)」「洗濯・掃除をはじめとした家事の供与」「健康管理」の内いずれか1つ以上をサービスとして提供している施設を指します。
有料老人ホームは、特養などの社会福祉団体や自治体が運営する公的側面が強い施設に比べ費用が高くなる傾向にあります。
また、有料老人ホームは、施設の特性によって「介護付き」「住宅型」「健康型」の3つに分類されるため、以下で詳しく解説します。
なお、健康型は自立の方を対象にした施設であるため、詳細な紹介は省きます。
介護付き有料老人ホーム
介護付き有料老人ホームは、24時間介護スタッフが常駐しており、入浴や排せつ、食事などの身体介護や掃除・洗濯といった家事サービスなどを提供している有料老人ホームとなります。
介護サービスが手厚いという特徴を持ちますが、通常の介護費用に加えて上乗せ介護費用が発生する場合があるなど、費用が高くなる傾向にあります。入居を検討する場合には事前に確認しておきましょう。
住宅型有料老人ホーム
住宅型有料老人ホームは、主に自立や要支援といった要介護度の低い方を対象とした有料老人ホームになります。ただし、施設によっては要介護5の方まで受け入れているなど、施設によって運営方針はさまざまです。
介護付き有料老人ホームと異なる点としては、介護サービスがサービス内容に含まれていない点が挙げられます。
住宅型有料老人ホームのサービスは食事の提供や掃除・洗濯といった家事サービス、見守りなどが中心であり、介護サービスを受けたい際には、外部の訪問介護事業所や併設の介護事業所と契約をして介護サービスを受けることになります。
外部の介護サービスを利用した際の費用は、施設の月額費用とは別途発生し、利用した分だけ支払う形になります。そのため、介護サービスの利用が少ない方は、毎月定額の介護サービス費が必要になる介護付きに比べ費用が安く済むというメリットがあります。
ケアハウス(自立型)
ケアハウスは、家庭環境や経済状況などが原因で自立して生活することが難しい高齢者を対象にした介護施設であり、自立型と介護型に分かれます。
自立型は、自立の方から軽度の要介護状態の方が入居することができ、介護サービスの提供はないものの、日常生活の援助や食事の提供、緊急時対応といったサービスを受けることができます。
なお、介護サービスを利用したい際には、外部の介護サービス事業者と別途契約する必要があります。
また、ケアハウスは種類に関わらず、費用が安いという特徴があるため、予算に余裕がない方でも入居しやすい施設と言えるでしょう。
サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)
サ高住とは、バリアフリーに対応した高齢者向け住宅の賃貸住宅であり、「安否確認」「生活相談」等のサービスを受けることが可能です。
サ高住は一般的には介護サービスの提供を行っていないため、介護サービスを利用したい際には、介護サービスを提供している介護型のサ高住に入居するか、外部の介護サービスを利用する必要があります。
また、サ高住は介護施設ではなく賃貸住宅という形になるため、施設のように決められたタイムスケジュールで生活する必要がなく、比較的自由度の高い生活を送ることができます。
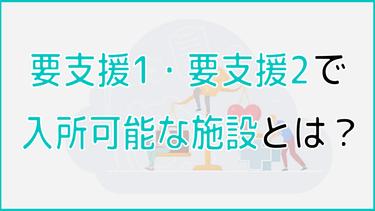
ケアスル介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができるためご希望に沿った施設探しが可能です。「プロに相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
要支援2で受けられるサービス⑥福祉用具のレンタル・購入

要介護認定を受けた方は、要介護度に応じた福祉用具のレンタル・購入が可能です。
要支援2の認定を受けた方がレンタル・購入することができる福祉用具は以下の通りです。
| 福祉用具の種類 | 詳細 | |
|---|---|---|
| レンタル | 手すり | 工事を伴わない、設置型の手すり。 起居動作や歩行が安定しない高齢者の方の生活のサポートが可能。 |
| スロープ | 工事を伴わない、設置型のスロープ。 段差部分に設置することで、生活環境の改善や事故防止等の効果が見込める。 |
|
| 歩行器 | 転倒しやすい状態にある高齢者の方の歩行を補助する福祉用具。 両腕で体重を支えることができるため、脚にかかる負担や痛みを軽減する等の効果がある。 |
|
| 歩行補助杖 | 歩行が安定しない状態にある高齢者の方の歩行を支える福祉用具。 歩行器同様、脚にかかる負担を軽減することが可能。 |
|
| 自動排せつ処理装置 | 自力でトイレまで歩くのが困難な方の排せつをサポートする福祉用具。 レシーバー部分に排尿することで、レシーバーとつながっている本体に尿が吸引される。 |
|
| 購入 | 腰かけ便座 | 和式のトイレや、洋式のトイレに設置する福祉用具。 座位や起居動作の安定などの効果が見込める。 |
| 自動排せつ処理装置の 交換可能部品 |
前述の自動排せつ処理装置の交換可能部分の部品。 尿タンクやホース、レシーバーなどが該当する。 |
|
| 入浴補助用具 | 自宅の浴室に設置する手すりやすのこなどの福祉用具。 設置することで、入浴時の動作の安定や転倒の防止などの効果が見込める。 |
|
| 簡易浴槽 | 居室などで簡単に入浴ができるための福祉用具。 居室に設置可能であるため、自宅の浴室までの移動が困難な方の入浴をサポート可能。 |
|
| 移動用リフトの吊り具部分 | 前述の移動用リフトの吊り具部分。 脚分離型やシート型などの種類があり、トイレや入浴など用途に分けて取り換えることが可能。 |
|
上記の表からも分かるように、レンタル・購入といった福祉用具の利用形態によって介護保険の対象となる品目が異なります。
また、要支援2の認定段階は、介護が必要ない比較的軽度の状態とされているため、介護ベッドや車いすといった福祉用具のレンタルには介護保険が適用されません。
とはいえ、手すりや歩行器などをレンタルすることで、日々の生活の負担を軽減することが可能であるため、在宅での介護をしている方は、福祉用具の利用を検討してみるといいでしょう。
介護保険サービスを利用する方法
介護保険サービスを利用するには、介護サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要になります。
ケアプランとは、どのような介護サービスを、いつ、どれだけ利用するかを決める計画書のことを指します。
ケアプランを作成するためには、ケアマネジャーに作成を依頼する必要があるのですが、要介護度によって依頼先が異なり、要支援2の方の場合は地域包括支援センターで受け付けています。
地域包括支援センターに依頼後は、担当のケアマネジャーと相談しながら、どのようなサービスを、いつ、どれだけ利用するかを決定します。
希望のサービスがあればそのサービスを伝えることでケアプランの作成がスムーズに進むかもしれませんが、どのサービスが良いのか分からないという場合にも、要介護者の身体状態や介護にまつわる状況などを考慮のうえ適切なサービスを勧めてくれるでしょう。
地域包括支援センターはお住いの市区町村が実施主体になっているため、詳しくはお住いの市区町村に問い合わせるといいでしょう。
出典:厚生労働省「サービス利用までの流れ」
要支援の方によく利用されているサービス
要支援2の方が利用できる介護保険サービスのうち、よく利用されている介護保険サービスは、以下の通りです。
- 介護予防訪問看護
- 介護予防通所リハビリ
- 福祉用具貸与
それぞれについて詳しく説明するので、「結局どのサービスを利用したらいいか分からない」という方は参考にしてみてください。
よく利用されているサービス①介護予防訪問看護
介護予防訪問介護は、看護師などが利用者の自宅に訪問し、療養上のお世話や診療の補助を行うサービスです。
厚生労働省の調査によると、令和3年度の介護予防訪問介護の利用者は約16万人となっており、訪問型のサービスのなかでは利用している人が最も多いサービスとなっています。
介護予防訪問看護では、健康管理や栄養管理といった要介護状態への進行・悪化を防ぐためのケアを受けることができるため、自立状態への回復が見込める要支援の方は利用が多い傾向にあります。
自宅での介護を検討しているかつ、要介護状態への進行・悪化を防ぎたい場合には、介護予防訪問看護の利用を検討してみるといいでしょう。
出典:厚生労働省「令和3年度介護給付費等実態統計の概況」
よく利用されているサービス②介護予防通所リハビリ
介護予防通所リハビリは、日帰りで施設に通い、要介護状態への進行・悪化を防ぐことを目的としたリハビリが受けられるサービスです。
厚生労働省の調査によると、令和3年度の介護予防通所リハビリの利用者は約25万人となっており、通所型の介護保険サービスのなかでは利用している人が最も多いサービスとなっています。
介護予防通所リハビリは、通常の通所型サービスと比べて専門的なリハビリを受けることができるため、自立状態への回復が見込める要支援の方は多く利用している傾向にあります。
要介護状態への進行・悪化の予防、または自立状態への回復を目指す方は、介護予防通所リハビリの利用を検討してみるといいでしょう。
出典:厚生労働省「令和3年度介護給付費等実態統計の概況」
よく利用されているサービス③福祉用具貸与
福祉用具の貸与は、手すりやスロープ、歩行器をはじめとした福祉用具をレンタルすることができるサービスです。
厚生労働省の調査によると、令和3年度の福祉用具貸与サービスの利用者は約82万人となっており、多くの方が利用しているサービスであることが分かります。
前述のように、福祉用具の貸与では、手すりやスロープ、歩行器をはじめとした日常生活上の負担を軽減するための用具をレンタルすることができ、1か月あたりの費用も低額であることから、在宅介護をしている方の多くは利用しているサービスとなっています。
在宅での介護を検討している方は、手すりやスロープなどの自宅での生活をサポートする福祉用具の貸与サービスを利用してみてもいいのではないでしょうか。
出典:厚生労働省「令和3年度介護給付費等実態統計の概況」
要支援2の方のケアプラン例
要支援2の高齢者は、在宅介護・施設・一人暮らしなどのさまざまな状況で生活しています。
ここからは、それぞれの生活スタイル別に分類したケアプラン例をご紹介します。
在宅介護の場合
要支援2の認定段階は、まだ本格的な介護が必要な状態ではないため、自宅で生活しながら介護をすることもあるでしょう。
在宅で介護をする場合のケアプランは以下の通りです。
| サービスの種類 | 回数/月 | 自己負担額(1割の場合) |
|---|---|---|
| 介護予防訪問リハビリ | 8回(週2回) | 2,320円 |
| 手すりのレンタル | 月々 | 1,000円 |
| 合計 | 3,320円 |
基本的には、ご家族の方からの援助を受けられるため、自宅で行うのは難しいリハビリをサービス利用するケアプランになりました。
このようにご家族からの援助が受けられる在宅介護の場合では、あまり多くのサービスを利用することなく生活していくのも可能です。
施設入居の場合
ご家族による在宅介護や一人暮らしの継続が難しい場合は、施設に入居するのも1つの手です。
施設に入居した場合のケアプランは以下の通りです。
| サービスの種類 | 回数/月 | 費用 |
|---|---|---|
| 施設利用料 | 月額 | 150,000円 |
| 日常生活費 | 利用分に応じて | 10,000~30,000円 |
| 合計 | 160,000~180,000円 |
これはあくまでも一例であり、入居先の施設によってはこの金額よりも高いケースも安いケースもあるため、注意が必要です。
施設に入居すると、生活援助・機能訓練等のサービスを受けられるだけでなく、常に職員が常駐しているため困ったときに助けてもらえるなど、家族の負担が減るでしょう。
しかし、施設入居は、介護サービス費の他にも食事や居住費といった費用が発生するため、在宅介護に比べるとどうしても費用は高くなる傾向にあります。
メリット・デメリットを総合的に判断して施設利用を検討しましょう。
一人暮らしの場合
要支援2の方は、一部の生活動作に手助けや見守りが必要な状態であるものの、基本的には自立した生活を行うことが可能であるため、一人暮らしをしている方も少なくありません。
一人暮らしのケアプランは、以下の通りです。
| サービスの種類 | 回数/月 | 自己負担額(1割の場合) |
|---|---|---|
| 介護予防訪問介護(調理や掃除など) | 8回(月額) | 2,433円 |
| 介護予防通所リハビリ(デイケア) | 8回(月額) | 3,615円 |
| 手すりのレンタル | 月額 | 1,000円 |
| 合計 | 7,048円 |
一人暮らしの場合は、在宅介護と比べるとサービスの利用頻度が増え、それに伴いサービス利用料も高額になっています。
とはいえ、介護保険適用のサービスであれば、費用にそこまで大きな差はないため、一人暮らしをすることのリスクなどを考慮のうえ、介護の仕方を選択するといいでしょう。
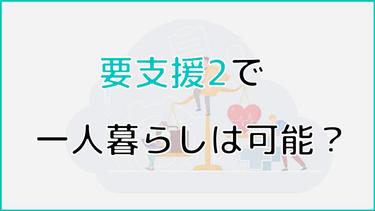
まとめ
ここまで、要支援2で利用できるサービスやその内容、利用方法などを紹介してきました。
介護保険サービスを適切に利用することで、要介護者本人の生活を支えるだけでなく、ご家族の介護の負担も軽減することができます。
適切な介護保険サービスを利用するには、サービスについて知っておくことが何よりも重要です。
利用可能なサービスやその内容を理解したうえで、要介護者本人の希望や介護状況、またご家族の方の身体的・精神的負担を考慮し、必要なサービスを利用しましょう。
利用者の自宅を訪問し介護を提供する訪問介護や、施設に通い介護サービスを受ける通所介護などがあります。詳しくはこちらをご覧ください。
要支援の方がよく利用する介護保険サービスとしては、「介護予防訪問看護」「介護予防通所リハビリ」「福祉用具貸与」が挙げられます。詳しくはこちらをご覧ください。