「地元で暮らしている親が要介護認定を受けた」「実家に一人で住んでいる親が心配」といったの理由から、親の介護のために地元へ戻るかどうか迷っている方はいませんか?
本記事では、親の介護で地元に戻るメリット・デメリットや、遠距離介護を続けるポイントなどについて詳しく解説します。
この記事を最後まで読み終えてもらえたら、親の介護が必要となった際、家族にとって望ましい場所を選ぶのに役立ちます。
遠方に暮らす親の介護でお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
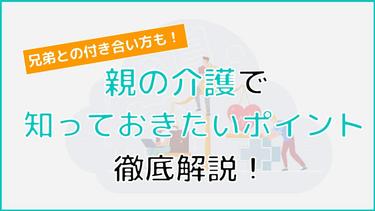
親の介護で地元に戻るケース
大学進学や就職、結婚といったを機に親元を離れて暮らしている方も多くいると思いいます。
しかし、介護が必要となった親のために一度離れた地元に戻るのは、さまざまな不安が生じるものです。
以下は実際に親の介護を理由に地元へ戻った方の事例です。どんなケースがあるのか確認してみましょう。
ケース①:介護を終えたタイミングで後悔が残らなかった
単身のAさんには、実家で一人暮らしをしている80代の父親がいました。父親は火の不始末をきっかけに認知症の診断を受けて、一人暮らしが難しいとわかりました。
しかし、ほかに頼れる兄弟がいなかったため、Aさんが地元へ戻りました。
認知症の症状は徐々に進行し、排泄の失敗や徘徊、暴言などが見られ始め、Aさんのストレスは高まり、「逃げ出したい」と思ったときが何度もありました。
介護している最中は辛かったものの、父親の介護を終えたタイミングでは「介護をしてよかった」と後悔を残すことはありませんでした。
ケース②:家族と離れ単身で地元に戻った
Bさんは実家で一人暮らししている母親の入院がきっかけで、地元へ戻りました。
結婚して家族がいましたが、勤めていた会社の支店が地元にあったため、異動願いを出して単身赴任しました。
自身の仕事を続けながら母親の介護や看病を行い、1年後に母親は逝去しました。
個人的な理由で異動願いを出したため仕事のキャリアに傷がつきましたが、親のそばで介護して、最期を看取れたのはよかったと感じています。
地元で老人ホーム・介護施設をお探しの際にはケアスル 介護がおすすめ。経験豊富な相談員が施設入居を検討している方のための無料相談を承っているので、お気軽にご相談ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
親の介護で地元に戻るメリット
現在住んでいる地域を離れて、親を介護するために地元へ戻ると、さまざまなメリットが得られます。
そこで、ここでは親の介護で地元に戻るメリットについて詳しくご紹介していきます。親の介護を理由に地元に戻るかを検討している方は、どのようなメリットがあるのかチェックしてみましょう。
メリット①:心身状態に合わせた対応が取りやすい
いつも親の近くにいるため、心身状態に合わせた対応が取りやすい点が最も大きなメリットといえるでしょう。
体調を崩したり、ケガをしたりしたときも、状況に沿って適切に対応できます。
認知症による徘徊や火の不始末といった行動が見られ始めても、状況が深刻になる前に策を講じられます。
また親の状態によっては、家事や子どもの面倒といったサポートを受けられるでしょう。
メリット②:出費を抑えられる
地元に戻ると、親の介護や生活に関する出費を抑えられる場合があります。例えば親の持ち家に同居する場合、毎月の家賃はかかりません。
アパートやマンションといった賃貸住宅の場合も、家賃を折半すれば負担を減らせるでしょう。食費や光熱費も減って、生活費を抑えられます。
また、これまでに訪問介護で食事や排泄、入浴といった介護をお願いしていた場合、介護を自分で行えば費用を減らせます。
メリット③:ケアマネジャーや介護サービス事業者と連携が取りやすい
すでに介護サービスを利用している、またはこれから利用を予定している場合、ケアマネジャーや介護サービス事業者と連携が取りやすいのもメリットといえるでしょう。
介護生活においてはケアマネジャーがキーマンであり、問題が起こった時は最初の相談相手になります。
ケアマネジャーや事業者と実際に顔を合わせて話をするとお互いの信頼関係が築きやすく、よりスムーズな連携につながります。
また同じ種類の介護サービスでも、事業者によって特徴やサービスは異なります。
スタッフの表情や声のかけ方、関わり方などを実際に見て、より親に合った介護サービス事業者を選べるのもメリットです。
親の介護で地元に戻るデメリット
地元へ戻るとメリットだけでなく、注意しておきたいデメリットもいくつか考えられます。
デメリットと感じるかどうかはそれぞれで異なりますが、程度によっては生活を続けるのが難しくなるかもしれません。以下を確認しましょう。
デメリット①:お互いの距離が近すぎてストレスがたまる
実の親でも別に暮らしていた時間が長ければ長いほど、お互いの生活スタイルやリズムに違いが生まれます。
考え方が異なる者同士が一つ屋根の下で一緒に暮らすと、ストレスを感じるかもしれません。
特に介護が必要な場合は親と過ごす時間が長く、お互いの距離が近くなりがちです。また、親子だからこそ遠慮のない言い方で喧嘩になることもあります。
関係が煮詰まると介護する側のストレスは大きくなり、苦痛を感じるようになる可能性があるでしょう。
デメリット②:新しい仕事を探す必要がある
これまで就いていた仕事を辞めて地元へ戻る場合は新しい仕事を探す必要があります。
これまでの職歴や持っている資格などによって異なるものの「仕事がなかなか見つからない」「以前より大きく賃金が下がった」といった状況が考えられるでしょう。
また業種を変えて就職する場合、これまで築いてきたキャリアが役に立たない可能性もあります。
デメリット③:地域によっては近所づきあいが求められる
地域によっては近所づきあいが求められ、慣れていない方にとっては負担を感じるかもしれません。特に田舎では、近所の方たちとの交流を密にしているところがあります。
草刈りや集会所の掃除のほか、地域で開催するイベントへの参加を求められたり、場所によっては住民の生活範囲が狭く、すぐに近所中に噂が広まってしまうなど、いつも見張られている違和感を感じるなども考えられるでしょう。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
親の介護で地元に戻るときの注意点
親の介護で地元に戻るときは、具体的にどのような点に注意しておけばよいのでしょうか。
事前に注意点を確認をして、地元に戻ってからの生活や介護がスムーズに進むよう準備しましょう。
主な注意点は次の4つです。
介護サービスを利用する
親の介護は家族だけで抱え込まず、介護サービスを上手に利用しましょう。専門的なサービスで質の高い介護が提供されるだけでなく、介護者のレスパイト(休息)にもつながります。
在宅介護で負担の軽減に役立つのは、以下のような介護サービスです。
| 種別 | 対象者 | 特徴 |
| 訪問介護 | 要介護1以上の方 | ホームヘルパーが自宅へ来て、食事や排泄、入浴といった身体介護や、買い物、掃除、食事の支度といった生活援助をしてもらえる |
| 訪問看護 | 要支援1・要介護1以上の方 | 看護師が訪問して、バイタルチェックや主治医の指示による医療処置などを行う |
| デイサービス | 要介護1以上の方 | デイサービスセンターへ日中通って、介護や食事、入浴、レクリエーションいったサービスを受けられる |
実際はケアマネジャーがケアプランを立て、どの事業所のサービスを利用するかを提案してくれます。担当のケアマネジャーから説明を受けて、納得のいくサービスを利用しましょう。不都合が合った場合は、すぐにケアマネジャーに相談しましょう。
相談できる機関とつながる
親の介護で何か困りごとが起きたときに、助けを求められる相談機関とつながっておくと安心です。
特に、介護中の家族が気軽に利用しやすい相談機関は次の通りです。
| 相談機関 | 対象者 | 特徴 |
| 地域包括支援センター |
|
居住地域ごとに担当する地域包括支センターがあり、主任ケアマネジャー、保健師や看護師、相談員(社会福祉士)が常駐している |
| ケアマネジャー | すでに介護サービスを利用している方 | 介護に関するさまざまな相談に乗ってもらえる |
地域包括支援センターやケアマネジャーに介護に関する悩みを相談すると、必要に応じて社会資源や介護サービスにつなげてもらえます。
お互いの生活スタイルが異なる点を理解する
実の親子でも生活スタイルや価値観は異なります。
親は毎日朝食を食べるけれど、子どもは食べない場合、一緒に住むと親が食べる朝食を準備しなければいけません。
また起床時間や就寝時間、見たいテレビ番組、エアコンの温度など、生活スタイルに関して親子で違う点はたくさんあります。
生活スタイルが違った者同士がストレスを減らして暮らすためには、どのような生活しているのか、何を大切にしているのかをお互いに確認しておきましょう。
介護の資格取得を検討する
介護には適切な方法やポイントがあり、理論に沿った方法をとると身体的・精神的な負担を軽減できます。
最近は通信講座で手軽に取得できる資格も多く、手軽に介護の知識を身につけられるでしょう。
自宅で学習しながら合格を目指せる介護の資格は次の通りです。
| 種類 | 特徴 | 取得方法 |
| 認知症介助士 | 認知症を正しく理解し、症状に合った適切な関わりに役立つ | 下記のいずれかの方法で取得可能
|
| 介護予防健康アドバイザー | 中高齢者が体を動かして、健康的な暮らしを続けられるようにサポートする | 通信講座でカリキュラムを学んだあと、検定試験を受ける |
介護の資格を取得することで学んだことが、実際の介護の場面で起こることの理由などが理解でき、冷静な対応ができるようになるでしょう。
親の介護が必要でも地元に戻らない選択肢もある
親に介護が必要になっても、地元へ戻らない選択肢があります。
例えば「一軒家を購入してしまった」「これまで築いてきた仕事のキャリアを失いたくない」「地元が好きじゃない」などのさまざまな理由から、戻らない決断をする方は多くいます。
現在利用できる介護保険制度・介護サービスは、一人暮らしの方が介護状態になっても、対応できるものです。
地元へ戻らず、さまざまな介護サービスを活用しながら親の生活を遠くからサポートする方法はあり、実践している人も多くいます。。
地元に戻らず遠距離で介護を続けるためのポイント
地元へ戻らず、遠距離で親の介護を続けるためには、いくつかのポイントがあります。
以下で紹介する4つのポイントを実践すると、遠く離れた場所からも親の生活をしっかり支えられるでしょう。
こまめにコミュニケーションをとる
遠距離では直接親と顔を合わせる機会が少なくなる分、こまめなコミュニケーションの心がけが大切です。
頻繁に親子間でやり取りすると、「離れていても子どもが気にかけてくれている」と安心感をもたらすのに役立ちます。普段の何気ない会話の中から生活状況や健康状態の変化、困りごとなどをキャッチし、適切な対応につなげましょう。
また、介護サービスを利用している場合、サービスの内容やスタッフの対応などについても聞いてみましょう。
もしも客観的に「親に合っていないかもしれない」と感じたら、担当のケアマネジャーに相談してケアプランを変更してもらえます。
ただし、連絡手段は電話やメール、LINE、ビデオ通話など、お互いに無理なく続けやすいものや手軽に取り入れやすいものを選んでください。
勤務先に遠距離介護する旨を話しておく
仕事をしている方は、あらかじめ勤務先へ遠距離介護する旨を伝えておきましょう。
これから遠距離介護する旨を伝えておけば、親が急に入院したり、家族のサポートが必要な状態になったりしたときに、休暇などの配慮・調整を受けやすくなります。
また勤務先からの理解を得られると、仕事を辞めずにこれまでのキャリアを継続できるというメリットもあります。
見守りサービスを活用する
遠距離でも親を見守ってくれるICT機器や緊急通報システムなどがあり、上手に活用すると親の安全を確保できます。
見守りカメラの中には「24時間の録画が可能」「スマホやタブレットで、親の様子をリアルタイムで見守れる」「カメラを通じて会話ができる」といった機能を持つものがあります。
また自治体によっては緊急通報システムを貸し出しているところがあるため、問い合わせてみるとよいでしょう。
さらに食事を届ける際に、一緒に安否確認をする配食サービスを行っている自治体や業者があります。
届けたときに返事がなかったり、いつもと違った様子が見られたりした場合、家族や行政、ケアマネジャーなどで連絡してもらえるので安心です。

状況によっては介護施設への入所も検討する
先に述べた訪問介護や訪問看護、デイサービスなどの介護サービスを利用すると、直接的なサポートだけでなく、見守り体制の構築にもつながります。
ただし、親だけで暮らすのが難しくなった場合は、特別養護老人ホームや介護付き有料老人ホームなどの入所施設の利用も検討しましょう。
主な入所施設の特徴や対象者は次の通りです。
| 種別 | 対象者 | 特徴 |
| 特別養護老人ホーム | 原則として要介護3以上 |
|
| グループホーム | 要支援2以上の認知症高齢者 |
|
| 介護付き有料老人ホーム | 原則65歳以上で、要介護度等の入居条件は施設によって異なる |
|
| 住宅型有料老人ホーム | 施設によって異なる |
|
| サービス付き高齢者向け住宅 | 60歳以上、または要介護認定を受けた60歳未満の方 |
|
具体的なサービス内容は施設によって異なるため、複数の施設を比較してみるとよいでしょう。
「親に安心して過ごしてもらえる施設を探してあげたい」と思っている方はケアスル 介護がおすすめ。ケアスル 介護は約5万件の施設情報を掲載しているため、それぞれの希望や状況に合った入所施設を教えてもらえます。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
親の介護で地元に戻るかは慎重に検討しましょう!
親の介護のために地元に戻る場合、メリットとデメリットの両面が生じます。
お互いの生活スタイルや必要とする介護の程度、家族構成などによって、地元に戻った方がよいのかどうかは異なります。
家族の介護負担や経済状況にも関わるため、慎重に検討しなければいけません。
親の介護が必要となった場合、親の意思を尊重する以外に、介護を担う家族にとって負担がかかりにくい方法の選択も大切です。
そのため、介護サービスや相談機関を上手に活用しながら、介護者・要介護者それぞれに合った関わり方を見つけていきましょう。
感じるメリットには個人差がありますが、近くに親がいるため、心身状態に合わせて迅速な対応がとりやすいでしょう。医療が必要な場合は、すぐに医療機関につなげられます。詳しくはこちらをご覧ください。
まだ介護保険サービスを使っていない方は、地域包括支援センターを利用できます。保健師や社会福祉士、主任ケアマネジャーといった専門スタッフが、個々の状況に合わせたアドバイス・サポートをしてくれます。詳しくはこちらをご覧ください。





