「一人暮らししている要介護2の父親に介護が必要となった」「要介護2でも入所できる施設や、必要な費用を知りたい」といった状況にある方はいませんか?介護保険の知識がないと、要介護2にある方がどのような施設を利用できるのか、また入所にあたってどのくらいの費用が必要なのか検討がつきません。
今回は要介護2の方が利用できる施設と費用相場について解説します。施設選びのポイントと費用を抑えるための方法も一緒に紹介するので、ぜひ参考にしてください。

要介護2で入所できる施設と費用
要介護2の方が入所できる施設一覧は、次の通りです。
| 施設の種類 | 対象者 | 主なサービス内容 | 主に必要な費用項目 |
|---|---|---|---|
| 老健(介護老人保健施設) | 65歳以上で要介護1以上の方 | 在宅復帰に向けたリハビリや介護、看護など |
|
| 軽費老人ホーム | 60歳以上の介護認定を受けていない高齢者(C型介護は65歳以上で要介護1以上) | 食事や生活サービス、介護サービスなど |
(費用項目は種類によって異なる) |
| 介護療養型医療施設 | 65歳以上で要介護1以上の方 | 手厚い医療や介護、リハビリなど |
|
| 介護医療院 | 65歳以上で要介護1以上の方 | 医療や介護、レクリエーションなど |
|
| 介護付き有料老人ホーム | 原則65歳以上で、要介護度は種類によって異なる | 介護や看護、レクリエーションなど |
|
| 住宅型有料老人ホーム | 施設によって入居できる下限年齢は異なる | 食事やスタッフによる見守りなど |
|
| サ高住(サービス付き高齢者向け住宅) | 60歳以上、または要介護認定を受けた60歳未満の方 | 食事やスタッフによる見守りなどだが、内容は施設によって異なる |
|
| グループホーム | 認知症の診断を受けている65歳以上で、要支援2・要介護1以上の方 | 認知症の症状に合わせた介護など |
|
それぞれの詳細を、以下で見ていきましょう。
老健(介護老人保健施設)
老健は介護保険施設の一つで、在宅復帰を目標としています。入所できる期間は3ヵ月~6ヵ月ほどのため、終身で利用できる施設ではありません。
対象者
65歳以上かつ、要介護1以上の方が入所できます。病状が安定しており、在宅復帰に向けたリハビリを必要とする方が対象です。
サービスの内容
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士といった機能訓練の専門スタッフが在籍し、一人ひとりの身体状態に合わせてリハビリを受けられます。
配置している職種は施設によって異なり、中には理学療法士や作業療法士に加えて、柔道整復師やあん摩マッサージ指圧師、針きゅう師などからサービスを受けられるところもあります。週2回以上はリハビリが提供され、効果的に身体機能の回復や向上に取り組めるのが魅力です。
また医師や看護師、介護スタッフが常駐しており、日常的な健康管理・介護サービスを実施しています。たんの吸引や経管栄養などの医療的処置にも対応可能です。
レクリエーションや季節のイベントなどを開催している施設も多く、楽しみながら在宅復帰に向けたケアを受けられます。
軽費老人ホーム
軽費老人ホームは自立生活に不安を感じる方を対象とした施設で、さらにいくつかのタイプに分かれています。
対象者
60歳以上の介護認定を受けていない人(C型介護は65歳以上で要介護1以上)で、さらに高齢・身体機能の低下などが原因となって在宅生活に不安がある方が対象です。
サービスの内容
現在はA型・B型・C型自立・C型介護の4タイプがあります。A型は食事提供とスタッフによる掃除・洗濯などの生活サービスが、B型は生活サービスのみが提供されます。B型は食事が提供されないため、自分で食事の準備をしなければいけません。
C型はケアハウスとも呼ばれており、自立型と介護型の2つに分かれています。自立型は食事提供と生活サービスを受けられ、一般的なケアハウスとして人気です。
一方の介護型は特定施設入居者生活介護の認定を受けており、特養や介護付き有料老人ホームのように24時間、365日の介護サービスが受けられます。
介護療養型医療施設
手厚い医療と介護が提供され、重度の方も安心して生活できるのが介護療養型医療施設です。
対象者
65歳以上で要介護1以上の方が対象です。また「伝染病がない」「病気を原因とする長期利用の必要がない」など、施設ごとに細かい条件が課されている場合もあります。
サービスの内容
医師や看護師、薬剤師といった医療スタッフや介護スタッフが在籍し、手厚い医療サービス・介護サービスを受けられます。医療ケアの管理やチェック、各種の検査、投薬、注射などを医師が日常的におこなっているため、医療ニーズがある方も安心です。胃ろうやカテーテルなどが必要な方も利用できます。
また理学療法士や作業療法士といったリハビリスタッフも配置され、一人ひとりの状態に合わせた訓練を受けられるのも魅力です。
ただし、レクリエーションやイベントなどは期待できない点や、2024年3月末に廃止予定の点には注意してください。
介護医療院
先で紹介した介護療養型医療施設に代わる施設で、医学的管理の下における医療・介護・住まいとしての生活支援サービスを提供するのが介護医療院です。
対象者
65歳以上・要介護1以上で、医療と介護の両方を長期的に必要な方が対象です。
サービスの内容
介護療養型医療施設と同様に、医療と介護が充実しているのが特徴です。医療機関へ入院するほどではないけれども、老人ホームでは適切な医療を受けられないような方に適しています。掃除や洗濯などの生活サービスも受けられます。
またレクリエーションが開催されるのも、大きな魅力といえるでしょう。生活施設として楽しめる体験をしたり、ほかの入所者と交流したりと、充実した毎日を送れます。
「介護医療院Ⅰ型」と「介護医療院Ⅱ型」に分かれており、それぞれでスタッフの配置基準が異なります。
Ⅰ型はより医療体制が整っており、様態が急変するリスクのある方に対して、喀痰吸引や経管栄養を中心とした日常的かつ継続的な医学管理をおこないます。そのために、医師の宿直が義務となっている施設です。これに対するⅡ型は、容態が比較的安定した方に対して医学管理をおこなう施設です。
介護付き有料老人ホーム
介護やレクリエーションといったサービスが充実しているのが、介護付き有料老人ホームです。介護専用型・混合型・自立型の3種類に分けられます。
対象者
原則65歳以上で介護専用型は要介護1以上、混合型は自立・要支援・要介護、自立型は自立の方が対象です。ただし、自立型に入居した後、介護が必要な状態になった場合でも入居を継続できるのが一般的ですが、介護度が重くなると、転居を促されるケースもあります。
サービスの内容
特定施設入居者生活介護の指定を受けているため、24時間・365日の介護を、一定の費用負担で受けられます。特養などの公的施設よりも人員配置が多めになっているため、食事や排泄、入浴など、手厚いサポートが必要な方も安心です。
看護師、または准看護師の配置も義務づけられているため、バイタルチェックや服薬管理なども受けられます。
民間企業が運営しており、具体的なサービス内容や費用は施設によってさまざまです。なかには看護師が24時間体制で常駐しているところもありますし、食のイベントについては、ほとんどの施設で定期的に開催しています。施設の数は多く、選択肢の幅が広いのは魅力です。
住宅型有料老人ホーム
住宅型有料老人ホームは主に自立や要支援、要介護度が低い方を対象とした施設です。
対象者
60歳以上もしくは65歳以上、自立〜要介護5など、施設によって入所条件は異なります。年齢・要介護度以外にも、認知症・医療ケアの有無などで入所制限をしているところもあります。
サービスの内容
具体的に提供されるサービスは施設によって大きく異なるものの、食事の提供やスタッフによる見守りが中心です。食事は入所者の身体状態・健康状態に合わせたものが提供されるでしょう。ソフト食やきざみ食、ミキサー食などの食形態に対応するため、安全に食事を楽しめます。
介護サービスが必要な場合は、外部の事業所と契約して利用するのが一般的ですが、建物内に介護事業者が入所しているケースもあります。ケアマネジャーにケアプランを作成してもらうと、訪問介護やデイサービスなどを利用できます。自分に必要なサービスを、必要なだけ選んで利用できるのがメリットです。
サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)
安否確認や生活相談が受けられる賃貸形式の施設が、サ高住です。
対象者
60歳以上、または要介護認定を受けた60歳未満の方が対象です。また施設によっては「認知症がない」「身の回りの世話は自分でできる」といった条件を設けているところもあります。
サービスの内容
賃貸形式の施設のため、自由度の高さが魅力です。基本的に外出や外泊に関する規則は設けられておらず、出前なども取れる施設もあります。入所前とできるだけ変わらない生活を送りたい方に適しています。
スタッフによる定期的な安否確認や生活相談が行われるため、一人暮らしの方も安心です。食事や夜間のスタッフ配置、レクリエーションなどの有無は施設によって異なります。
介護が必要な場合は、外部の事業所と契約してサービスを利用するのが一般的。施設内に訪問介護事業所を併設しているところもあるでしょう。
グループホーム
グループホームは認知症の方が入所して、ほかの入所者やスタッフと共同生活を送る施設です。
対象者
医師から認知症の診断を受けており、65歳以上で要支援2・要介護1以上の方が利用できます。
サービスの内容
1ユニット9名以下のグループで共同生活を送ります。少人数のため、アットホームで落ち着いた雰囲気の中で暮らせる環境です。
認知症があってもできるだけ自立した生活を送れるように、食事の準備や片付け、掃除、洗濯などの家事活動は、可能な限り入居者自身が担当します。介護スタッフは24時間体制で常駐し、介護を含めて必要なサポートを行います。
認知症の方に特化しているため、一人ひとりの症状に合わせたケアを受けられるのが特徴です。症状を和らげたり、進行を遅らせたりするような関わりを通して、安心した毎日を過ごせます。
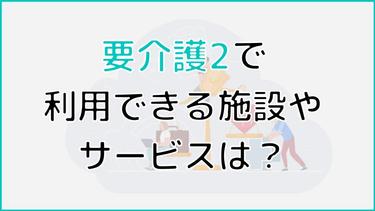
要介護2で施設を利用する場合の費用相場
要介護2の方が施設を利用する際、どのくらいの費用が必要なのでしょうか?以下の表は、「介護サービス情報公表システム」の試算に基づいた概算料金です。
| 施設の種類 | 月額 | 1割負担の自己負担額 | 2割負担の自己負担額 | 3割負担の自己負担額 |
|---|---|---|---|---|
| 老健(介護老人保健施設) | 294,770円 | 29,477円 | 58,954円 | 88,431円 |
| 介護療養型医療施設
※2024年3月末で廃止 |
272,220円 | 27,222円 | 54,444円 | 81,666円 |
| 介護医療医院 | 291,260円 | 29,126円 | 58,252円 | 87,378円 |
| 特定施設入居者生活介護(指定を受けた有料老人ホームと軽費老人ホームなど) | 206,850円 | 20,685円 | 41,370円 | 62,055円 |
| グループホーム(認知症対応型共同生活介護) | 284,290円 | 28,429円 | 56,858円 | 85,287円 |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護(指定を受けた入所定員30名未満の、有料老人ホームや軽費老人ホームなど) | 204,900円 | 20,490円 | 40,980円 | 61,470円 |
食費や居住費、介護保険が適用されないサービス費用などは、施設によって別に必要です。また高級な有料老人ホームでは、入居一時金として5000万円から1億円くらいかかるところもあります。月々の合計費用は施設によって異なるため、入所前に確認してください。
要介護2の方が安心して暮らせる施設選びのポイント
要介護2の方がこれから施設入所を考える場合、安心して暮らせる場所を選ぶ必要があります。施設選びのポイントは次の3つです。
- 必要なものに優先順位をつける
- 介護の専門家へ相談する
- 実際に訪問して見学する
詳細を以下で解説します。
必要なものに優先順位をつける
本人や家族が抱えるすべての希望をかなえる施設を探すのは難しいため、事前に希望条件をリストアップして、さらに優先順位をつけましょう。検討すべき主な内容は次の通りです。
- 介護や看護サービスの内容
- レクリエーションやイベントの有無
- 食事の内容
- 立地
- 予算
介護や医療を必要とする場合、介護・医療体制をチェックしましょう。夜間を含めたスタッフ体制や施設内で提供される医療サービス、提携している医療機関の対応内容などがポイントです。レクリエーションやイベントがあると、充実した生活を送れます。
また食事は毎日の楽しみとなるため、実際に提供される献立やセレクトメニューの有無、介護食・療養食への対応などを確認してください。
自宅からあまりにも遠いと、家族が面会に訪れにくくなります。一般的に都市部から離れているところは費用が安いため、予算と相談しながら立地を選ぶとよいでしょう。
介護の専門家へ相談する
すでに介護サービスを利用している場合は担当のケアマネジャーへ、利用していない場合は地域包括支援センターといった介護の専門家へ相談してみましょう。地域にある施設の情報や評判などに精通しているため、客観的なアドバイスをもらえます。
ただし遠方の施設を検討している場合は、より広範囲の相談に対応している民間の紹介窓口を使う方法があります。
実際に訪問して見学する
多くの方にとって長期にわたって過ごす場所となるため、実際に目で見て詳細を確認する必要があります。見学するときにチェックしておきたい点は、次の通りです。
- 居室は縦長か、横の幅はどのくらいか
- どのような共有スペースがあり、設備が整っているか
- どのようなレクリエーションがおこなわれているか
- スタッフは笑顔で接しているか
- 入居者の表情は明るいか
入居する本人と一緒に見学して、気に入ったところを選びましょう。また事前にチェックしておきたい点や、質問したい内容をメモにまとめておくのも効果的です。バタバタしたなかで「確認するのを忘れた」「スタッフに質問するのを忘れた」などの状況を防げます。
施設の費用を抑えるための方法
どのような施設を利用するにも、ある程度の費用が必要です。最後に施設の費用を抑えるための方法を、全部で3つ紹介します。
特定施設の指定を受けている
介護を提供する有料老人ホームでも、「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている施設と、受けていない施設があります。近年では、自治体が指定を出し渋る傾向にあるためですが、指定を受けていない施設の場合、在宅と同じような扱いになるため、介護度が進むと介護費用が高くなる可能性があります。
いっぽう、特定施設の指定を受けている施設の場合、包括報酬制度になっているため、介護度ごとに決められた介護費用で24時間・365日の介護が受けられます。
遠方の施設を選ぶ
遠方の施設を選ぶ方法もあります。都市部などの便利なロケーションにある施設は費用が高く、反対に都市部から離れれば離れるほど、低くなっていくのが一般的です。
また最寄り駅から離れているような、交通の便が悪いところも費用を抑えられるでしょう。
入居一時金を一括で支払う
有料老人ホームの入居一時金の支払いには、入居一時金を一括で払うタイプの他、月々の費用に上乗せして支払うタイプ、いくらかは入居時に支払い、残りは月々の費用に上乗せして支払うタイプがあります。長く住むことが想定できる場合には、入居一時金を一括で払うタイプを選びましょう。
入居一時金が不要なタイプは初期費用を抑えられる反面、その後の月額費用は高くなるのが通常です。そのため、一時金を支払った方が長期的な節約につながります。

要介護2でも入所できる施設を知って安心した暮らしを送ろう
老健や介護付き有料老人ホーム、サ高住など、要介護2の方が入所できる施設はたくさんあります。
ただし、要介護以外で提供されるサービス、費用などが異なるため、注意して選ぶようにしましょう。







