認知症の症状により、問題行動が起きてしまうのはよくあります。しかしながら、問題行動なようで、認知症の方にとっては「理由」のある行動なのです。
向き合うのは大変ですが、受け止めてあげなくてはいけないという気持ちで辛くなっていませんか?
この記事では、認知症の方が起こす問題行動について解説します。上手な対応方法についても紹介しているので参考にしてください。
認知症の症状による問題行動の原因とは
認知症の症状による問題行動は、社会常識から外れた行動、マナーから逸脱した行動などを指します。
これらの問題行動は、高齢者の場合、老化・認知力の低下が原因です。
問題行動と言われる認知症の症状には、大きく分けると以下の2つがあります。
- 中核症状
- 周辺・心理症状
中核症状は、日常生活に支障があるもの忘れ記憶障害・失認・失行・判断力の低下・言葉が出にくくなるなどの言語障害(失語)・見当識障害などの症状です。
周辺・心理症状には、歩き回る徘徊・せん妄・抑うつ・興奮・睡眠障害などが挙げられます。
ここでは、中核症状と周辺・心理症状が引き起こされる原因を詳しく解説します。
認知症の中核症状
認知症の中核症状は、脳の機能障害によって引き起こされ、認知症の方のほぼ全員に現れる初期症状です。
判断力が鈍くなる、時間や場所がわからなくなる、今までしていた仕事や家事ができなくなるなどが特徴的な症状です。
これらの中核症状によってストレスや不安が生まれ、その心の状態の不安定さから周辺・心理症状が引き起こされます。周辺・心理症状は、認知症の方の心の状態が大きく影響します。
周辺・心理症状の一つであり、問題行動とされている「徘徊」は、時間や場所を正確に把握できていないなどが原因で起こります。
たとえば、本人は朝に近所を散歩していると思っているとします。
しかし、実際には深夜であると、認知症の方とケア側に認識の差が生まれ、「問題行動である」と言われます。外から見れば異常に思われる行動でも、認知症本人は、場所や時間を把握しているという認識であるため間違えてはいないのです。
認知症の周辺・心理症状
認知症の周辺・心理症状は、自分の思うままに行動したいがどうしていいかわからず、感情が不安定になることで引き起こされる症状です。
記憶障害や言語障害などの中核症状によって、仕事や家事など今までできたことができなくなります。
そのため、「なんとかしなくてはならない」という思いはあるが、自分の思いや理由を相手に伝えることができず、不安や混乱が生まれます。
その不安や混乱が、周辺・心理症状である徘徊やせん妄、興奮の原因です。
周辺・心理症状は、認知症の方の性格や生活環境、人間関係などが影響するため、現れる症状が人によって異なります。
問題行動を起こした認知症患者でも入れる老人ホーム・介護施設を知りたい方は、ケアスル介護での相談がおすすめです。
ケアスル介護なら、全国5万を超える施設の中からあなたにあった施設を選ぶことができ、施設選びを安心して進めることが可能です。
もちろん無料で相談できますので、老人ホーム・介護施設を探している方はぜひ相談してみてはいかがでしょうか。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
問題行動には理由がある
認知症の症状である中核症状や周辺・心理症状などが問題行動と言われます。
これらの行動は、心理的状況によって大きく異なり、個人差もあります。
問題行動は、介護者にとって不可解なことばかりですが、認知症の方なりにその行動を取る理由があります。
「どうしていいのかわからない」「行動したいがうまく行動に移せない」など、不安や混乱によるものが多くなります。
問題行動が起きる状況に応じて必ず理由が付いてくるため、認知症の方が「わからないこと」「できないこと」は何なのかを理解することが重要です。
認知症の方が起こした問題行動の実例
ここまで認知症の症状の内容や原因について簡単に解説しました。
では、認知症の方が実際に起こした問題行動とはどのようなものなのでしょうか。ここでは、以下の4つの問題行動について解説します。
- 暴言や暴力などの行為
- 多動症状
- 薬や食事に関する行動
- 排泄の失敗
これらの問題行動には、認知症の方それぞれの理由があり、その行動に対して介護する側の家族にも適切な対応方法があります。
問題行動の実例と、原因、介護者の対応方法について詳しく解説します。
暴言や暴力などの行為
認知症の方が実際に起こした問題行動の1つ目は、介護者や家族に対して急にきつい言葉を吐く、叩く蹴るなどの暴力行為です。
暴言や暴力などの行為が現れた場合は、認知症の方が怒りやストレスを持っていることがあります。健常な脳であれば、怒りやストレスを持っていても抑えることが可能です。
しかし、認知症の方は、前頭葉の神経細胞にダメージを受けており、脳の機能が低下した状態にあります。
そのため、健常な方よりも感情のコントロールができなくなります。暴言や暴力などの行為が現れる原因には、過去の嫌な経験や記憶を思い出している可能性もあります。
暴言や暴力に対して、介護者や家族も感情的になると、ヒートアップさせてしまうことがあります。
この場合は、認知症の方の話をよく聞き、相手を受け入れる話し方で対応するようにしましょう。
認知症の方は、理解してもらいたいことを抱えている可能性もあります。
それでも、暴言や暴力が続く場合は時間をあけて、気持ちが落ち着くのを待つことも大切です。
暴言や暴力は、介護側の負担になる場合もあるため、すみやかに改善できるよう注意してケアを行いましょう。
多動症状
認知症の方が実際に起こした問題行動の2つ目は、落ち着きがなくなる、部屋の中を動き回る、同じ時間に同じ行動をするなどの多動症状です。
多動症状が現れる原因は2つ考えられます。
1つ目は、「不安を抱えている」「緊張状態である」ことです。その不安や緊張が行動に現れて落ち着きがなくなっている可能性があるでしょう。
2つ目は、「記憶障害」によるものです。
自分がしたことを忘れてしまい、同じ行動を繰り返していることが考えられます。
多動症状の対応方法は、周辺環境の変化を作らないことです。
環境の変化は、認知症の方のみならず誰にとっても不安や緊張に繋がります。
同じ時間に同じ行動をしてしまう場合は、その行動を日常のケアに取り込み、習慣にする工夫をしましょう。
薬や食事に関する行動
認知症の方が実際に起こした問題行動の3つ目は、薬や食事に関する行動です。
認知症の症状により食事したことを忘れる、脳機能の低下で満腹中枢が働きにくいことで食べすぎる場合があります。食べすぎる場合は、1度の食事量を少なくして調整する、果物などの軽食を促す方法が最適です。
また、食べ物ではないものを食べるという「異食行為」もあります。
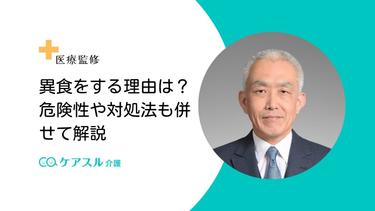
異食行為は、脳機能の低下により、食べ物とそうでないものの認識ができなくなることが原因です。
異食行為の対応方法は、間違えて口に入れてしまいそうなものを本人から遠ざけることです。
口に入るような小さいサイズのものは、身近に置かないようにしましょう。
また、異食してしまった場合は、無理やり取り出そうとせず、他の食べ物で誘導するなど工夫が必要です。
他に、服薬の拒否も認知症の方によく見られる症状です。
認知症の方は、自分の身体状況を正確に把握できておらず、まだまだ健康であると思っている場合があります。そのため、健康な自分に対して介護されることを嫌い、拒否することもあるでしょう。
服薬を拒否する場合は、時間をあけてからもう一度促す、食事と共に提供するなどの対応方法もあります。
食事や薬は、認知症の方にとっても欠かせないものであるため、注意してケアを行いましょう。
排泄の失敗
認知症の方が実際に起こした問題行動の4つ目は、トイレへの移動が間に合わない、トイレの場所を忘れてしまうなどの排泄の失敗です。
排泄の失敗は、物事を行動に移すことに時間がかかる実行機能障害や、場所がわからなくなるなどの見当識障害が原因で起こります。
排泄の失敗は精神的なダメージが大きくなるため、認知症の方のプライドを傷つけないようにしましょう。
排泄の失敗をした場合は、厳しく指摘しないようにしましょう。失敗を責めてしまうと、その失敗を隠そうとして、汚れ物を触ることや隠されてしまうこともあります。
介護者の負担を増やす原因にもなるため気をつけましょう。
尿意を感じてからトイレへ移動するまでに時間がかかる場合は、移動式の簡易トイレを設置することで対応できます。
トイレの場所がわからない場合は、トイレまでの道のりがわかるように矢印などを付ける対応方法があります。
性的異常行動
認知症の方が実際に起こした問題行動の5つ目は、性的異常行動です。主な行動は、介護者や家族に対して卑猥な言葉を言う、異性の身体を触ろうとする、性器を露出することです。
誰にでも性的欲求はあるものですが、認知症の症状によって判断力が低下し、抑制ができない状態であることが原因とも考えられています。
性的異常行動を起こす認知症の方には、自尊心を保ちたい、家族からもっと愛情がほしいという思いを持っている可能性があります。
記憶を過去にさかのぼって失い、最後に残った記憶の世界が本人の現在の世界になるという「記憶の逆行性喪失」も、性的異常行動を取る原因の一つです。
自分がまだ若者だと思っているなど、認知症の方は昔の世界に戻っている状態です。
性的異常行動は、強い口調で注意すると逆効果になることもあるため、さりげなく注意するようにしましょう。
性的異常行動の対応方法は、日常的に軽いスキンシップを取ること、食べ物や趣味など他のことに関心を向け、認知症の方の気持ちを落ち着かせる方法です。
性的異常行動は、家族や介護者にとっても受け入れ難い問題行動であるため、対応に困った場合は、ケアマネジャーや医師、包括支援センターなどに相談しましょう。
問題行動を起こした認知症患者でも入れる老人ホーム・介護施設を知りたい方は、ケアスル介護での相談がおすすめです。
ケアスル介護なら、全国5万を超える施設の中からあなたにあった施設を選ぶことができ、施設選びを安心して進めることが可能です。
もちろん無料で相談できますので、老人ホーム・介護施設を探している方はぜひ相談してみてはいかがでしょうか。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
認知症による問題行動への向き合い方
認知症による問題行動とうまく向き合うポイントは、主に以下の3つがあります。
- 認知症の方の心を理解する
- 環境変化によるストレスも影響していることを知る
- 自己肯定感を高めてあげる
認知症の症状は、記憶障害などの中核障害、そこから付随する周辺・心理症状があることを解説しました。
認知症による問題行動には、本人なりの理由があります。暴言・暴力行為、多動症状などが現れた場合は、心理的な理由が大きくなります。
認知症の方の問題行動を理解し、改善できるようケアしていくことが重要です。
認知症の方の心を理解する
認知症による問題行動への向き合い方の1つ目は、「認知症の方の心を理解する」です。
今までできていたことができなくなる不安や悔しさは、本人が一番良くわかっています。そのような状況で、家族や介護者から注意されると、怒りやストレスなどに繋がります。
認知症の方が、「なにに苦しんでいるのか」「なにに困っているのか」「どうしたいのか」という思いを汲み取ることが大切です。
認知症の方は、思いをうまく整理できず、言葉にして正しく伝えることができません。
認知症の方の行動や心理的な状態から相手の心を理解し、紹介した対応方法を参考に、少しずつケアをしていきましょう。
環境変化によるストレスも影響している
認知症による問題行動への向き合い方の2つ目は、「環境変化によるストレスも影響していることを知る」です。
認知症の方は環境の変化に敏感であり、不安やストレスから精神状態が不安定になることで、問題行動などの症状が現れます。
また、精神状態が不安定になればなるほど、認知症の症状が悪化する可能性もあります。
急な環境変化の代表的なものは、引っ越しや模様替えです。引っ越しをした場合は、家具の配置などは変えず住み慣れた環境を作るようにしましょう。
模様替えなどもなるべく変えないようにし、本人に馴染みのある音楽を流すなども効果的です。
また、ケアを行う際は、認知症の方の生活リズムを変えないようにしましょう。
起床・食事・入浴・就寝などの時間を急に変えてしまうと混乱や不安を生む原因になります。
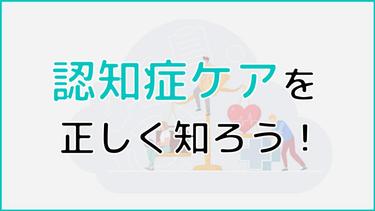
自己肯定感を高めてあげる
認知症による問題行動への向き合い方の3つ目は、「自己肯定感を高めてあげる」ことです。
自己肯定感とは、ありのままの自分を受け入れる肯定する感覚です。他者と比較せず、今の自分を認めることで自信がつき、原動力になります。
認知症の症状は、自己肯定感と大きく関係していると考えられています。
「自分の存在価値」を持つことで、周りの人たちから必要とされているという安心感や自信が生まれます。
認知症の症状による行動で抱えたストレスは抱え込まない
ここまで、認知症の症状である問題行動と対応方法について解説してきました。
認知症の症状に個人差があることと同じで、それらの症状に対する効果的な対応方法にも個人差があります。
認知症の方の心を少しずつ理解しながら、さまざまな対応方法を試すことの繰り返しです。
介護側の負担も大きくなり、ストレスが溜まることもありますが、抱え込まないようにしましょう。ストレスを抱え込まないようにするためには、周りの人や地域の専門機関に相談することが重要です。
認知症に関する悩みを相談できる窓口は、主に以下の4つがあります。
- 地域包括支援センター
- 公益社団法人 認知症の人と家族の会
- かかりつけ医
- 医療機関 もの忘れ外来
地域包括センター
相談窓口1つ目の「地域包括センター」は、各市町村が主体となり、それぞれの地域にあります。
介護・医療・保険・福祉などの専門知識を持つ職員が常駐しており、高齢者が住み慣れた地域で生活できるよう支援する相談窓口です。
認知症に関することではなく、介護・医療についても相談できます。

公益社団法人 認知症の人と家族の会
相談窓口2つ目の「公益社団法人 認知症の人と家族の会」は、認知症に関する悩みを電話で相談できます。
認知症の知識や介護の経験者が対応します。
ストレスを抱え込まないようにするためには、解決策を探すだけではなく、悩みや不安を話すことも重要です。
かかりつけ医
相談窓口3つ目の「かかりつけ医」は、認知症の方を担当する医師のことです。
認知症本人の普段の状態を知っており、相談もしてくれる身近な存在です。
認知症に関する相談を、医療面からも相談できます。
医療機関 もの忘れ外来
相談窓口4つ目の「医療機関 もの忘れ外来」は、認知症の専門外来です。
認知症の専門外来には、認知症に関する知識が豊富な医師がいます。個人差の多い認知症の症状でも、専門の医師に相談すると安心です。
ストレスを抱え込まないために、これらの窓口を活用しましょう。
認知症の症状で起こる問題行動は本人にとって理由のある行動
認知症の症状で起こる問題行動には、本人なりの理由があります。
介護者は、それらの問題行動が起こる理由を知り、それぞれに合わせた対応方法があると解説しました。
認知症の方の心を理解し、本人に合わせたケアを心がけることが重要です。
しかし、問題行動が改善されない場合もあります。その場合は、介護者だけで抱え込まず、相談窓口を尋ねるようにしましょう。
認知症の方の想いを聞いてあげるようにしてください。気持ちを受け止めてあげて、どうしても厳しい出来事があった場合は、地域包括支援センターの方に相談するなど、誰かに助けを求めましょう。詳しくはこちらをご覧ください。
記憶の逆行性喪失により、認知症の方が子どもに戻っているため性的な行動を取ってしまいます。相手の方の性格によりますが、ソフトに断ったうえで別の出来事に気を紛らわすなどしましょう。また、どうしたらよいかわからなくなったら、ケアマネージャーに相談して抱え込まないでください。詳しくはこちらで解説しています。






